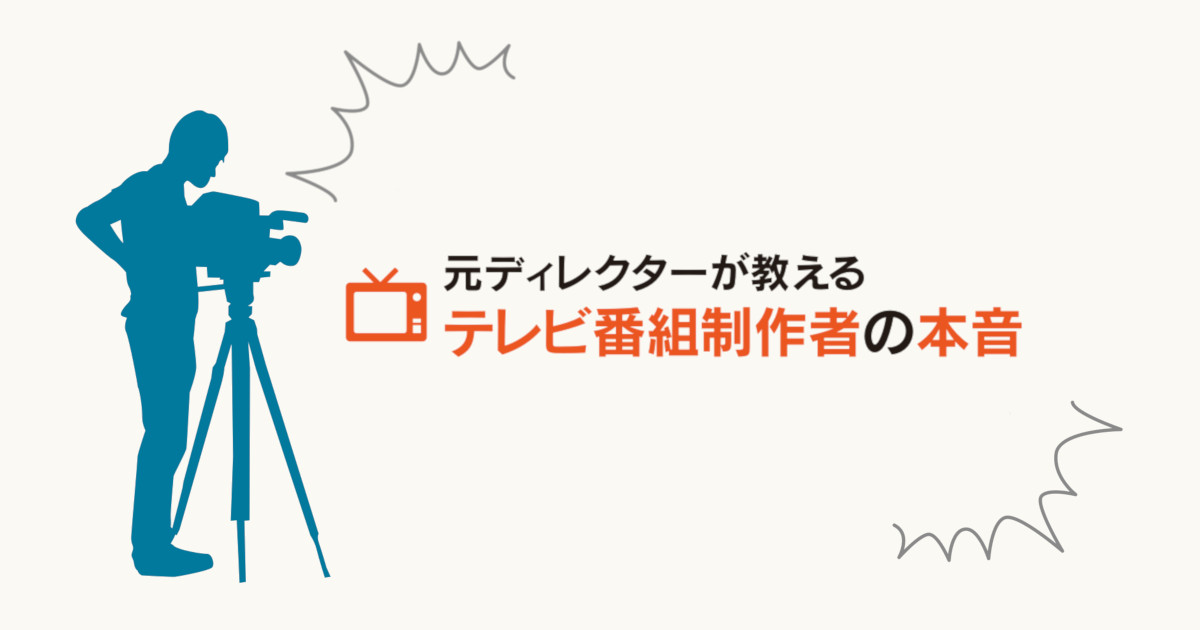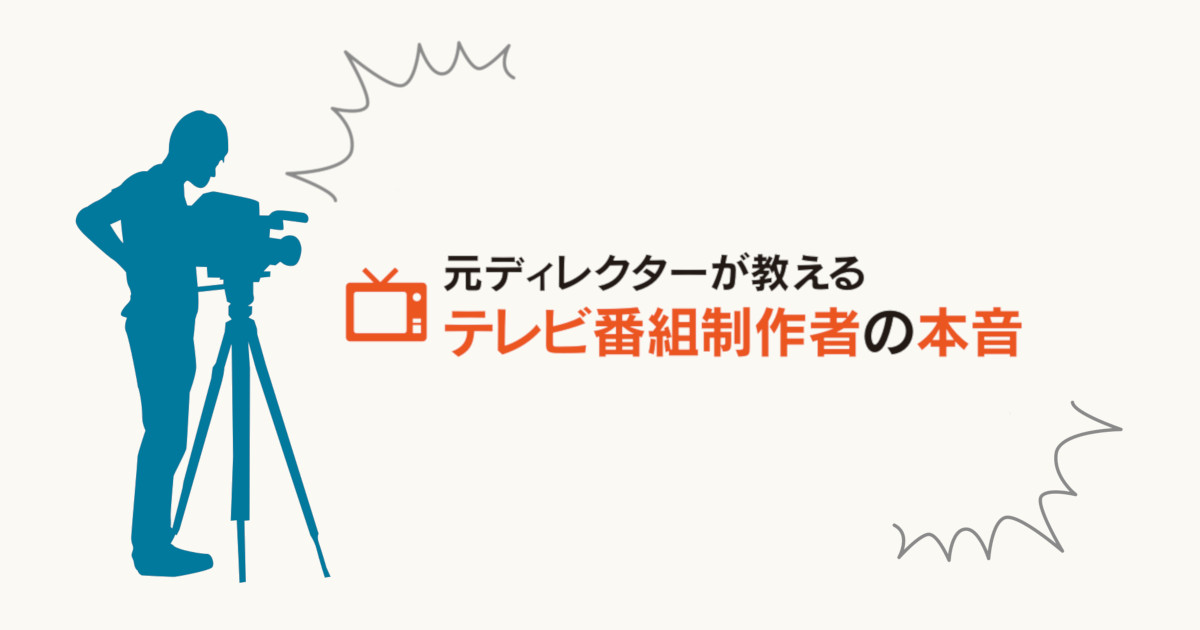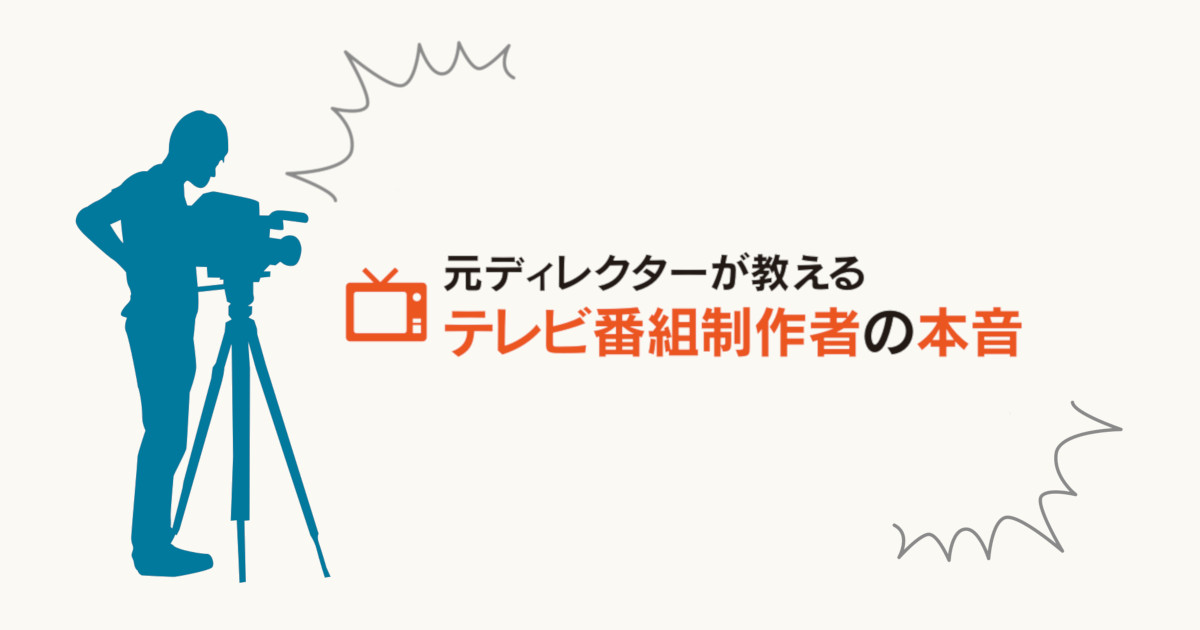経済報道に強いテレビ局としてのイメージがあるテレビ東京。実は、社内体制が経済一辺倒となったのは最近のこと。そのため、幅広い取材経験を持つ人員が番組制作に関わっている。
前回、『WBS』を事例にテレビ東京の経済報道の論調について解説した。そこで今回はテレビ東京が経済報道に力を入れるようになったきっかけを遡り、“取材を受ける側”の広報対応のあり方を探る。
きっかけは『ガイア』の成功
テレビ報道の主流となっているのは事件・事故・災害など。これらは日本全国で24時間365日発生しうるため、対応するにはそれに応じた取材体制を敷いておく必要がある。
対照的に、経済報道では「重装備」は必要ない。取材相手は企業やビジネスパーソンなので、一部の夜回りが発生する記者を除けば、取材時間は通常のオフィスタイムに収まるし、取材場所は東京などの都市部に集中している。
他のキー局に比べて記者の人員や地方のネット局数、予算などが圧倒的に少ないテレビ東京では、経済報道に力を入れるほうが合理的なのである。
ただ、最初から経済報道に大きく軸足を置く体制であったのかといえば、そうではない。対外的にはかなり前から「テレ東といえば経済」というイメージが定着していたように思うが、実はそれが報道局の内部での共通認識となったのは、最近のことだ。
私が報道局に配属になった約20年前のこと。当時、報道局管轄の番組といえば、早朝の『モーニングサテライト』と“経済以外”を主に取り上げる夕方のニュース番組、『ワールドビジネスサテライト』(当時)だった。まだ『ガイアの夜明け』も『カンブリア宮殿』も始まっていない時代である。
経済番組出身者が報道局長などの要職を占めているというわけでもなく、経済部門を担当する人員と政治・警察・司法など経済以外の取材に割かれる人員とは拮抗していた。どこか「テレビ報道の花形」を捨てきれずにいたのだ。経済と経済以外の担当者間で、微妙な空気が流れることもあった。
「経済担当は事件現場を回るような地を這う取材をしていない。報道として、それが正しい姿なのか」。六本木の居酒屋で報道局員同士が激論を交わすことも頻繁にあった …