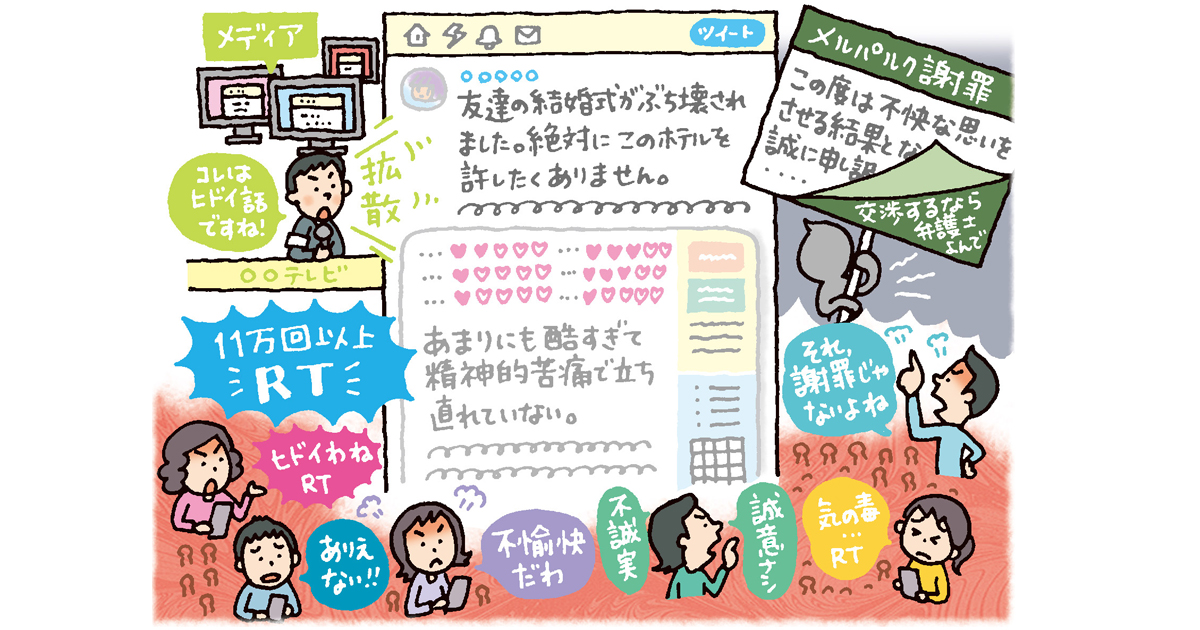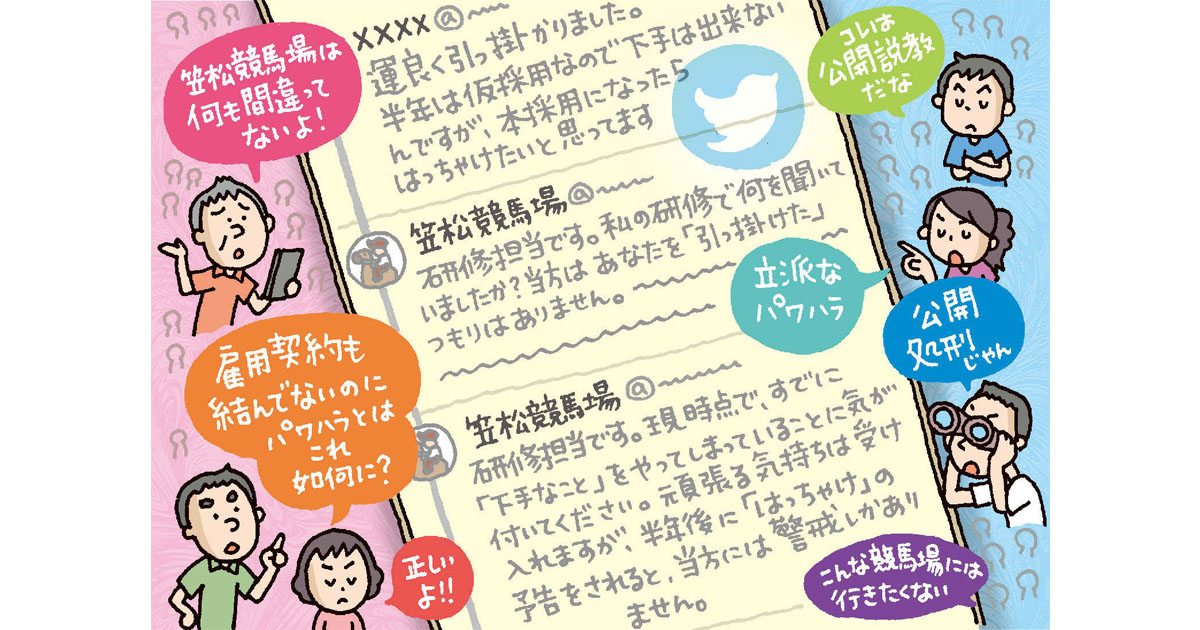ブログや掲示板、ソーシャルメディアを起点とする炎上やトラブルへの対応について事例から学びます。

イラスト/たむらかずみ
問題視された組織のネットルール
送別会の案内を公用メールで送ったことを問題視した大阪府が7月末、職員を処分すると発表した。報道で注目を集めた結果、大阪府知事は「時間外なら許容する」とした。
退職した元幹部の送別会の案内を大阪府職員が公用メールで送ったこと、また同僚から集めた記念品の代金保管を職場でしていたことがいずれも内規違反だとして、7月末、大阪府は関係者を処分すると発表した。これに対して職員に同情する意見などが多数寄せられたことなどもあり、府は知事や幹部職員らによる検証会合を開き、結果として勤務時間外なら公用メールでのやり取りを容認すると決めた。
処分の発表直後、関心は「送別会の案内をメールしただけで処分されるのか」と「職場の送別会は業務か否か」という点に集まった。これらについて、「J-CASTニュース」の取材で、大阪府の人事課は「飲み会の準備は仕事ではないのは明確」と答え、総務省の公務員課は「どこまでが業務か明確な基準というものはなく、自治体トップの判断になる」とコメントしている。
明確さと周知徹底が必要
一見、これが問題視されること自体に疑問を持つが、情報を追うと、一般にイメージされる有志による送別会とは趣きが異なる印象を持つ。報道によると、送別会の案内メールは法務課幹部の指示で送信され、最大で約590人の職員が閲覧した可能性があるという。案内文は府幹部名だった。これらを踏まえると、業務とするかどうかは別にして、私用の域は超えているという声があがっても無理はなさそうだ。
ただウェブリスクの対策・対応として注目したいのは、これが業務か私用かよりも、ルールが現場で判断できるように明確になっているかどうかと、そのルールが周知徹底されているかどうかである。運用できなければ意味がないからだ。そして府が処分発表後に対応を変えたということは、ルールが明確でなかったことにほかならない。
処分の前に注意喚起を
大阪府の対応には2つの問題がある。ひとつは、いきなり処分を発表したこと。送別会の案内が公用メールで送信されたことが初めてだったとは考えにくい。過去に例があったのなら、いつ、なぜ、ルールを変えるのか・変えたのかが明らかにされるべきだ。仮に初めてだとしても、ルールが周知徹底されていないなら最初にするのは処分ではなく、注意喚起だろう。
もうひとつの問題点は、結果的にルールを明確にしなかったこと。時間外の公用メール利用の容認だと、上司から指示された部下が数百人にメール送信して個別の返信に対応する時間は、すべてサービス残業になるのではないか。これでは断れない現場の職員が最も負担を抱えることになる。しわ寄せはどこに出るのだろう。
業務かどうかは曖昧なことが多いが、逆に言えば、曖昧さは余裕の証でもある。本来はそれを前向きに活かしたい。しかしひとたび問題視されたら、その時にルールを明確にしなければ、同じ問題が再び起こる。今回の対応はその貴重な機会をつぶし、結果的に問題をうやむやにしただけだった。
社会情報大学院大学 特任教授 ビーンスター 代表取締役社会情報大学院大学特任教授。米コロンビア大学院(国際広報)卒。国連機関、ソニーなどでの広報経験を経て独立、ビーンスターを設立。中小企業から国会までを舞台に幅広くコミュニケーションのプロジェクトに取り組む。著書はシリーズ60万部のベストセラー『頭のいい説明「すぐできる」コツ』(三笠書房)など多数。個人の公式サイトはhttp://tsuruno.net/ |