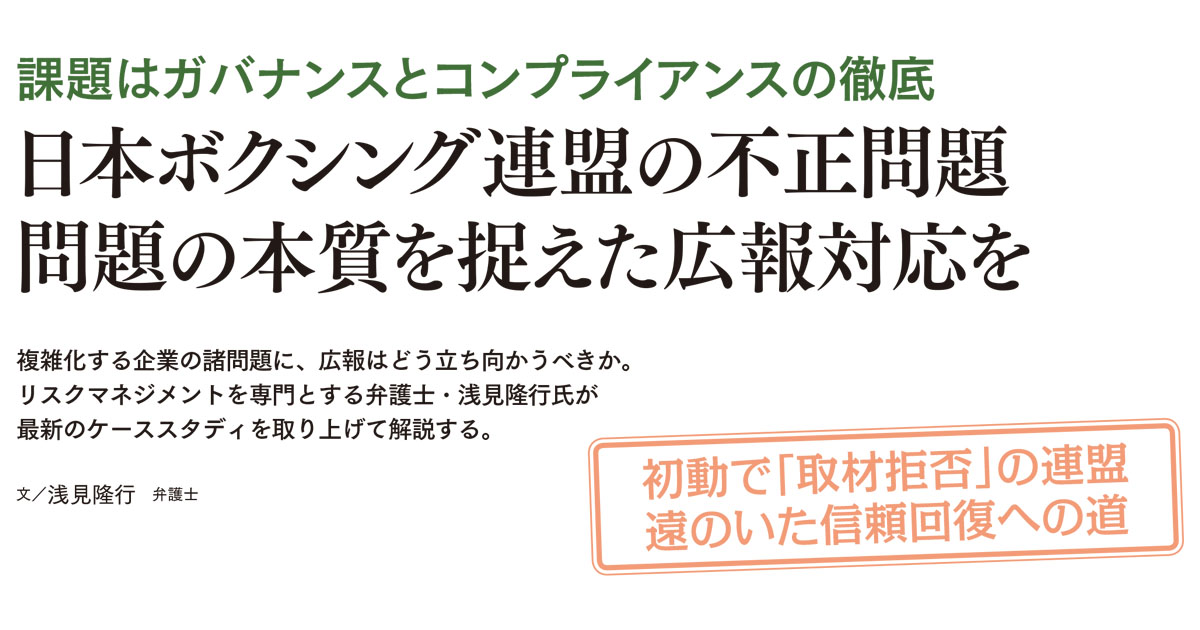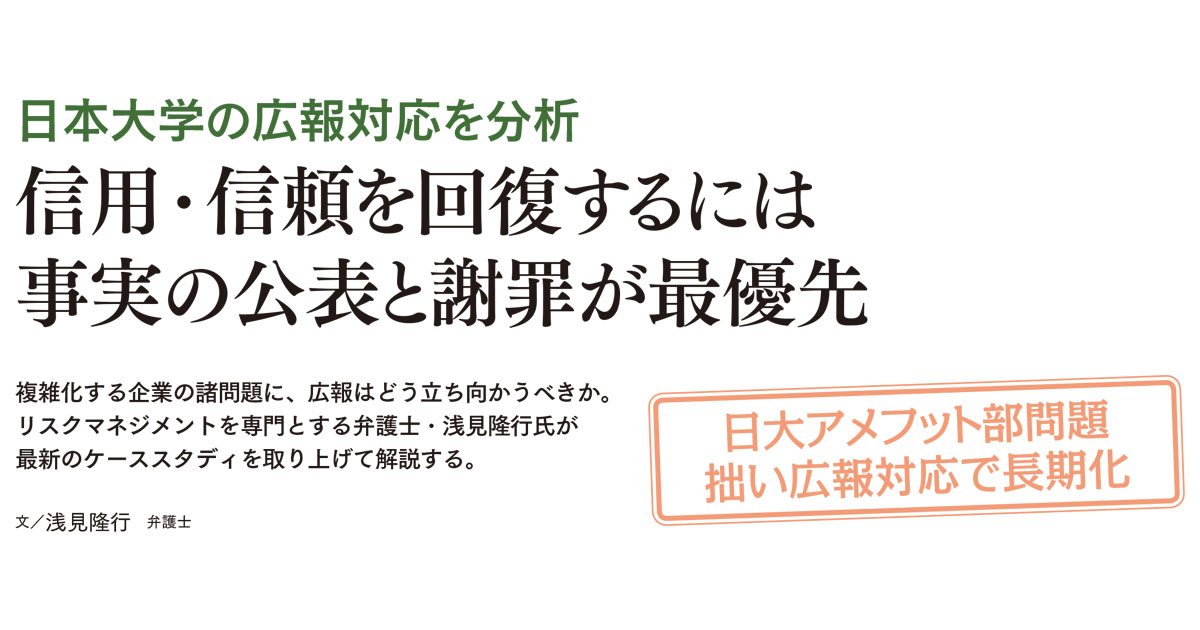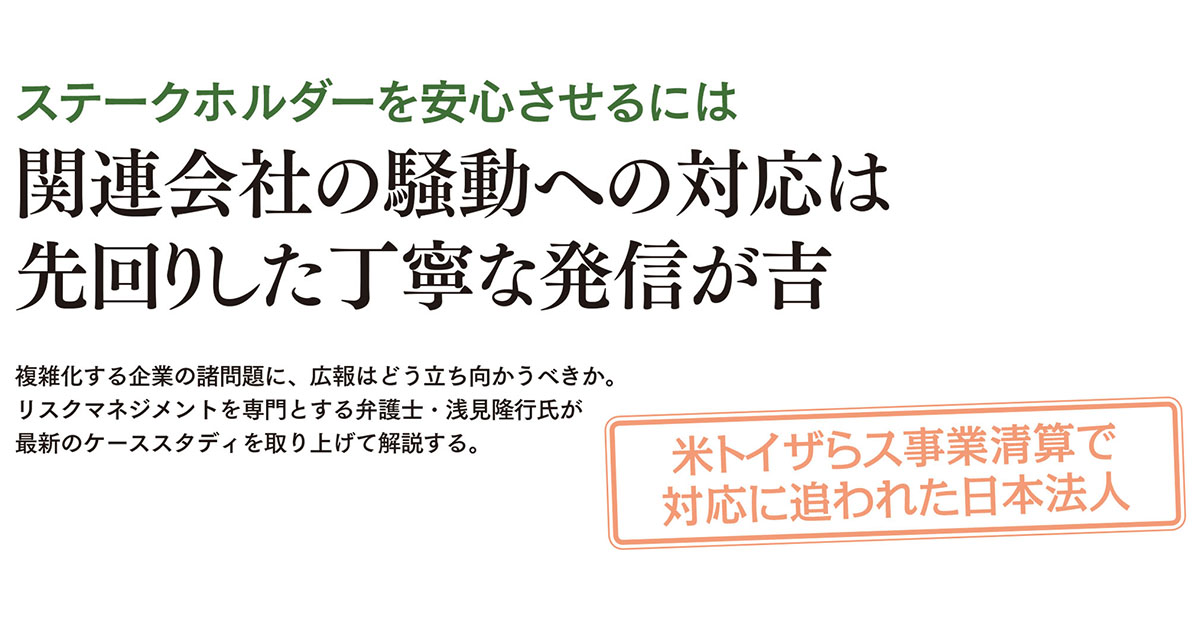複雑化する企業の諸問題に、広報はどう立ち向かうべきか。リスクマネジメントを専門とする弁護士・浅見隆行氏が最新のケーススタディを取り上げて解説する。
問題の経緯
2018年8月27日

2014年8月22日に朝日新聞が配信した英文記事に、ネット上の検索結果から除外される「検索回避タグ」を埋め込んでいたことが発覚した。同社では2018年8月27日以降、自社ホームページにて「設定解除作業の漏れがあったため」と経緯を順次説明。さらに日本語記事にも同様のタグが埋め込まれていた件は「今回の指摘を受け、確認作業をした際に誤ってタグを設置してしまった」としている。いずれも「苦しい言い訳」などと批判が集中した。
2018年8月、朝日新聞が2014年8月22日にネット配信した記事のソースコードに「検索回避タグ」を埋め込んでいたことが判明しました。慰安婦問題が誤報であることを認める記事だったこともあり、インターネット上の検索で引っかからないよう「意図的に隠したのではないか」との批判が集まりました。
今でこそ、多くの企業が情報漏えいやリコールなどの不祥事を起こしたときにリリースを公式ウェブサイトに掲載して情報公開することは常識となっています。一方で、「なるべく人目に触れないようにしたい」「事実隠しだと批判されるから、やむなく公表している」という本音を抱いている企業も少なくないのではないでしょうか。
そこで、今回は企業にとって謝罪やお詫びなどネガティブな情報に関するリリースを公式ウェブサイトに掲載する場合の留意点を解説します。
海外にも届かなければ意味なし
検索回避タグが埋め込まれていたことが最初に発覚したのは、「(韓国)済州島で連行 証言 裏付け得られず虚偽と判断」「『挺身隊』との混同 当時は研究が乏しく同一視」と題する記事の英語記事2本。いずれの記事にもネット検索を回避するための「noindex」「nofollow」「noarchive」といったタグがソースコードに埋め込まれていました …