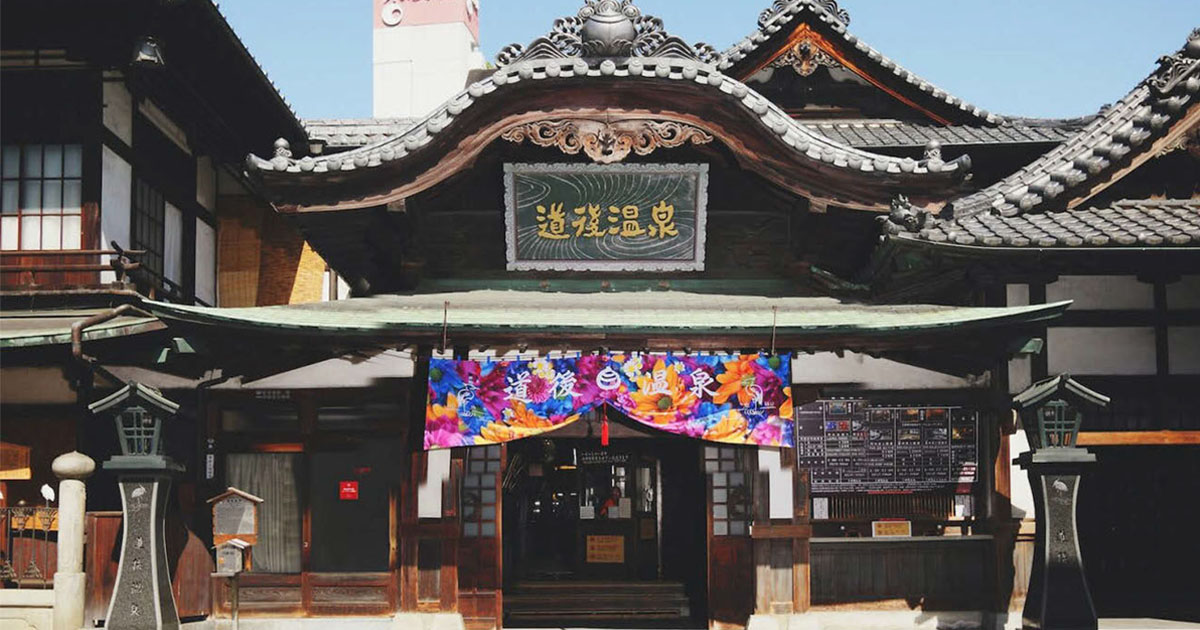多くの自治体が取り組んでいるシティプロモーション。「予算の確保が難しい」「職員に専門的な知見が蓄積されにくい」といった行政ならではの課題が横たわっています。
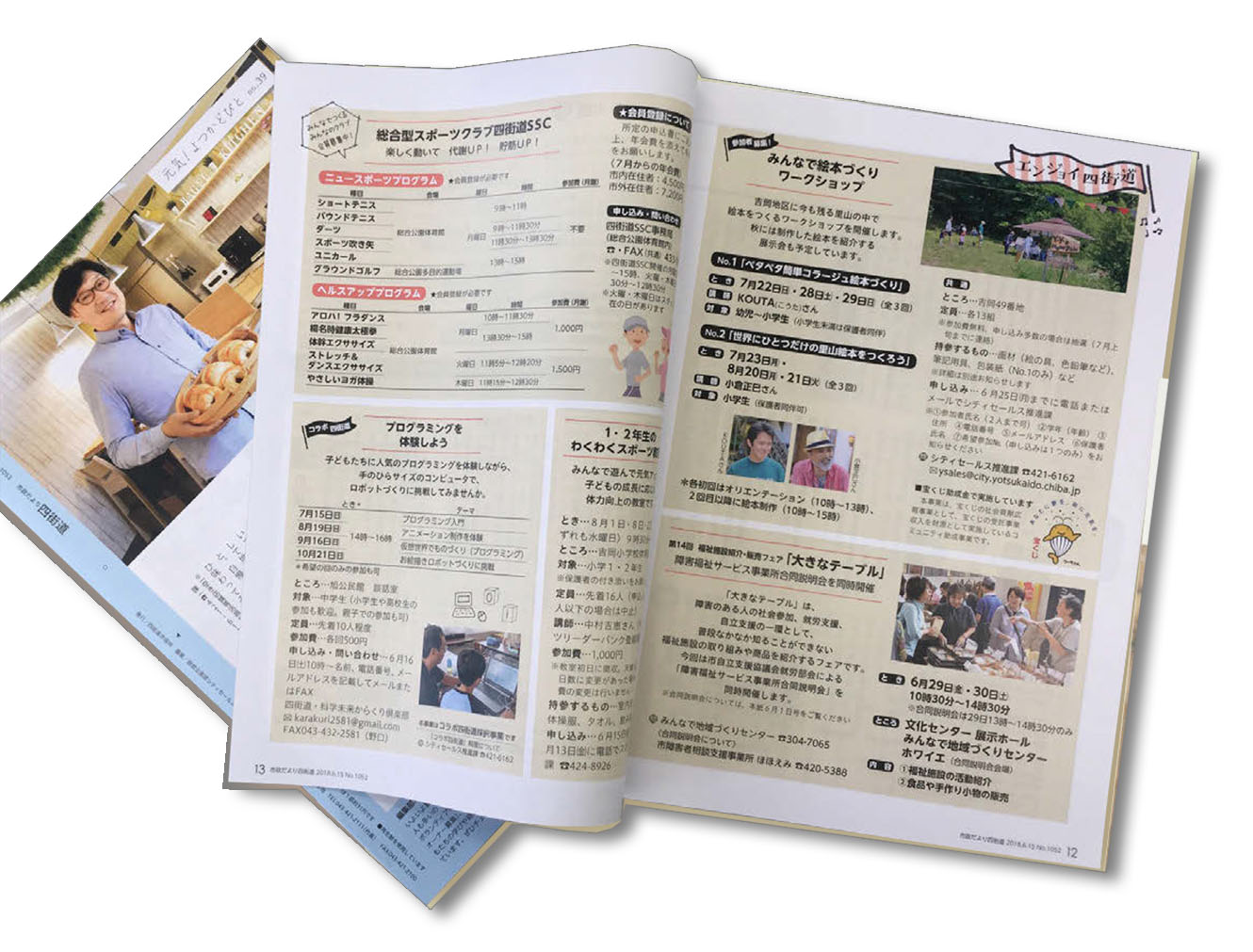

2018年4月にリニューアルした広報誌は、写真やカラーページを増やし文字も大きくしている。こうしたデザインの改善も「スキルの適正化」のひとつだ。
四街道市シティセールス推進課長に就いて約3年が経過し、おぼろげながらシティプロモーションに関していくつかの課題が見えてきました。それは次の4つを「適正化」するということです。
(1)ミッション (2)成果指標 (3)スキル (4)リソース
これらは四街道市に限ったことではなく、ほかの地方自治体でも同様の課題が潜んでいると思っています。
そもそも「シティセールス」とは?
まず、第一にシティプロモーションの「ミッション」の適正化についてです。行政ならば「事務分掌」の適正化と言い換えてもいいでしょう。
四街道市のシティセールス推進課の事務分掌のひとつはこんな風に書かれています。「シティセールスに関すること」。シティセールスのふたを開けてみると、また「シティセールス」。マトリョーシカ人形のようです。それでは「シティセールス(シティプロモーション)」とは何を指しているのでしょうか?
そもそも、広告業界や広報業界では「セールスプロモーション」という言葉はあるものの「シティプロモーション」は存在していません。「シティセールス」に至ってはさらに微妙です。「セールス」は文字通り「営業」なので「街の売り込み」を意味していると思いますが、事務分掌で使用するにはやはり抽象的です。このことによって、行政内部でもシティプロモーションやシティセールスの業務領域について若干の混乱があるという話をほかの自治体職員からも聞いたことがあります。
「シティプロモーション」「シティセールス」に新しい何かを織り込もうとしていることは理解できますが、結果的にそのミッションを曖昧にしてしまうならば本末転倒です。
積極的で戦略的な広報活動やPRイベントという意味を持たせたいのであれば、「広報活動に関すること」「PRイベントに関すること」と粛々と定義しておけば十分です。「ブランディング」「ブランドマネジメント」を含めたいなら、そのように正確に記述すべきです。マーケティング用語にない曖昧な規定をするべきではありません。これは些細なことのようで、シティプロモーションの職務の出発点としてはとても大事なことなのです …