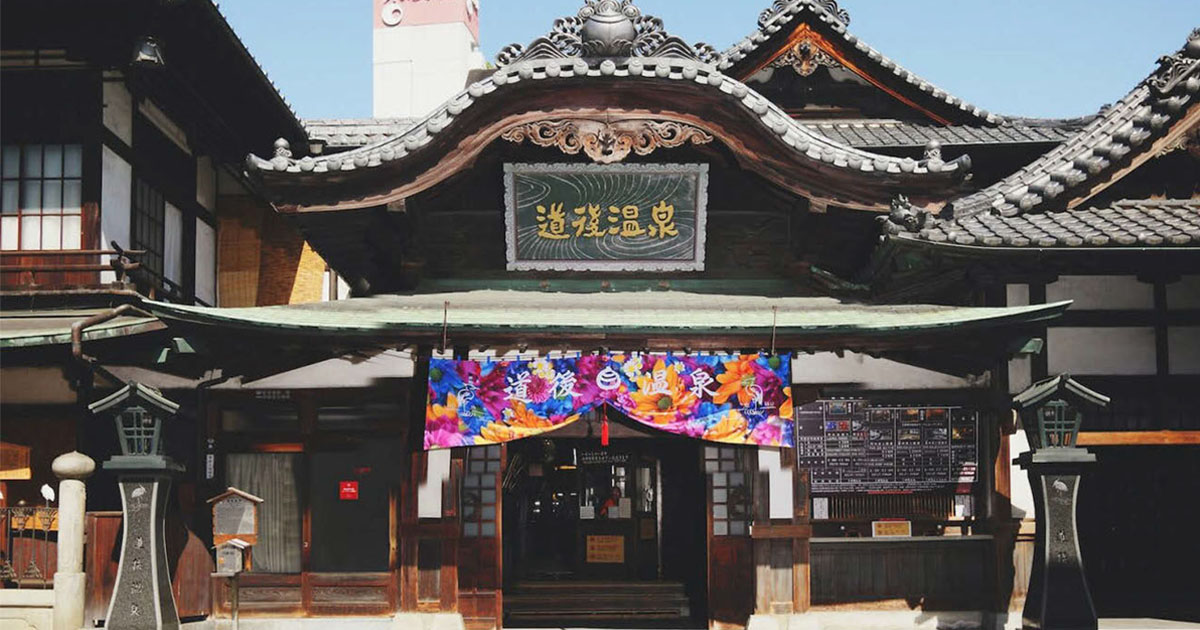四街道市のシティセールス推進課内にある「みんなで地域づくり係」。市民による課題解決プレゼンや参画型のワークショップを通じて、まちの中から魅力を醸成しています。


Y・Y・NOWSON(わいわいのうそん)プロジェクトの様子。東京情報大学のケビン・ショート教授の案内による里山散策などが行われている。
正直なところ、四街道市にはこれといった強い名産品があるとは言えません。名所もなければインスタ映えするスポットもない。調べてみると、市には3万年以上前の旧石器時代の遺跡が多数ありますし、縄文遺跡も弥生遺跡もあります。江戸時代には柿、桐、茶が三大農産物で、特にお茶は徳川幕府に献上されていたほどです。明治時代以降、第二次世界大戦までは、陸軍演習地となっていたことによって街は栄えてきました。
そんな姿は浮かんでくるものの、現代では「夢の国」も海もなければ、コンベンションセンターも華やかな航空機レースもありません。
しかし、ないものを羨んでいても始まりません。四街道市シティセールス推進課の「みんなで地域づくり係」はそんな状況下で街の魅力づくりを進める部門です。ないものはつくる、そんな気概で挑むグループなのです。
寺子屋プロジェクトの成功体験
社会人類学者クロード・レヴィ=ストロースは、名著『野生の思考』のなかで「ブリコラージュ」という概念を紹介しています。創造の手法として、何もないところからつくるという考え方に対し、「ブリコラージュ」とは「すでにあるものを組み合わせることで新しいものを生み出す」という概念です。では、四街道市に「すでにあって活かせるもの」とは何でしょうか。
それは「市民とその暮らし、市民の活動そのもの」であると改めて気づいたのです。四街道市は、農村文化と戦後の開発による新興住宅地の文化が入り交じり、年代的にも高齢者から若者まで行き交う街となっています。二十世紀後半以降はアジア圏の外国人も増え、その多様性の中から生まれてきた様々な市民活動は次第に活発なものとなっていました。そして、2015年度のシティセールス推進課設立を機に、四街道市は「市民協働事業」をさらに大きな強みにしていこうと考えました …