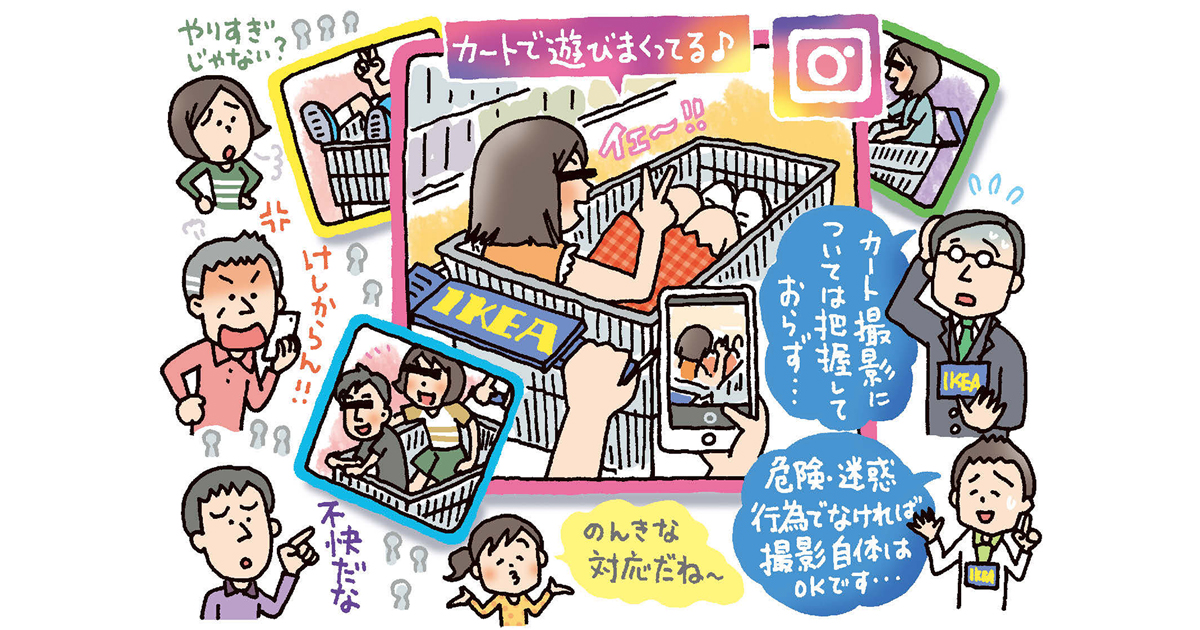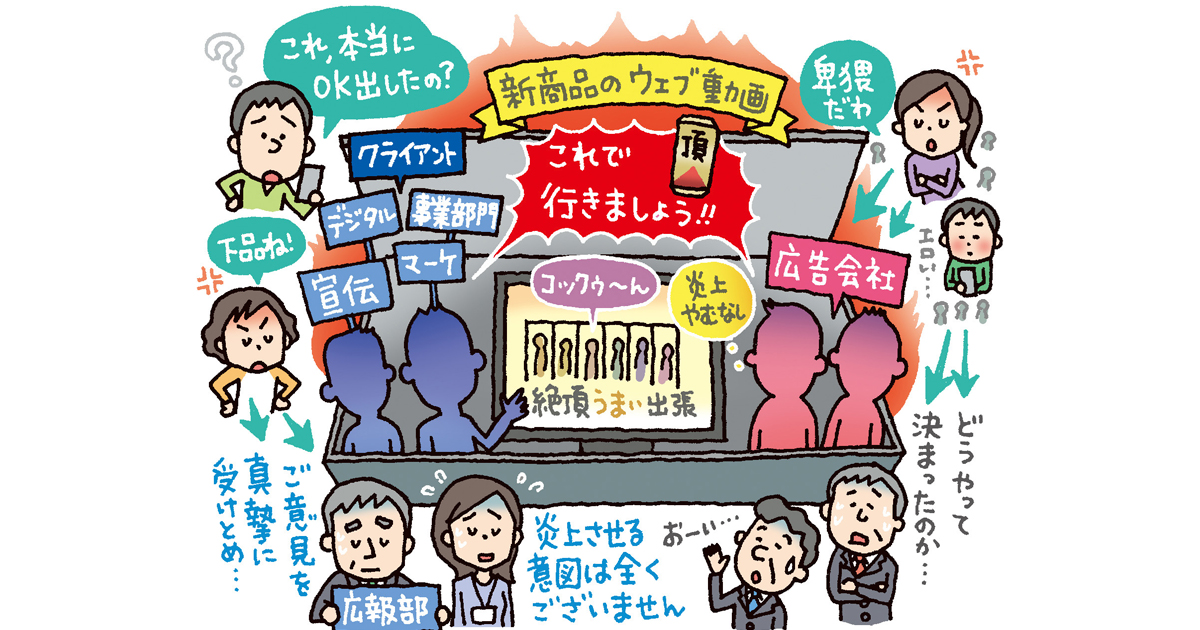ブログや掲示板、ソーシャルメディアを起点とする炎上やトラブルへの対応について事例から学びます。

イラスト/たむらかずみ
ネットへの書き込みから不正告白へ
東レ子会社のデータ改ざんが明らかになった。その事実に加えて記者発表で東レの日覚昭広社長が語った「ネットで書かれたので公表した」という言葉も衝撃を与えた。
2017年11月、東レは子会社で製品検査データの改ざんがあったことを発表した。社内では1年以上前に把握していたという。記者会見で「なぜこのタイミングに発表したのか」と問われた東レの日覚昭広社長は、「公表するつもりはなかったが、ネットで書かれたので公表した」と答えた。
データ改ざんがあったのは、東レの子会社で自動車用タイヤの補強材などを製造する東レハイブリッドコード。2016年7月に社内アンケートで指摘があり、社内調査を経て、同年10月段階で日覚社長まで問題が報告されていたが、「法令違反ではないため公表は考えていなかった」と話した。
注目されたのは「ネットで書かれたので公表した」という社長の言葉。このような発言をさせてしまった広報の不甲斐なさをまず問題視したい。
守るべきは「一貫性」
不都合な情報を公表するかどうかは理想論で済む単純な話ではないが、公表すべき情報を隠ぺいしたと見られて失う信頼の大きさを説けない広報は、その役割を果たしていない。
法令違反がなく安全性に問題がなければ、弁護士や法務部門の一般的な見解は「公表の必要性なし」だろう。しかしそれは、あくまで法的側面で見た場合だ。企業には社会的責任と継続的に発信しているメッセージがあり、その方針や姿勢と一貫性があるかどうかをチェックするのが広報の重要な役割である。メッセージに一貫性がなければ信頼性や説得力は生まれない。
東レは、経団連会長を輩出する日本の代表的企業であることに加え、経営方針には「誠実で信頼に応える経営」「高い倫理観と強い責任感」「経営の透明性を維持して社会の信頼と期待に応えます」などと立派な言葉が並ぶ。また東レは2011年に経済広報センターの企業広報功労・奨励賞を受賞。広報のお手本とお墨付きを与えられている。
これらを踏まえれば、何年にもわたって検査データを書き換えて出荷していた事実が明らかになった時点で公表しなかったこと自体が失敗だといえる。
告発は現場の不信と悲鳴
この発表の前日、東レ出身の榊原定征経団連会長は定例会見で、神戸製鋼や三菱マテリアルなどで起きたデータ改ざんについて「日本の製造業に対する信頼が揺らぎかねない深刻な事態」と厳しく述べた上で、情報開示の在り方についても「発覚時点で公表するのが原則だ」と明言していた。榊原氏は、翌日の発表について自らが在任中にデータ改ざんが起きていたことを知らされていなかった様子で、大恥をかかされた形になった。
一般的に告発の多くは関係者によるもので、内部通報制度などで解決が期待できない場合に取られる手段だ。言い換えれば、現場の不信と悲鳴の象徴である。「ネットに書かれたから公表した」という社長の発言は、経営も現場もネットの書き込みに屈したことを示すという事実を広報としてしっかり噛みしめたい。
社会情報大学院大学 客員教授・ビーンスター 代表取締役米コロンビア大院(国際広報)卒。国連機関、ソニーなどでの広報経験を経て独立、ビーンスターを設立。中小企業から国会までを舞台に幅広くコミュニケーションのプロジェクトに取り組む。2017年4月から社会情報大学院大学客員教授。著書はシリーズ50万部のベストセラー『頭のいい説明「すぐできる」コツ』(三笠書房)など多数。 |