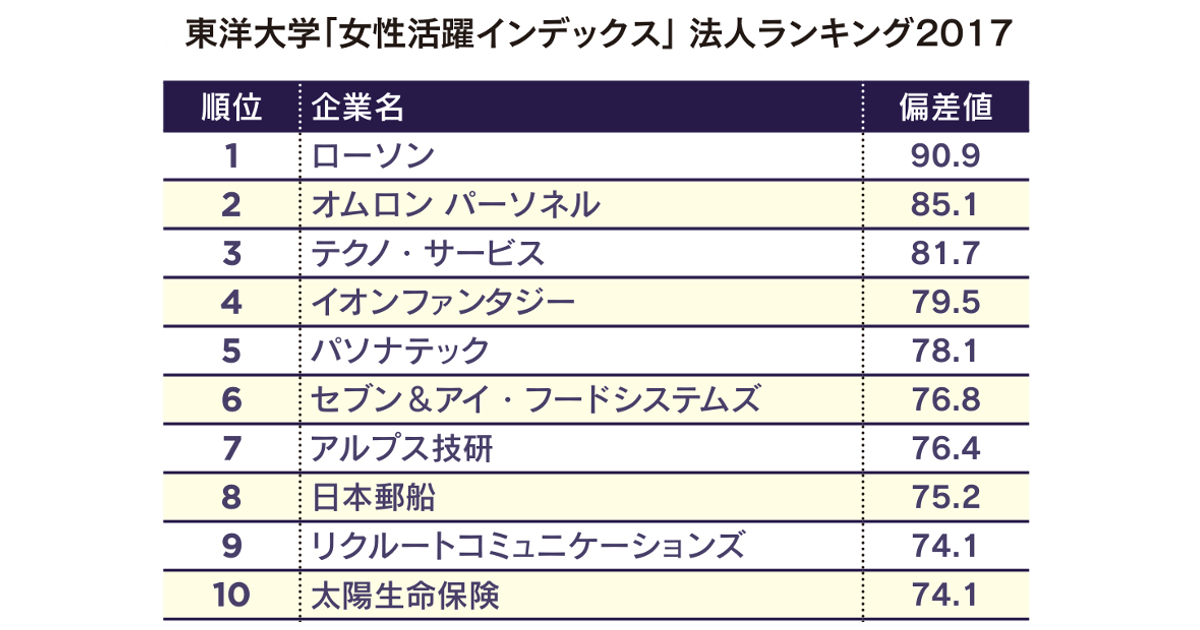800近くある国公私立大学が受験生や資金を求めて競争する教育現場。スポーツ選手を多く輩出する東洋大学で広報を務める榊原康貴氏が、現場の課題や危機管理などの広報のポイントを解説します。

東洋大学広報課入口に貼り出された新聞各紙。桐生祥秀選手が100メートルで日本人初の9秒台を出したことが大きく取り上げられている。
広報の仕事のひとつとして、外部への露出による効果の検証があります。東洋大学の場合、広告換算や内容分析をすることによって、組織としての知見を蓄えている状況です。学外での講演などの際に、具体的な東洋大学のKPIの設定や考え方について質問を受けることが多くありますが、こうした可視化や評価を課題に感じている大学が多いことに気がつきます。
そこで今回は、広報の反応として生じた効果や評価について、いくつかの具体的な事例を紹介します。
数字からみる広報効果
大学広報の効果としてよく引き合いに出されるのが、その年の入学試験の志願者数ではないでしょうか。「対前年比で◯%増」「志願者数ランキング◯位」などの一覧が週刊誌などで取り上げられる機会が多くあります。
大規模な私立大学では10万人以上も志願者を集める一方、前年から大幅に志願者を減らした大学は経営が危ないなどの切り口で少子化や大学経営と結びつけて記事になることも。特に週刊誌や場合によっては経済誌などにもこうした記事が「特集」として組まれることが多いので、その効果はとても大きいものがあります。
また、テレビでの露出も大きな広報効果が現れます。広告換算でもテレビでの露出は桁が変わるほど、そのインパクトは大きなものと考えています。
端的なものとして、箱根駅伝があります。大学スポーツの花形ともいえるこの競技は、お正月の生放送で30%(関東地区限定、ビデオリサーチ調べ)を超える高い視聴率を獲得するということもあり、テレビ生中継での露出は極めて高い効果があります。例えば東洋大学が2012年に優勝したときの広告換算は、東洋大学独自の尺度ではありますが、170億円程度の価値を算出しました。多くの大学の年間広告予算は多くて数億円というレベルですから、そのインパクトの大きさは計り知れないものがあります。
さらに、この影響は公式ウェブサイトにも現れます。実は東洋大学で一番ウェブサイトへのアクセスが集中するのがこの箱根駅伝が実施される1月2・3日なのです。テレビの中継を見ながらウェブサイトを見るという観戦スタイルがある程度定着している証です。
また、大学の独自コンテンツをつくるニーズも一定数あることが分かります。こうした状況を見て、東洋大学は駅伝応援企画として、動画コンテンツを立ち上げました。新たに「10分間で箱根駅伝を体験できる」早回し動画を制作し、大会直前の2016年12月27日に実験的に配信を開始しました。
この動画は選手たちの活躍もあり、短期間に万単位の再生回数をはじき出しました。ウェブサイトへのアクセス数などの推移はコンテンツを提供するタイミングなどを検討する際にとても有効だと考えます ...