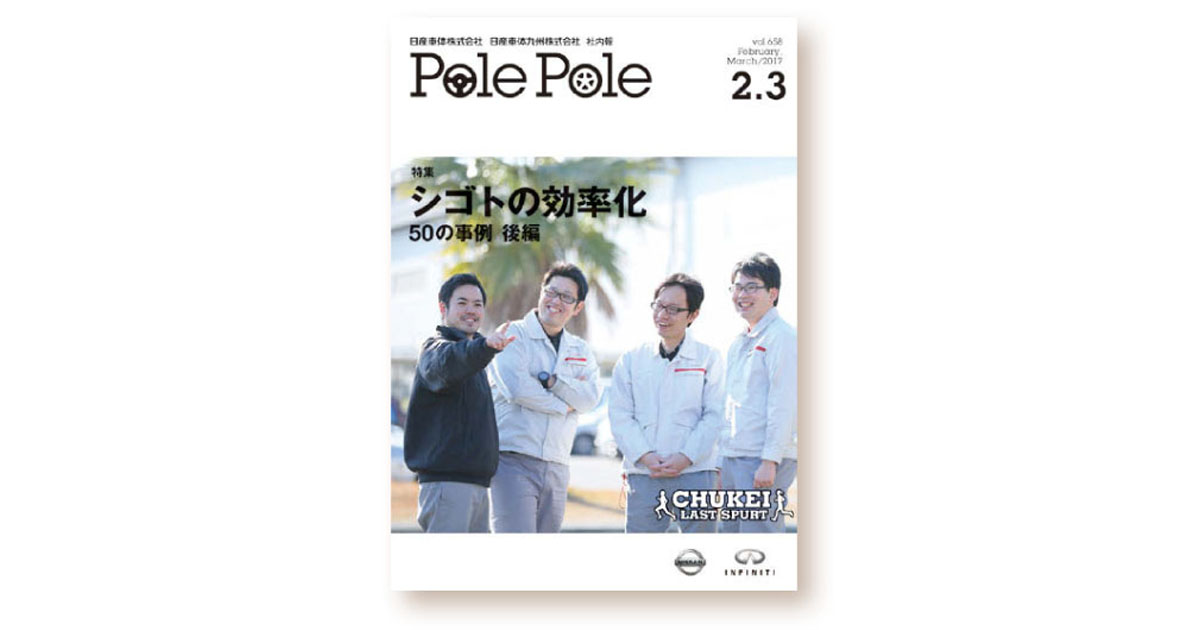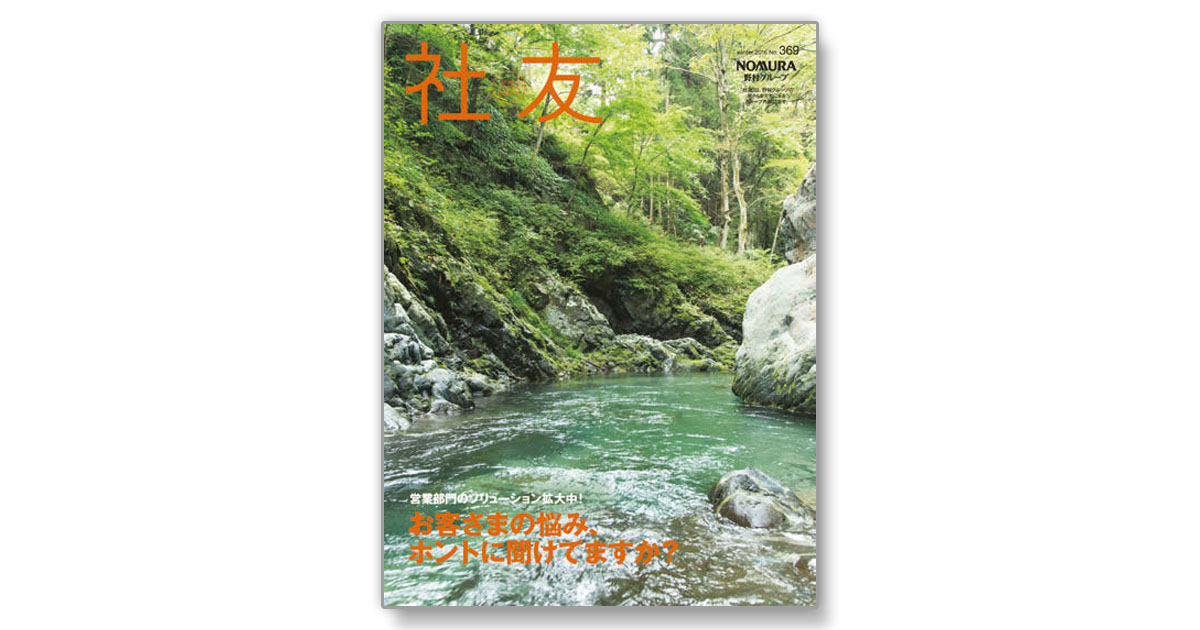インターナルコミュニケーションを活性化させ、事業の成長を後押しする役割を担う社内報。今回はキリンホールディングスのグループ報制作の裏側に迫ります。
キリンホールディングス
『きりん』
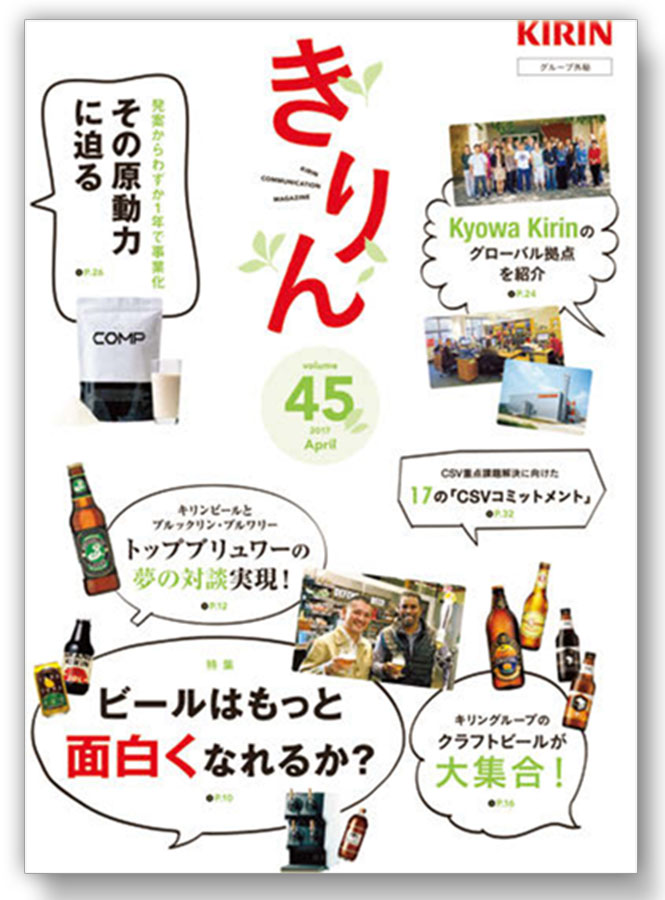
国内外で酒類、飲料、医薬・バイオケミカル事業を展開するキリンホールディングス。グループ約180社で働く従業員は約3万人に上る。そのうち国内で働く約2万5000人に配られているのが、グループ報『きりん』だ。
リーダー予備軍をターゲットとした内容にリニューアルし、グループの目指す方向性を示すとともに自身の仕事に落とし込むことができるグループ報へと生まれ変わったのは2015年のこと。「経営方針、グループ情報の共有」「従業員のモチベーションアップ」を目的に発行している。
「従業員にアンケートを取ったところ、グループ報への若手からの評価が高くないことが分かりました。これからの会社を担っていく世代に向けたアプローチが必要と考え、若手リーダーやその候補となる30代を読者対象に絞り込みました」と社内報制作を担当するグループコーポレートコミュニケーション担当の原田志保氏は話す。
とはいえ、一気に従業員の意識を変えていくことは難しい。そこでリニューアルにあたり、「おもしろがる」「自分に何ができる?」「やってみよう」という3つの段階に分け、従業員の行動変容につなげる誌面づくりにこだわってきた。
例えば第一段階となる2015年は「視野を広げ、好奇心を生むフェーズ」と位置づけ、キリングループ全体を知り、理解を深める特集企画を毎号掲載。2016年以降は「自分は何をやりたいか、やれるのか」を考えてもらおうと、同年に策定した中期経営計画を通して、会社が目指す方針に対する各社の現場の取り組みを掘り下げて特集で紹介している。
このほかの代表的な企画は「隣の芝生は、たしかに青い」だ。新たな価値を生み出し続ける企業を従業員が訪問、自身が得た気づきを誌面でコメントする。良い刺激となる事例を持つ企業を選定し、親和性のある部署に訪問してもらうことで多様な気づきを得られる、参加者にも読者にも好評のシリーズだ。
グループ報の発行ごとに実施しているアンケート調査では、リニューアル後の評価は右肩上がりだという。目下の課題は、前述した3段階のうち最終段階である「やってみよう」を体現する企画をいかに立案するか ...