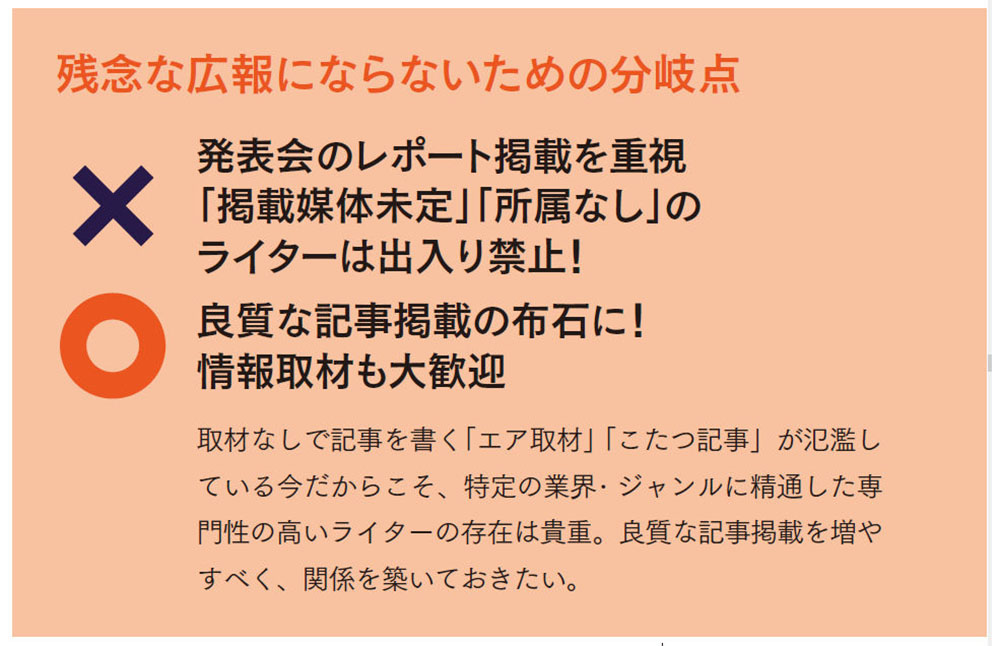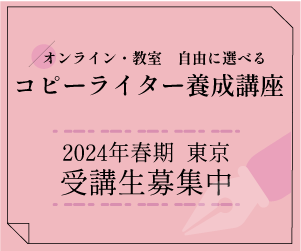記者と広報は、なぜすれ違う?第一線で活躍するメディアの記者に本音で語ってもらいました。
週刊誌 編集記者 Mさん(男性)某出版社の書店営業を経て、ライバル企業の週刊誌編集記者に転身。営業のつらさからは解放されたが、出版不況で雑誌の売れ行きが落ち込む中、将来への不安も募る日々。ネット展開が遅れる自社を見捨てて、急成長している新興ウェブメディアへのさらなる転職も視野に入れている。 |
「Mさん、ご無沙汰しております」。
EさんからFacebook経由でメッセージが届いたのは昨年秋ごろだ。
「以前の会社を辞め、転職したばかりのベンチャー企業でも広報を担当しています。ついては新しい会社についてぜひ記事に取り上げていただきたく。来週のご都合はいかがでしょうか?」。
メッセージにはそんな内容が綴られていた。「Eさん……誰だっけ?」。
1200人を超えるFacebookの友だちリストを見ると確かに名前がある。アラサーとみられる若手の男性で、個別メッセージのやり取りは2回目だった。記憶をたどってようやく思い出した。Eさんは数年前に出席した、ある懇親会に来ていた某ベンチャー企業の広報担当者だった。
某ベンチャーといっても、失礼ながら一般的にはほとんど名前を知られていない企業だ。顔を合わせて話をしたのはその一度きり。会合後に届いた友だちリクエストを承認して、当たり障りのない挨拶をメッセージでやり取りした後に、「ウチの会社を取材して記事にしてほしい」という趣旨の電話が二度かかってきていた記憶も蘇った。
彼はとにかく自社の取り組みを記事にしてほしいようだった。ただ、世を見渡してみて何か斬新なテーマや切り口があるワケではなく、隠れたトレンドを浮かび上がらせたものでもなければ、社会的な問題を提起している内容でもなかった。こちらにしてみれば、それを取り上げる必然性がなく、ただの会社の宣伝になってしまう。要は媒体の特性に合っていない提案だったのだ。
当時の私はEさんにアポも取材の提案も遠慮させていただく方向感を伝えた。それでも彼は食い下がってきた。「なぜ記事にできないか」を延々説明してようやく断ることができた。私自身が10年近く前の新入社員時代に生命保険のセールスレディから受けた勧誘のような熱心さと、ある種の「しつこさ」が同居したような売り込みだった。
変わらぬベンチャー広報の芸風
あれから数年。私は意を決してEさんに会ってみることにした。せっかく声をかけてきてくれたのだから、門前払いするのも気が引ける ...