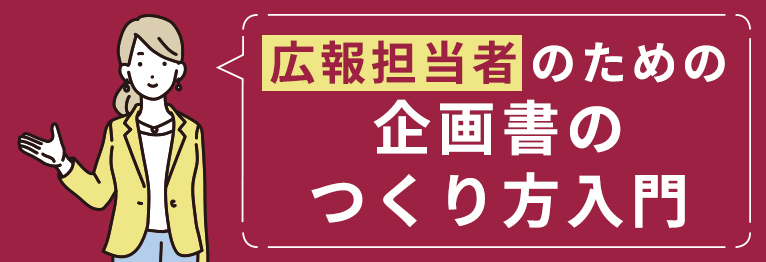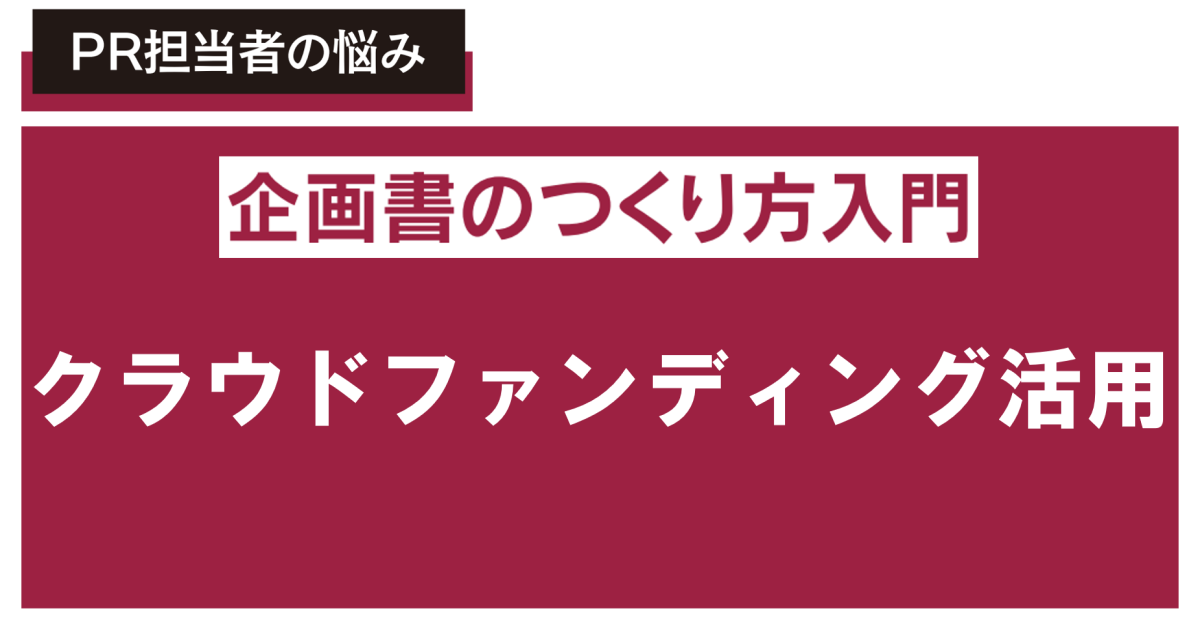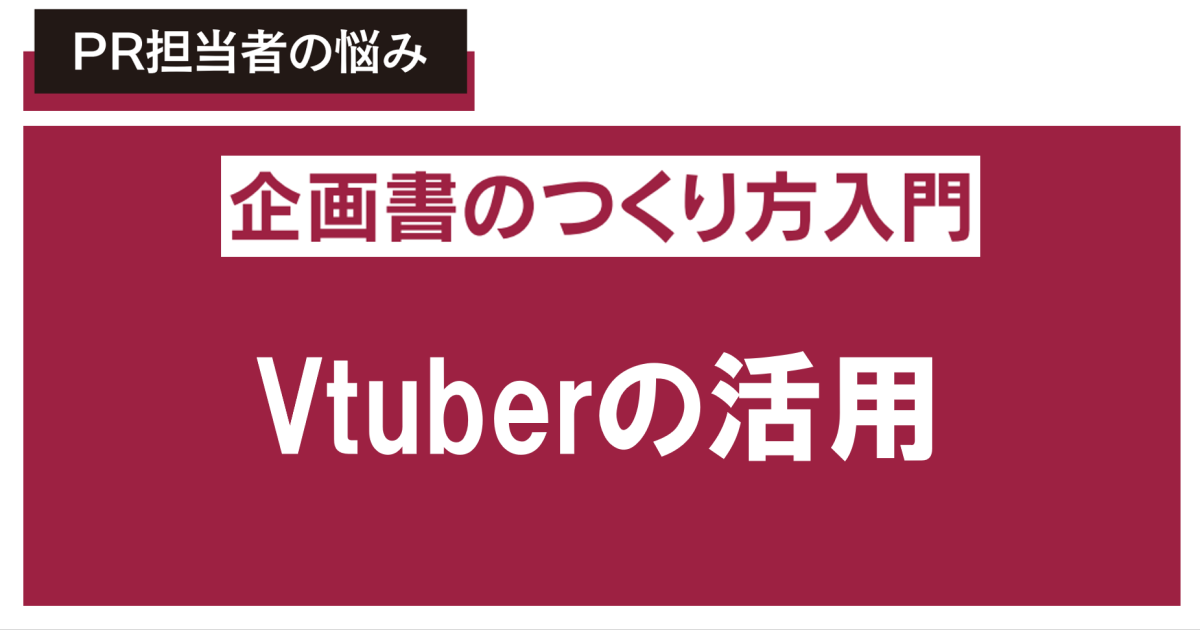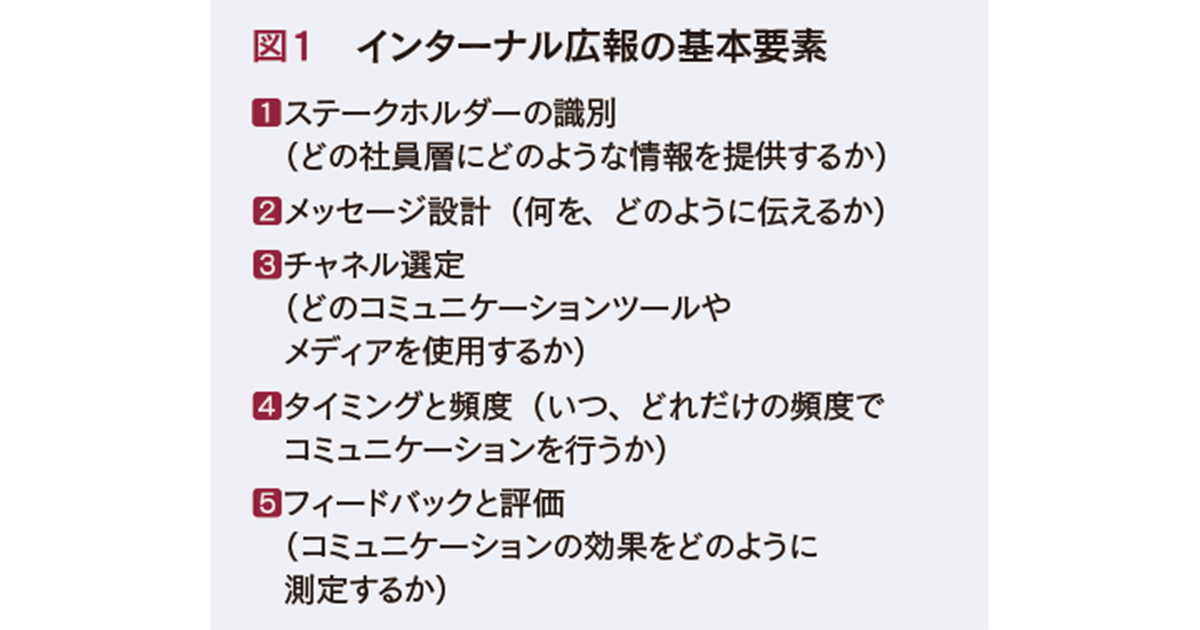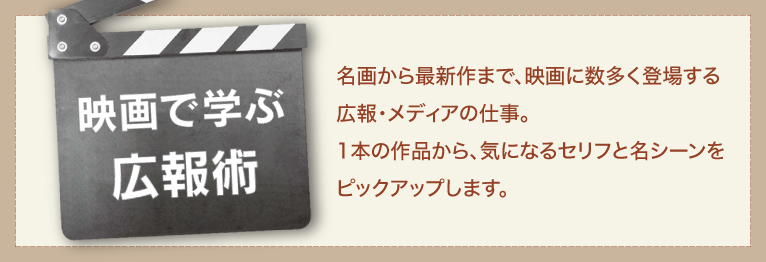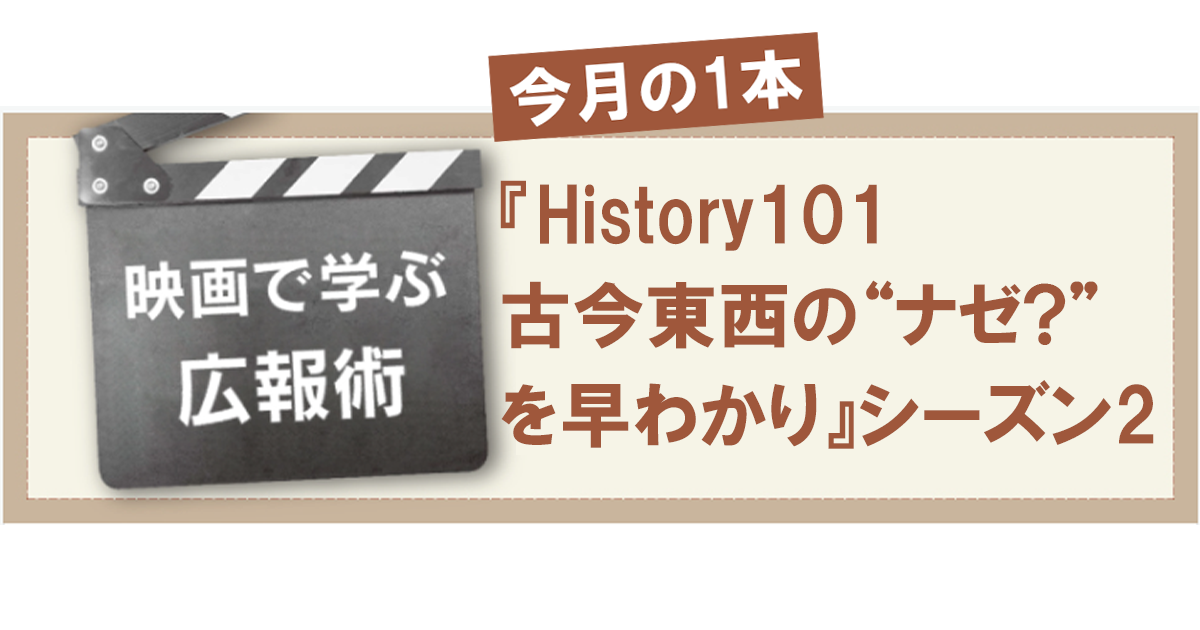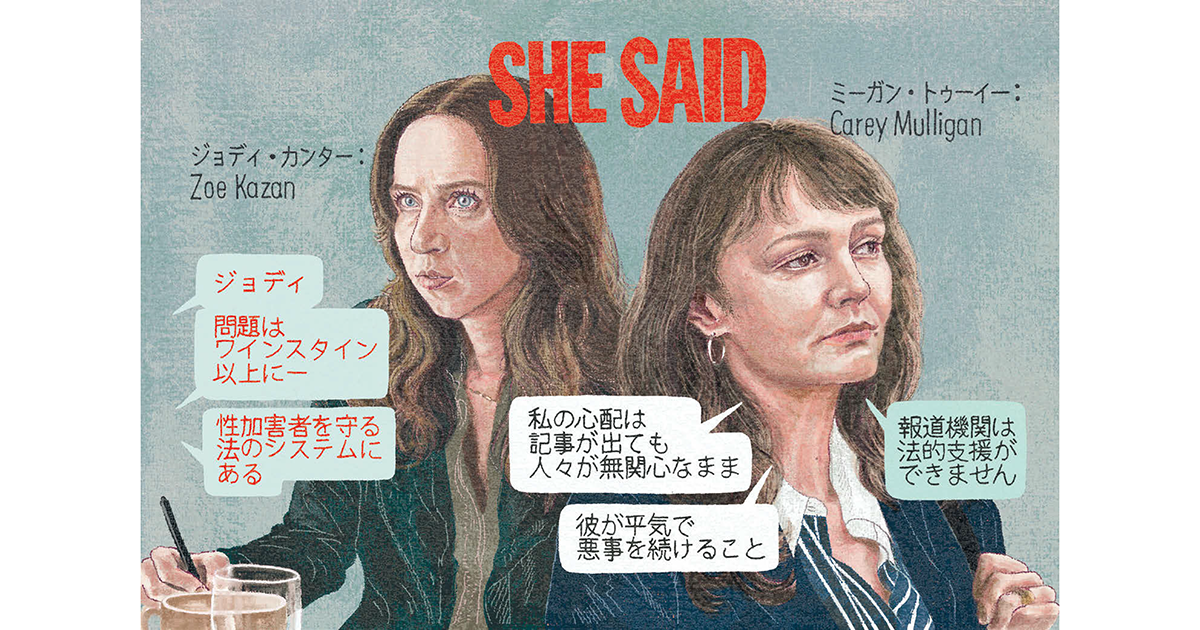今回から、佐賀県の有田焼創業400年事業における海外への発信や国内マーケットの需要喚起策などから、地域活性のヒントを探ります。

有田焼の発祥は江戸時代初期。文禄・慶長の役の際、佐賀藩主の鍋島直茂公が連れ帰った朝鮮陶工の一人、李参平が現在の佐賀県有田町にある泉山で良質の陶石を発見し、1616年に日本初の磁器として生まれたと言われている。
はじめまして。今回から5回、このコーナーを担当することになりました、佐賀県有田焼創業400年事業推進グループのリーダーを務める志岐宣幸です。皆さん、有田焼のことはご存知でしょうか。
有田焼は県を代表する地場産業です。その歴史は古く、1616年に誕生。17世紀半ばから18世紀にかけてオランダ東インド会社により遠くは欧州まで盛んに輸出され、その白い輝きで王侯貴族たちを魅了しました。国内向けは高級割烹食器を中心に、戦後の経済成長によって需要が伸びていきます。しかし1990年代初め、日本経済の崩壊とともに売上高は激減。年々減少を続け、今日では最盛期の6分の1にまで落ち込むなど、大変厳しい状況に直面しています。時代とともに陶磁器という産業を取り巻く環境が大きく変化する中で、市場の需要を喚起できなかったことが要因です。
次の100年に向けた礎を
今年創業400年を迎えた有田焼ですが、遡ること3年半前の2013年4月、佐賀県に有田焼創業400年事業を担当する専任組織(当時は4人のチーム)が立ち上がり、私がリーダーとなりました。有田焼に関わるのは今回が4回目です。1989年に県立窯業技術センターの整備を担当して以来、「世界・焱ほのおの博覧会」の開催、産地再生支援事業の立ち上げと有田焼の振興事業に携わってきました。
これまで創業300年の節目には陶祖・李参平の記念碑を建立したほか、創業350年を機に焼き物専門の美術館「佐賀県立 九州陶磁文化館」の開設といった取り組みもありました。今回は有田焼を産業として再生させ …