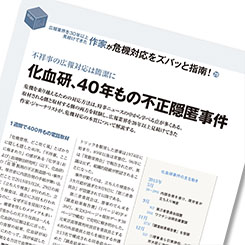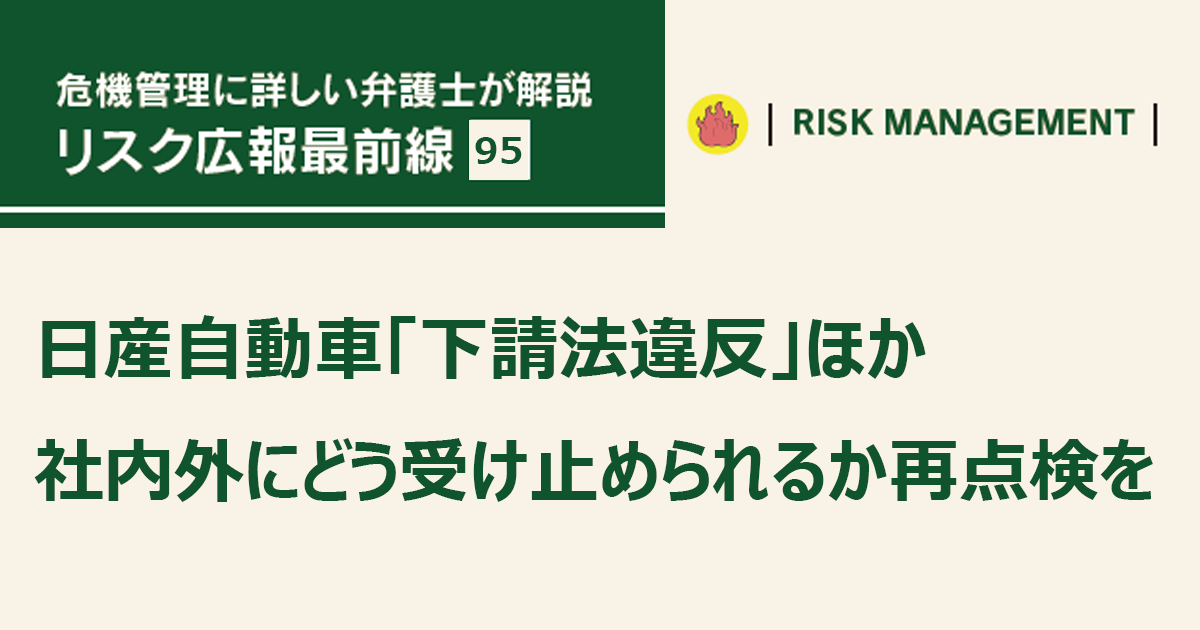広報業界を30年以上見続けてきた作家・ジャーナリストが時事ニュースの中から特に注目すべき事案をピックアップ。事件の本質と求められる広報対応について解説する。

FotograFFF / Shutterstock.com
「社内広報誌は、『社員のコンプライアンス意識』をどこまで変えられるか」「広報に社内不祥事を抑止する力はあるか」
これが、今回のテーマだ。三菱自動車(以下、三菱自)の広報が「当社製車両の燃費試験における不正行為について」と題したプレスリリースを発表し、社長が会見して不祥事が明るみに出たのは、4月20日のことだった。
そこに至るまでの細かい経緯は、別表に記したが、大ざっぱにいうと2015年11月に共同開発相手の日産自動車から「届出数値と実験データの数値が違う」との指摘を受け、内部調査した結果、データ偽装が事実と判明。リリース発表となったのだが、その間、半年。開発担当副社長に報告があったのは4月12日、社長が知ったのは翌13日で、情報伝達スピードが遅く、そこから広報発表までさらに1週間も過ぎている。慎重を期したい気持ちは分かるが、「事実把握から発表に至る間の迅速性が欠如」しており、「危機管理」としては失格だ。
再犯企業の欠陥とは
報道によって、一連の三菱自の「燃費偽装事件」について初めて知ったときの世間の反応は、以下の2種類だった。
「まさか!?」「やっぱり!」。同社は、過去に2度(2000年、2004年)も「リコール隠し」をし、その都度、メディアや世間の激しいバッシングにさらされ、企業存亡の淵に立たされているので、「まさか!?」という反応が圧倒的だった。「あれほど痛い目に遭いながら、まだ懲りていなかったのか」という驚きと失望の声である。一方、「やっぱり!」と思った人は、心のどこかで「あの三菱なら、やりかねない」というマイナスの企業イメージを持っていた人だ。
「企業犯罪」に対するメディアや世間の目は極めて厳しい。再犯ともなれば、なおのことだ。単純比較はできないが、法務省がまとめた「平成26年版 犯罪白書」によれば、窃盗の前科が3回以上ある者の「再犯率」は40%近い。何度刑務所にぶち込まれても改心しない犯罪者が多いということだ。若者と老人とでは、老人の再犯率の方が高い。その点 ...