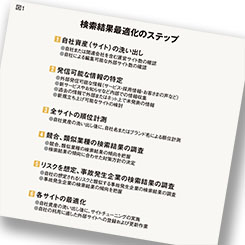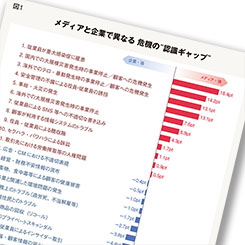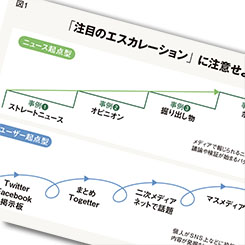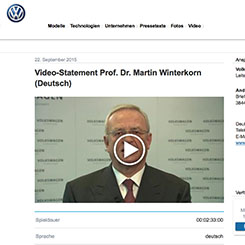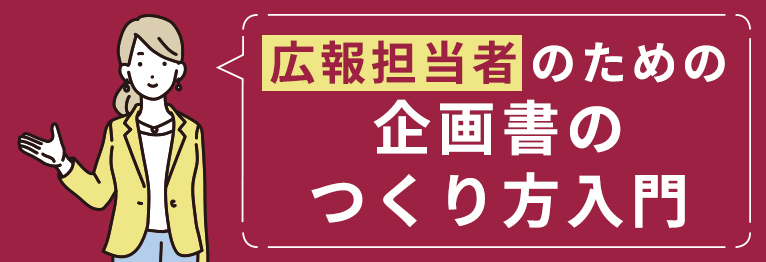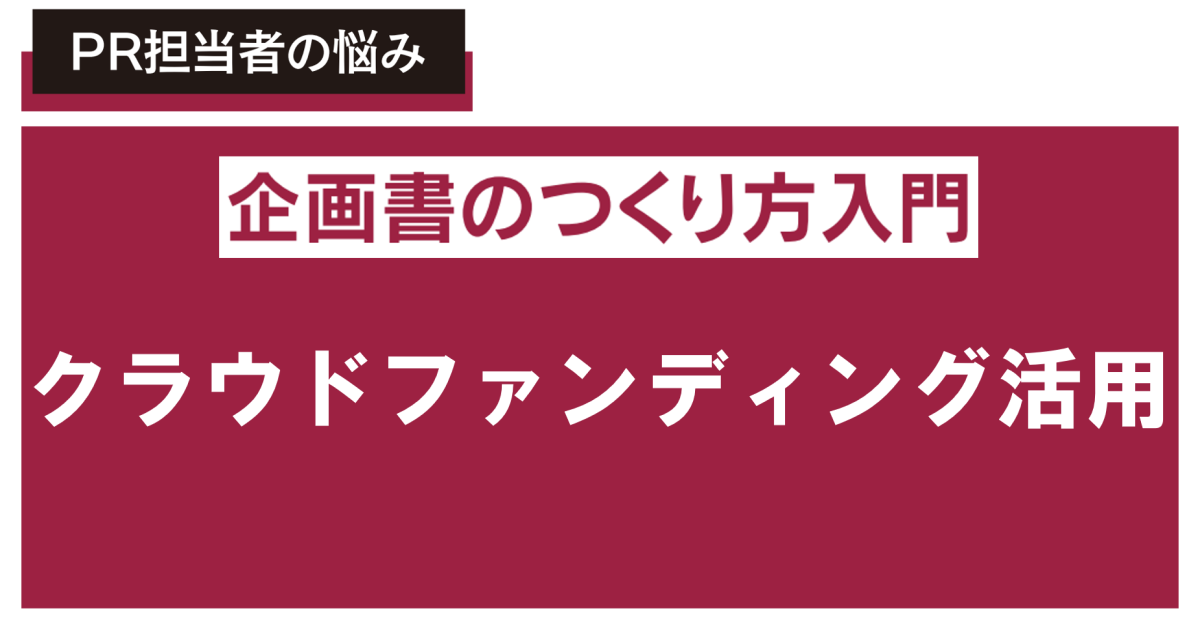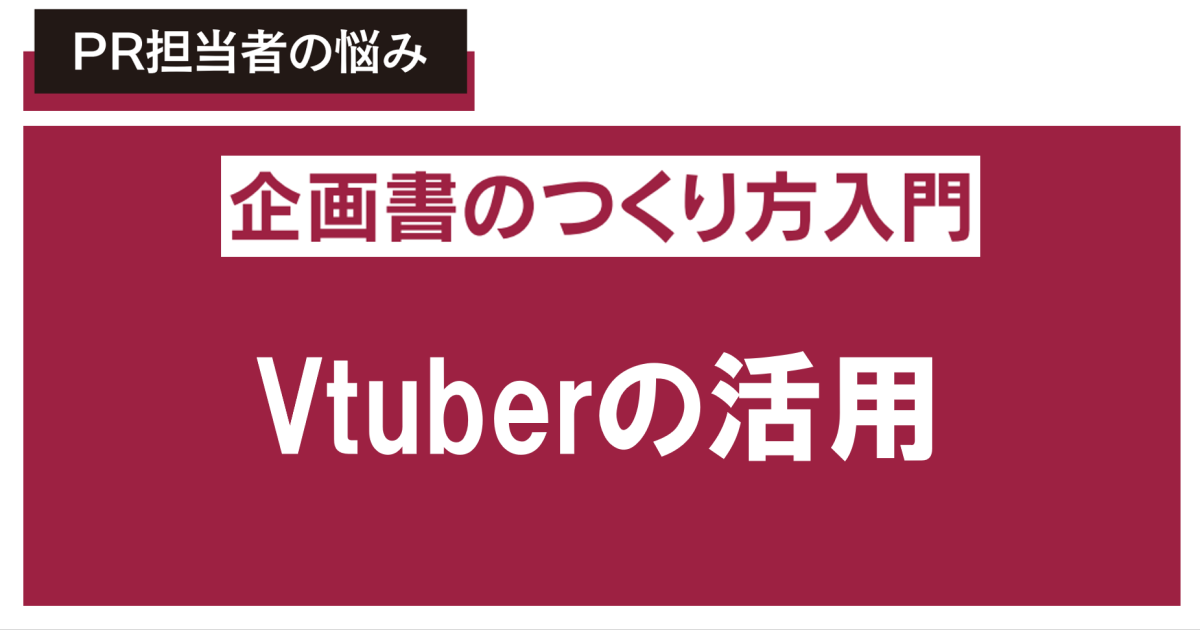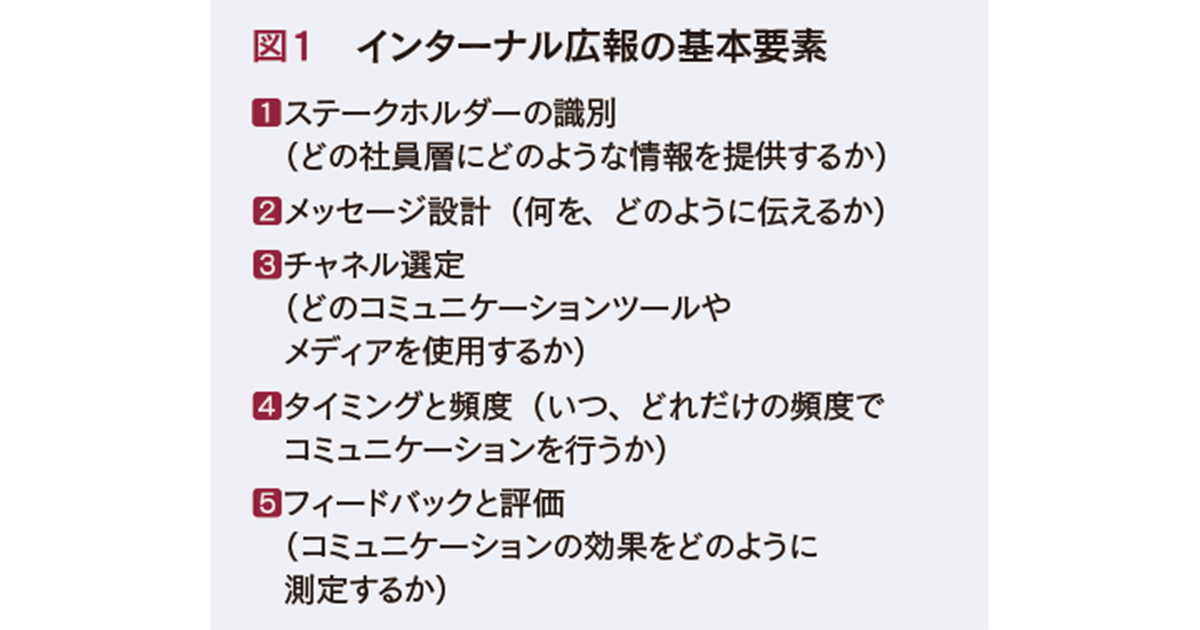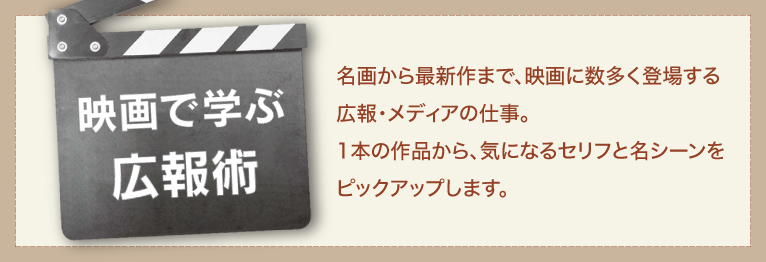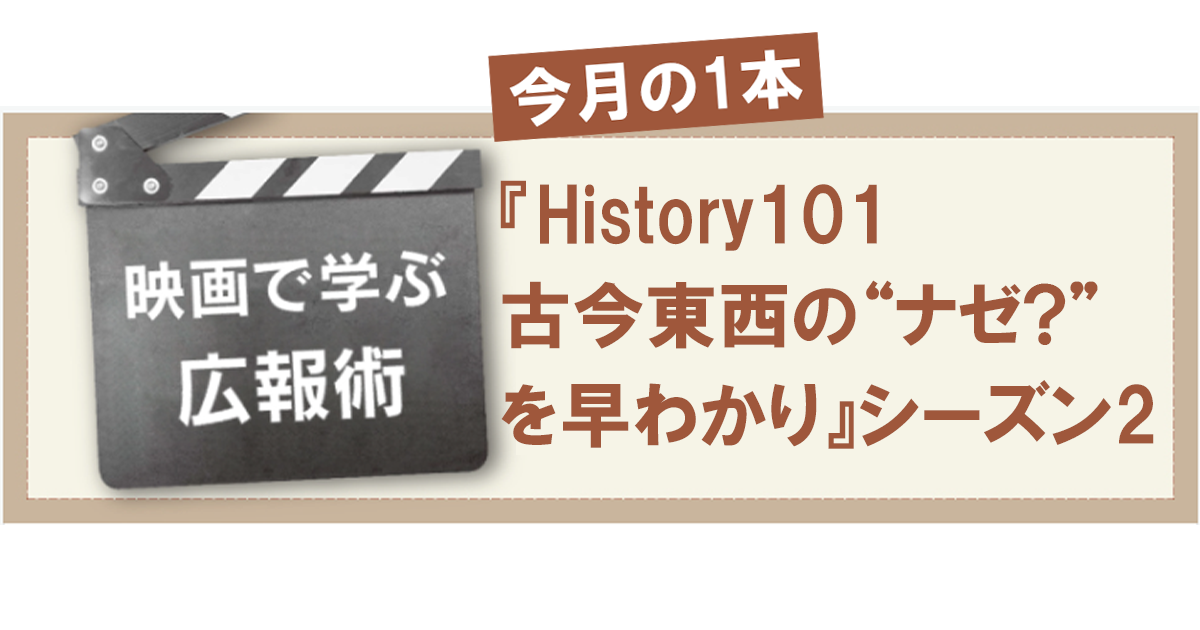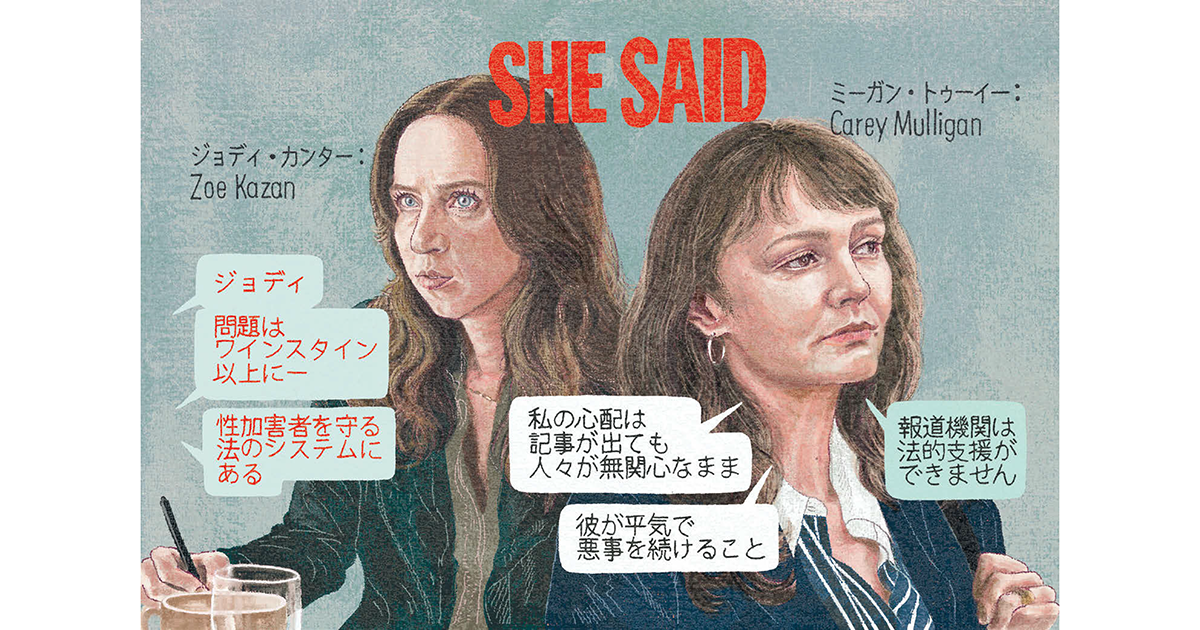なぜ、あの企業は社会の批判を浴びたのか――。大手、BtoB、外資系など2015年に発生した様々な不祥事について、広報、危機管理など9人の専門家に解説してもらった。
CLOSE UP
2007年の教訓生かせず 広報は経営のドライバーであれ

2013年3月、社長就任時の信木明前会長(写真右)。「企業力を高める」を経営のキーメッセージに据えていたが、問題は繰り返された。一連の問題を受け、7月1日付で辞任した。
東洋ゴムと言えば、2007 年の耐熱パネルの偽装が記憶に新しい。これに続いて二度目の不祥事に、専門家からは「過去の失敗を教訓にすることができなかった」との批判が集まった。
佐々木政幸氏は「前回の隠ぺいに懲りず同じことを繰り返すことは、内部牽制の作用がまったく機能していない証左だ」と指摘。「間違った方向に流され、言われるがまま対応を行う広報は広報ではない。公表時期や公表スタンスを正す意志を持つことも広報に求められる資質である」とし、危機の時こそ広報が経営のドライバーになるべきと主張した。
また、城島明彦氏は「東洋ゴムは優良企業だったが、『叩けばホコリの出る企業なのか』と疑われてしまった点は、取り返しがつかない。広報は針のむしろだろう」と、信頼回復への道のりが厳しいものになると予測した。
※分析にご協力いただいた専門家:ACEコンサルティング・白井邦芳氏、郷原信郎弁護士、フライシュマン・ヒラード・ジャパン代表・田中愼一氏、アズソリューションズ代表・佐々木政幸氏、弁護士ドットコムニュース編集長・亀松太郎氏、エイレックス代表取締役社長・江良俊郎氏、ジャーナリスト・城島明彦氏、日本アンガーマネジメント協会代表理事・安藤俊介氏、弁護士・浅見隆行氏
 |
危機管理コンサルタント 白井氏はこう見る
|
会長、社長ら常勤取締役5人が辞任する事態となった免震ゴム偽装問題は、途中公表経過でモタモタした感は否めなかったが、役員報酬の一部返上、賞与の全取締役不支給などに加えて、経営陣の大掛かりな刷新を経て、一定の事態の鎮圧に成功したかに見えた。
しかし、その後も不正製品の出荷が発覚し、調査能力の限界を露呈、本事案の根の深さを改めて知らしめることになる。不正事件の調査の過程で新たに不正を発見してしまう事例は、危機管理の問題ではなく …