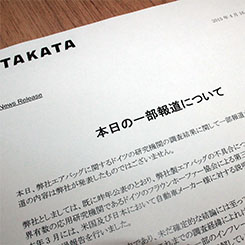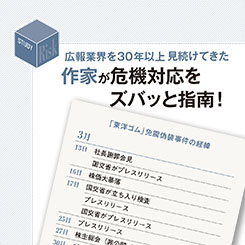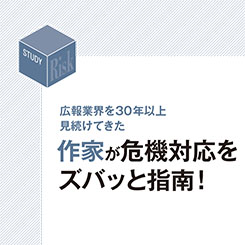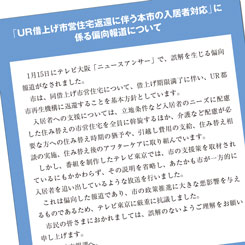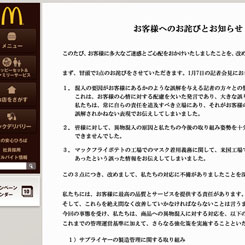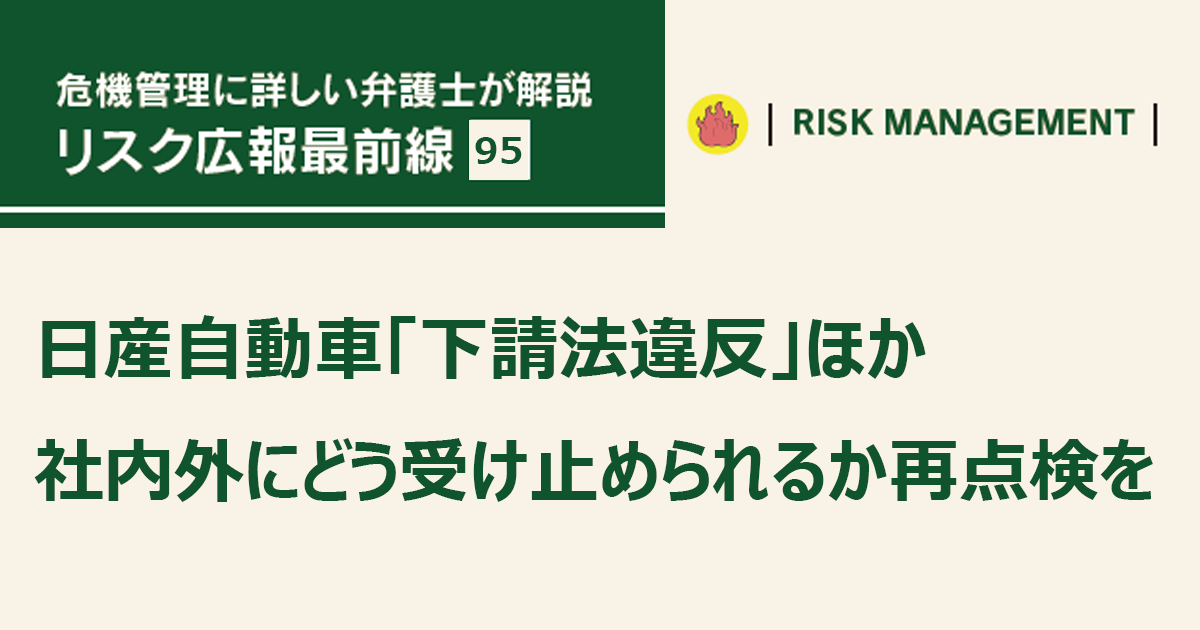危機を乗り越えるための対応方法は、時事ニュースの中から学べる点が多くある。取材される側と取材する側の両方を経験し、広報業界を30年以上見続けてきた作家・ジャーナリストが、危機対応の本質について解説する。
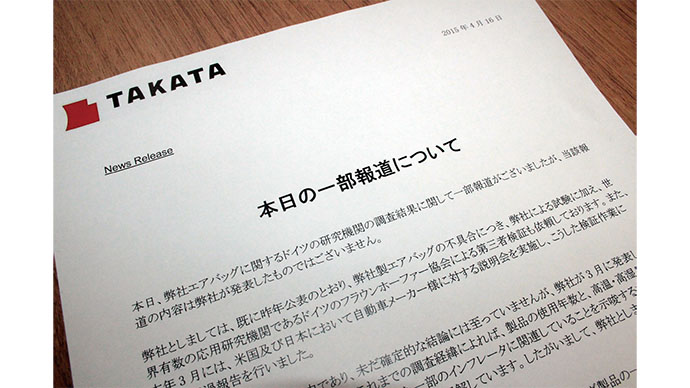
報道の火消しを狙ったタカタのプレスリリース
読売新聞の報道を受け、タカタが発表した4月16日付のプレスリリース。「一連の報道は当社が発表したものではございません」とし、火消しに走ったものの、この後もメディア各社は続報を続け、世論の高まりは収まらなかった。
“技術立国”日本の安全神話が揺らいでいる。国土交通省自動車局が4月10日に発表した6枚綴りのプレスリリース「平成26年度のリコール届出件数及び対象台数について」には、メーカーが届け出たリコール(回収・無償修理)総数は約956万件で過去最高と記されていた。そうなった主な理由は2つ─50万件超の届出が5回もあったことと、「タカタ製欠陥エアバッグ」によるリコールの届出をした車(輸入車も含む)が約220万台に達したからだった。
だが、これはあくまでも国内に限った数字。舞台を世界に広げると、「タカタ製欠陥エアバッグ」を搭載したリコール車の3月までの累計は、不具合の原因が判明していなくてもメーカーが自主的に回収・無償修理する「調査リコール」(全数回収調査)も含めると、事件が表面化した2008年以降、日本メーカーだけで2000万台を超えている。
中でもホンダは、タカタにエアバッグの開発を依頼した関係もあり、半数の車に同社製エアバッグを搭載しており、それに小型ハイブリッドカー「フィット」の度重なるリコールが加わって売上を圧迫する事態に発展、「技術のホンダ」の企業イメージを大きく損なった。
不祥事企業トップの「説明責任」
当のタカタはというと、広報が2015年3月期(前期)の連結決算発表を5月8日にセッティングし、経理・財務担当の執行役員が説明にあたった。米国では、タカタ製欠陥エアバッグの破裂事故で5人の死者が出て訴訟に発展、上院・下院の聴聞会に喚問されたこともあって、メディアは“問題企業”の決算に大きな関心を寄せていた。NHKも「リコール関連費用として556億円の特別損失を計上、赤字に転落した」などと詳しく報道したが、肝心の高田重久会長兼社長は顔を出さず、「逃げている」「考え方が甘い」と批判された。メディアのなかには、「『自動車メーカーが主役であって、部品メーカーは脇役。縁の下の力持ちのような地味な存在』とする考え方がCEOや広報にあるのではないか」と見る向きもあるが、不祥事を起こした企業のトップには「説明責任」があり、逃げ隠れして済む問題ではない。
発表すべきことを発表しない罪
国交省のリコール集計発表から6日後の4月16日 …