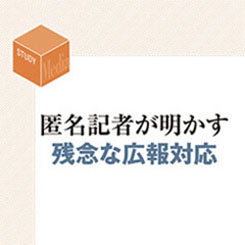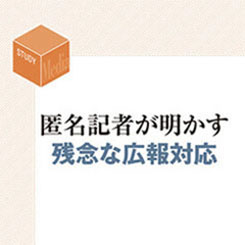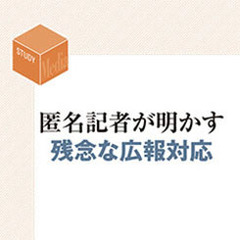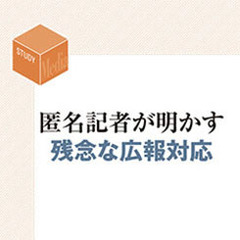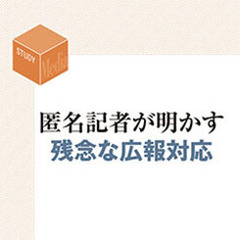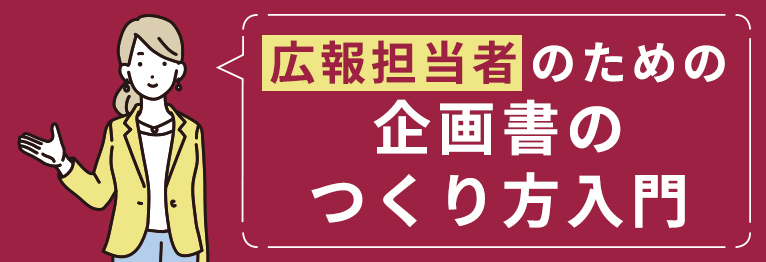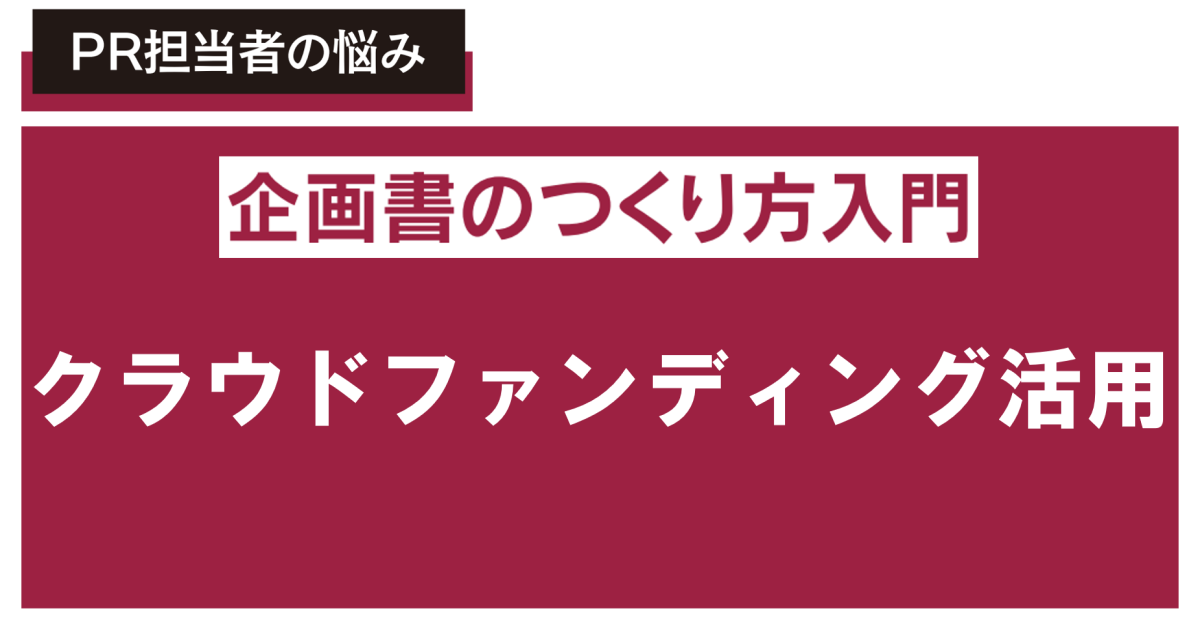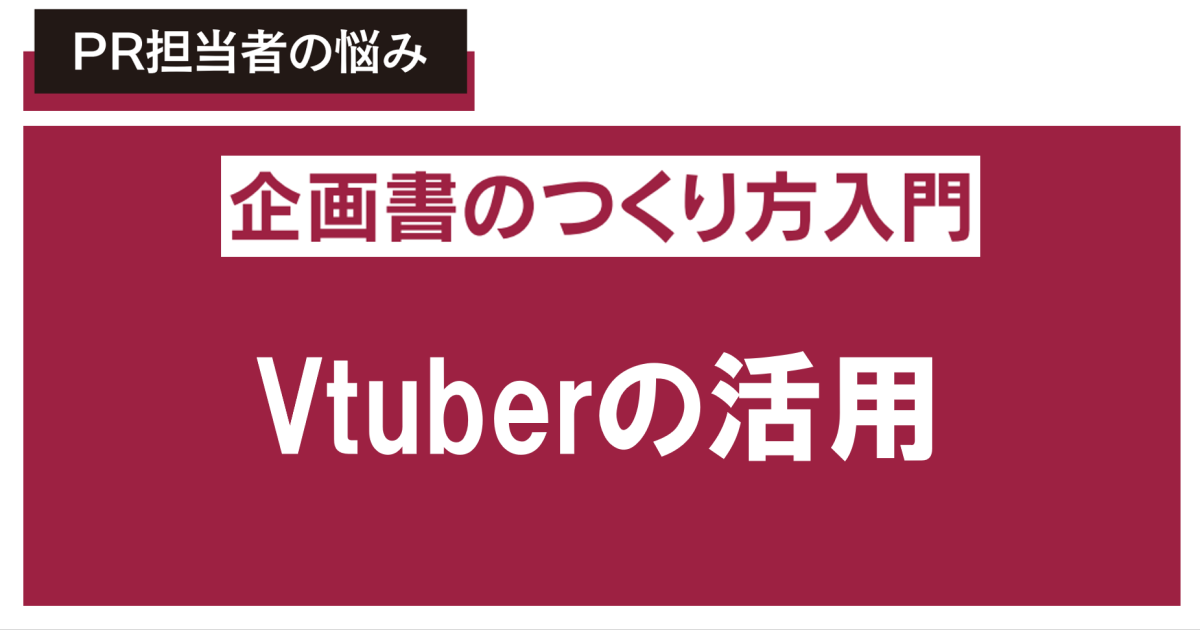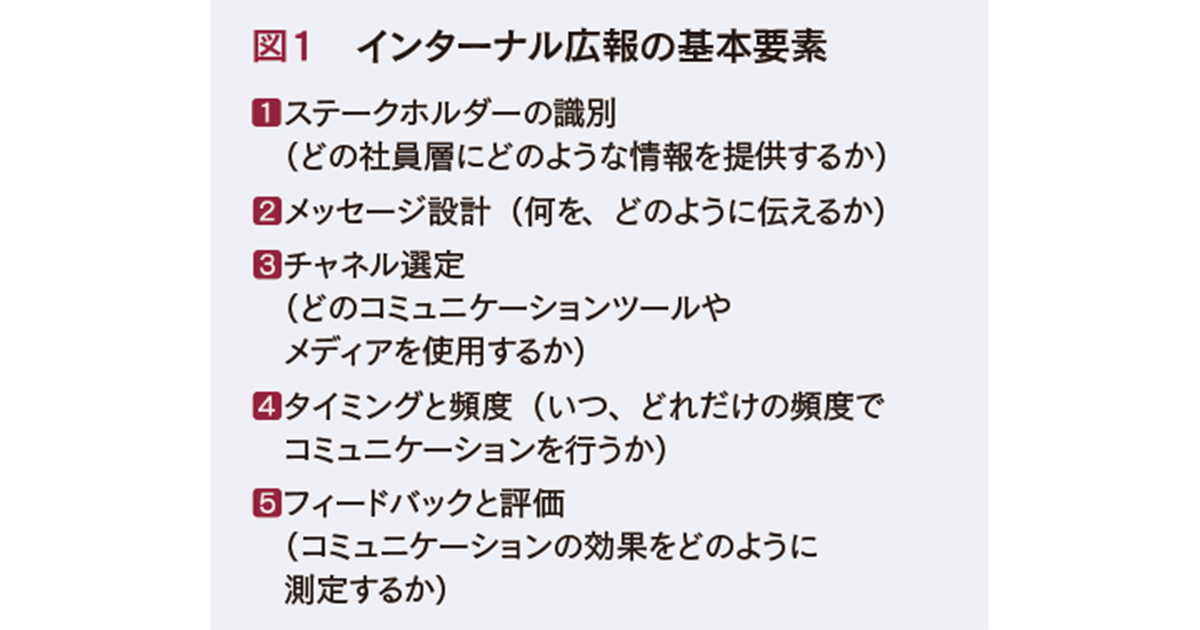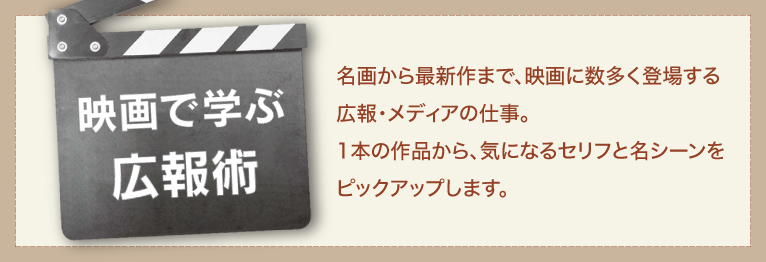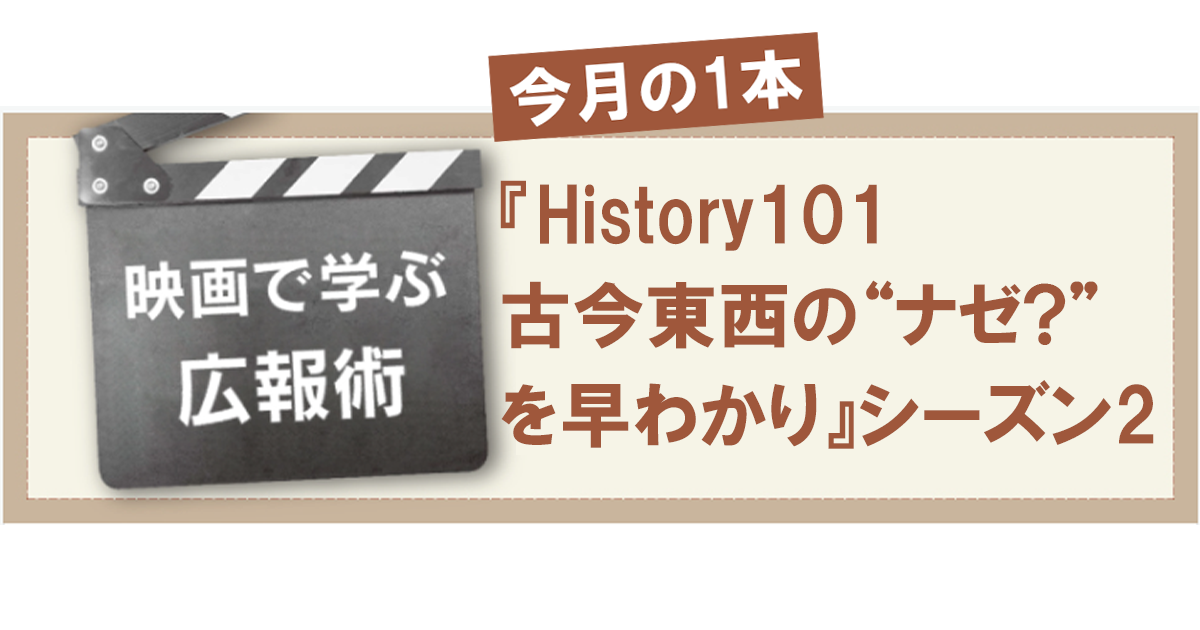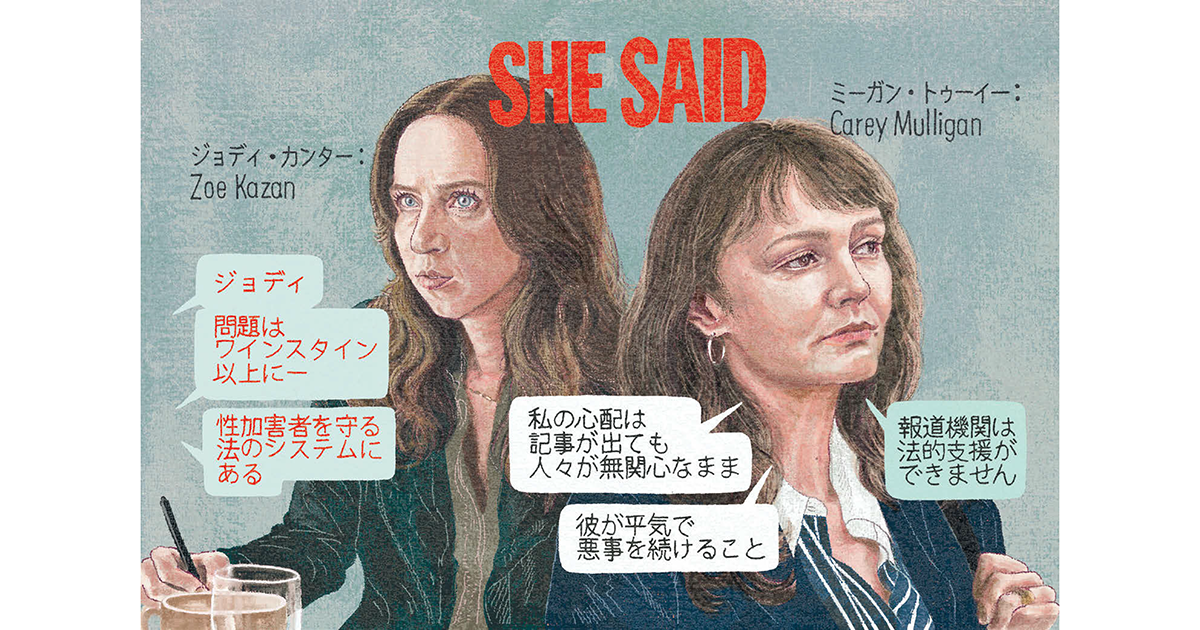記者と広報は、なぜすれ違う?第一線で活躍するメディアの記者に本音で語ってもらいました。
 |
ウェブメディア 記者 Mさん(男性)その幅広い知識と経験から、バズ系のネタから真面目な話題まで、なんでもござれのスーパー記者。たまの休みに近所を散策し、好みの猫を見つけるのが癒しだとか。最近は、地方関連のネタにも関心が高い。 |
聞けなかった「過去の失敗談」
それは某メーカーの開発担当者へのインタビューだった。新商品がネットでもたびたび話題になる、大手の企業。ヒットを生み出す開発陣の生の声を紹介したいと思い取材を申し込んだ。
窓口の担当者は、ロングセラー商品の説明、新商品の特徴など、取材できそうな項目を挙げてくれた。
しかし、聞きたかったことは、そういった類いのものではなかった。私が読者に紹介したかったこと、それは「過去の失敗」だった。
なぜ「失敗」か?それは、メーカーとしては発信しにくい情報だと思ったから。たとえ、そのメーカーが自社サイトの特設ページで失敗談を含む開発秘話を掲載したとしても、それはあくまで公式見解。メディアによって伝えられる情報とは、性格がまったく異なる。
私がそのメーカーに取材をお願いした理由は、記者として、そのメーカーの取り組みに意義を感じ、多くの人に知ってもらいたいと思ったからだ。逆説的だが、そのためにはメーカーの欠点が必要だった。読者に説得力をもって伝えるには、ネイティブ広告を書く編集プロダクションにも、メーカーのオフィシャルサイトにある商品紹介にもない、「何か」が必要だった。
担当者は検討を重ねてくれたが、結局、「企業秘密」ということで触れることはできなかった。結果的に、記事の内容は通り一遍のものになり、掲載したウェブ媒体での数字も伸びなかった。
対照的な例がある。その食品メーカーは、およそ商品にならない試作品も、担当者が半ばネタとして紹介してくれた。また、毎日、同じものを試食する現場の開発担当者が生み出した裏メニューも教えてくれた。それは、本来の商品のコンセプトからはかけ離れた、ブランディングも何もあったものではない食べ方だった。
食品メーカーの記事は意外性をもって受け止められ、ソーシャルメディアなどでも拡散した。印象的だったのは「あの商品の裏にこんなストーリーがあったとは」「定番商品が生まれるまでには、そんな苦労があったんだ」といった感想が多かったことだ。
記事には大きく分けて、「何かを批判する記事」と「何かを応援する記事」がある。
「何かを批判する記事」の場合 …