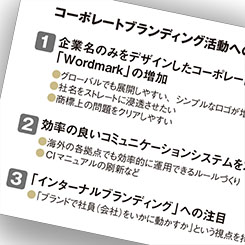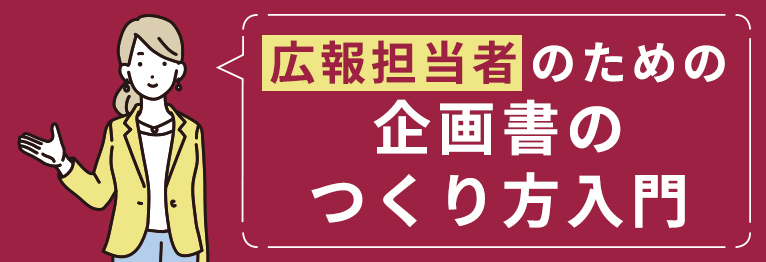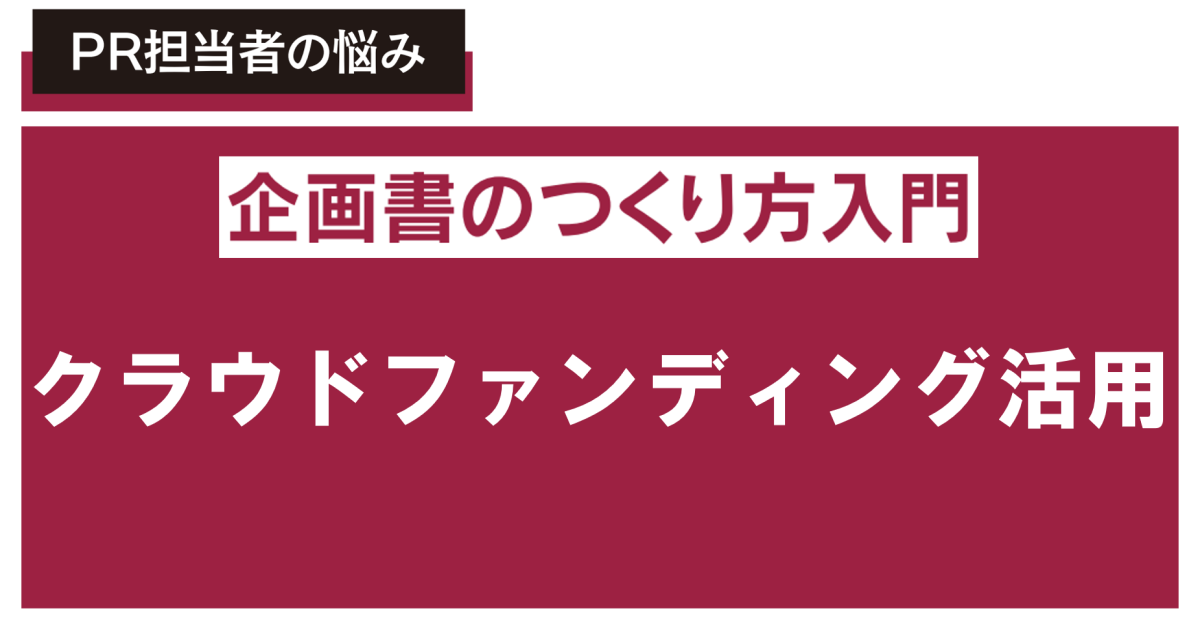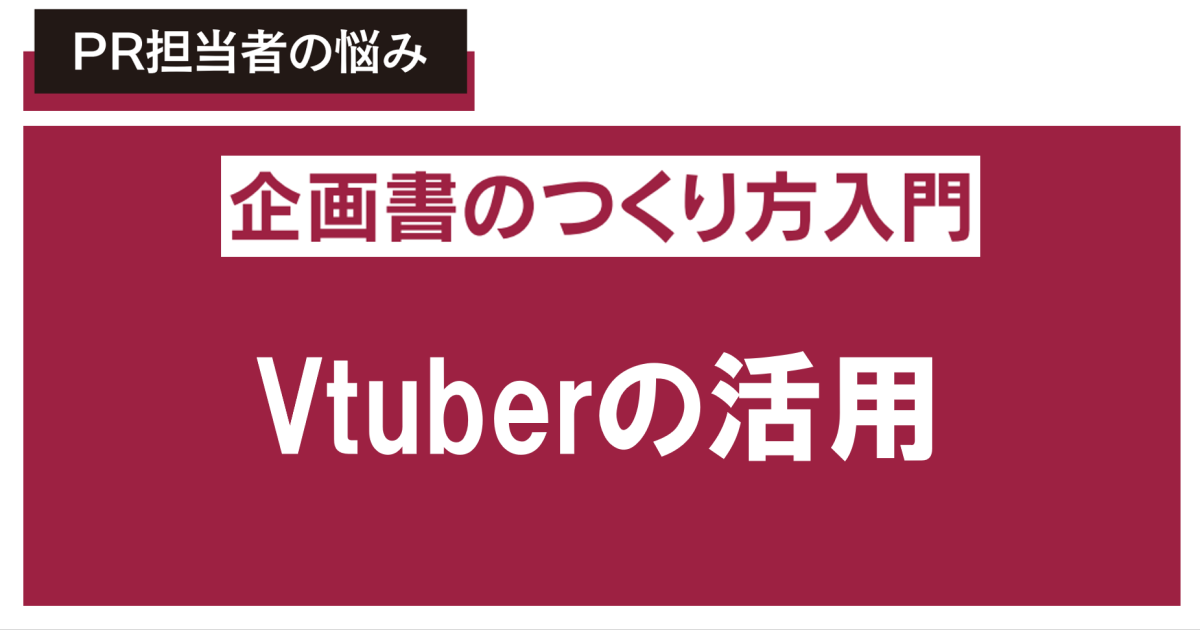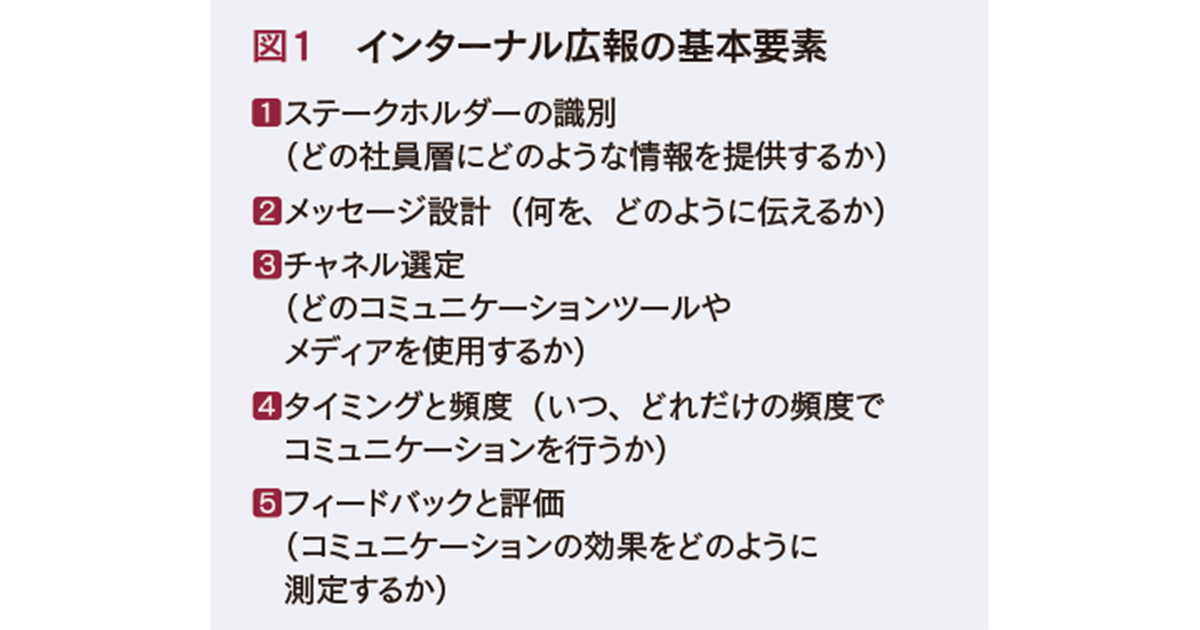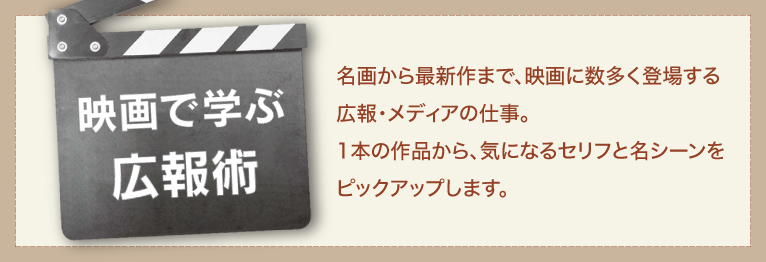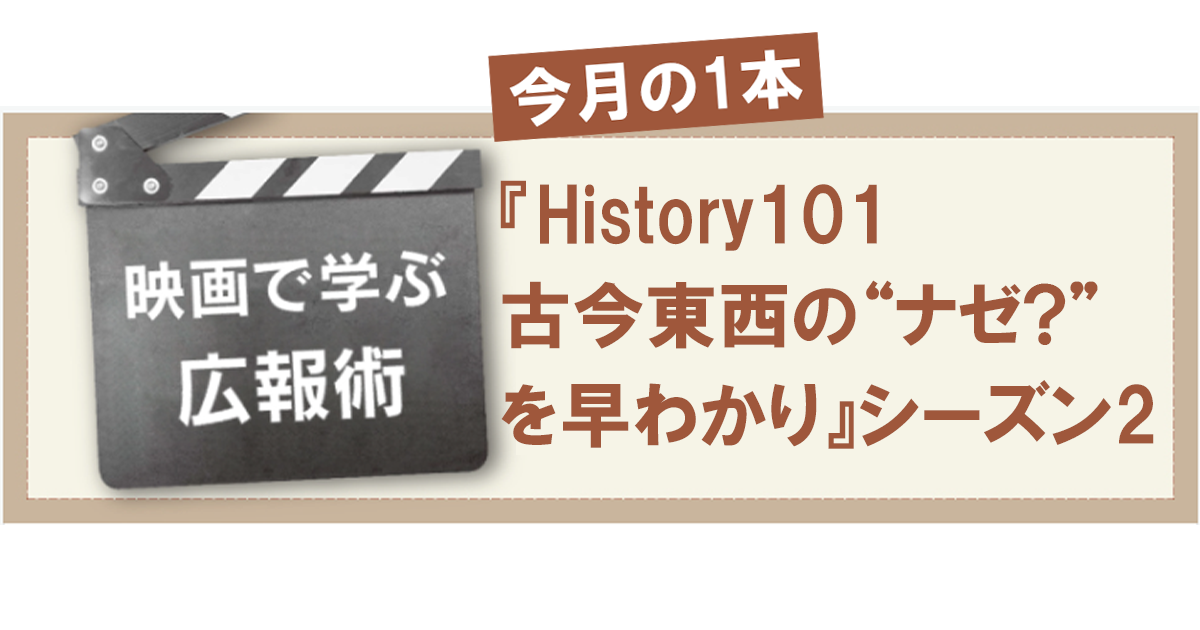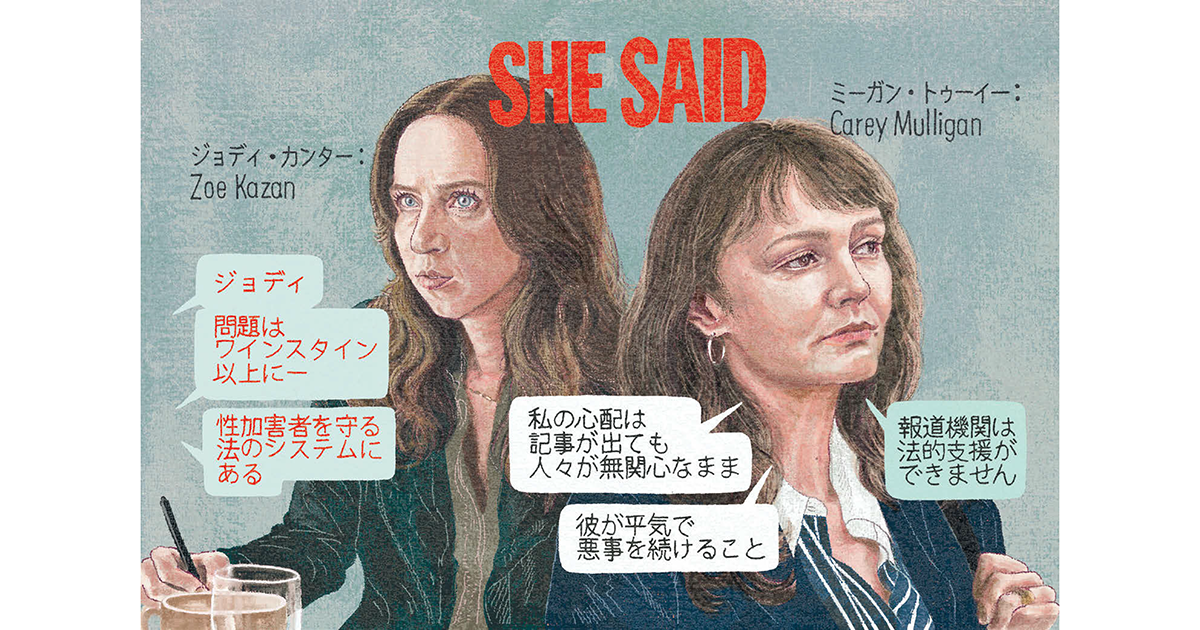現場担当者の悩みに応えるセミナー「社内広報実践シリーズ」。第2回は、「社内広報リニューアル」をテーマに、グループワークを交えた講義が行われた。

セミナーでは、実際に現場で社内報編集に携わる鹿島建設の財部浩司氏(写真左)と、産業編集センターの相山大輔氏による特別対談が実施された。
| プログラム | |
|---|---|
| 14:00~ 14:50 |
第1部 講演「インナーはカスタマーである」 顧客発想で考える インナーの心動かすツールのツボ 博報堂 シニアクリエイティブディレクター 吉澤 到氏 |
| 15:00~ 15:50 |
第2部 特別対談なぜ社内報は読まれないのか? 担当者が陥る課題と解決のポイントを探る 鹿島建設 広報室 次長 財部浩司氏 産業編集センター はたらくよろこび研究所 部長 相山大輔氏 |
| 16:00~ 16:50 |
第3部 講演「よまれる社内報」をつくるための5つのチェンジ 「読まれる」を実現する課題アプローチ法 鹿島建設 広報室 次長 財部浩司氏 産業編集センター「よまれる社内報」事業部 部長 簗瀬太郎氏 |
現場担当者の悩みに応えるセミナー「社内広報実践シリーズ」。4回目となる今回は『読まれる社内報のつくり方』がテーマだ。社員に支持され、愛される社内報づくりのヒントを探った。
2014年11月18日に宣伝会議本社ビルで開催されたセミナーでは、第一部に博報堂 シニアクリエイティブディレクターの吉澤到氏が登壇。昨今、社内広報にもターゲットやゴールを明確にし、効果的に伝わるための手法を工夫するという「広告的発想」が求められていると語る。吉澤氏は「従業員は広報にとっての“顧客”。声に耳を傾け、インサイトを的確に捉えることが大切」と強調した。
第二部では、実際の社内報制作現場の声からその課題や工夫を聞く、特別対談を実施。鹿島建設の社内報『月報KAJIMA』の財部浩司編集長と、産業編集センター はたらくよろこび研究所の相山大輔氏が登壇した。
『月報KAJIMA』は50年以上の歴史を持ち、財部氏を含む4人の編集部員が取材、執筆、撮影などをほぼ内製している。趣向を凝らした特集企画が社内外から好評で、実施したアンケート調査によると、社員の約75%が愛読しているという。
特徴的なのは、社員だけでなく、得意先やメディア関係者など、同社に関心を持つ人にも配布している点だ。財部氏は「社外に誇れることを発信すれば、社内コミュニケーションや社員のモチベーションアップにつながる。毎号時流を意識して扱うテーマを選びつつ、誌面に登場する人の本音や思いが伝わるような取材を心がけている」と語る。これに対し、相山氏は「従業員間のコミュニケーションが希薄になる中、社内広報は注目され始めている。社内報には『月報KAJIMA』のような従業員の感情に働きかける工夫が重要性を増している」と評価した。
第三部では、「『よまれる社内報』をつくるための5つのチェンジ」と題し、産業編集センター「よまれる社内報」事業部の簗瀬太郎氏が登壇。広報が着手すべき改善点について、(1)担当者の意識・視点(2)編集体制(3)編集の重心(4)効果の検証方法(5)つくり方そのもの─を挙げ、編集委員や通信委員との効果的な連携方法や従業員に軸足を置いた編集などについて解説した。
※次回(vol.5)は「周囲を巻き込み、会社をリードする社内広報」をテーマに開催予定です。
お問い合わせ
株式会社産業編集センター http://www.shc.co.jp
〒113-0021 東京都文京区本駒込6-5-3 ビューネ本駒込1F
E-mail.aiyama(アットマーク)shc.jp (担当 相山)