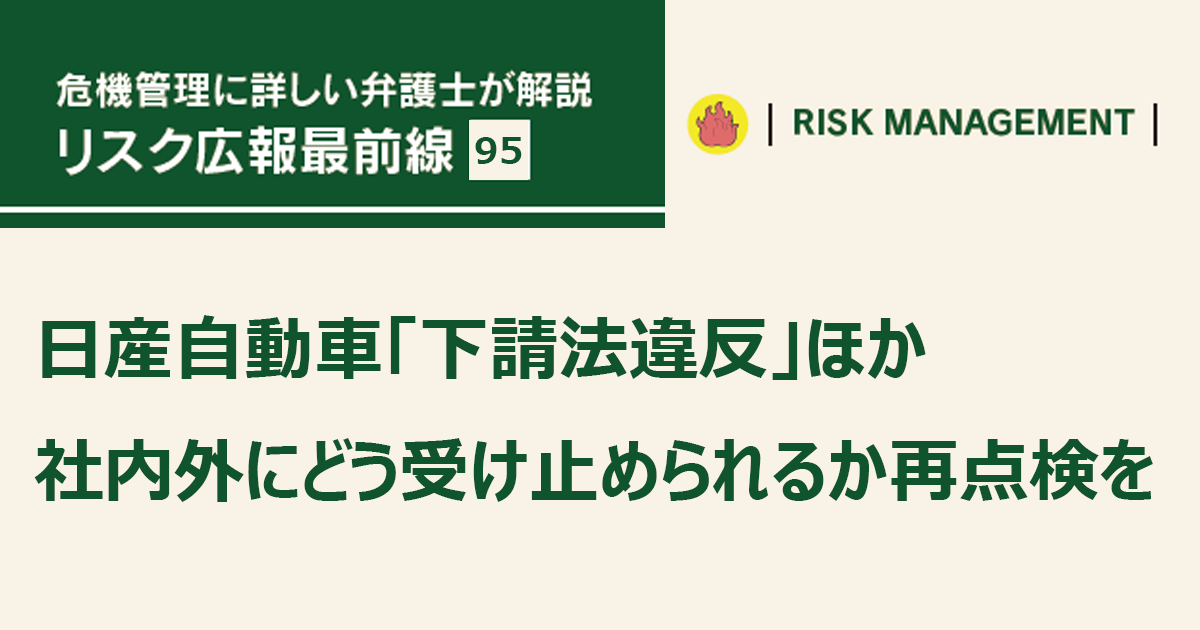あの不祥事は、なぜあれほど世間から批判されたのか─?顧客情報漏えいからフードテロ、取引先・子会社の不祥事まで、2014年の危機管理広報の誤りを専門家と振り返りながら、広報の視点で会社を守り、評判を高めるためのポイントを徹底解説します。
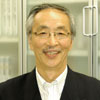 |
労働ジャーナリスト 金子雅臣氏はこう見る
|
企業でも起こりえる問題
6月に発生した東京都議会での「結婚したら」「産めないのか」などの野次騒動では、発言者である議員はもちろん、都議会自民党、議会、舛添都知事までもが、セクハラへの無理解を露呈してしまった。
当事者のセクハラ認識を端的に示していたのは、議員の釈明会見での発言である。彼にとってセクハラというものの認識は、(1)発言した動機は「結婚したらどうか」という悪意のない発言。(2)「産めないのか」などの発言であればひどいと思うが、私はそんなことは言っていない、というものだった。
つまり、彼の認識によれば、セクハラとは(1)発言の動機に悪意があるかどうか、(2)言ったことが下品なものかどうか、で判断されている。
今回の野次は、決してマナーにとどまる問題ではない。まさに女性差別であり、人権侵害であることが問題なのだ。ジャッジポイントを付け加えると次のようなポイントがある。それは、(3)言った人と言われた人の力関係、(4)受けた人の屈辱感の度合い、ということである。
考え方の基本的な違いは、表現された言葉・内容だけに注目するのではなく、その発言の背景に注目するところにある。具体的には、(3)は都議会自民党のベテランでもある議員が初当選の議員に浴びせた暴言である。しかも議会という公的な場所で行われた。(4)は、(3)という状況のなかで反論も許されない、一方的ないわれのない非難を受けた屈辱感である。