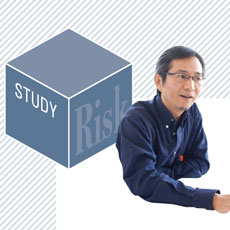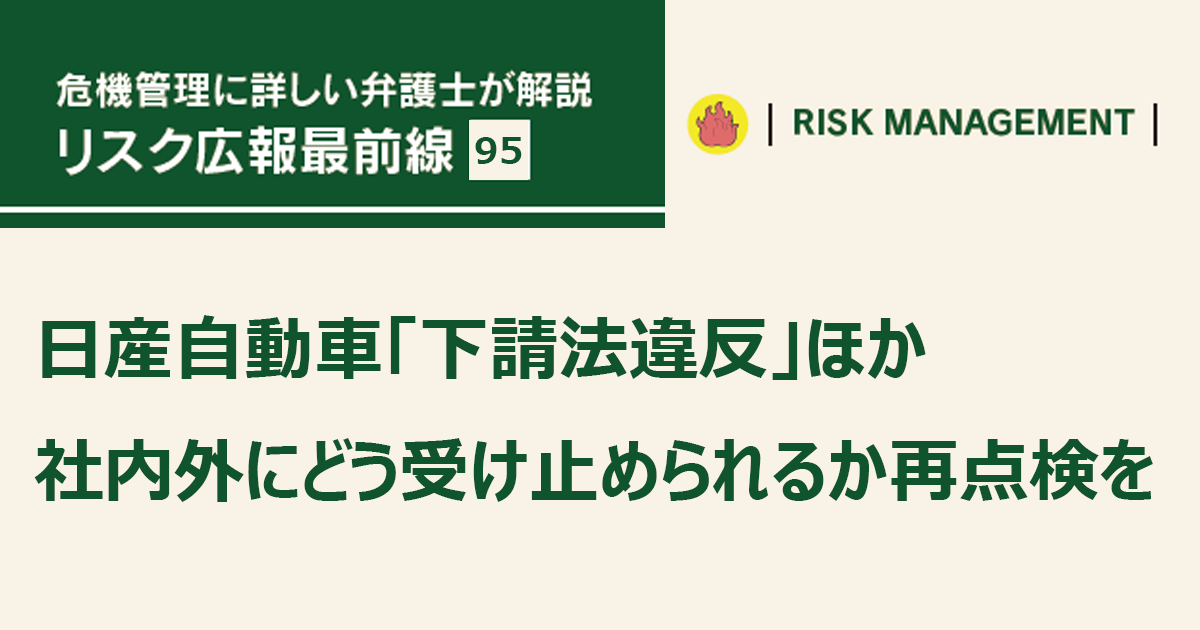危機が発生したとき、その後の広報対応によって世の中に与える印象は大きく変わる。本連載では、ある時はメディアの立場で多くの危機を取材し、またある時は激動の時代の内閣広報室で危機対応を行った経験を持つ下村健一氏が、実際にあった危機の広報対応について説く。

東電福島第一原発事故発生から、3年。あの時、首相官邸の広報が直面した《確かな情報が何も無い中での継続的な広報》という超難問は、国家レベルでも組織レベルでも、いつまた突き付けられるか分からない。その時、あなたが広報担当者だったらどうするか。前号に続き、リアルに問題提起したい。
「不都合隠すな・不確か流すな」
原発事故発生後、当時の首相と官房長官は、大臣達を集めた緊急会議の席上でも、我々官邸内スタッフに対する指示でも、何度も同じ事を言っていた。「不都合な事でも、一切隠さない。ただし、不確かな事は、一切流さない。」―――これが、国家存亡の危機(誇張でないことは前号で述べた通り)に直面してトップが打ち出した、日本国政府広報の大方針だった。
ずっと推進してきた安全神話を覆すようなデータが現れても、経済活動を妨げるような指示の必要に直面しても、「不都合だから黙っていようか」という躊躇は決してせず、隠さずに発表すること。しかし、間違いかも知れない情報を流して(本当の情報を流して、ではなく!)社会をパニックに陥らせることは、絶対に避けること。この2つの広報方針は、当時私も、極めて正しい姿勢だと思っていた。
だが...結果的にこの方針は、本当に正しかったのか? まずは、この最も根本の問いに向き合おう。
とにかく原発事故に関しては、ほとんどが「不確か」な情報ばかりだった。だから、方針に則り「流さない」という状況が、延々と続いた。