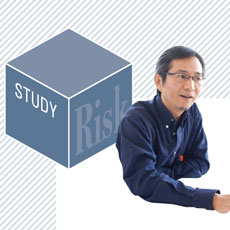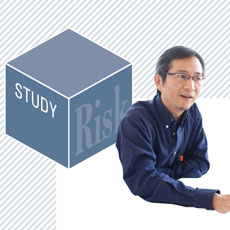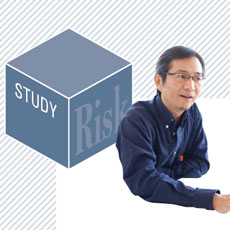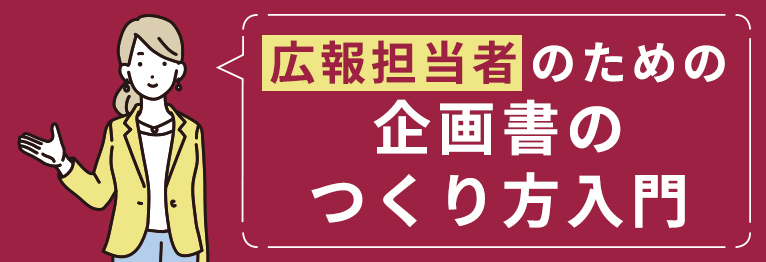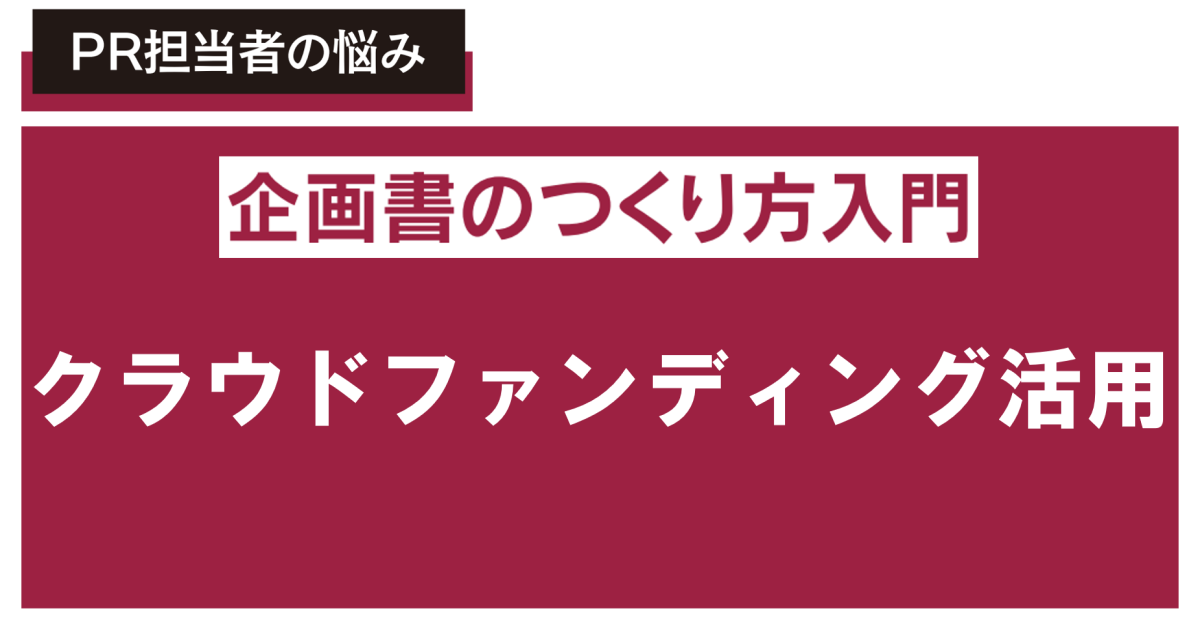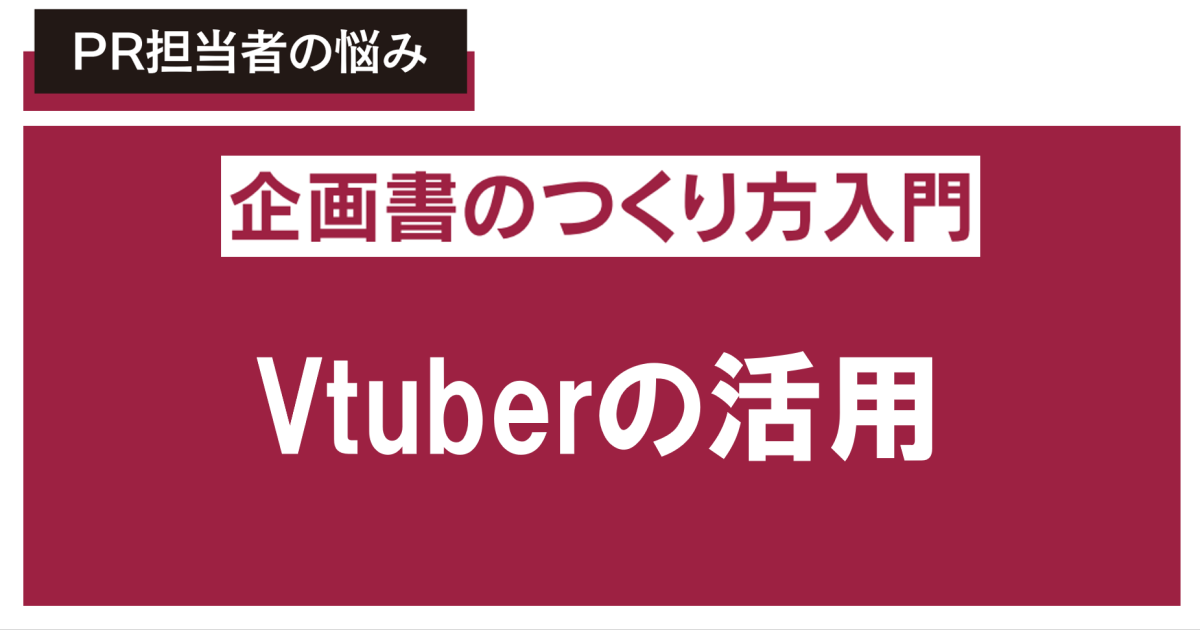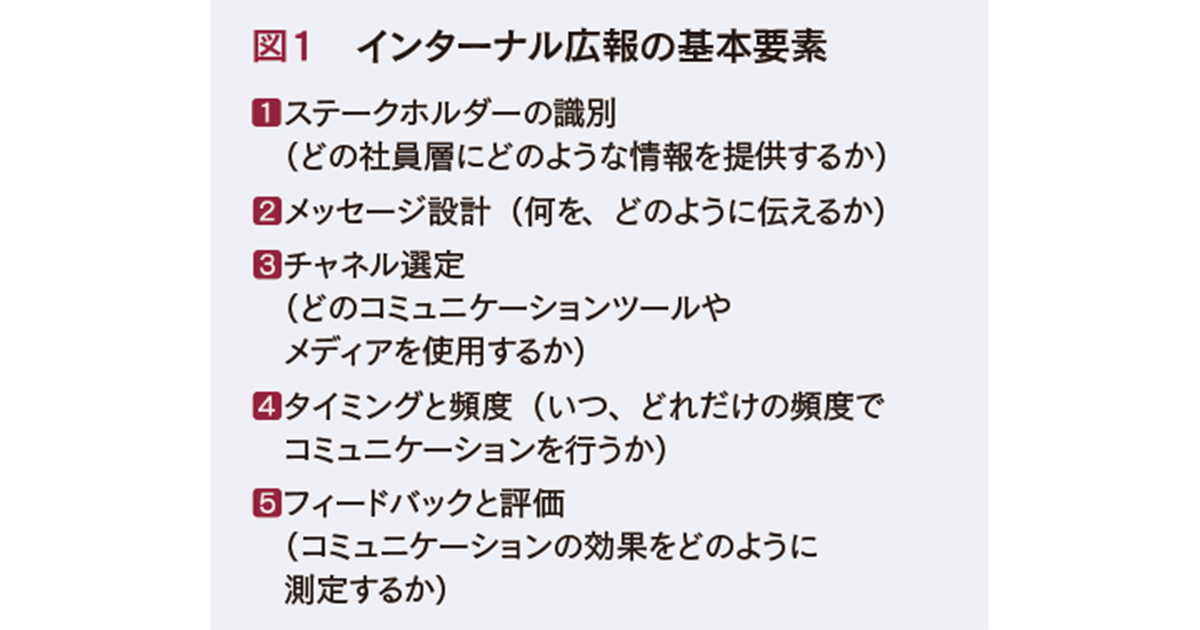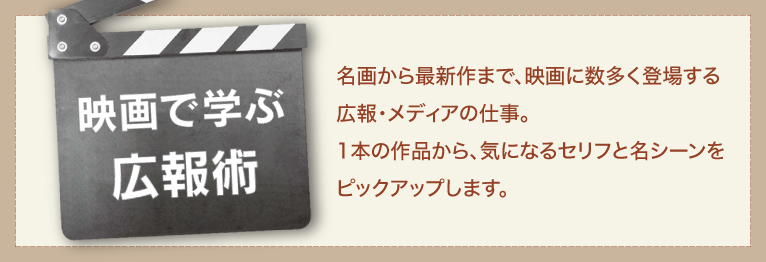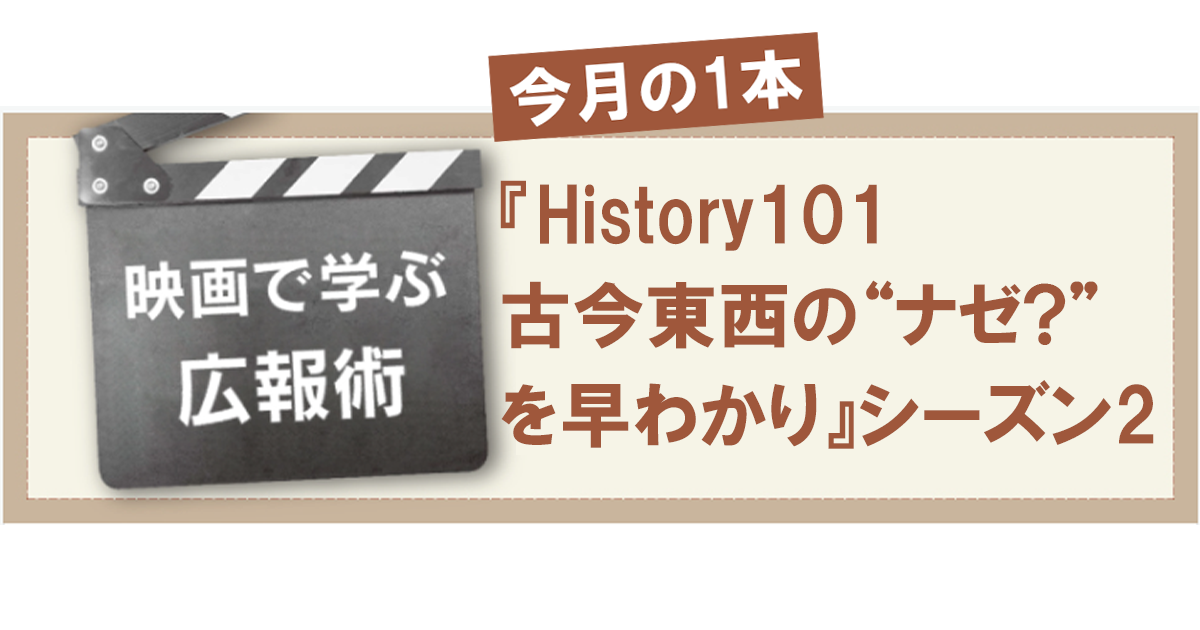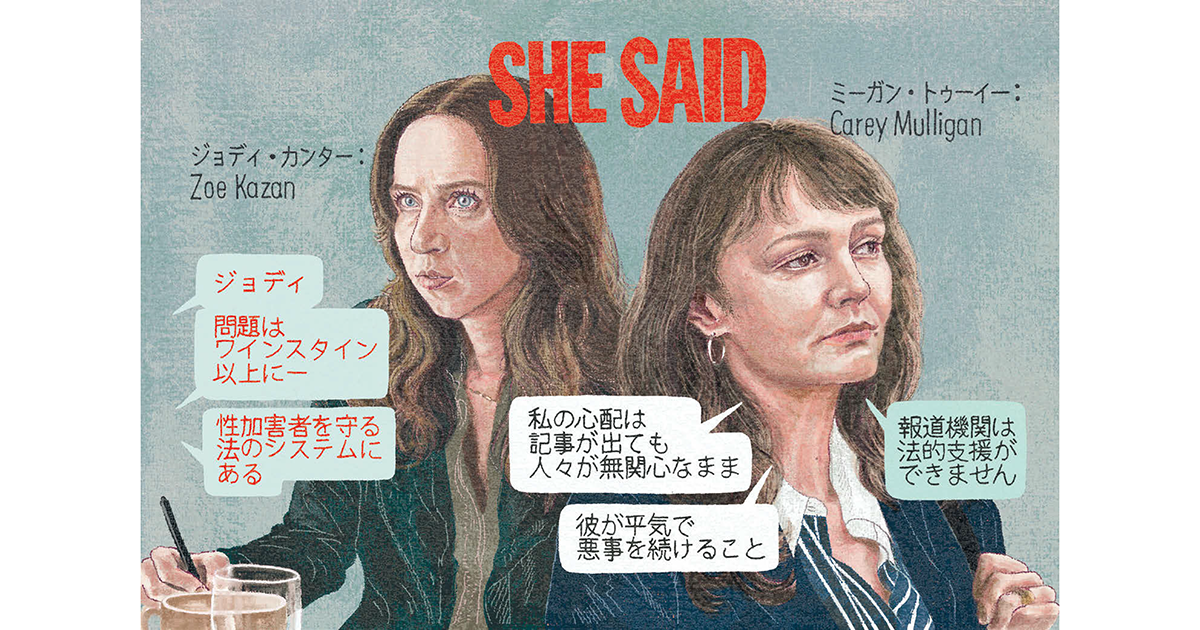危機が発生したとき、その後の広報対応によって世の中に与える印象は大きく変わる。本連載では、ある時はメディアの立場で多くの危機を取材し、またある時は激動の時代の内閣広報室で危機対応を行った経験を持つ下村健一氏が、実際にあった危機の広報対応について説く。

野田佳彦首相による東京電力福島第1原発の"冷温停止状態"の宣言が、"原発収束宣言"として広く世の中に広がった。会見の後、多くのメディアで批判報道が相次いだ。
ちょうど2年前の今頃、野田首相が「原発事故収束宣言」を発した─と、メディアが一斉に報じた。当時、内閣官房という"内側"に在籍していた私の目から見ても、これは民主党政権が犯した原発事故関連広報の最大の失敗の1つだった。誰がどう見ても収束などしていないあの事故について、一国のトップに、なぜあんな発言をさせてしまったのか。その深層心理には、広報という仕事が《一番落ちてはいけない落とし穴》があった。
誤報を誘ったキーワード提供
まずは、あの時の言い回しを正確に再現しよう。2011年12月16日。首相官邸内にあるいつもの会見室で行われた内閣総理大臣記者会見の場で、野田首相は、こう切り出した。
「福島の再生の大前提となるのは、原発事故の収束であります。」...(a)
そして、「原発の外の被災地域では」...(b)、除染・瓦礫処理・避難者の帰宅など、まだまだ課題が多いと前置きした上で、「原発それ自体につきましては」...(c)、安定して冷却水が循環し、原子炉底部と格納容器内が100℃以下に保たれていることを確認した、と説明。その上で、明確にこう宣言した。
「原子炉が冷温停止状態に達し、発電所の事故そのものは収束に至ったと判断をされる、との確認を行いました。これによって、事故収束に向けた道筋のステップ2が完了したことをここに宣言をいたします」。...(d)