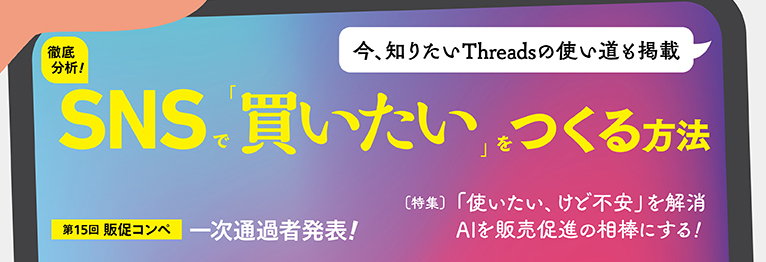買い物に「失敗したくない」と感じる傾向が強いといわれているZ世代。しかし、彼らにとってSNSは商品・サービスの情報を集める主要な接点だ。消費に慎重なZ世代は、実際に商品を手にとって確かめることが難しいSNS上の投稿や広告をどのように見ているのだろうか。
2023年に発表された総務省の「令和4年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」では、10代の平日ソーシャルメディア利用率が64.2%、20代が87.3%という結果に。40代や50代の結果と比べてもSNSを使用するZ世代の割合が高いことがわかる。
このような背景を踏まえても、SNSとZ世代の親和性は高いと考えてよいだろう。また、Z世代からトレンドやバズが生まれやすいということもある。情報感度が高い彼らに向けてはどのような情報発信が好ましいのか。Z世代を動かすブランディング支援やオンライン・オフライン統合プロモーション設計などを行う電通プロモーションプラスの若者消費ラボに話を聞いた。
「若者消費ラボでは、様々な視点からZ世代向けの販促について研究・提案を行っています。その中で生まれたのが『エモ販促』というキーワード。Z世代は、感情が動くこと=エモに価値を見出し、その揺らぎを求めてモノやサービスを購入することが多いです。そういった感情の機微を生み出すのは人間の直感。消費者の直感トリガー(Googleが提唱する「直感センサー」について同ラボ内ではこう呼ぶ)を刺激することがSNSでも重要になってきています」と話すのは電通プロモーションプラス若者消費ラボの所長を務める五十嵐響介氏。
同ラボで、Z世代マーケティングの際に意識しているのは「For me(自分にぴったり)」「Adventure(自分が知らなかった)」の2点(図1)。
つまり、SNS上であっても自分にぴったりという心地よさと、初めて見たという驚きを与えることが重要だと言える。
また、SNSネイティブであるZ世代は情報精査に費やす時間が短いことも特徴。他世代でも同じく言われている傾向ではあるが、Z世代ではそれがより加速。一般的に店頭では3~7秒という短い時間で判断していると言われている。
SNSではさらに短いコンマ数秒で判断していると、同ラボでは考えており、その短い時間で購入の選択肢に入るためには、一目でわかる「ぴったり感」と「新しい驚き」を動画のサムネイルや画像で伝えることが必要なのだという。また、SNSのリツイートやいいね、トレンドなどから得られるような、自らの趣味嗜好には基づかない情報が潜在的な購買意欲を掻き立てることにも注目したい。
長く使う商材は信頼感と説得力を意識
では具体的にどのような投稿がその直感トリガーを刺激するのか。「当ラボでは、この直感に刺さる投稿をさらに、『左脳=ロジカル』に訴えかけているものと、『右脳=感情』に訴えかけているものに分けて考えています(図2)」(五十嵐氏)。
左脳に刺さる投稿はレビュー系のものが多く、相性のよいカテゴリは「化粧品・雑貨・金融商材・家電」。長く使うものや、自分だけで購入を判断することが不安である商品カテゴリは、第三者からのレビューのような投稿が刺さりやすいと言える。
また、企業や店舗からの発信であったとしても、「年間100杯のラーメンを食べた」「化粧品に100万円を使った」といったように、その専門性や説得力を数値でわかりやすく伝えることが重要なのだという。「失敗したくない」というZ世代の心理を踏まえても、こういった信頼感の醸成が必要不可欠だろう。