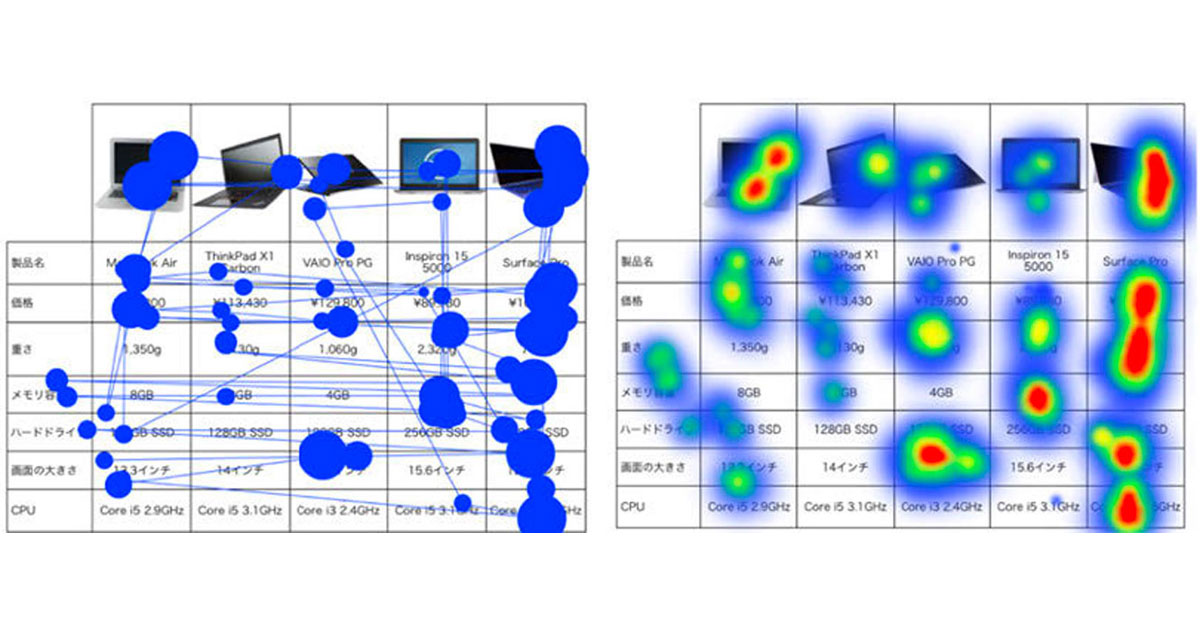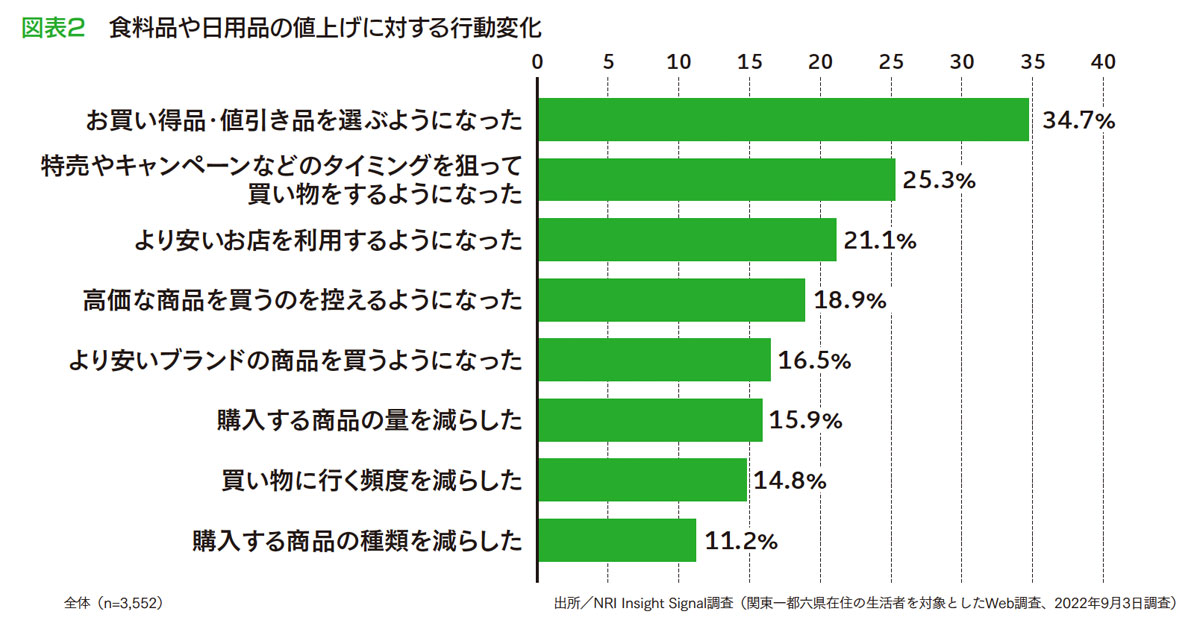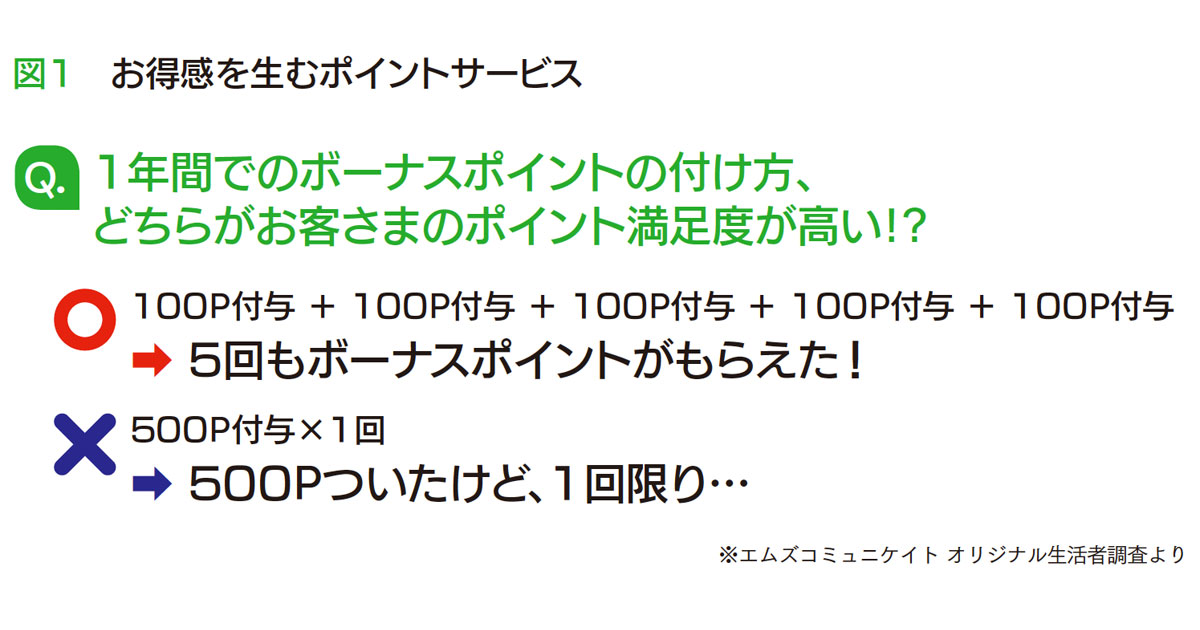食品ロスの削減に一役買っている話題のサービス「TABETE」。廃棄を出したくない事業者と、環境にいいことがしたいユーザーとをマッチングするこのサービスは、価格面の安さを特段アピールしていないという。では、どのようにしてお得感を感じさせているのか。コークッキングCPOの伊作氏に話を聞いた。

アプリで購入した商品は、ユーザーが直接お店に取りに行く仕組み。
より多くの人に「食品ロス」と向き合ってもらうために
──「TABETE」について教えてください。
「フードシェアリングサービス」と呼ばれる、食品ロス削減に着目したアプリです。廃棄の恐れがある商品を、廃棄前にユーザーとマッチングさせることで食べてもらいます。食品ロスになってしまいそうな商品に困っているお店を、アプリで探して注文。その後商品をお店に受け取りに行くというものです。パン屋や菓子店をはじめ、スーパーなどのチェーンも参加しています。
ユーザーの方は「食品ロス削減」に関心の高い層が多く、エシカルな消費がしたいと考えている方が多く利用しています。
出品する事業者の中には、食品の廃棄が約90%減少したという方もいます。
──どのような経緯でサービスを開始したのでしょうか。
元々当社社長の川越や私が料理に関する事業や研究をしており、その知見を活かして社会的な取り組みができないかと考えたことから生まれました。ちょうどその時、日本スローフード協会の青年支部から、一緒に企画をやりたいという話をもらって。規格外野菜でスープをつくって提供し、食品ロスについて啓発するイベントを行ったことがきっかけです。
イベントは大いに盛り上がったのですが、労力のわりに波及効果は小さい。そこで、本当に食品ロスを削減するためには、普段の生活やビジネスの中に仕組みを組み込まないとどうにもならないと考え、アプリの構想に至りました。
──「食品ロス削減」を広める中で、苦労した点はありましたか。
はじめはそもそも「食品ロス」に対する社会的な認知が低く、「それ食べ残しじゃないの?」とか「腐っているんじゃない?」といった声があり、誤解をとくのに一苦労でした。
また、サービスに参加してもらう事業者の方からは、ブランディングの観点から廃棄を出していることを知られたくないという反応もありました。「食品ロス=生ごみ、捨てるもの」というイメージもあり、それとお店を関連付けられたくない、という考え方です。
──どのように解決しましたか。
「食品ロスに...