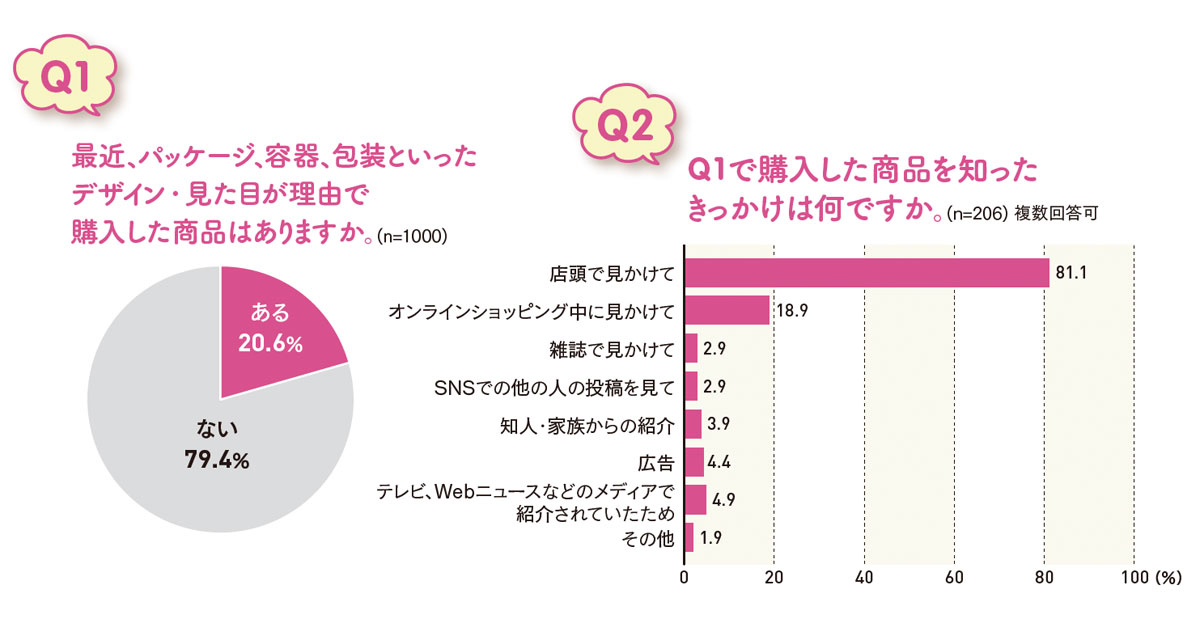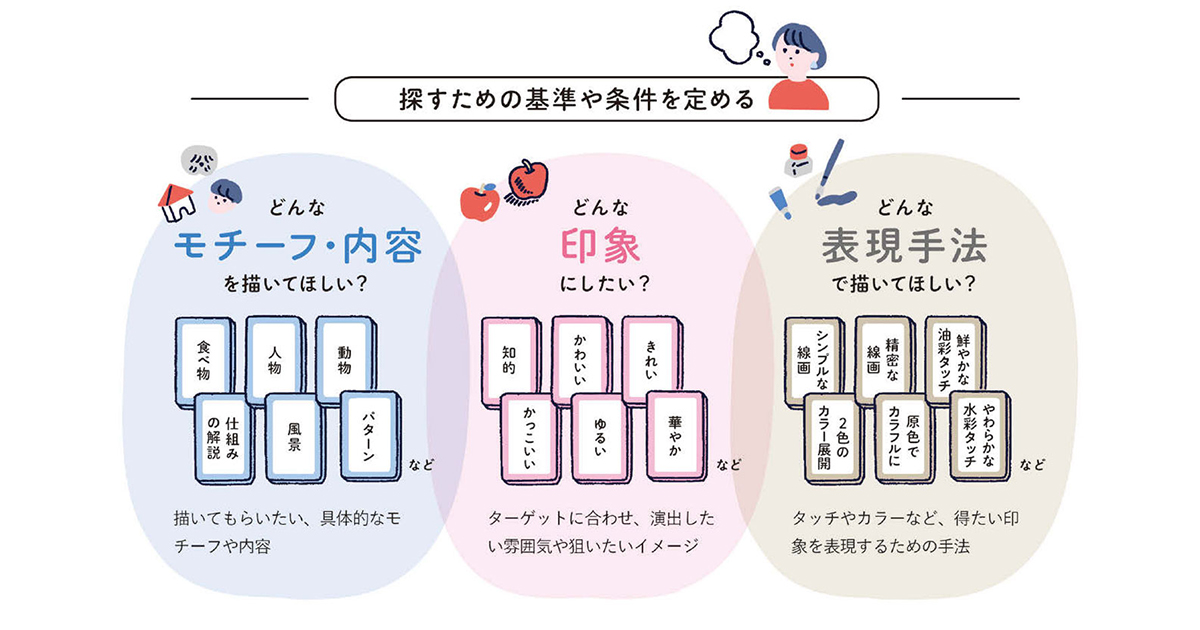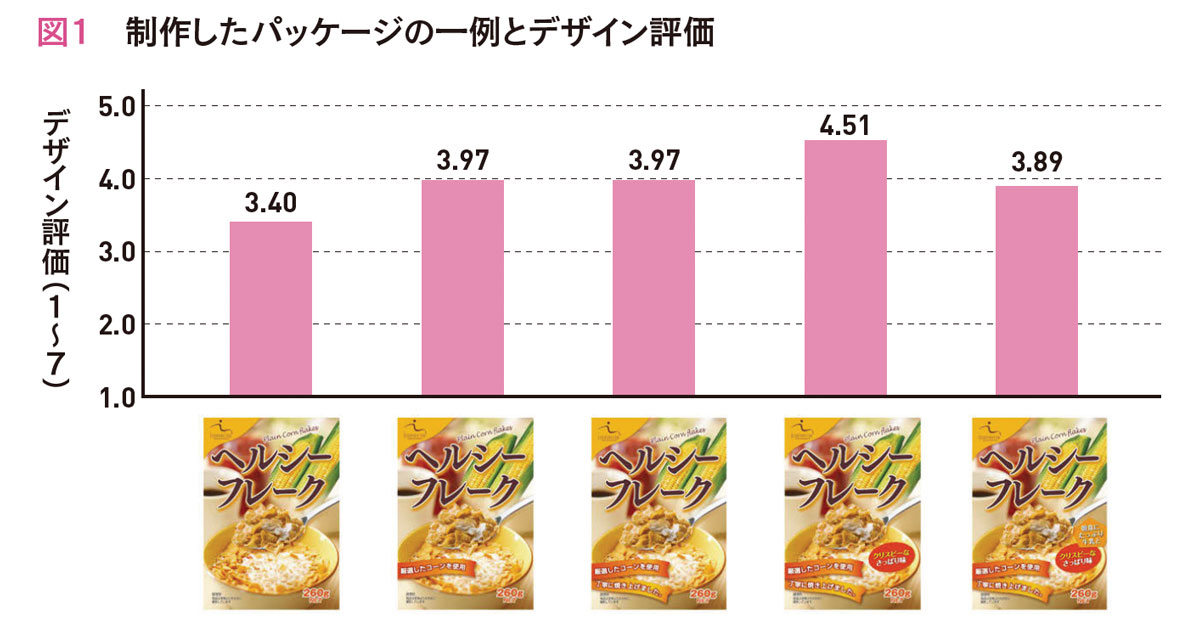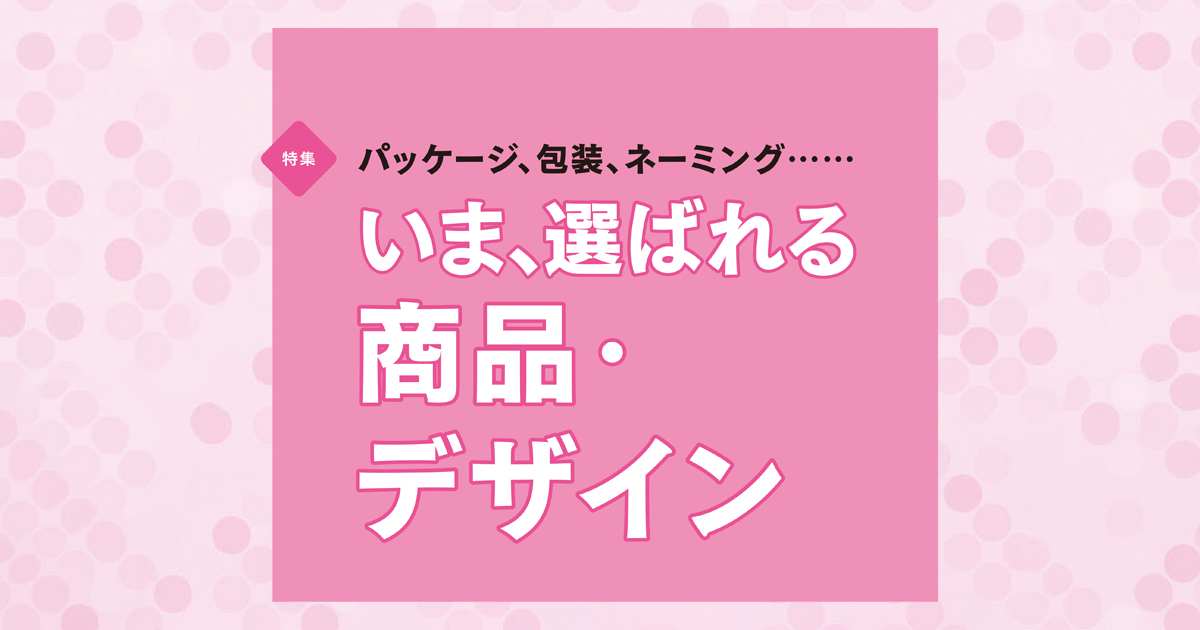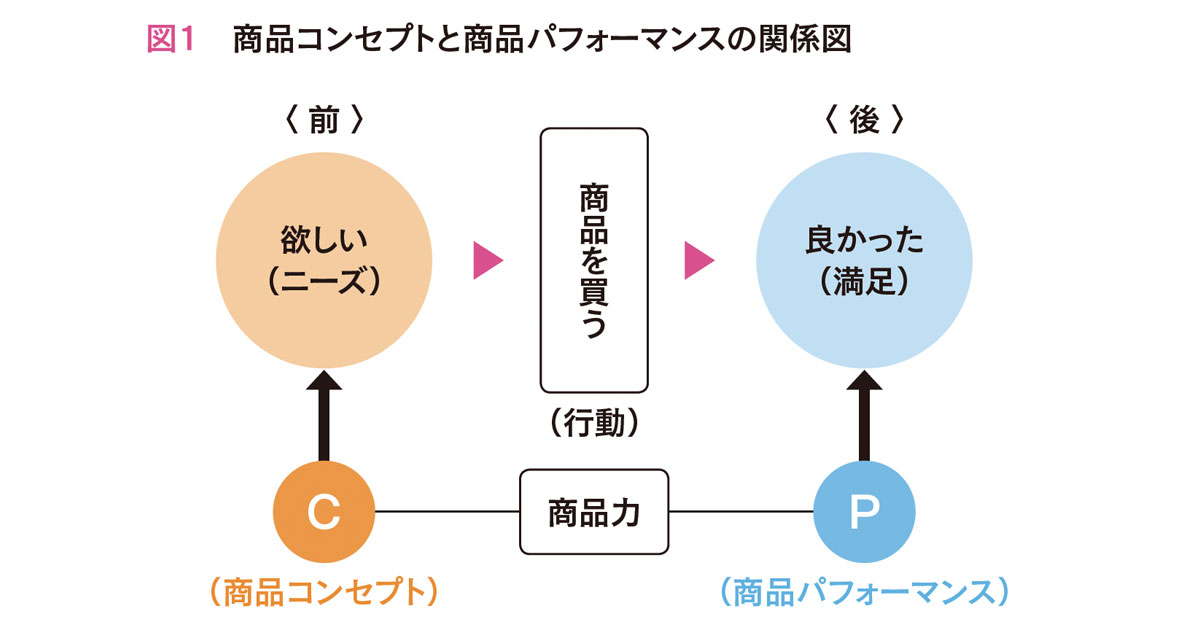商品・サービスの見た目というと、パッケージや包装だけではなくネーミングも入るだろう。店頭で目に入るのはもちろん、ECやSNS上でテキスト情報として目に入る。ここでは、商品自体の在り方、見え方を変えてしまう言葉の考え方を学ぶ。
現在はコロナ禍での生活が長く続き、消費の形態が大きく変わってきています。実店舗の売上は落ち込み、逆に自宅にいながら商品が届く通販の売上は大きな伸びを見せています。
ライフスタイルの変化に伴い、消費者の嗜好も多様化し、商品や販売経路によっても売れるネーミングの要素は変化し続けているのです。
ネーミングの考え方(基本要素)
①短さ
②わかりやすさ(意味)
③覚えやすさ
④伝わりやすさ(機能、メッセージ)
⑤響きの良さ
この時節、企業からの依頼内容に、ひとつの特徴がでてきている、と感じられます。それは「商品内容をわかりやすく」伝えるネーミングです。「伝わりやすさ」は上記のネーミングの考え方(基本要素)のひとつとして、今回ピックアップしていきます。
ここ数年は「王道でわかりやすい」ネーミングの商品がヒットし、数多く取り上げられています。例えば、「バスタブクレンジング」「パジャマスーツ」「生ジョッキ缶」「のんある晩酌」「内脂サポート」など。
いずれのネーミングも一見するだけで、だいたいどんな商品かが類推できます。
「生ジョッキ缶」を例に取って、ネーミングの構成などを見ていきましょう。まず「生」の部分で生ビールのような味、「ジョッキ」で飲んでいるような泡とシーン、「缶」で形態がわかります。
このように、簡単でわかりやすい単語構成(②)、どのような商品(WHEN/WHERE/WHAT/HOW)かを伝える(④)ネーミングというのが必要とされています。
先に、ネーミングの基本要素の一部を取り上げましたが、基本要素=売れるネーミングとは一概に言えません。例として、「バターなんていらないかも、と思わず声に出したくなるほど濃厚な食パン」(モスバーガー)などがあります。長いネーミングが面白いとSNSで話題となり、多くのメディアでも取り上げられました。完全予約制という限定感がまた、消費者自身で発信したくなるポイントだったとも考えられます。
基本要素から外れていても売れる。それでは、良いネーミングというものはあるのでしょうか。結論を言うと、ネーミングに「絶対の正解」は...