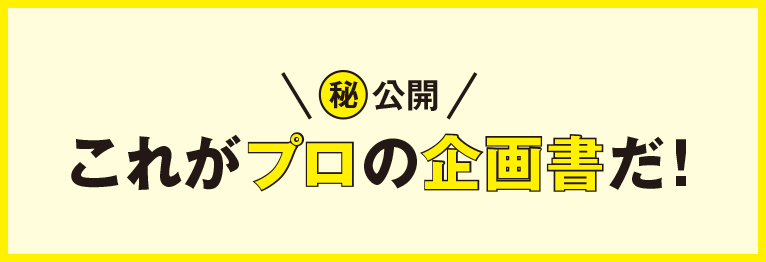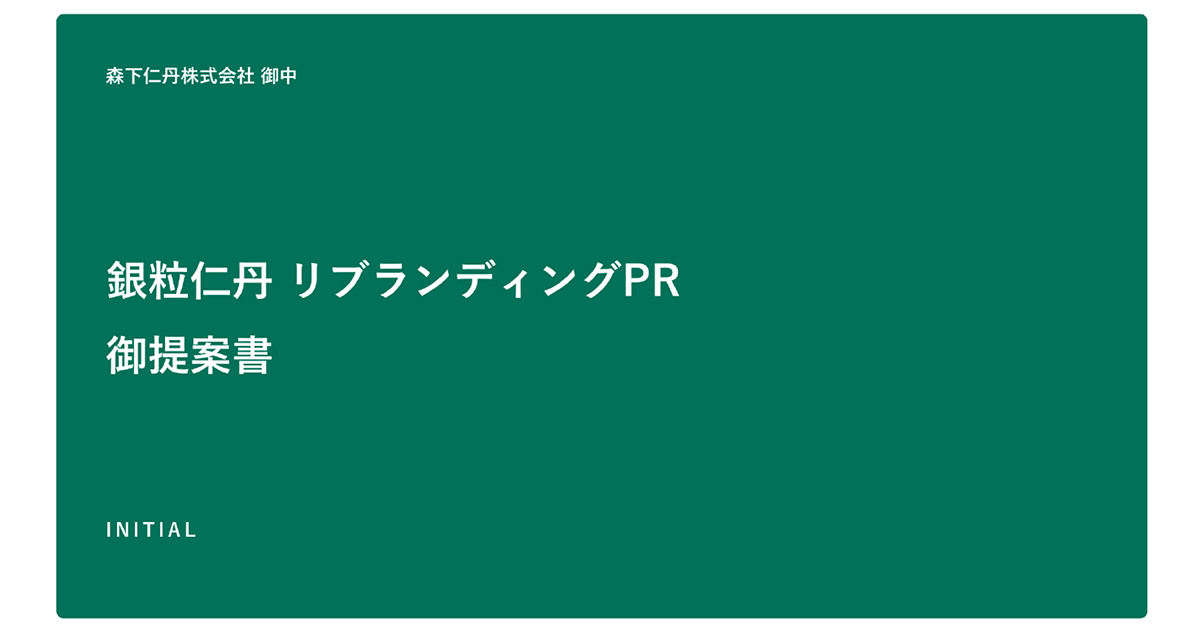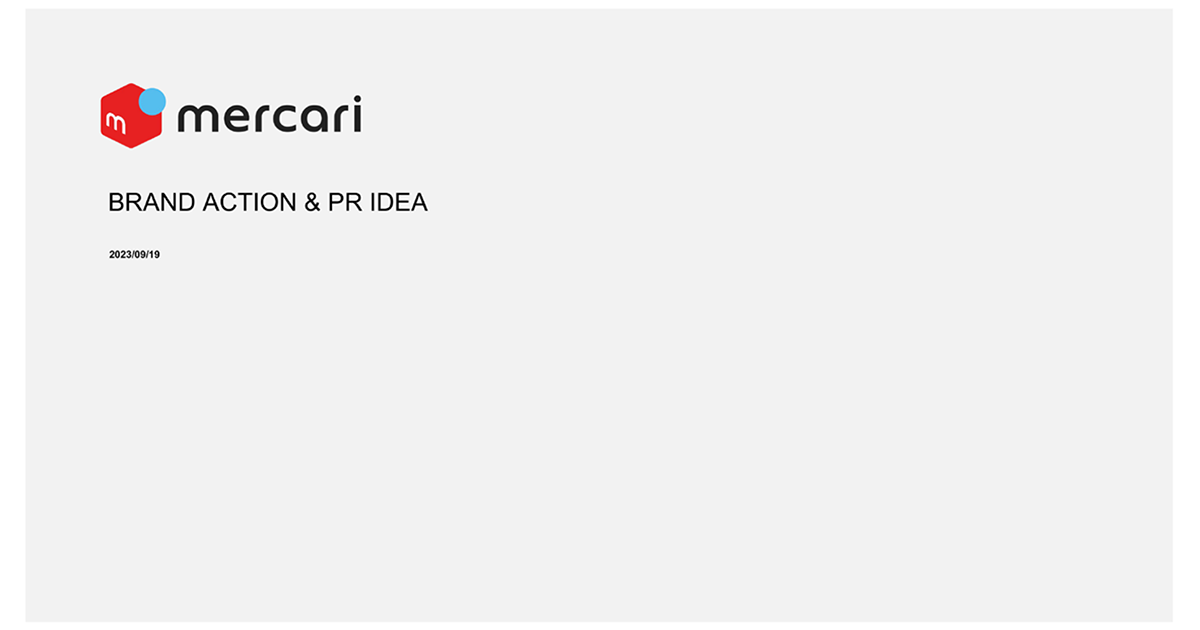コロナ禍を受け、店舗を持つ企業は、接触機会の減少などの感染防止策を講じつつ、新たなチャレンジを続けている。これまで消費者ニーズの変化に敏感に対応し続けてきた小売2社が、「店頭体験の向上とオペレーションを両立させる販促の現場」をテーマに議論。コロナ禍における本部と現場の連携の状況とその中で新たに生み出された顧客体験を通し販促の現場を説明し、これからの店舗について語った。

グッデイ
1978年、福岡県大野城市にホームセンター・グッデイ1号店を出店。福岡や大分、佐賀、熊本、山口の各県など、北部九州を中心に64店舗を運営する。データ分析やAIを仕入れの際などに活用していることでも知られ、エンジニアなど専門人材の育成に注力。近年は他社にデータ活用のノウハウを指南する事業も展開している。

ルクア大阪
JR大阪駅の大規模リニューアルを機に、2011年に開業した複合商業施設。2015年には既存の「ルクア」に加え、旧JR大阪三越伊勢丹を衣替えし「ルクアイーレ」が開業した。テナントは約400店舗。ルクアは20〜30代の働く女性がメインターゲット。ルクアイーレはファミリー層も取り込む。百貨店やファッションビルがひしめく梅田地区で有数の集客力を誇る。
デジタルツールで情報共有
──コロナ禍では本部も現場も直接会ってコミュニケーションをする機会が減ったと思われますが、皆さんは本部と現場の連携をどのようにしていますか。また、コロナ前と現在とで変化したことや気づきなどお聞かせください。
河原畑:JR大阪駅に隣接した大型商業施設「ルクア大阪」の運営を担当しています。会社自体は小さな組織で現場の中に本部があるような組織のため、当社の場合は本部と現場の距離は感じません。一方で、出店いただいているテナントは東京の会社が多いため、そこでの本部と現場の距離はあります。
コロナ禍で私たちが留意しているのは、各社の状況が変化しているので、オーナーや経営層も含めて、皆さんとのコミュニケーションをより密にして、どういうかじ取りを考えておられるのか、今まで以上にコミュニケーションを心がけています。さらに現場で起こっていることをオーナーにお伝えするなど、テナントの本部と現場をつないでいく役割も担っています。
市川:福岡県ほか北部九州をメインにホームセンター「グッデイ」を店舗展開しています。コロナ禍の前から当社はGoogleのビジネスツール(Google Workspace)を利用して本部と店舗の情報共有を即座にできる体制を整えてきました。われわれの店舗がある九州は自然災害を受けやすい地域です。そういう時もどういう状況か、スプレッドシートを立ち上げて、情報を全員で共有しています。
またコロナ以前は社長を中心に各店舗に頻繁に視察に行き、店舗の状況を把握していたのですが、コロナ禍ではそれはかなわなくなりました。その場合もGoogle Meetを使って各店舗とコミュニケーションを図っています。
店頭の役割はコロナ禍でも健在
──「三密を避ける」「営業時間の短縮」など、お客さまの行動が制限される中で、購買における顧客の体験価値を上げるために、どのような工夫をしていますか。
市川:コロナ禍で在宅時間が増えたことで、「DIY」や「園芸」を楽しむ傾向が見られました。そこで店舗でも園芸を含めて「DIYを学ぶ・楽しむ」ツールを準備し、お客さまに「DIY」を体験していただけるコーナーを設けました。店舗にはガーデニングに詳しいスタッフがいますので...