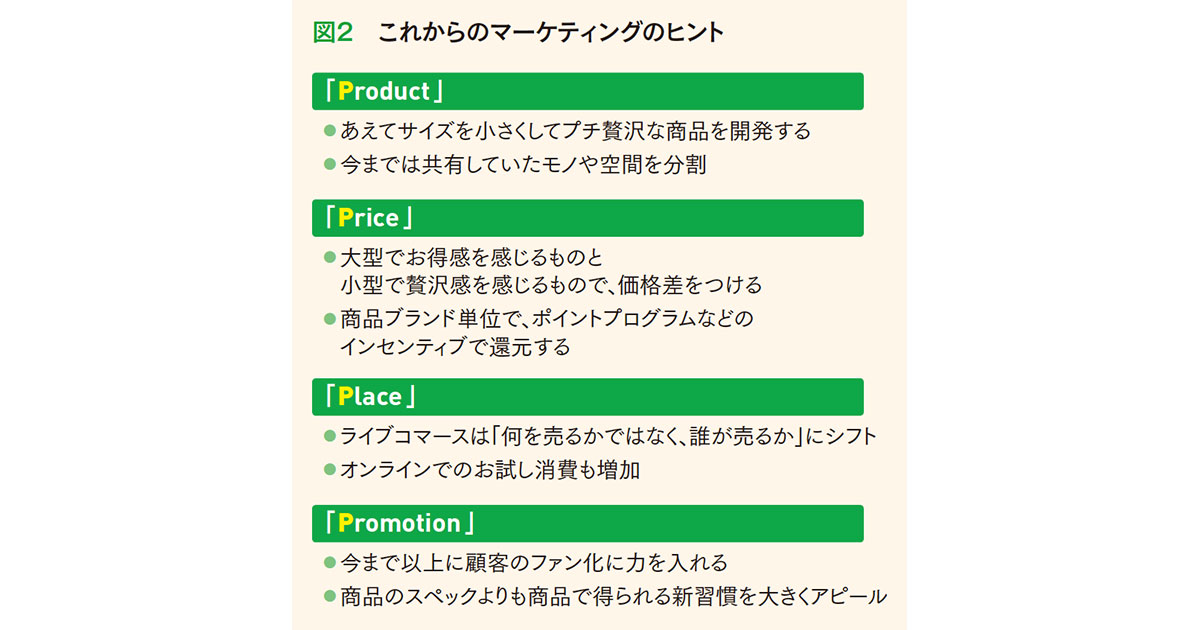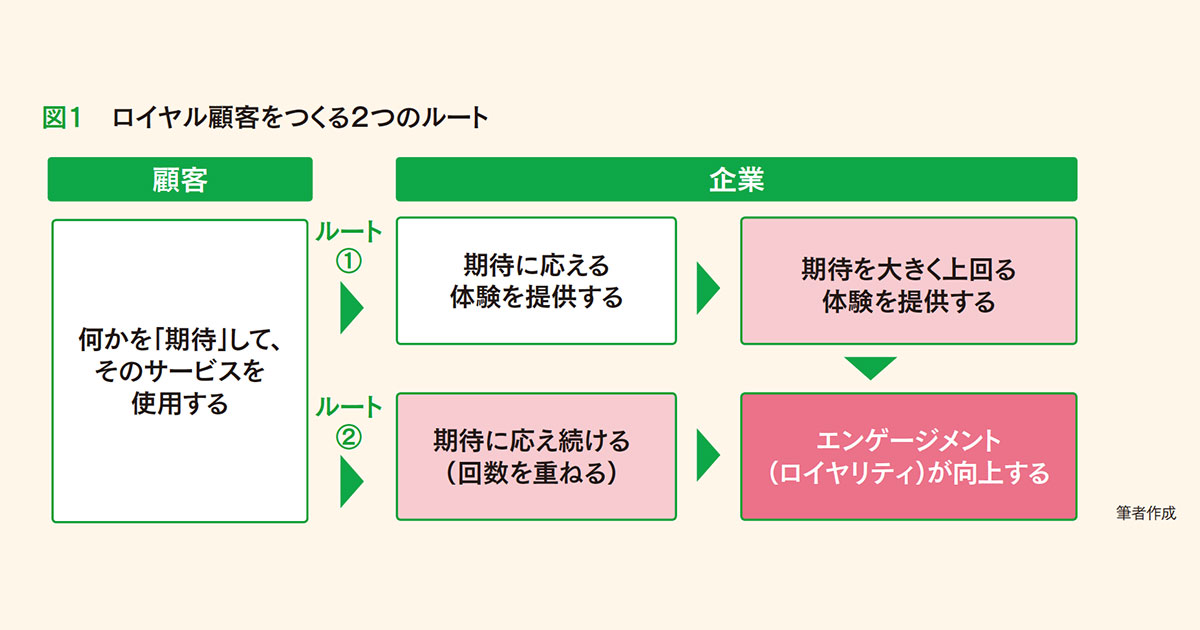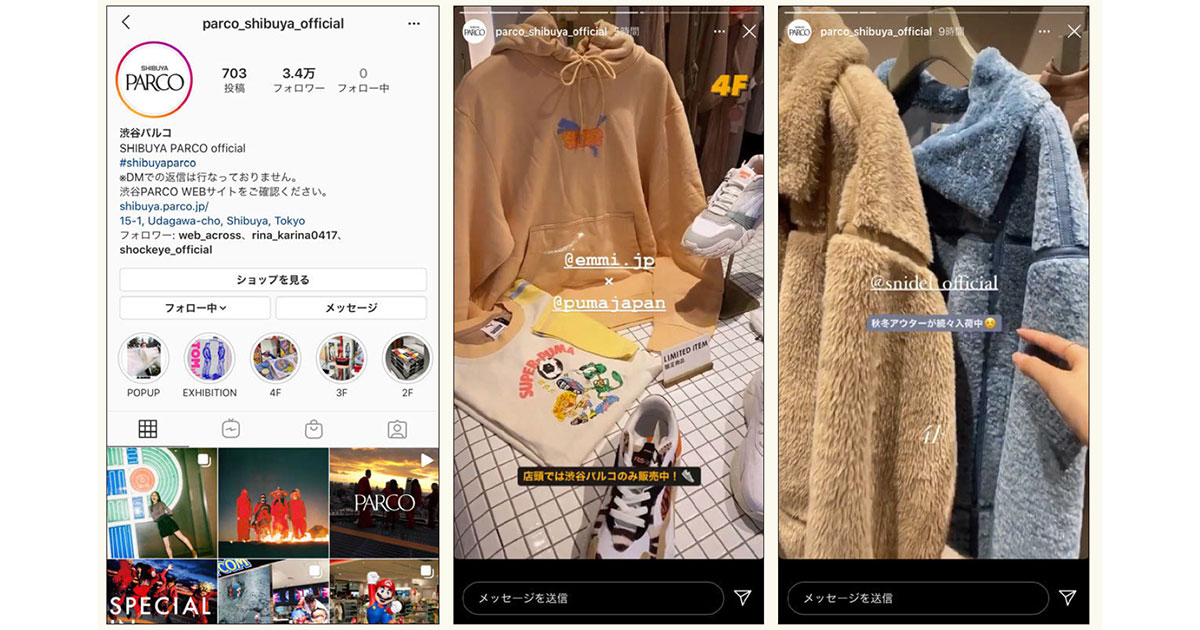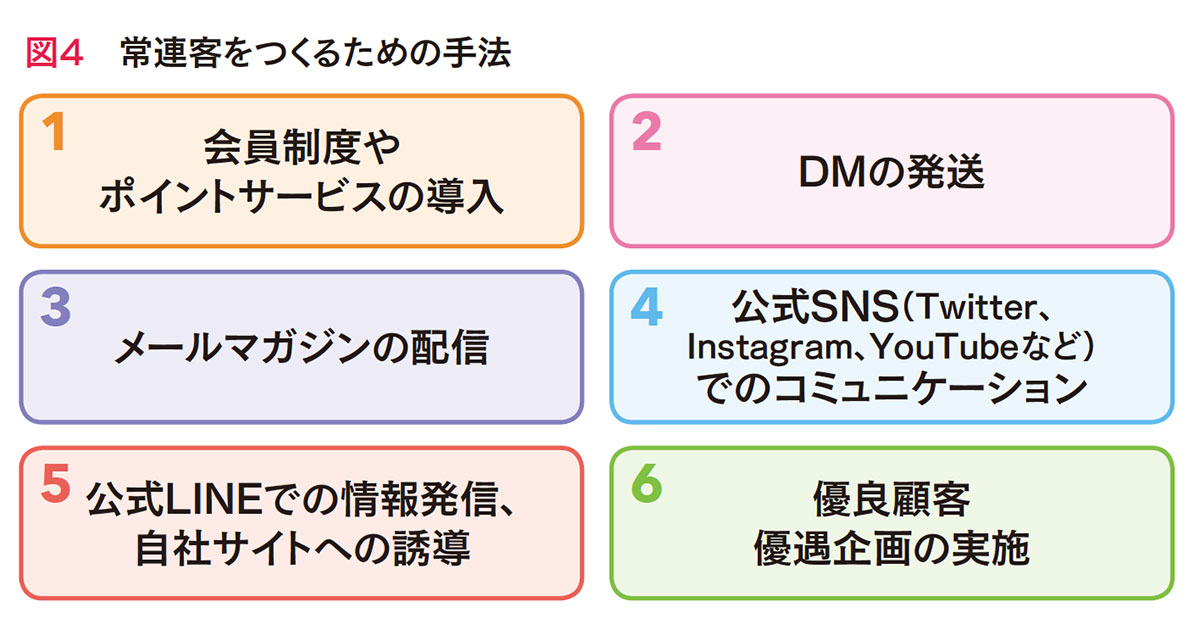創業翌年の1946年に誕生した「豚まん」を看板商品とする551蓬莱(大阪市)。関西に58ある店舗は、行列ができるなどいつも活気にあふれている。長きにわたり常連をつくり続けてきた店舗運営の工夫を聞いた。
5月の通販売上は前年比300%
──新型コロナウイルスの影響で店舗休業や営業時間短縮があった一方で、通販は需要増と好調ですね。
安木:当社の店舗は主に、百貨店のテナント、駅や空港などの“駅ナカ”、地域密着の郊外店の3形態あり、合わせて関西に58店舗あります。4月に緊急事態宣言が出た直後は一時休業や営業時間短縮もあり、ダメージが最も大きかったですね。
特に観光客や出張でのビジネスマン向けに土産用のチルド商品を販売していたJR新大阪と伊丹空港の店舗では、乗降客数や便数の減少に伴って売上が半減しました。6月には8割に回復しその後徐々に持ち直したとはいえ、9月になっても例年の約8割〜9割に留まっています。コロナ前は、新大阪駅の5店だけで全店舗の15%を売り上げるほどの繁盛ぶりでしたので、人の移動が減ると土産市場がここまで縮むのだと痛感しました。
土産用以外でも、大阪市中心部である梅田や難波にある店舗の売上は減少しました。一方で、地域密着の郊外店はすべて前年度比で100%を超える売上となりました。おそらく、都心でのお買い物や通勤などの際に立ち寄ってくださっていたお客さまが、地元で購入されるようになったのでしょう。
この郊外店での売上が土産需要の減少分をカバーする形になりました。地元の皆さまに愛していただいているブランドであることを再認識し、感謝しています。
通信販売は、5月の売上が前年比300%に伸び、9月でも同130%の高水準をキープしています。大多数は関西在住の方が関東方面への発送を依頼されるケースですが、関西の方がご自宅用に注文されるケースも多いです。また、百貨店の催事が中止になった代わりに、という全国の551ファンの方からのご注文もありました。
チルド商品とはいえ、製造当日に出荷し、最短で翌日にはお客さまのお手元に届くようにすることで、実店舗に引けをとらない鮮度を保っています。
また、箱や手提げ袋などの包材も店頭販売と同じものを使い、配送用段ボールにも「551」のロゴマークを入れています。届いた瞬間に「あ、551が来た!」と感じていただけるのではないでしょうか。
店舗


集客のポイントは実演販売。ガラス張りにして豚まんを包む様子を見せることで、シズル感を演出している。また、クオリティを保つために、蒸し上がってから30分以内にお客さまの手元に渡るように調整している。
来店頻度を月3回以上に
──メインターゲットは。
安木:実は、メインターゲットを定めたことはありません。あえて言葉にするとしたら、「関西に住んでいる(お越しになる)すべてのお客さま」ということになります。実際の購入者の年齢層は、40〜60代が中心です。
客単価は店舗ごとで少し違いますが平均すれば1000円程度ですので、“4人家族で豚まん4個”という、テレビCMで打ち出しているイメージそのものだと思います。
常連客についても細かな定義はありませんが、既存顧客の食卓に当社の商品が並ぶ機会を増やしていきたいという目標はあります。2010年に百貨店のテナント店舗で集計したデータによると、常連客の来店頻度は月1〜2回強。これをいかにして3回以上に近づけていくかが課題です。
──既存顧客のリピート購入を促すために、具体的にどのような工夫をしてきましたか。
安木:前提にあるのは商品のクオリティを絶対に下げないことです。特に「豚まん」の生命線は鮮度にあります。オリジナルの発酵生地は本社(大阪市浪速区)併設の工場で製造しているのですが、そこから150分圏内にしか出店しないのが鉄則です。
各店では、成形段階から製造し、蒸し上がったらすぐに店頭で販売します。蒸し上がってから30分以内にお客さまにお渡しするように調整しています。たとえ売り残しが出たとしても、値下げはしません。
販促面では、店づくりにこだわりがあります。ポイントは、ガラス張りにして豚まんを包む様子を見せる実演販売です。テキパキと作業するスタッフの様子や立ち上がる湯気、漂う香りなどでシズル感を演出し、お客さまを惹きつけているのです。
関西人の方なら、幼少期にお店のガラスの前に張り付いて豚まんを包む様子を夢中になって見た経験が一度はあるのではないでしょうか。そうした原体験がブランドへの愛着につながり、大人になってから常連客になっていただけるという側面もあります...