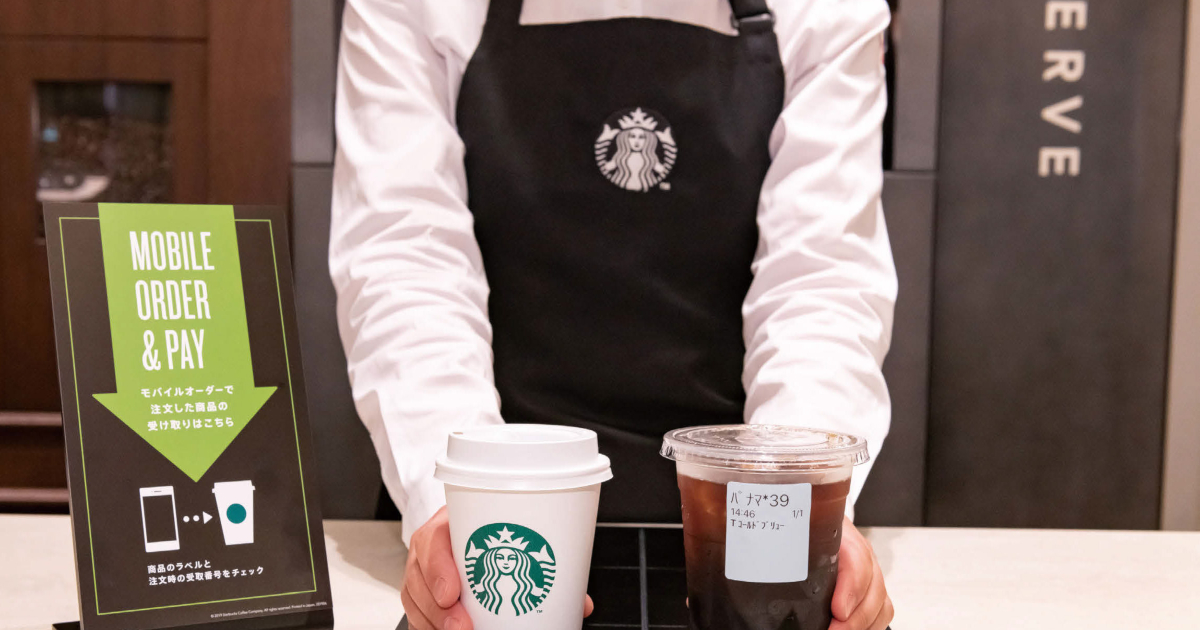「商談が決まらない」─こうした悩みを持つメーカーの営業担当者は少なくない。なぜ、小売業バイヤーに響かないのか。これを解決する期限は刻々と迫っている。「なんだかんだ言っても仕入れはあるから」──という現状肯定のままでは、時間切れになるかもしれない。オフィス イオニックマネジメントの谷雅之氏が語る。

開催日は消費税が10%に上がった10月1日。定員を大きく超える人が集まった。
小売業とメーカー 本部商談にまつわる問題意識
消費税が10%に上がった。買い控えを防ごうと価格を実質下げるケースは少なくない。キャッシュレス還元も実施されているが、値引きでは顧客は定着しない。値下げした分は、必ずどこかに歪みを生じさせる。なにより、完全な消費者などいない。誰もが生産者、労働者という顔を持つ。しわ寄せは、必ず誰かのもとにやってくる。
いまこそ、サプライチェーンに関わるプレーヤーが手を携えなければ、これから本格化する人口減少や高齢化にも対応できないだろう。そういった事態をどのように解消するか。小売業とメーカーの関係から考えてみたい。
現在、メーカーの営業担当者から聞こえてくるのは、こうした声だ。「本部商談はできているが、想定通りの発注が来ない」「先方の求める内容が変化し、本部商談にこぎつけてもバイヤーと合意せず、企画が決まらない」「そもそも商談機会を得ることが難しく、なかなかバイヤーとの接点がない」──。
一方、商圏内で顧客を作る事に成長戦略を変えている小売業が増えている。こうした小売業は、メーカーの新製品発表会に参加して、店頭で商品の価値を伝える方法を真剣に考えている。そうした小売業の幹部から、「メーカーさんの提案で困ってしまう事がある」という声を聞く。
いわく、「新製品でも改良品でも、メーカー都合だけを考えた一方的な提案を持って来られても困る」。
「メーカー社内でマーケティング担当か商品開発担当が作ったプレゼンテーション資料を転用し、営業担当がそれを読みあげるだけの商談。こんなすごい技術を用いて開発した。こんなに大量の宣伝をやる。事前の消費者アンケートでは8割が欲しいと答えた──立派な資料だが、大体のメーカーで同じことを言う。その商品をどうやって買ってもらうのかという話を持ってきてほしい」
「今月の数字が厳しいとか、これぐらいの販売計画で取引したいと言われる。その気持ちはわかるが、それでは商談にならない」
「現実を無視した理想的なブランド一体陳列の絵を見せられても、そんなことができる店は無いか、あっても限られている。我が社では取り扱っていない商品が平気で提案に入っている、実際の売場や、商品の取扱い状況を知った上で、実現できる企画を持ってきてほしい。小売業の仕組みやオペレーションについても前もって理解しておいてほしい」
「新製品なので入れてくださいというが、売場に空きスペースがあるわけではない。当然、他の商品と差し替えることになるが、どれと差し替えるべきなのか。それはなぜなのか。あるいは発売時の売場展開でどれぐらいのPOS金額を目標にしているのかを提示してくれないと、その商品を扱うべきかどうかを検討する事ができない」
小売業が抱えている課題、提案を採用して得られるメリット、実際のオペレーションを理解した売場展開手順を持って提案に来てほしい──こうした声は、増え続けている。これを「小売業側の一方的な都合だ」ととらえるか、提案の仕方を変えるか。これが、本部商談の機会を得る、あるいは商談が成立するかどうかを左右することになるだろう。
客数減と人口減少、高齢化 小売業の現況と社会現象
どうやって来店客数の減少に歯止めをかけるか、というのが、小売業にとっては喫緊の課題だ。スーパーでは軒並み既存店の客数が前年より減っている。コンビニエンスストアもいよいよ同じ状況となりそうだ。好調なドラッグストアも既存店がマイナスになるところが出てきた。
これは各企業の問題というよりも、そもそも人口減少という社会課題である。小売業にとっては、来店客の分母が減るということだ …