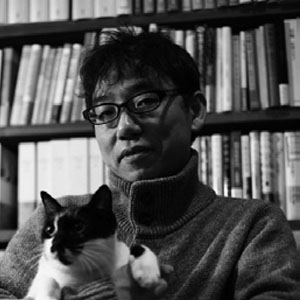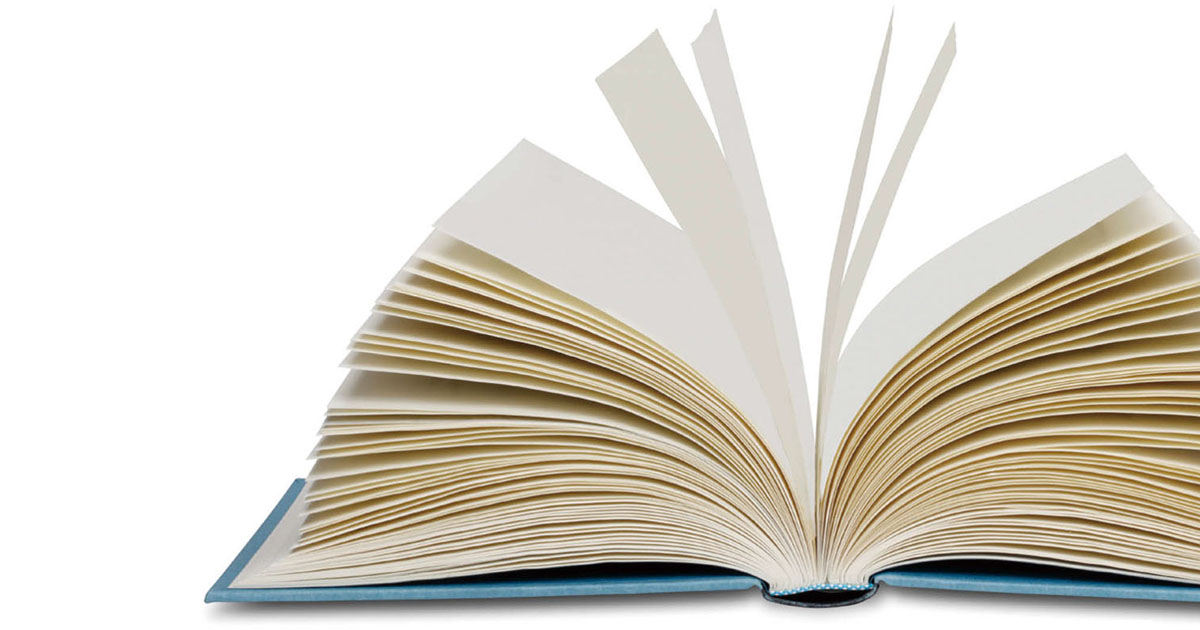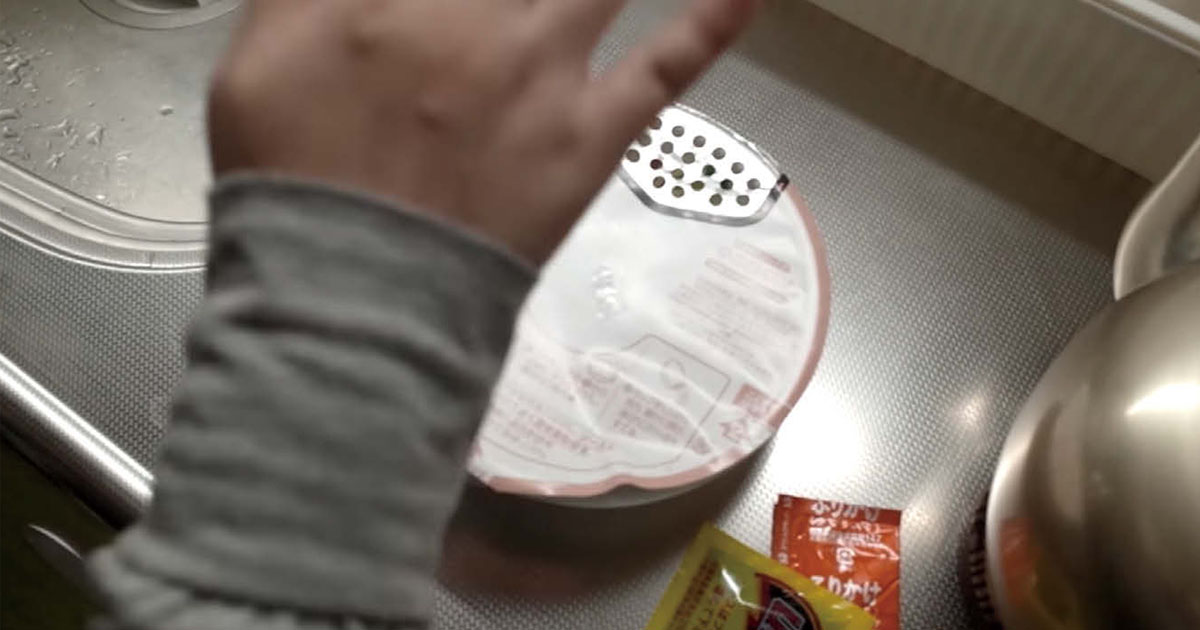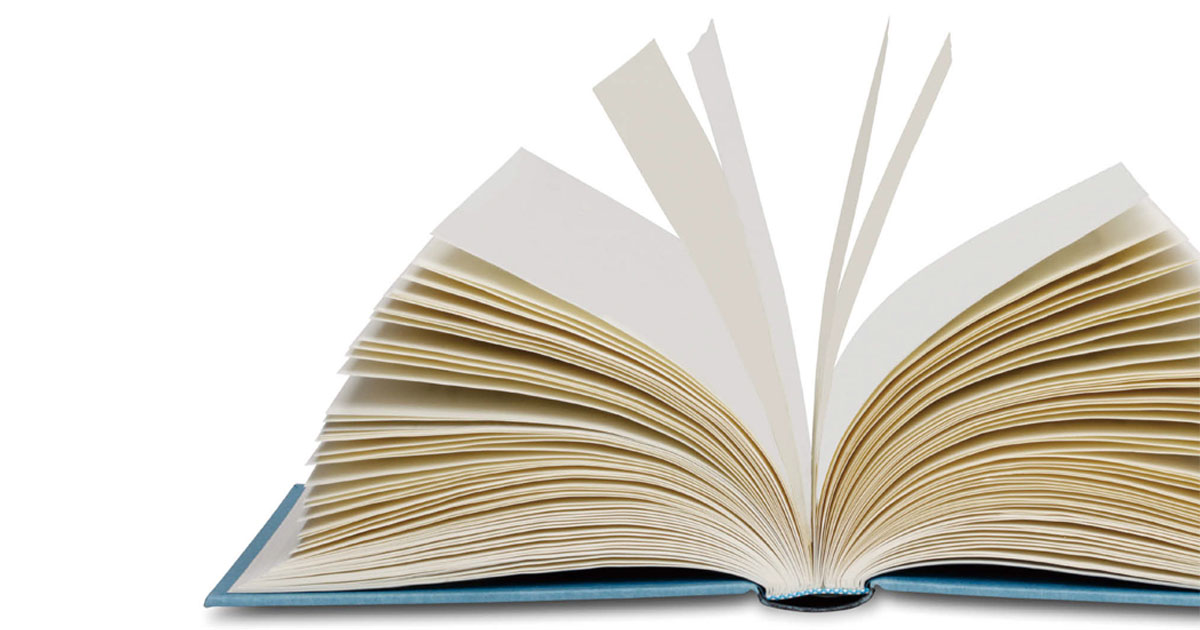人は誰かが発した「物語」を、どう受け取るのか。「ストーリー」と「物語」の性質、「炎上」のしくみ、「物語」の制作側が持つべき責任に至るまでを、『人はなぜ物語を求めるのか』(ちくまプリマ―新書)の著者、文筆家の千野帽子氏が語る。

ストーリーはできごとの継起が脳内に表象されたもの
人が世界を認識するとき、脳内でストーリーが展開しています。ストーリーはあくまで脳のなかのもので、脳の外には実在しません。受けた刺激(入力情報)から読み取られ、意識に上るのがストーリーだからです。
たとえば、今朝のできごとを振り返ってみましょう。自分は6時に起床した→トーストとベーコンエッグの朝食を食べた→8時に家を出た→8時15分の電車に乗った、といった前後関係の形で、思い出しませんでしたか?人は自分や世界を、「時間軸のなかで前後のある一連のもの」(シークエンス)として、つまりストーリーという形で、把握しています。
ただし人間にとって、できごとをありのままで受け取ることは容易ではありません。多くの要素がストーリーのなかに採用されず、カットされます。さきほどの例では、調理や身支度の詳細、家から駅までの道すがら目にしたものなど、多くの要素が省略されています。
ストーリーの形をとって把握されるのは過去のことだけではありません。現在進行中のできごとの実況中継、未来のできごとの予測、「あのとき、ああしていたら」という反実仮想、完全にフィクションの展開などもストーリーです。
ストーリーはできごとの継起に勝手に意味を与える
2018年の平昌パラリンピックで、ある選手が日本代表に選ばれたときだったか、大会で好成績を残したときだったか、選手の父親がテレビの取材に対して「努力が報われるということが証明された」と答えていました。
その選手が努力したことは間違いないでしょうが、他の選手がその人に比べて努力が足りなかったことは証明されていません。
このように、人はよく、前後関係を因果関係だと思いこんでしまいます。つまり、ストーリーの時系列のなかで、先に起こったことが原因、後に起こったことが結果だと勘違いしやすい、ということです。逆に言えば、できごとの原因や理由がわからなければ、そのできごとがわかったという気になりにくい──人間の思考(というか感情)はそのように設計されています。
さきほどの話に戻ると、苦労のすえの喜びを、このような「原因──結果」の必然性という形で表明してしまうのは、やはり人間の思考のバグです。
ストーリーの味つけに使われるのは、因果関係だけではありません。人はできごとを把握したと感じるために、外部から入力された刺激を手持ちの予断や推測によって勝手に意味づける傾向があります。たとえその予断や推測が間違っていても。
「わかった」という感覚は感情の問題であって、知の問題ではありません。そして予断や推測は個体間で大きくばらついているので、同じ事態を前にしても、人によって違うストーリーで把握されることがあります …