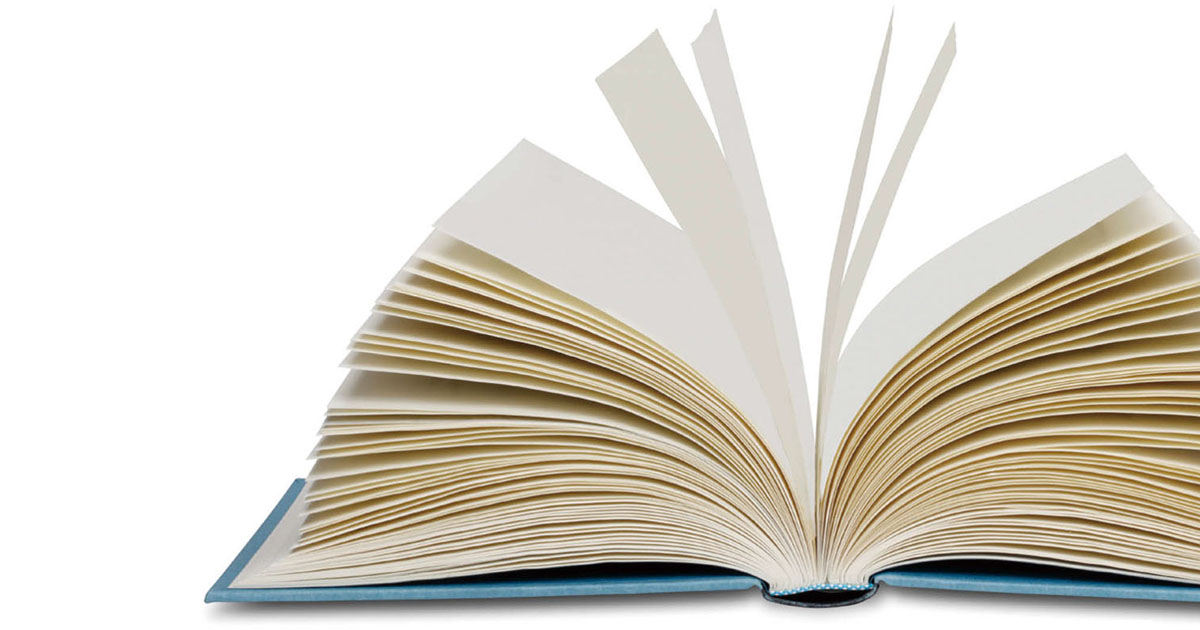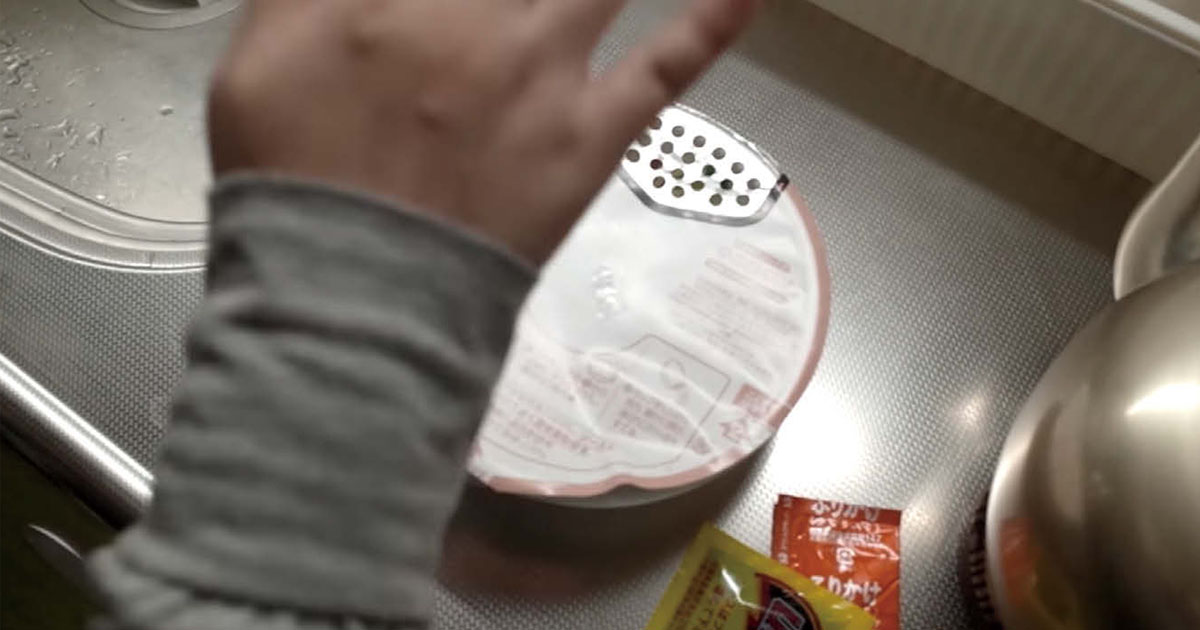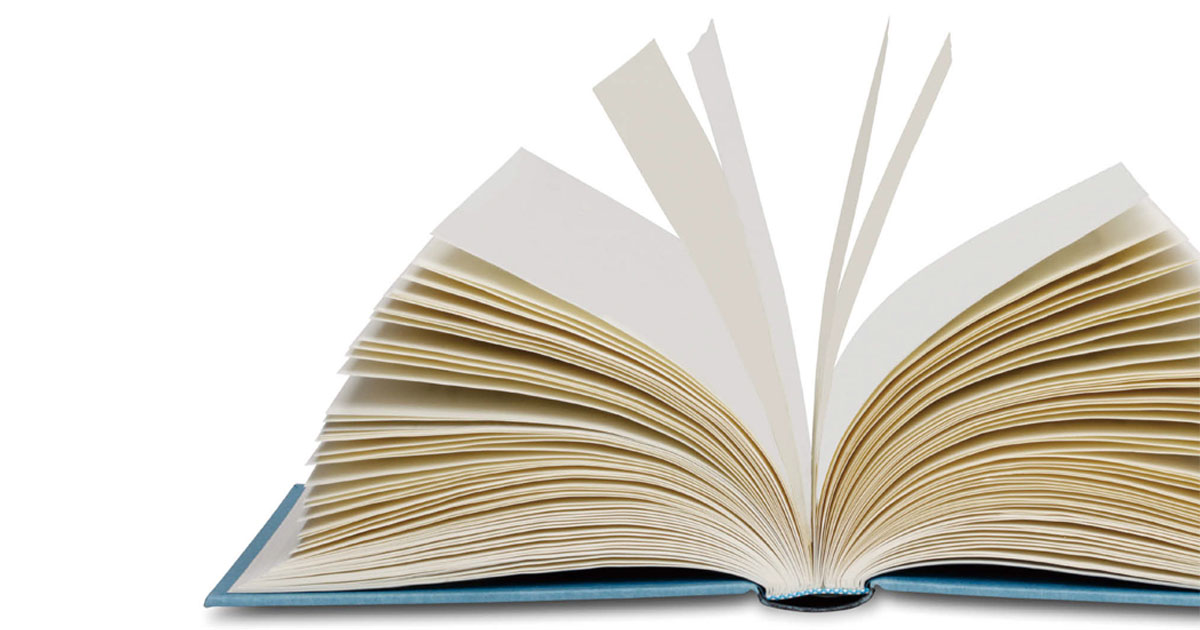広告も「物語」のひとつである。ストーリーが感じられるものはもちろん、一見、それらしきものが見い出せなかったとしても、よくよく分解してみると、私たちがストーリーを読み取るときの性質を利用した表現であることは少なくない。脚本家とプランナーの二足のわらじを履く、DRAWING AND MANUAL(ドローイングアンドマニュアル)の唐津宏治氏は、人の意識を変えるものは「物語」だと説く。

興味や好奇心によって集めたガラクタのような情報
プランナーに必要なのは、世の中をどう変えたいかという「意思」と、興味や好奇心によって集めたガラクタのような情報を収めておく仮想の「引き出し」だと思います。
与えられた、あるいは自分で考えたテーマに対して、どのようにアプローチするかを決めるのが「意思」で、その「意思」を企画にする時に「引き出し」の中の情報を使います。
最近手がけている短編映画『ボケとツッコミ』では、介護をテーマにしました。これは、かつて自分の両親が倒れ、一時期介護が必要になったこと、他県での仕事で高齢者介護施設─そこでは70歳を超える介護助手が同世代を介護していました!─を取材したという経験が背景にあります。
また、自分がこれまでに読んだ本やインターネットの記事の中に「アルツハイマー患者が一瞬だけ見せる正気のような─」といった冷ややかな比喩があったり、「カーステレオで音楽を流している間だけ記憶が戻る祖父の話」というエピソードもありました。こういったものが引き出しに入っていたのです。
地方自治体の仕事をするうちに、日本の地方、あるいは「先進国」(←嫌な言葉ですね)には共通する課題があり、「高齢化」もそのひとつと言えます。高齢者が増える、介護施設が足りない、介護士が少ない、家族が負担を強いられる、認知症の親によって仕事を辞めざるを得ない。
そういった暗く、どんよりと、絶望的なイメージを持つ「高齢化」という課題に対して、なんとかイメージを変えるアプローチができないか、というのが「意思」の部分でした。
僕自身は、「物語」こそが、中長期的に人の意識を変えると考えています。高齢化、中でも特徴的な認知症の親と、その子どもの物語を書こうと思いました。
『レインマン』で自閉症患者の、『アルジャーノンに花束を』で知的障害者のイメージが変わったように、物語を用いて認知症患者と介護する人のイメージを変えたいと思ったのです。暗く、絶望的な現場を、できるだけ明るく希望にあふれるものに変え、緊張を緩和させるようと……。
あとは物語的な作法に則って物語を書き、その裏付けや肉付けとして、たくさんの本を読んだり、映像を見たりしました。インターネットも利用しますが、独自性や深みを求められる案件ではできるだけ利用しないようにしています。
目的と結果の設定 あるいはそのほかの企画の指針
自分が作るコンテンツは、超面白くてたくさんの人が見るけど、一瞬で忘れられて、世の中になんの役に立たないものではなく、(見る人は少数かもしれないけど)見た人が感動して、結果的に後の世の中の役に立つような、できるだけ「善きもの」でありたいと考えています。
なので重視するのは、「顧客満足度」です。観てくれた方がどれだけ深いところで満足するか。観て良かったなと思えるか。明日からの生活が少しだけ変わるか。みたいな漠然とした指標です。
たとえば、昨年に企画と脚本を担当した、Mr.Childrenの「here comes my love」というミュージックビデオでは、「難聴の男性」を主人公にしました。耳が聞こえないということは、ミュージックビデオという案件にとっては逆説的なアプローチですが、日常的に聞こえている音楽が、聞こえない人にとって、どのような存在になるのか、というポイントを物語の核にしました …