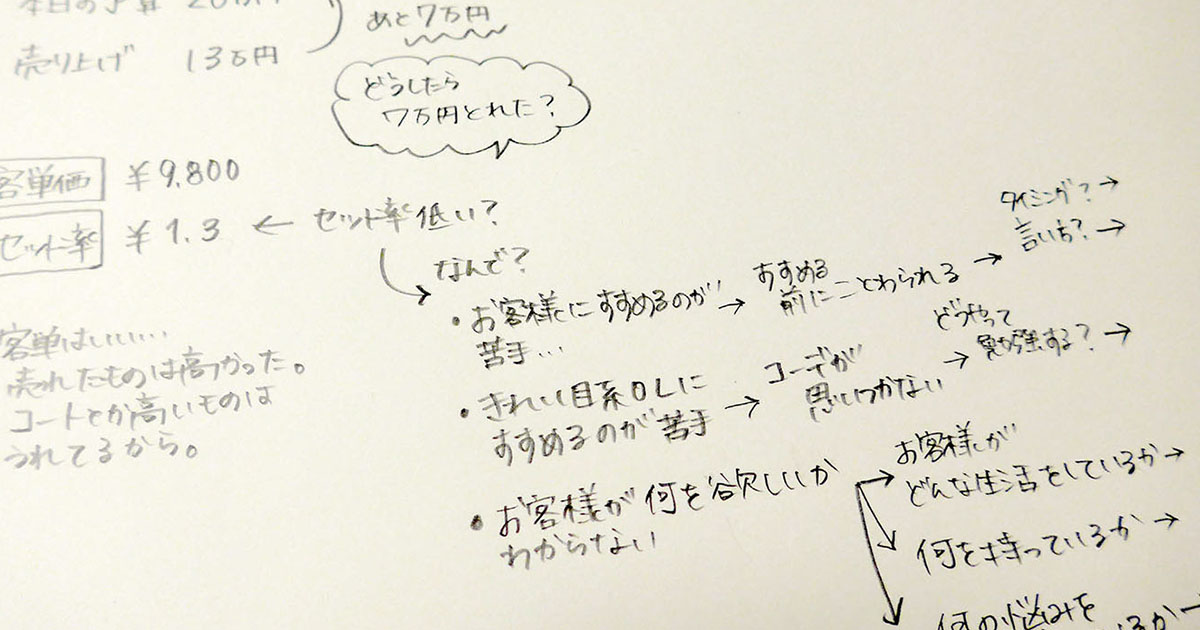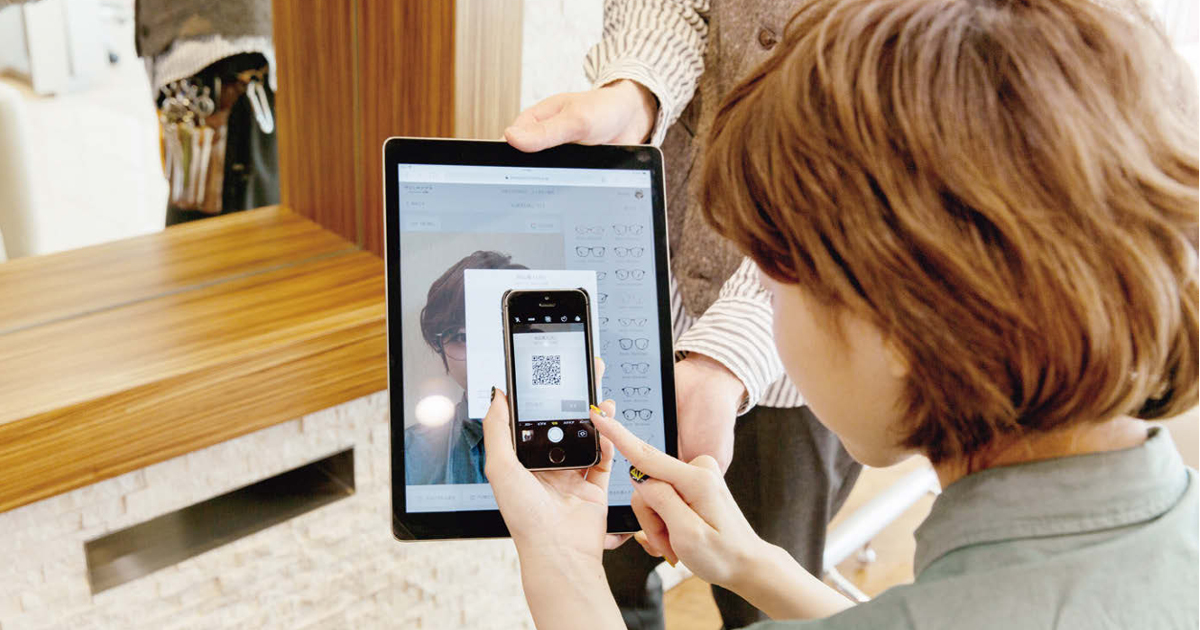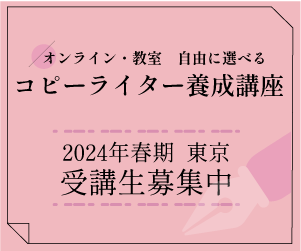ユーザーが身をもって納得したものだけが残る現代。BASSDRUM/PARTY NYのテクニカルディレクターの清水幹太さんは、「«考える・説明する»クリエイティブ・ディレクション以上に、«実現する・動かす»テクニカル・ディレクションが必要不可欠になる」と説きます。

"これからは「考える・説明する」ことだけでなく、「実現する・動かす」テクニカル・ディレクションが必要不可欠となる"と清水幹太氏は述べる (写真=123RF)
テクノロジーがあぶり出した広告のパラドックス
2018年である。20世紀に少年時代を過ごした筆者にとって、2018年などというのは「未来」以外の何物でもない。
インターネットの登場によって、テレビが終わるとか、それによって広告業界の仕組みが揺らぐとか、そんなようなことがうわさ話でなく、肌で感じられるようになって、どれくらい経っただろうか。商業クリエイティブにとってのこの20年は、それまであまり関係のなかった「テクノロジー」といかに付き合うかを模索してきた20年でもあった。
「広告業界」は、八方塞がりの状態だ。一方で、商業クリエイティブとテクノロジーのあるべき関係についての「答え」がようやく見えてきている。もしかしたら、やっと、インターネットの登場に端を発する、長い長い「過渡期」が終わろうとしているのではないか。そんな感じがする。
この過渡期は、まず既存のやり方が通用しなくなることから始まった。
ぐっと来るコピーと、ぐっと来るビジュアルで商品のポスターやテレビCMをつくったところで、ソーシャルメディアでやりとりされる商品についての生の声に正体を暴かれてしまう。ウソをついてもバレる。過剰にあおっても、消費者は冷静だったりする。
これはインターネットがもたらした基本的な事象だが、広告業界はそんな状況に対応しようといろいろなことを試みてきた。
たとえば、スマホアプリに代表される「使える広告」だ。一方的に伝えたいことを伝える広告表現ではなく、ユーザーの不便を解決したり、日常的に使ってもらえるような機能を提供し、それを通して商品の周辺に新しいコミュニケーションをつくったり、ブランド価値を向上したりする。
これは、アプローチとしてはとても理にかなっていて、「使える広告」が消費者と商品の仲立ちとなって、両者の間に継続的な関係づくりを目指すわけだから、一時的・一方的なコミュニケーションよりも、よほど費用対効果が良さそうだ。
しかも、私たちは毎日スマホに触り、なにがしかのアプリを開いている。スマホの登場、インストール型の「アプリ」という概念の登場によって、サービスやツールにとっては、ユーザーのスクリーンに常駐し、より多く「使ってもらえる」だけのチャンスが増大したといえる。
しかし、そんな「使える広告」はさまざまな形でトライされてきたが、きちんと使われ続けている事例は、世界を見回してみてもそんなにない。多くの人が利用しているアプリの中に、広告として提供されたもので、それを通して商品やブランドとの新しいコミュニケーションを実現しているものは、どれだけあるのだろうか? …