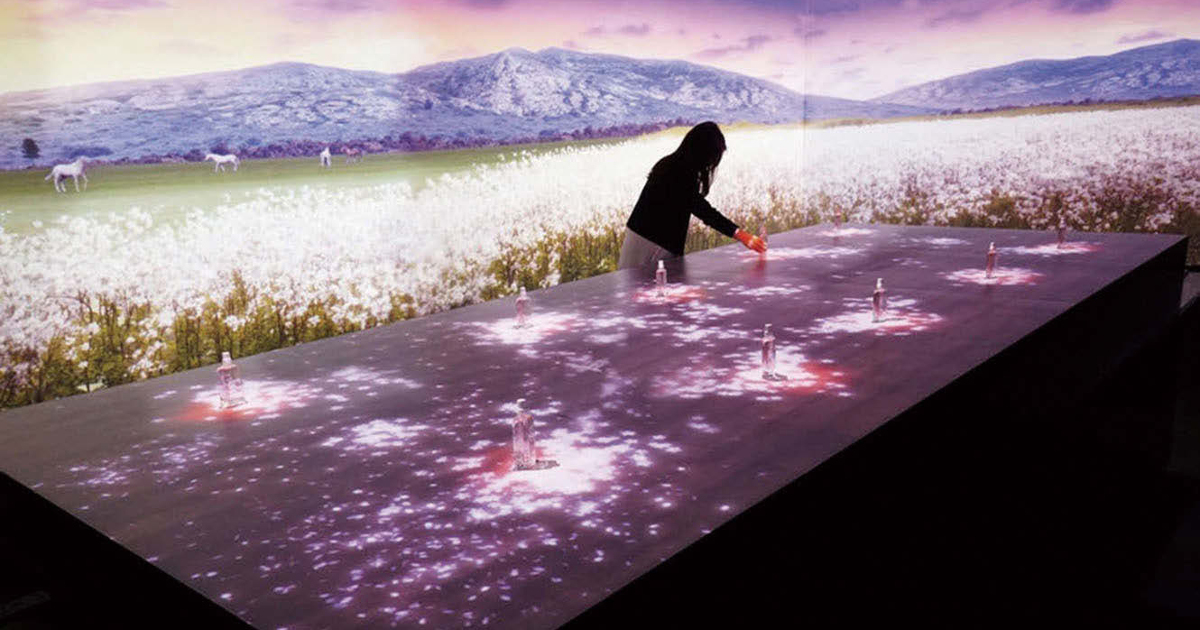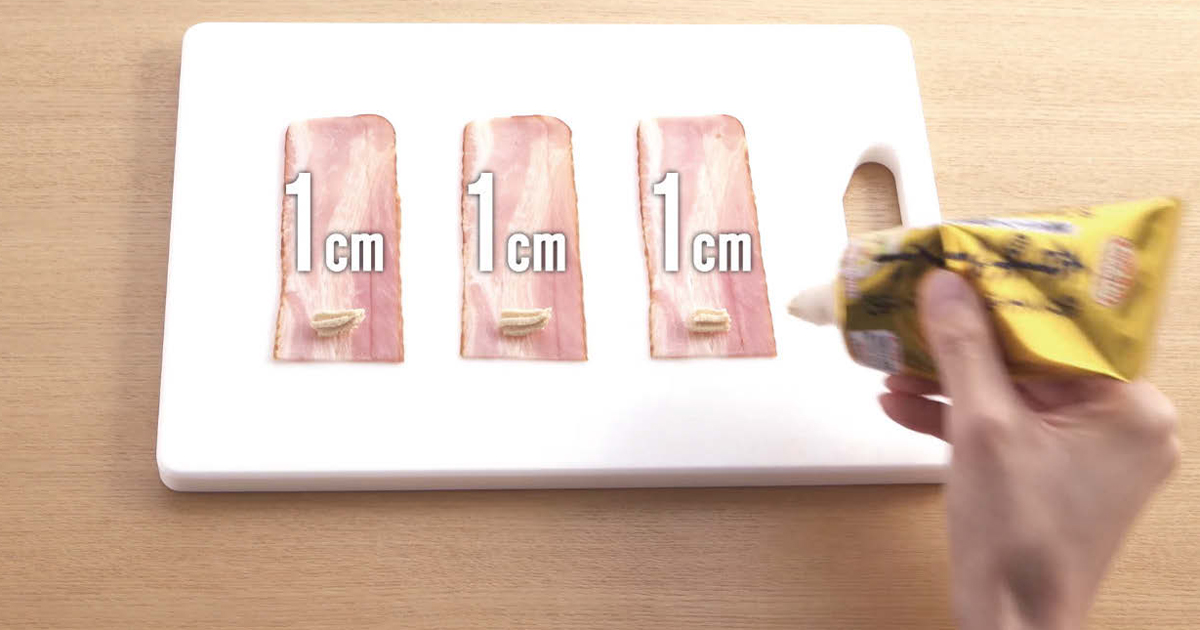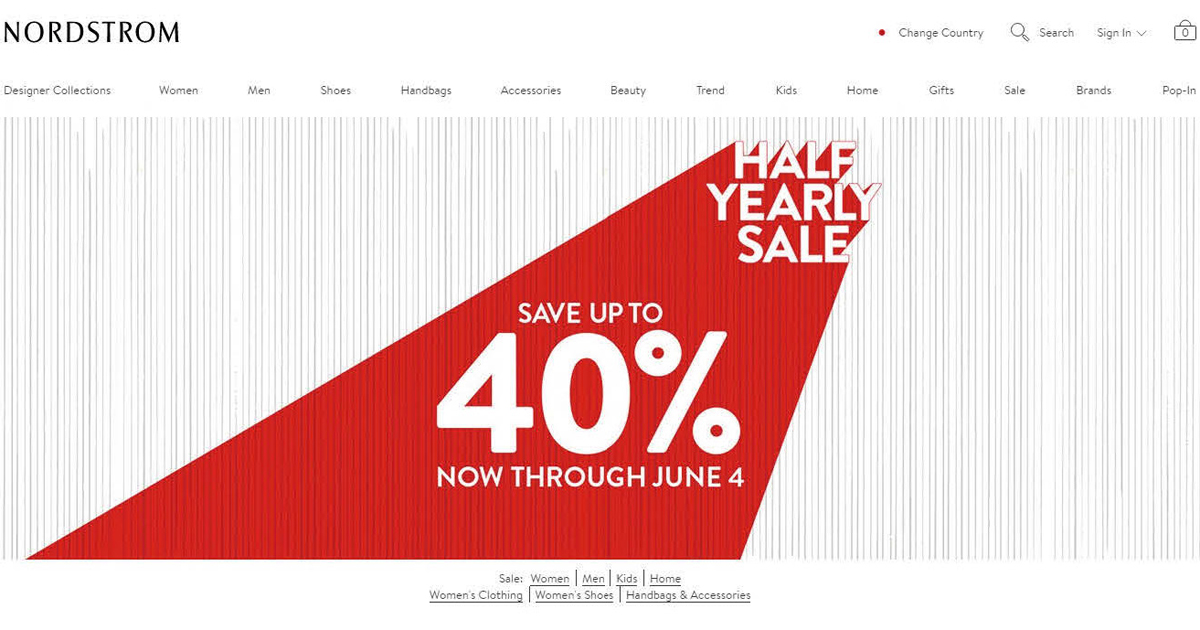宣伝会議は9月7日、8日の2日間、「東京国際フォーラム」(東京・千代田)を会場に、「宣伝会議プロモーションフォーラム2017」を開催した。テーマは「motivate & activate-モノを売る、人を集めるための顧客体験と共感・瞬間を考える-」。来場者は2日間でのべ6000人超。注目の講演を紹介する。
Report 1
ヤッホーブルーイング 代表取締役社長 井手 直行氏
ネスレ日本 飲料事業本部 レギュラーソリュブルコーヒービジネス部部長 島川 基氏

ヤッホーブルーイングの井手 直行社長(左)と、
ネスレ日本の島川 基・レギュラーソリュブルコーヒービジネス部部長(右)
小さくても際立つビール会社とコーヒー世界大手の共通点は
ヤッホーブルーイングとネスレ日本の共通点は、ビールとコーヒーといういずれも成熟した市場に新たな市場を創造し、成長を続けていること。
ヤッホーブルーイングは、日本ではシェアナンバーワンを誇るクラフトビールメーカー。ターゲットやマーケットに応じてブランドを創出する個別ブランド戦略をとる。1997年に創業後8年間赤字が続いたが、その後は12年連続で増収増益を記録している。
ネスレ日本は、インスタントコーヒーを日本に浸透させた老舗コーヒーメーカー。代表ブランドのネスカフェは今年で発売57年目を迎える。市場が成熟した2000年以降に一時成長が止まったが、レギュラーソリュブルコーヒーの発売や企業向けのサービスなどが寄与し、ここ5年で大きく業績を伸ばしている。
対談では、両社が顧客ニーズの捉え方やイノベーティブな思考の育て方を明かした。

常識に囚われない考え方で顧客の潜在ニーズを探る
──どちらも成熟した市場で新たな価値を創造されていますが、なぜそういったことが実現できているのでしょうか?
井手氏:まず前提として、我々は市場の狭いところを狙っているんです。世の中には成熟した市場があったとしても、誰も踏み入れたことがないような、常識にとらわれないポイントは必ずある。それは例えば可能性が少なかったり、険しい道だったりという理由があるかもしれないけれど、そこには必ず潜在的なニーズがあるということを、経験上確信しています。
我々は小さな会社なので、大手ビールメーカー4社と同じ方向に行ってしまったら勝ち目はない。だからそことは違う道を、100人いれば2~3人しか行かない道をあえて選ぶんです。
島川氏:我々とはマーケットにおけるブランドの歴史や立ち位置などがまったく違いますが、ただ一つ共通していると感じたのは、顧客の潜在的な問題を見つけるということですね。我々が一番大事にしているのは、仮説を立ててきちんと検討し、調査では絶対に出てこない顧客の潜在的な問題を見つけること。大がかりな調査は行いますが、それは最後で、立てた仮説をまとめるために行うだけです。
井手氏:我々の場合はすべて自分たちで調査を行います。小人数を対象に深く掘り下げて、仮説を立てて検証し、可能性を感じたら一気に行くんです。
島川氏:そのスピード感は会社が大きくなるとなかなか難しくなりますね。ただ当社でもここ数年間はスピードを重視し、仮説を立てたらまず検証してみるよう言われています。アイデアだけだと、それがどんなにおもしろくても認めてもらえない。社内では失敗しても怒られない文化をつくっていますね。
全社的には5~6年前から、仮説を立てて検証し、結果につながった事例を募集して表彰する「イノベーションアワード」も行っています。これらを通して経営者や管理職の目も養おうと考えているんです。
井手氏:僕が経営者として持っている判断基準は、世の中にないアイデアであること。それをクリアした上で、もしターゲット層が女性や若い世代なのであれば僕の価値基準では判断できないので、直接その層に聞くようにしていますね。

ネスレ日本の島川氏、ヤッホーブルーイングの井出氏の対談講演は朝9時30分からスタート。早めの時間にもかかわらず、多くの人が詰めかけた。