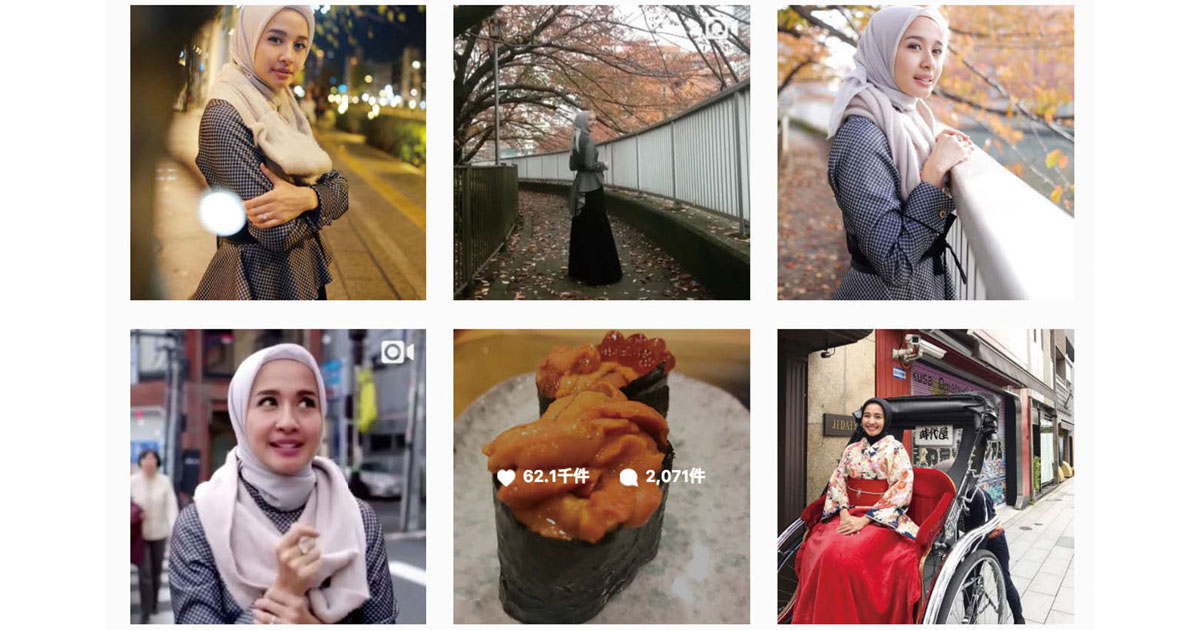地方にある商品に「かわいい」という付加価値をつけ、若者向けにプロデュースするハピキラFACTORY。「地方×女の子」という新たな領域を切り拓く彼女たちは、「かわいい」を入り口に地方を元気にしていきたいと話す。地方の名産品を若者たちに届けるプロデュース術について聞いた。

地方商品のプロデュースは「作る」「広める」「売る」
─ハピキラFACTORYでは地方の名産品の「新たな売り方」を開拓していますが、こうした取り組みはどのような経緯で始めたんですか。
正能茉優:最初のきっかけは、長野県小布施町の名産品である和菓子「栗かの子」をバレンタインギフトとしてプロデュースしたことです。私たちが大学生だった5年前に「まちづくりインターン」として小布施町に行ったのですが、当時はまだ「地方創生」といった言葉も普及していなくて、私たち自身も地方に関心があったわけではなかったんです。
小布施町にある老舗栗菓子店の小布施堂本店を訪れた際に、「栗かの子」(同店では「栗鹿ノ子」)を食べたのですが、それがすごくおいしくて。100年もの歴史があり、原材料は栗と砂糖だけで添加物も一切入っていない。そして何よりおいしいのですが、実際に自分が買うかと言えば買わないなと。それは単純にパッケージがかわいくなかったからなんですね。
山本峰華:小布施堂本店の社長と話をしてみると、「バレンタインデーの商品が売れない」とおっしゃっていて、見せてもらうと「ハッピーバレンタイン」と書かれたシールを貼っただけのものだった。「たしかに売れなさそう」という雑談から、「私たちでバレンタインに売れる『栗鹿ノ子』を作る」というプロジェクトが始まったんです。
正能:それで中身はそのままに、かわいいパッケージにしたのが「かのこっくり」です(下写真)。当時は勢いだけで始めてしまったのですが、大学の先輩のツテをたどってメディアにアプローチしたり、売り場を貸してもらおうと地道に営業するなどして、結果的には渋谷パルコで「かのこっくり」2000個を売り切りました。
山本:「東京の若者女子が地方とコラボしている」というのがメディアにも注目されて、話題にもしてもらえましたね。
正能:その経験を通して、「かわいい」を入り口にすれば、地方と若者をつなげられるのではないかと思ったんです。「かわいい」は、女の子が地方に興味を持つ切り口の一つになる。かわいいからと買ってもらえた商品が小布施町のものだったら、小布施町自体も知ってもらえるチャンスになるじゃないですか。そうして地方にある名産品をプロデュースして地方を元気にしていこうと始まったのが、ハピキラFACTORYなんです。
─プロデュースする際には、どんなことを意識されているんですか。
正能:私たちのプロデュースは「かわいいものを作る」とカン違いされがちなんですが、大事なのは「作る」「広める」「売る」をセットで考えることで、「作る」は全体の3分の1でしかないんです。
最初に「かのこっくり」を作ったときも、自分たちで手売りをしたことで、10日間で2000個売ることができました。でも大手百貨店にただ置いてもらうだけだと、なかなか売れないわけです。当たり前ですが、商品を作ったらそれをステキだと思ってくれる人に対して広めないといけないし、そうして知ってくれた人が買いに行ける場所に商品がないと売れません。私たちも当初、かわいいものを作って、その後に販路を開拓しようとしていたのですが、そもそも販路がないものを作ってはいけないことに気づいたんです。
山本:「『売る場所』が最も大事」というのは、5年間活動を続けてきて確信したことです。いくらかわいいものを作ったとしても、販路をどうするかが最も大事なことなんだなと。ただ同時に、買う人にとって価値を感じてもらえる中身でないといけないというのも、もちろんあります。
正能:以前ある番組でご一緒した堀江貴文さんが、「自分が行ったこともない地方なんて、自分には関係ない」と言っていて、「その通りだな」と思ってしまったんです。東京にいる人からしたら、「小布施という栗が有名な町があって、栗菓子がたくさん売れないと町が潰れてしまうかもしれないんです」と言われても、「自分には関係ない」と思ってしまう。だからこそ、そこに行ったことのない人たちにとって価値を感じてもらうストーリーに変換できるかどうかが大事なんです。
たとえば「100年の歴史がある栗菓子屋さんが大切に作った『栗かの子』なんですが、すごくおいしいんです」と伝えたら、興味を持ちやすい。そうしたストーリーがあってはじめて、かわいくできる。「かわいい」はあくまで中身やストーリーありきなんですよね ...