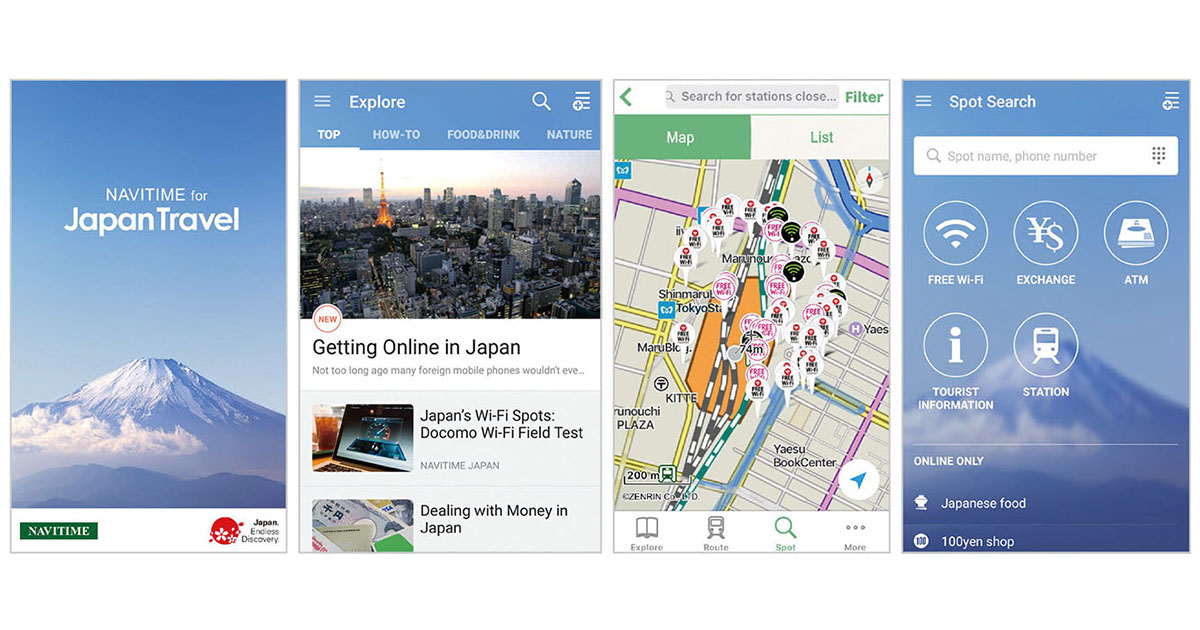LGBTの市場規模は約6兆円(電通調べ)に上るいま、企業がLGBTに配慮したサービスの向上などを考える際にはまず何から考え、どのように配慮すべきなのか。東京レインボープライドの杉山文野・共同代表に聞いた。

マルイがイベント「東京レインボープライド」に出店した際に用意した靴は22.5センチ~30センチまで揃えた
セクシュアルマイノリティも一人の消費者であることを大前提とする
企業が、「LGBTを意識した取り組みをしていこう」と考えるとき、キーワードとなるのは「前提条件」です。
最近はLGBTについての話題が各所で取り上げられるようになってきたことで、「新しい何かが始まった」ととらえている人もいます。しかしそもそもLGBTは最近出てきた新しい人というわけではない。これまでも同じ社会でともに過ごしてきたし、これからもそうです。
セクシュアルマイノリティと聞くと、何となくテレビのバラエティ番組に出ている人や水商売の人など、遠い世界の人だと思われがちですが、実はすぐとなりにいるような身近な存在であり、同じ消費者なのです。
2015年に渋谷区で同性同士のパートナー関係を社会的に証明する「パートナーシップ証明書」の発行が開始され、それをきっかけに世間の認識は大きく変わりました。行政が取り組みを始めたことで、それまでは意図せずとも「いない」という前提のもとに話されてきたことが、「いる」という前提条件になった。
企業も同様にLGBTも一人の消費者であるということを大前提として、LGBTに向けてどうというのではなく、LGBTも含めたすべての顧客、すべての従業員にとってよりよい商品やサービスを考えていくことが大切です。
例として、多様な性・生き方への共感を促すイベント「東京レインボープライド」にも参加している総合小売りの丸井グループでは、そもそものミッションとして「すべてのお客さまのために」というキーワードを掲げています。「すべて」というのは、もちろんLGBTも含めた「すべて」
たとえば、女性用の靴は22センチ~25センチ程度の商品を揃えれば、だいたいマーケットの7割を網羅できるそうなのですが、それよりも足の小さい人もいれば大きい人もいる。LGBTに関して言えば、MTF(男性の身体を持って生まれ、女性の性自認を持つ人)トランスジェンダーは平均的な女性よりも、足の大きな人が多い ...