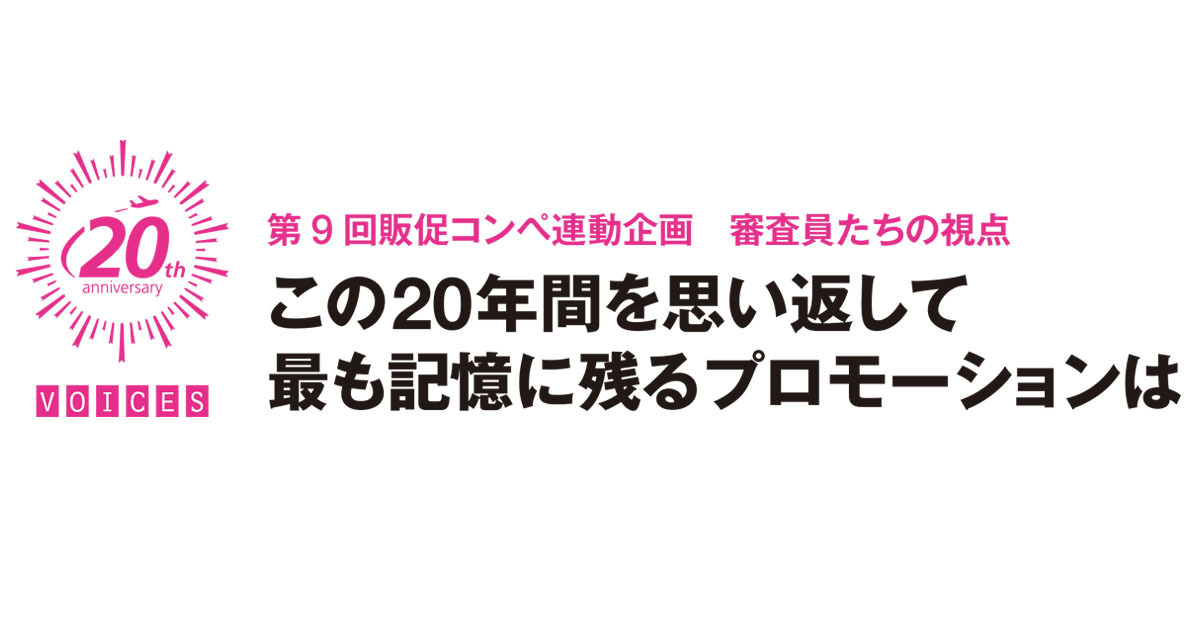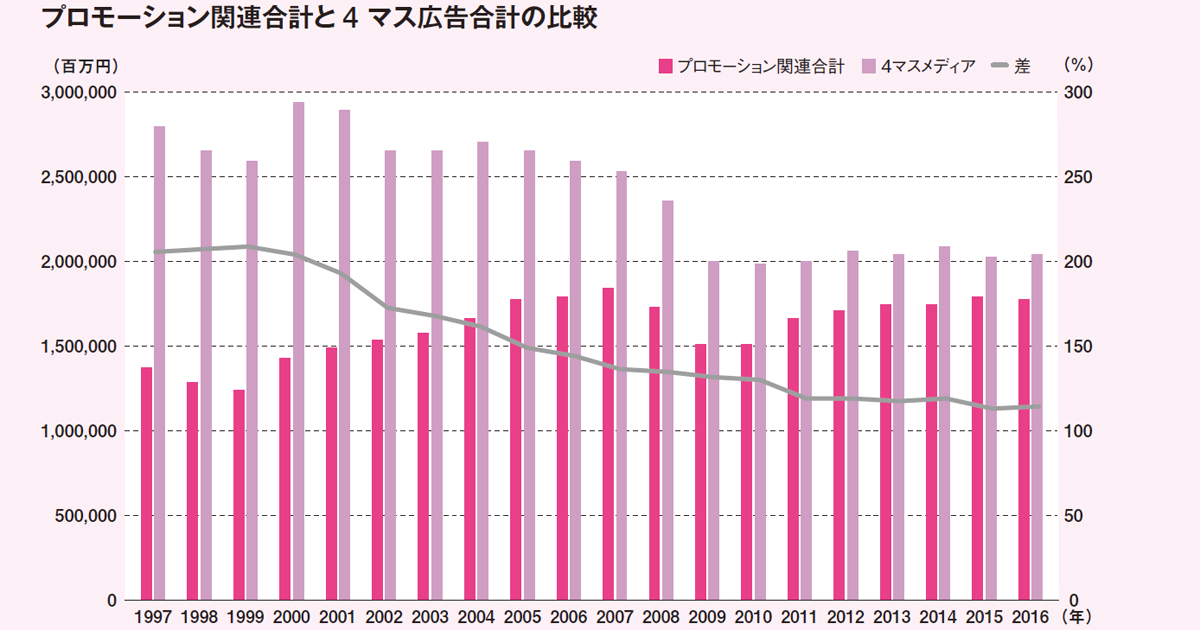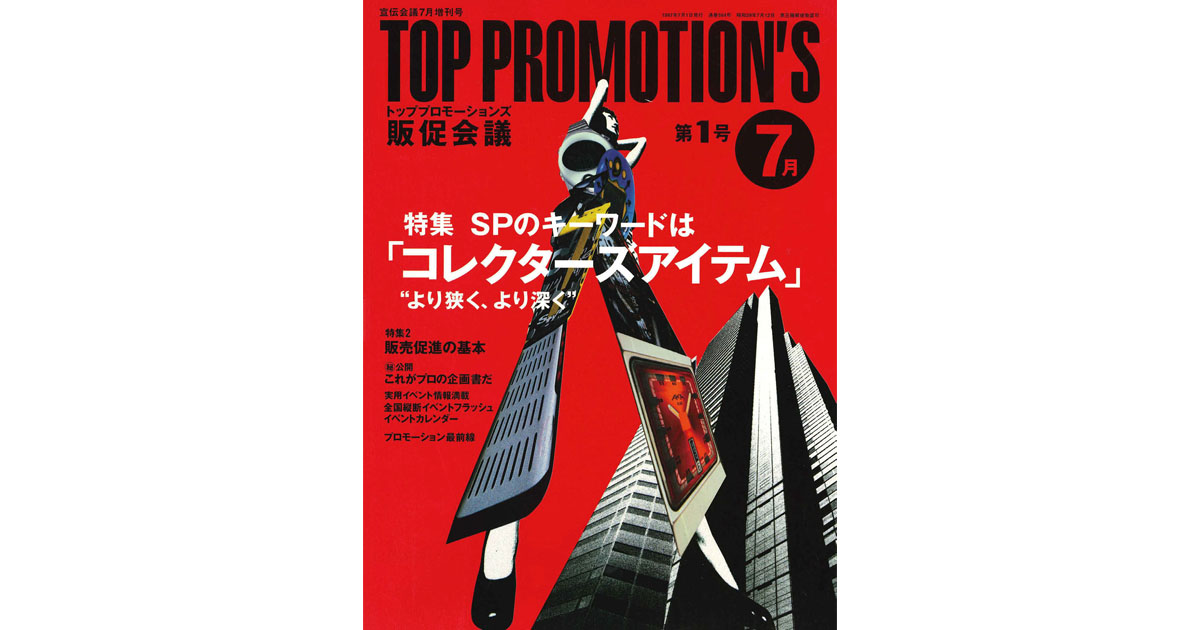訪日外国人観光客数は、2003年に「ビジット・ジャパン(VJ)キャンペーン」を開始して以来、初めて2013年に政府目標の1000万人を突破し、2016年にはすでに2403万人を突破した。ドン・キホーテのプロジェクトリーダーとして活躍しつつ、ジャパン インバウンド ソリューションズ代表、そして日本インバウンド連合会理事長を務め、日本全体の観光立国のけん引役ともなっている中村好明氏に聞いた。

タイTITFに出展した関西美食ツーリズム推進協議会(理事長を中村氏が務める)。
リピーター創出のカギは 来店中の満足度の最大化
──これからのインバウンドビジネスを考える上で、どんなことが重要でしょうか。
まずは、何度も日本に来ている"リピーター"と言える人々を、今後いかに増やせるかが重要です。現在、訪日客の実に60%以上が"リピーター"になっており、いままでの新規客狙いの戦略だけでは通用しなくなりました。新規客向けの施策に加えて、リピーター客向けの施策を作る必要があります。
そこで必要なのが顧客分析です。アジアの国々が豊かになりつつある中、これまでの「これだけお得ですよ」といった低価格プロモーションだけでは、目が肥えたリピーターを獲得するのは厳しい。一度先入観を捨てて、訪日客へのアプローチも国内市場のスペックと同等のハイレベルで取り組むべきでしょう。つまり、しっかりと顧客管理をして満足度を高め、収益をアップさせるCRM的な発想が必要な段階に入ってきたのです。
国内市場並みのハイスペックで取り組むと言っても、もちろん市場そのものがまるで違います。日本人の好みとたとえばアジア各国の人々の好みは大きく異なっています。同じ国でも地域性があり、男女でも違いがあります。それを国内マーケティングにおけるF1層やF2層のように、細かく分析していく。
免税手続きをする際にパスポートの情報を確認しますから、国籍別の分析も容易にできます。こうして精密な市場分析とプロモーションを重ねていけば、訪日客に「ここに来ればあなたが欲しいものが揃っています!」というイメージを訴求できます。その結果として訪日客の顧客満足度が高くなり、リピーター化を促進できるのです。
訪日外国人客を対象とするビジネスに成功している我がドン・キホーテにおいても、品揃えを豊富にして、国ごとにセグメントして売り出しています。タイ人に売れている商品はタイ語のポップを出すなど、商品ごとにターゲットを想定して販売していて、それが"リピーター"化につながっているのです。
こうした訪日客向けのビジネスの転機は2014年10月に訪れました。62年ぶりに免税制度が変わり、それまでは時計やデジカメや炊飯器などの非消耗品だけが免税対象になっていましたが、消耗品も新たに免税対象になりました。そこで一気に訪日客の購入品の幅が拡がり、売り上げの規模が急拡大したわけです。さらに、翌2015年5月には免税手続きに必要な購入者誓約書・購入記録票のデジタル化が許容され、顧客の情報解析がしやすくなりました。
この2014年~2015年の変化は、訪日客ビジネスが劇的に進化する契機となりました。そこから厳密なCRM的発想を持ち、きめ細かいマーケティングを進めていった企業が着実に伸びていますね。
今後、"リピーター"を創出していくためにも、現場スタッフの対応は重要です。アフターフォローももちろん大事ですが、まずは「いま来店していただいている訪日のお客さまの満足度をどう最大化するか」に着目すべきでしょう。そのカギを握るのが現場スタッフです。
正直なところ、訪日客は日本人と文化が違いますから、現場スタッフがコミュニケーションに抵抗を感じるシーンも珍しくありません。言語の壁もあります。それはある意味自然な感情なので、現場の悩みをしっかりヒアリングして解決することが大切です。従業員満足度(ES)を高めていかない限り、グローバルなおもてなしは実現できません。従業員満足度(ES)と顧客満足度(CS)は比例しています。現場スタッフが満足して働けてこそ、笑顔の訪日客の接客が可能になるのです。
たとえばドン・キホーテでは、悩みの種になりやすい言語の壁を払しょくするために、外国人対応スタッフを特に訪日客の多い店舗に配置し、ネイティブのスタッフによるコールセンター「ウェルカムデスク」を設けて、タブレットのテレビ電話で24時間対応できるようにしています。

台湾STE夏期旅遊博会場全体の様子。
「ゼロサム」ではなく「プラスサム」で考える
──これから新しい訪日客を獲得したい店舗であれば、どのような意識を持つことが必要でしょうか。
主要観光地であれば、駅やバス停などの外国語表記やガイドなどの基礎インフラがすでに整っていることでしょうが、整備できていない地域は地域全体でのテコ入れが必要です ...