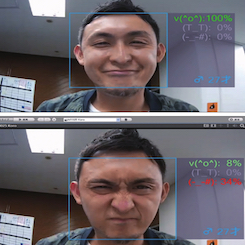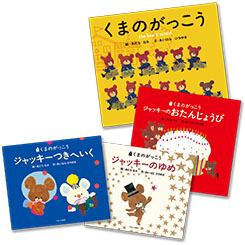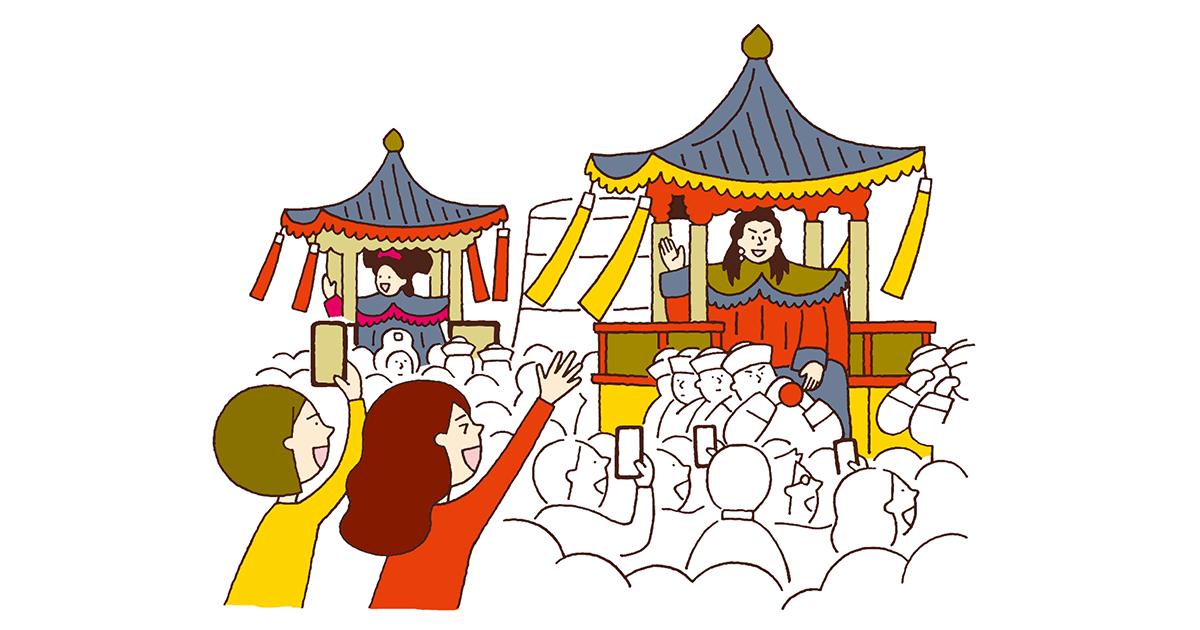企業のマーケティング手法の幅が広がり、最近はデジタルでの施策が主軸になりつつある。紙メディアとしてのダイレクトメール(DM)の価値や活用法はどのように変化したのか。DMだからこそ響くコミュニケーションについて、第31回全日本DM大賞の審査員を務める2人に語ってもらった。

ダイレクトメールはコンバージョンに強い
奥谷孝司(以下 奥谷)▶︎ 私は前職の良品計画でWeb関連施策を担当し、1年ほど前にオイシックスに転職したのですが、正直なところダイレクトメール(DM)については常に受け取る側の立場でした。そういえば、小さい頃に「進研ゼミ」から届くDMは開封していました。あれには僕自身、当事者感覚を持っていましたから。
早川剛司(以下 早川)▶ 私の場合は、ベネッセコーポレーション入社当初から主にDMの制作に携わってきました。「マーケティングといえばDM」という会社だったこともあって、とにかく修行のようにDMを作っていました(笑)。ただデジタルでの手法がマーケティングの世界にも浸透し、私自身もネットマーケティング部を経て、現在はベネッセのグループ会社である東京個別指導学院に所属しています。紙もWebも、一通りのマーケティングは経験してきました。
奥谷▶︎ 広告があふれている現代だからこそ、改めて紙メディアとしてのDMの価値を考えてみてもいいのかもしれません。ベネッセや東京個別指導学院では、DMは内製なんですか。
早川▶ 内製ですね。顧客分析から始め、企画を考えたり、紙面の構成をつくったり、原稿を書くのも、すべて自分たちで行います。進研ゼミのDMにはマンガ冊子が同封されていて、DMは「開封する」というステップがあるんですが、お子さまはマンガを楽しみにしてDMを開封していたのではないでしょうか。
奥谷▶ Webの場合は、パソコンやスマートフォンの画面を通じて平面的な見方しかできない一方、紙は広げるなど立体的に見ることができますよね。そう考えると、実はコミュニケーションの幅が広いと思うんです。早川さんは、紙とWebのマーケティングを長年見てこられて、DMをどう位置づけていますか。
早川▶︎ 最終的なコンバージョンにつなげるメディアとしては、私はDMがやっぱり一番強いと思っています。進研ゼミの場合は通信教育なので、手紙であるDMと相性がよかったということもあります。また「手にとって読める」という点は、訴求力を強める働きが大きいですね。
DMは継続的なコミュニケーション
奥谷▶︎ オイシックスでも、マーケティング手法として紙に関する議論をします。ことし8月にクリエイティブディレクターに就任した水野学さん(グッドデザインカンパニー)が、「紙は、ブランドにとってのクレディビリティ(信頼感)だ」と話すのを聞き、「ああ、なるほど」と思いました。例えば、進研ゼミや塾であったら「子どもにとってのわくわく感」だったり、オイシックスであれば「安心や安全」かもしれない。こうした信頼性は、Webよりも重厚感のある紙のほうが得意分野なのではないかと思います。
早川▶ おっしゃるとおりです。私は同時に、(信頼性を)ストーリーとして伝えることも必要ではないかと考えています。それができるのも、きちんと読んでもらえるDMならではです。私は「刈り取る」という言葉を使わないようにしているんです。マーケティングに携わっていると使いがちな言葉ですが、「信頼性を伝える」という目的とは大きくかけ離れていますよね。我々が姿勢を改めないと、顧客に対しても失礼ではないかなと。
奥谷▶ なるほど、そうですね。
早川▶ DMでも、目先の数字ばかりでなく、継続的にコミュニケーションを図る姿勢が重要です。例えば当社のDMでは、いきなり「今回のDMで入塾してください」というコミュニケーションはせず、まずは「学習のお悩み・お困り事はございませんか?」という入り方をする。経験上、そういう姿勢を示した方が結果もよくなります。DMを受け取ったタイミングで都合よく学習塾を検討している人は少ないですが、おそらく多くの人にとって塾を必要とする時期はあります。そのときにふっと思い出してもらう存在になりたいですね。
奥谷▶ DMも、カスタマージャーニーを描くべきだということですね。
DM大賞では、右脳と左脳を使った作品を期待
早川▶ 最近は、「DMとスマートフォンの相性はけっこういいのではないか」と考えています。スマホで二次元コードを読み取ってもらえば、DMから動画へ誘導することもできる。従来のDMでは伝えることが難しかった授業のようすを見せることもできます。DMを補完したり、連動したりするツールがたくさん出てきていますね。
奥谷▶ 「DM×ソーシャルメディア」や「DM×二次元コード」などの手法にも期待がかかりますね。紙を見て「なるほど」と思ってからアクションするというのは、昔からあったコミュニケーションチャネル。それがいまは、おっしゃるとおり、二次元コードを通じてすぐに動画を見ることもできる。DMという一方通行ではない、「紙→Web」のコミュニケーションはまだまだ可能性を感じます。私はついWebから考えていたので、実は「紙ってそんなに効くものなのか」という疑念もなくはありませんでした。けれどDMは、送付する相手を選べるし、コンテンツも届ける相手によって変えたり、効果測定もできる。そう考えると、紙メディアを用いることに先入観があったと気付かされます。
早川▶ 当社の商材(学習塾)だと「DM×場」もあります。「学習相談の招待券」としてDMを送るのですが、会場まで持って来られる方は少なくない。
奥谷▶ そういえば、少し前に全く知らない学生から、「取材をしたい」と手書きの手紙をもらいました。いまの時代、ふつうメールじゃないですか。だからこそインパクトがあったのでお会いすることにしたんですね。こうした驚きは、私たちマーケターも、お客さまに提供できるのではないかと思います。
早川▶ 私は、自宅に届くDMは一通り目を通すのですが、「担当者の思いが全く入っていない」ということはわかります。「全日本DM大賞」でも、「数字につながる」ことは当然として、制作者の思いが伝わるものをきちんと評価できればと思います。「全日本DM大賞」は、クリエイターやプランナーだけでなく、誰でもチャンスがある広告賞なので、さまざまな視点を持ったDMに出合えるのが楽しみです。
奥谷▶ 私は「右脳」と「左脳」をしっかり使ったDMを期待しています。クリエイティブとして優れているものも好きですが、同時に「これだけ数字が取れた」ということを示したDMを評価したいと思います。現代はソーシャルメディアなどを通して、「消費者から消費者へ」伝わることが理想でもあるからこそ、「One to One to Them」のような企画も話題になるかもしれません。

オイシックス
統合マーケティング部 部長
COCO
奥谷孝司氏
1997年良品計画入社。2010年よりWEB事業部長に。「MUJI passport」のプロデュースで、2014年日本アドバタイザーズ協会Web広告研究会の第2回WebグランプリのWeb人部門でWeb人大賞を受賞。2015年10月よりオイシックスに入社し、Chief Omni-Channel Officerに就任。

東京個別指導学院
グループマーケティング
推進部 部長
早川剛司氏
1995年、ベネッセコーポレーションに入社し、以降、長年DMを中心としたダイレクトマーケティング業務に従事。またCMやデジタルマーケティングなど、幅広いマーケティング領域での業務に携わる。2012年、ベネッセグループの東京個別指導学院へ出向し、マーケティング改革や新事業・サービス開発を推進。2015年4月より転籍、現在に至る。
応募締切は10月31日(月)
「第31回 全日本DM大賞」応募締切近づく
戦略性・クリエイティブ・実施効果などにおいて、優れたDMを表彰する「第31回 全日本DM大賞」がDM作品を募集中。
オフィシャルサイト(https://www.dm-award.jp)から応募を受け付けている。
お問い合せ
全日本DM大賞事務局(株式会社宣伝会議内)
TEL.03-3475-7668
E-mail.info@dm-award.jp
https://www.dm-award.jp