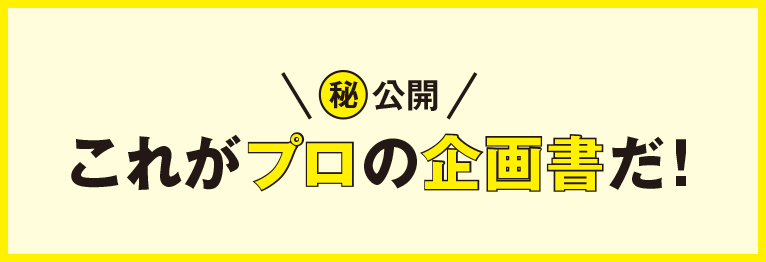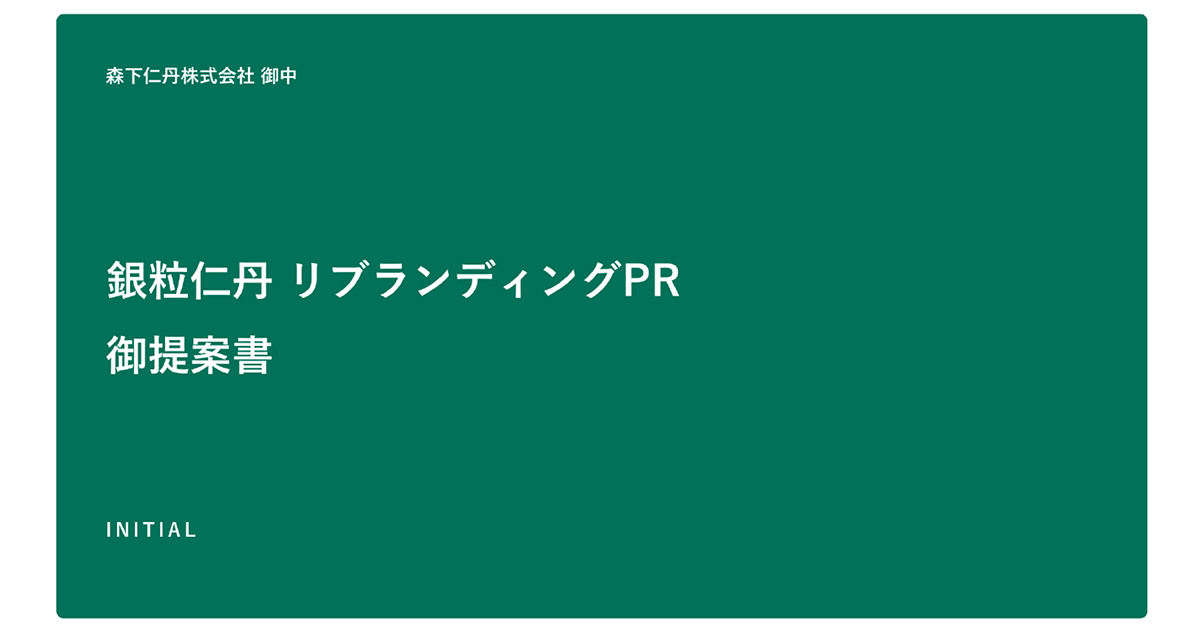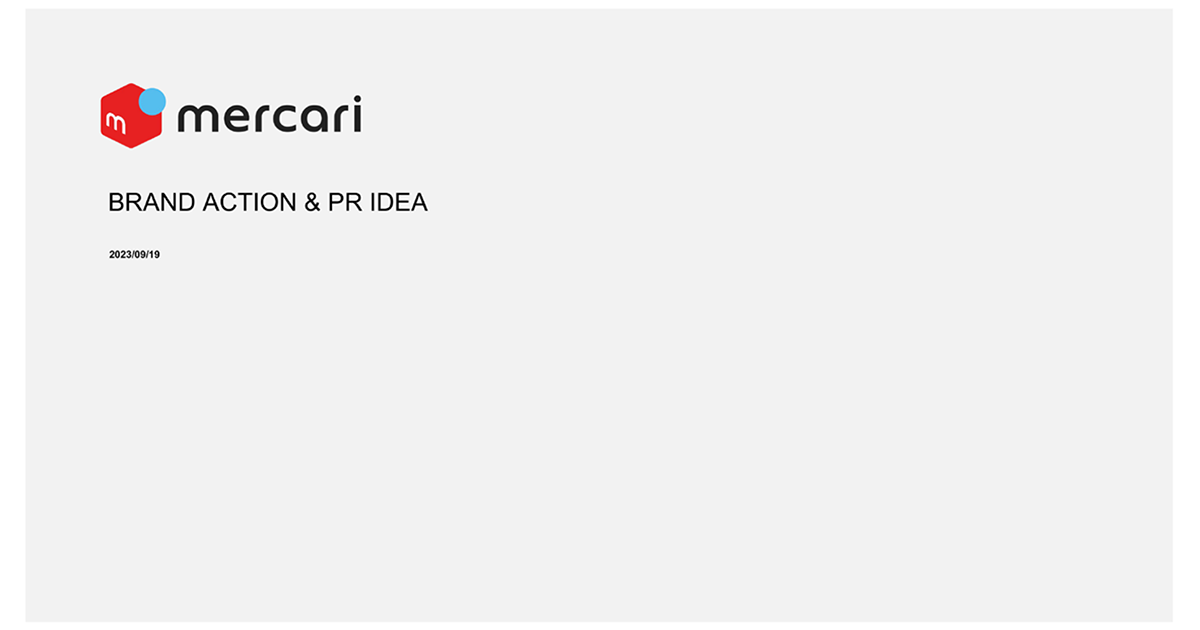データ重視の研究から再認識される広告の力
横浜国立大学経営学部の鶴見ゼミは鶴見裕之氏が流通経済研究所を経て、同大学の准教授に着任した2010年の後期からスタートした比較的新しいゼミ。鶴見准教授の専門分野はマーケティング。特にFSP(ID-POS)データや消費者パネルデータといった購買履歴データを活用した小売店の店頭プロモーションを、いかに顧客満足につなげるかという視点で研究を進めている。
近年は、ソーシャルリスニングに注目し、ツイッターのつぶやきが消費者の購買行動とどのように関連しているのか分析することをメインテーマにしつつあるという。「商品名をキーワードにつぶやきを集め、テキストマイニングをかけて売り上げと関連の強いキーワードや、そのトレンドを抽出する、といったことを研究しています」と鶴見准教授は話す。
こうしたソーシャルリスニングから見えてきた傾向としては、「美味しい」、「身体に良い」といった製品の評価よりも、テレビCMや中吊り広告の内容や印象についての方が売り上げとの関連性が強いことだという。この傾向は、新商品の発売初期に限ったものではあるが、広告で話題を呼ぶことが売り上げ増につながるという結果が出ている。「昨今、広告の評価が下がっていると言われていますが、過小評価するのは危険。広告の効果をしっかり評価するためのリサーチツールとしてツイッターなどのソーシャルメディアを活用することは、今後していかなければならないと思います」と広告が依然として影響力のあるものだと指摘した。
現在は、消費者がツイッターで無意識につぶやいたものを広く、薄く収集し、そこから売り上げと関連するものを抽出しているが、今後はさらに精度を高め、MROC(マーケティングリサーチオンラインコミュニティ)を活用した、より目的を明確にしたデータの収集方法への取り組みも始めている。ただ、MROCには…