シャレや異論が通じる社会に。広告もコミュニケーションも、もっと多様でいい。
マンガ家・イラストレーターの江口寿史さんは、1977年に『週刊少年ジャンプ』でデビュー。その後、ヒットメーカーとして日本のギャグマンガを革新させてきた。また、活躍の場をイラストレーションに広げ、独自の画風によって、広告、雑誌・小説の装丁、CDジャケット、キャラクターデザインなど多彩な分野で今に至るまで「江口ワールド」を広げている。

マンガ家・イラストレーターの江口寿史さんは、1977年に『週刊少年ジャンプ』でデビュー。その後、ヒットメーカーとして日本のギャグマンガを革新させてきた。また、活躍の場をイラストレーションに広げ、独自の画風によって、広告、雑誌・小説の装丁、CDジャケット、キャラクターデザインなど多彩な分野で今に至るまで「江口ワールド」を広げている。

ハリのあるよく響く声と、明るく溌剌とした表情でユーモアを交えながらも、情熱的に語りかけるその人・佐伯チズ氏は1943年生まれの人気美容家。73歳の今もお客さまに対して直接施術を行い、テレビや雑誌、講演会などを通じて美容家・生活アドバイザーとしても活躍している。

在学時代からバーチャルリアリティに興味を抱き、SFアニメ「攻殻機動隊」に登場する技術「熱光学迷彩」を実在化させた鬼才のエンジニアとしてその名を知られる、東京大学 先端科学技術研究センター教授の稲見昌彦氏。SFと科学、人間能力の拡張した先に交錯した未来とは、どんな世界なのだろうか。世界が注目する研究の裏側や熱い想いなどを聞いた。

日本がメディア芸術大国になれるか否か、ここ数年が勝負の分かれ目だと言われている。国内で5番目の国立美術館として開館し、躍進を遂げる、東京の「国立新美術館」。館長・青木保さんに、文化人類学的フィールドワークの視点に立った現代アートの発展と、現在のマスメディアにおける課題など、話を聞いた。

人間国宝5代目柳家小さんを祖父にもち、自らも戦後最年少の22歳で真打に昇進した柳家花緑さんは、古典落語はもとより、これまでにない現代の落語にも取り組み、敷居が高い古典芸能という落語のイメージを払拭して、多くの人々に親しまれてきた落語本来の姿を取り戻そうと奮闘している。

料理研究家の行正り香さんのレシピ本は、普段見慣れたメニューが、おいしくお洒落に、しかも簡単にできることで人気だ。2007年に電通を退職してからは、料理のほか、インテリア、Webコンテンツ・アプリの開発、レストラン経営など、活動の場が、ますます広がっている。
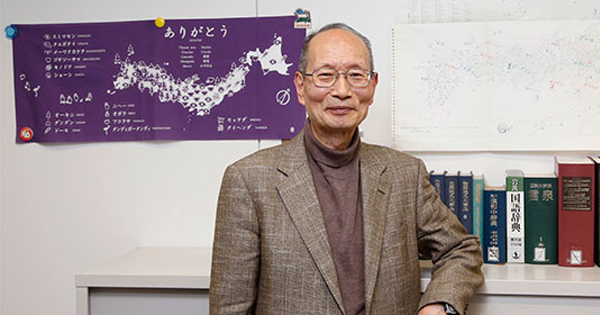
かつて方言は「訛り」と言われ田舎者の象徴だった。ところが昨今では、方言をネーミングやデザインに使った「方言みやげ」「方言グッズ」が続々と登場するなど、むしろポジティブに受け入れられている。こうした現象はなぜ起きるのか。方言研究の専門家で、東京外国語大学名誉教授の井上史雄さんに話を聞いた。

2013年、「和食」がユネスコ無形文化遺産に登録され、世界の大都市を中心に和食ブームが過熱している。登録の立役者となったのが、日本文化史や茶道史に精通する歴史学者・熊倉功夫さん。無形文化遺産登録の裏側や、和食の価値、人と人との絆を育む日本の食文化について話を聞いた。

主人公の食事シーンや心理描写を描く漫画『孤独のグルメ』。これまでにないスタイルが注目され、異例のロングヒット作となり、テレビドラマ化もされた。原作者であり、漫画家、文筆家、ミュージシャンなど多岐にわたり活躍する久住昌之さんに話を聞いた。

グローバルに活躍する人材の育成が日本社会におけるテーマになる中、国際バカロレア(以下、IB)への注目が高まっている。IBディプロマ・プログラムの一部科目の授業と試験・評価を日本語で実施する「日本語と英語によるデュアルランゲージ・ディプロマ・プログラム(以下、日本語DP)」の普及を目指す、国際バカロレア・デュアルランゲージ・ディプロマ連絡協議会の会長、長谷川 正さんに話を聞いた。