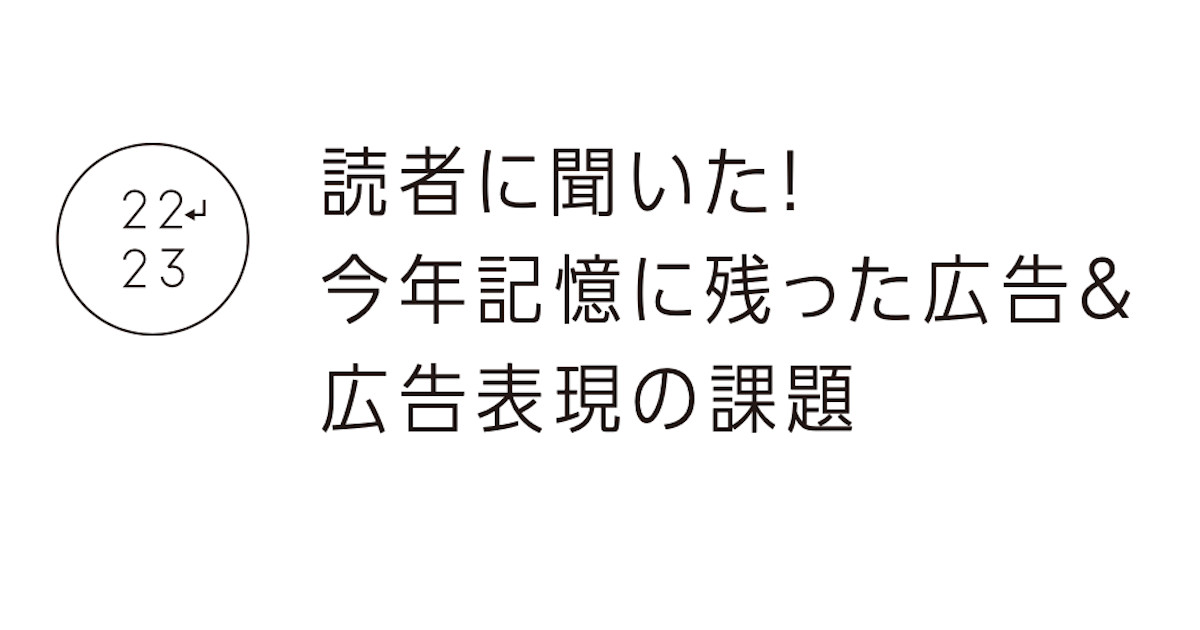2022年も終わりに近付いた今。皆さんはこの1年をどう振り返りますか?今回は今年話題になった広告を多数手がけた電通関西支社 古川雅之さん、博報堂 小島翔太さん、kakeru 明円卓さんに集まっていただき、2022年特に記憶に残った広告や「広告が元気ない」問題について、また2023年に取り組んでみたいことなどを語ってもらいました。
2022年に感じた「新しさ」
──2022年を振り返り、注目した事例は何でしたか?
明円:素敵な仕事がたくさんある中で迷いますが、2021年の衆院選に続き、2022年の参院選でも投票を呼びかける動画「投票はあなたの声」を制作・公開した「VOICE PROJECT」を挙げたいです。僕個人としては、広告業界で勉強したこと、企画する中で学んだことを他のプロジェクトや創作物に転用していけたらいいなと思っていて。「VOICE PROJECT」は発起人が関根光才さんや菅原直太さん、大越毅彦さんといった広告業界で映像をつくってきた人たちで、だからこそ一流のスタッフを巻き込んでプロジェクトとして成立させていたのが印象的でした。
これを見て、今後は企画やプロジェクトをつくれる人が活躍するんだろうなと強く感じましたし、自分のスキルを用いてあんな風に社会に打ち出していくのが、志が高くて素晴らしいなと思いました。

参議院選挙公示日の6月22日に公開された、「VOICE PROJECT」による投票を呼びかける動画の2022年度版。
古川:コロナ禍でリモートが当たり前になってきてから、特に若い世代が軽やかにつながっていく感じがいいなと思っています。遠くにあった才能が自由に結び付いて、面白いものをつくってまた分かれていくみたいな。同じチームでずっと続ける伝統的なつくり方もあるけど、どんどん新しいものが生まれる素地を感じました。
小島:僕も迷いましたが、松田翔太さんが出演したコインチェックのCMシリーズ(2021年9月~)を挙げます。2021年の事例になりますが今のこの時代において飄々としていて、抜け感がめちゃくちゃあって。クライアントの業態的にも一見難しそうな仕事なのに、あんな仕上がりになるのはすごいなと思いました。僕はアクティベーションの出身で、テレビCMのようなメディア費が確保されていないことが多い中で、とにかくデジタルでバズらせなきゃと戦ってきたので、「世の中で既に面白いとされているもの」のエキスを用いた企画じゃないと怖いという癖がなかなか抜けなくて。
それに対してこのCMは、世の中にあるようでなかった面白さを打ち出しているのが、飄々としていて最高だと思いました。もし自分にあの仕事が来たら、どうしただろうな……と考えちゃいましたね(笑)。
古川:たしかに。つい商品やサービスの中身を、ちゃんとうまく説明しなきゃって思ってしまいますもんね。
小島:そうですよね。古川さんはいかがですか?
古川:2022年のACC賞のラジオ&オーディオ広告部門の審査委員長をやらせていただいて、その中のBカテゴリー(音声コンテンツ)でゴールドを獲得した「COTENRADIO(コテンラジオ)」です。簡単に説明させてもらうと、世界史のデータベースを開発しているスタートアップ企業のCOTENが、知名度がない・人材が集まらない・資金が集まらないという悩みを一発で解決できる広報活動がないかと考える中で、自分たちの武器である歴史への愛を音声で届ける、つまりポッドキャストの番組をつくることにしたと。それを通じてブランド広告・リクルート広告・投資家へのプレゼンテーションという3つの課題をいっぺんにクリアした、鮮やかなPR活動でした。

スタートアップ企業のCOTENが2018年11月から配信する「歴史を面白く学ぶCOTEN RADIO」。
小島:僕もACC賞のブランデッド・コミュニケーション部門の審査委員をやらせていただいて、そのBカテゴリーではグランプリでしたね。
古川:多くのカテゴリで高い評価でした。僕自身、面白いポッドキャストのひとつとして聞いていたんですが、それがACCに応募されたということに最初はびっくりしました。でも歴史が好きでたまらないという「個人の好き」という力だけで、こうも切り開いていくのがとても今っぽいなと。
小島:僕も以前から聞いていて、ACCに出てくるんだと驚きましたね。でもひとつのコンテンツが担う役割が多く、ベンチャー企業の広報活動としてとんでもなく正しいなと。歴史には経営者層が学べることがたくさんあるので、その面からもアプローチできる、などと審査では話が挙がりました。
明円:ACC賞の2022年の受賞ラインアップを見ると広告に境目がなくなっているのが特徴的ですよね。僕も自分でお店や企画をやったりしているんですが、そういうのも対象になるのかなと「コテンラジオ」の受賞を見て思いました。
小島:出したら賞を獲れる可能性があるものがたくさんあるなと気付かされましたね。現場の僕らからすると「じゃあどうすればいいんだ」と悩まされるところですが、同時に可能性を広げることになるので、転換点になるかもしれないと感じました。
古川:2021年のACC賞では「THE FIRST TAKE」のプラットフォーム、コンテンツ力が話題になりました。一気にブレイクするようなビッグアイデアもまだまだある。
古川さんの2022年の仕事から

日清紡ホールディングス 「歌おう!ニッシンボー」シリーズ 「うま」篇・「カワウソ」篇
10年前の犬の二人羽織から始まったシリーズ。「名前は知ってるけど、何をやってるか知らない」という歌の反応が良かったので、犬、タレント起用、マレーグマと、形を変えながら続けてきました。2022年は3頭のうま篇、カワウソ篇をつくったら、これまでで一番スコアが高くなりました。「10年目。今、なぜ話題になっているのか正直わからない(笑)」のが正直な感想ですが、情報量の少なさから子どもたちにも人気で歌ってもらえているみたいで、続けてきたのが確実に財産になっていると感じます。
「広告業界は元気がない?」への答え
──新たな事例が生まれる一方で、「広告の元気がない」という声も挙がります。皆さんはどう見られていますか?
明円:メディア環境が昔とは違って、みんなが見ているものがバラバラだから、必然的に昔のようにお茶の間のみんなが知っている広告は生まれづらくなっているとは思います。
古川:『ブレーン』『コマーシャル・フォト』『広告批評』とか広告雑誌をみんな買って読んでいて、若者は会社の先輩の机から盗み読みして、みんなで話題にするっていう頃があった。いま良いとされている広告を貪欲に知りたいと。いま世代を超えて広告をフランクに語る機会は減ってますよね。
小島:ACC賞を改めて見ても、みんなが知っていてみんなが大好き!というものが昔に比べると減っているかもしれないですね。
古川:若い人が広告賞にどれだけ積極的かというのも元気のバロメーターですよね。もちろん広告から派生した広告以外のことを目指す人が増えるのも健全でいいと思うけど、純粋に広告のアイデア一本で突破することを目指す人はどれくらいいるのだろうか、と心配になることもあります。何をもって「広告が元気」と思うかといえば、見たことない、ようこんなん考えたな、クライアントもよく通したな、という新しさや挑戦のある表現を見たときですよね。