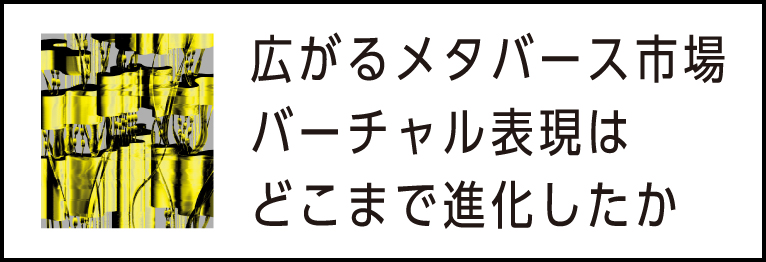川村元気さんによる原作・脚本・監督作品『百花』は、主人公・葛西泉(菅田将暉)と認知症を患った母・百合子(原田美枝子)の「記憶」を巡る物語だ。日々記憶を失っていく百合子の対比として描かれたのが、泉と妻の香織が仕事で制作したバーチャルヒューマンアーティスト「KOE」。KOEは数々のアーティストの記憶から生成される。忘れていく人間と、記憶の集積で生まれるAI、その狭間の描写で川村さんが描こうとしたものとは。

バーチャルヒューマンアーティスト「KOE」。
「記憶」と「人間」の関係性
そもそもKOEは、原作『百花』(文春文庫)では生身の人間として描かれていた。自主制作のミュージックビデオを通じてネットで話題になり、約1年でレコード会社との契約に至った“破格の新人”KOE。その宣伝担当になったのが主人公・泉だ。しかしデビューに向けたレコーディングの直前で、彼女は突然姿を消し「音楽を忘れてしまった」と話す。それに対し泉は「KOEが音楽の記憶を失った代わりに得たものは何か」と疑問を抱く──。
川村元気さんがこの小説を書くきっかけとなったのは、自身の祖母が認知症になったことだった。対談集『理系。』(文春文庫)において、記憶にまつわる話を深掘りする中で、川村さんは人工知能の研究者 松尾豊さんとこんな話をする。
「人工知能は、コンピュータにひたすら記憶をさせることでできるのだと。ということは、記憶を詰め込んでいけば人間が生まれるのか。逆に、記憶が失われると人間ではなくなるのか。記憶を失っていく人間に人間らしさは残らないのか、と不思議に思って。そこで反対に、完璧な記憶を持つAIはどうしたら個性を持てるだろうか、と考えました。もし自分で画家のAIをつくるなら、ゴッホやピカソなどあらゆる画家の記憶を入れた後に、特定の記憶を抜くだろうなと。たとえば『赤』という記憶を抜くと、AIは失った『赤』を表現するために一生懸命ユニークなものを生むのではないかと考えたんです」。
記憶から何かが欠損した時に、それを補い満たすものにこそ、その人らしさが表れるのでは。それが映画『百花』では、母・百合子の姿を通じて描かれている。その様をより鮮明に描くべく、KOEは映画版で、あらゆる歌の記憶を詰め込まれ完全な記憶を有す人工知能/バーチャルヒューマンとして描かれたのだった。

映画公開に合わせて公開された、劇中でKOEが歌う主題歌のミュージックビデオ。

「KOE」は劇中で、記憶の集積で生まれたAIを有す、完璧で異質な存在として描かれた。

映画『百花』は第70回サン・セバスティアン国際映画祭にて日本人初となる最優秀監督賞を受賞した。
©2022「百花」製作委員会
完全さと、個性の無さを両立する表現
そのため、KOEの制作時は「あらゆる歌の記憶を持つ」人工知能としての完璧な魅力と、それが故に現実と非現実の境が曖昧になるような没個性の異様さを併せ持つ姿を具現化することが求められた。そこで「日本中のVFXやCGのプロデューサーに会った」と...