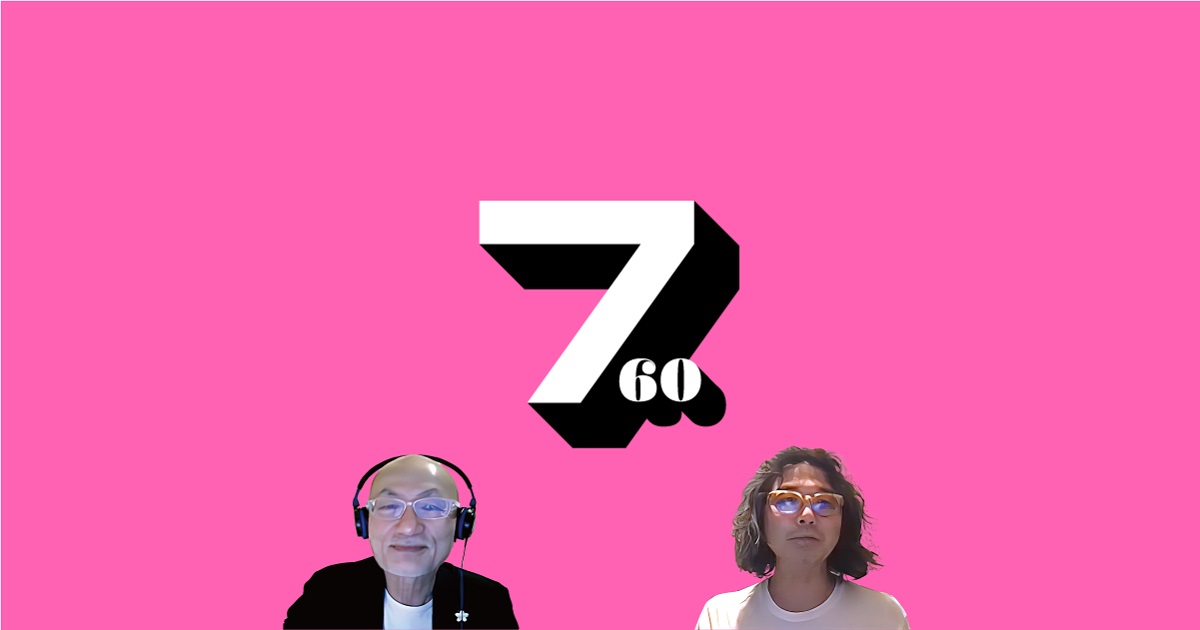近作『チョコレートドーナツ』をはじめ、数々の舞台作品で、LGBTQや障害といった社会課題に触れるほか、コロナ下では医療従事者などを支える「上を向いてプロジェクト」を立ち上げた宮本亞門さん。コミュニケーションテクノロジーによって人類の孤独を解消することを目指して、分身ロボット「OriHime(オリヒメ)」の開発や社会実装に取り組む吉藤オリィさん。
舞台演出、ロボット開発と、それぞれのフィールドで活躍する一方、青春時代にはともに引きこもりを経験した2人に共通している、クリエイティビティの源泉とは。社会課題や多様性との向き合い方や、その覚悟、さらにこれからの時代を生きるためのヒントをうかがった。

人間は多様性に対する許容度が高い
吉藤:「人間が動けなくなった後、寝たきりの先に憧れをつくる」を研究テーマに、「OriHime」という遠隔操作できる分身ロボットの開発をしています。ALS(筋萎縮性側索硬化症)をはじめ、重度障害を持った人が、OriHimeを使ってコミュニケーションをとったり、イベントに出演したり。私はかつて引きこもりを経験して、生きることに絶望した人間なので、何もできなくなってしまうことが本当に怖くて。最終的には、大きなOriHimeをつくって、寝たきりになっても自分で自分の介護ができる時代が来ると信じています。
宮本:素晴らしい!自分で自分の介護ができる時代ですか。誰も好き好んで介護をしてほしいわけではないですからね。
吉藤:ありがとうございます。番田雄太という、亡くなってしまった私の親友がいるのですが、彼は4歳のとき交通事故に遭ってから20年以上、ほぼ体を動かすことができませんでした。OriHimeに腕が付いているのは、彼のこだわりによるものなのですが、「番田雄太です。寝たきりです。盛岡から操作しています」と言って、手をバタバタしながら話すと、アイスブレイキングの効果が全然違うんです。
宮本:アイスブレイキングが起こるなら、たとえば手が千手観音のように何本もあってもいいですよね?
吉藤:そうですね。VTuberやVRの世界では、もはや人は人の形をしていなくて、尻尾を振ることが感情表現のひとつになっています。しかも、見た目はかわいい女の子だけど、声を聞いてみるとおじさんというケースもよくあって(笑)。初めはそれに違和感を感じますが、しばらくすると慣れてしまうんですね。
宮本:おじさんの声がするキャラクターと恋に落ちることもある(笑)。ますますジェンダーフリーになりますね。
吉藤:そういう未来は、全然あり得るでしょうね。初音ミクやアニメのキャラクターもそうですが、キモかわいいとか、エモいといった新しい感覚によって、私たちはこれまで想像もしていなかったものを受け入れてきたわけです。人間は、多様性に対する許容度が意外と高いぞ、というのはすごく感じます。
宮本:セクシュアルマイノリティの概念もまだ特別なことのように語られるけれど、「そういえば昔、LGBTQなんて言ってたよね」という時代が来ることを願っています。
吉藤:ええ。インターネット上のコミュニケーションにおいては、身体の障害は障害化しませんし、見た目もアバターなどを使うことでコントロールできますから。
宮本:オリィさんは、確か大学時代に演劇をやっていましたよね。身体の意味という点では、コロナ下では「生の肉体が、そこにあることこそが演劇だ」という意見もありましたが、どう思います?
吉藤:もはやそれは、選択肢のひとつですね。私たちは今、初音ミクのVRライブを見て熱狂することができるまでに進化していますし、人形浄瑠璃のようなツールを使った演劇は昔からありました。反対に、生身の人間がツールを使わずに演じる、その価値が高まることもあり得るでしょう。
宮本:人形浄瑠璃は、人形と人間。歌舞伎や宝塚は、異性の役になって演じ、“カブく”ことで、一段と本質や魅力を引き出す。それって、日本独特の面白さかもしれない。
吉藤:表現の違いについては明るくないのですが、開発者の視点からいえば、日本人はロボット的なものを許容する素養がかなり高いと感じます。私たちは、あらゆるものに命を見いだす種族ですし。
宮本:八百万(やおよろず)の精神ですね、生身の人間とあらゆるモノ、自然にも魂を感じ、同じように受け入れる。
吉藤:ハリウッド映画では、ロボットやAIは反乱を起こす悪いものとして描かれますが、日本の場合は、ドラえもんや鉄腕アトムのように友だちになれる。そもそものイメージがポジティブですよね。
宮本:では、あえてネガティブな質問をすると、人間がコントロールできないようなロボットが現れたら?
吉藤:そうですね。これまで私たちは、100%言うことを聞いて、完璧に仕事をしてくれる、従順なロボットしかつくってきませんでした。でも今は、ソニーのaiboのように未完成なロボットが登場しつつある。愛おしさみたいなものに価値があるという方向に変わりつつあるのも面白いところで。
宮本:完成されすぎていない方が愛着を持ち、応援したくなるというのは芸能界でも同じですね(笑)。オリィさんは、そもそもなぜロボットの研究を始めたんですか?
吉藤:高専時代には元々、人工知能の研究をしていたんです。友だちをつくるのって大変じゃないですか。出会って、話しかけて、仲良くなって、連絡先を交換して……何か人間の友だちってコスパ悪いぞ、と(笑)。それで人工知能の研究を始めたのですが、AIから、いくらいいリアクションをもらっても、うれしくないんですよ。
宮本:なるほど(笑)。
吉藤:いつかAIのキャラクターに何かを言われて、喜びを感じられる時代が来るのかもしれませんが、まだ人類はそこまで進化していません。人と話すことが苦手なのであれば、コミュニケーションを補助してくれるような機器をつくった方がいいという方向にシフトしていきました。

ミュージカルショートムービー『ギョロ 劇場へ』。
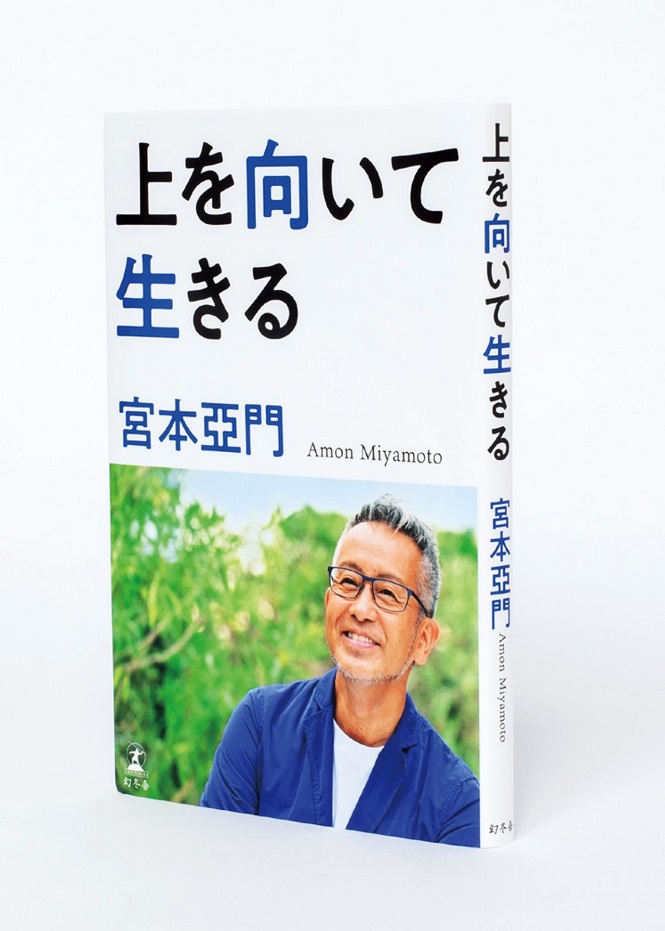
『上を向いて生きる』(幻冬舎)。

モーツァルト『魔笛』東京二期会オペラ劇場にて、9月に上演予定(撮影:三枝近志)。
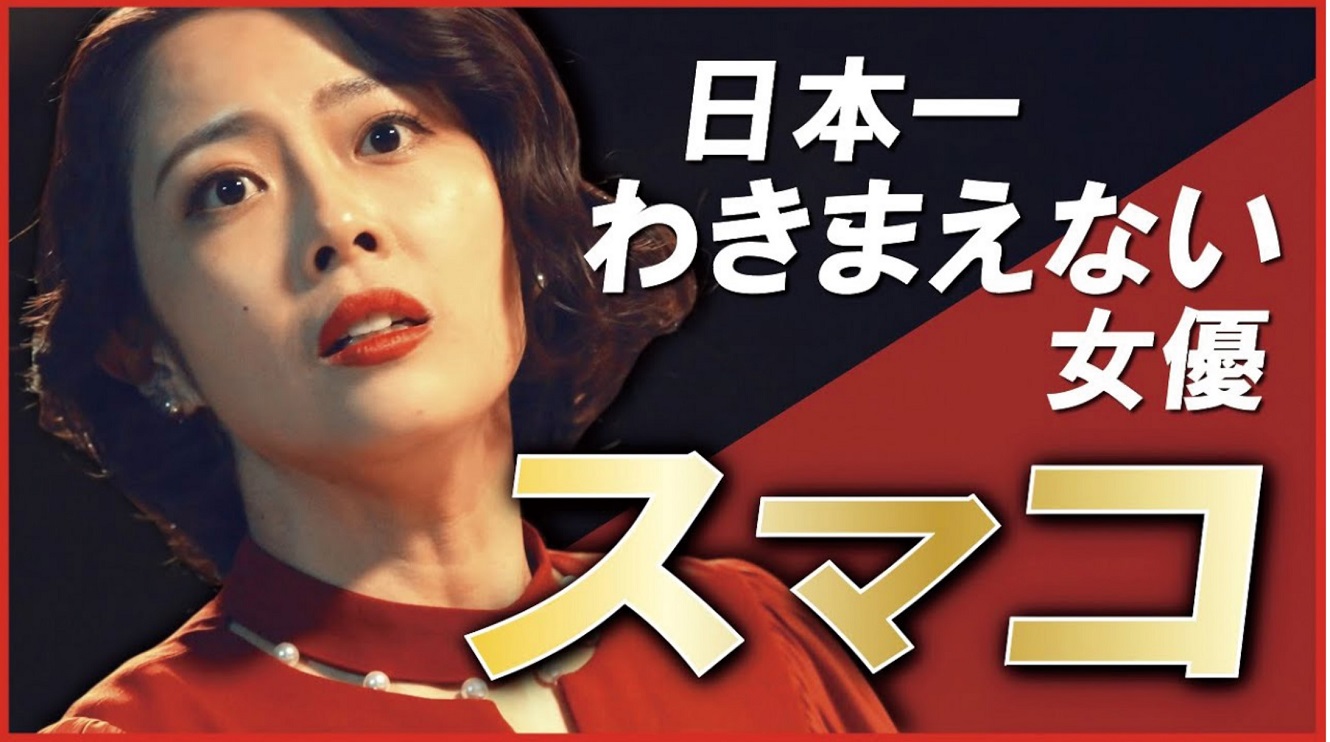
『日本一わきまえない女優「スマコ」~それでも彼女は舞台に立つ~』(YouTubeで無料公開中)。
引きこもり、コミュ障からの脱却
宮本:僕は学校が好きではなくて、いつも息苦しかった。日舞やお茶、仏像と、趣味が変わっていたから、誰とも会話が合わなくて。だから子どもの頃に、コミュニケーションを補助してくれるものがあったらと思って。でも、いつかロボットが助けてくれる時代が来るかもしれませんね。
吉藤:ロボットじゃなくても、そういうツールはつくれそうです。たとえば、めちゃくちゃコミュ力の高いナンパ師のAIが搭載されたメガネがあって、目の前の人から言われた内容を音声認識して選択肢を出してくれる。あとは、選んでしゃべるだけ、なんてことも実現できるかもしれない。
宮本:それは大人になっても、メガネを外せなくなっちゃうな(笑)。オリィさんも僕と同じように、不登校や引きこもりの経験があると聞きましたが、いつ頃からこういうふうにペラペラしゃべれるようになったんですか?
吉藤:大学に入ってからですね。17歳のときに「孤独の解消」に人生を捧げようというテーマを決めたものの、人工知能でつまずいてしまった。やっぱり人間と話せないと説得力がないということで、コミュ力の猛特訓をしたんです。演劇をしたり、パントマイムをしたり、社交ダンスをしたり。中でも、キャンプ場の説明員のアルバイトはよかったですね。私が10分以上話し続けると子どもたちが飽きて遊び始めてしまうので、限られた時間の中で用件を伝える訓練ができました。
宮本:「孤独を解消したい」というより、どうすれば人と早くコミュニケーションを取れるようになれるか、という欲求のほうが強い気がしますね。
吉藤:私の「孤独」の定義は、ただひとりぼっちでいることじゃなくて、自分は誰からも必要とされてないんじゃないか、どこにも居場所がないんじゃないかと感じてしまう状態のこと。そのつらさを解消したいんです。ちなみに亞門さんは、なぜ演出家を志したのでしょうか?
宮本:高校生のときは、四畳半の部屋に引きこもって、音楽ばかり聴いていました。そうしたら、脳内世界がどんどん広がってしまって、自分の中に...