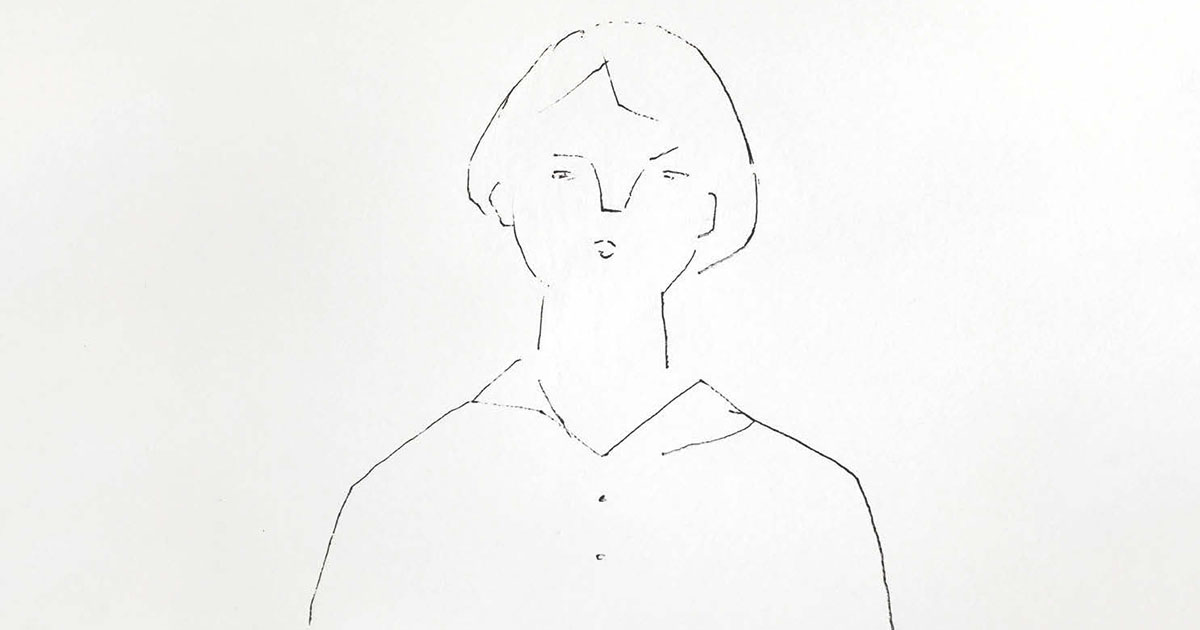広告はもちろん、空間デザインやテクノロジーを活用した企画などさまざまなアートディレクションを手がけてきたDentsu Lab Tokyo 小柳祐介さん。「見たことのないものをつくる」というイズムが根底にある。

小柳祐介(こやなぎ・ゆうすけ)
アートディレクター。1982年東京生まれ。東京藝術大学デザイン科、大学院にてコマ撮りアニメを8年間研究後、2010年電通入社。現在、Dentsu Lab Tokyo 所属。広告、スペースデザイン、テクノロジーなど、領域に垣根なくトータルでのアートディレクションを得意とする。プレ・アルスエレクトロニカ栄誉賞、文化庁メディア芸術祭推薦作品選出、レッドドット賞、CANNESLIONSシルバー、One Showゴールド、London International Awardsゴールド、The Clio Awardsシルバーほか受賞多数。
チームもクライアントも家族のような関係に
──ここ10年、仕事の環境が大きく変化していると思いますが、小柳さんが特に実感されているところはありますか。
やっぱりコロナで劇的に変化しましたね。僕が新人の頃によく一緒に仕事をしていた先輩ADのチームはADとデザイナーが全員集まって、アイデアを出し合いながらデザインを考えていました。自分には思いつかないアイデアが生まれることがあって、僕も参考にしていたんです。ただコロナの影響でリアルの場に集まれなくなると、微妙なニュアンスをくみ取ることが難しくなった。一方メリットもあって、家と家がリモートで繋がったことで、より家族のような関係性に。自分の家族に話しかける感覚で、チームで何ができるか考えるようになりました。以前より関係がフラットになり、そこで解決したことも多いです。
──コロナでコミュニケーションの形が変化しましたよね。
そう思います。今、クライアントも含めてひとつのチームとして一緒になって考えることが増えています。プレゼンへの参加人数制限もなくなり、社長さんや担当の方の考えを直接聞ける機会が圧倒的に増えました。手元のPCでクライアントのアイデアを、リアルタイムにデザインに反映し、確認いただく。お茶の間でクライアントと一緒につくりあげる感覚は新鮮でした。
あと、偶然の新しい出会いは減りましたが、会いたいと思った人に会いやすくなりました。実際、デジタル音響処理に精通しMax/MSPのスペシャリストとしても知られる電子音楽家のカツヒロ チバさんや、普段全く接点のない多くのスペシャリストの方に話を聞くことができました。Web会議だからこその気軽さで、大御所の方にもお願いしてみると、意外と繋がってくださる。企画の幅や可能性の広がりを感じています。
今までに見たことのないものをつくる
──小柳さんは広告以外のアートディレクションも多数手がけられていますよね。
僕は東京藝大出身で大学に根付く「見たことのないものをつくる」というイズムが好きで、それを強く意識しています。
例えば、現在、自主制作として壺をレコードにするプロジェクトを開発しています。ろくろで回してつくる壺は、一つひとつがレコード盤のよう。そこでレコード台に壺を置いて針を落としたら音楽が奏でられるんじゃないかと思って。それが実現できると土の特徴、フォルムや焼き方によって、日本中にある壺の全てが一つひとつ違うレコードになって音を奏でる。きっと壺を介して、いろんな人と繋がれると思うんです。
──リモートで完結したサントリーの「話そう。」シリーズも驚きました。
サントリーの「話そう。」シリーズは...