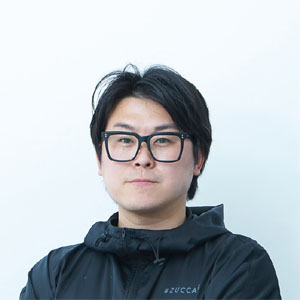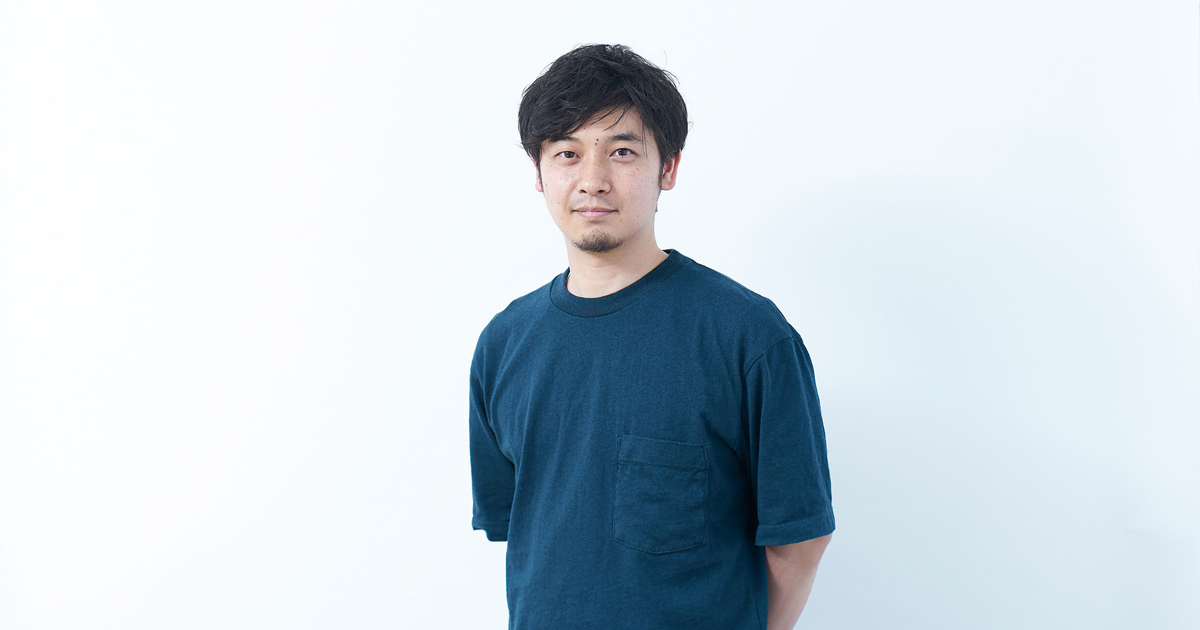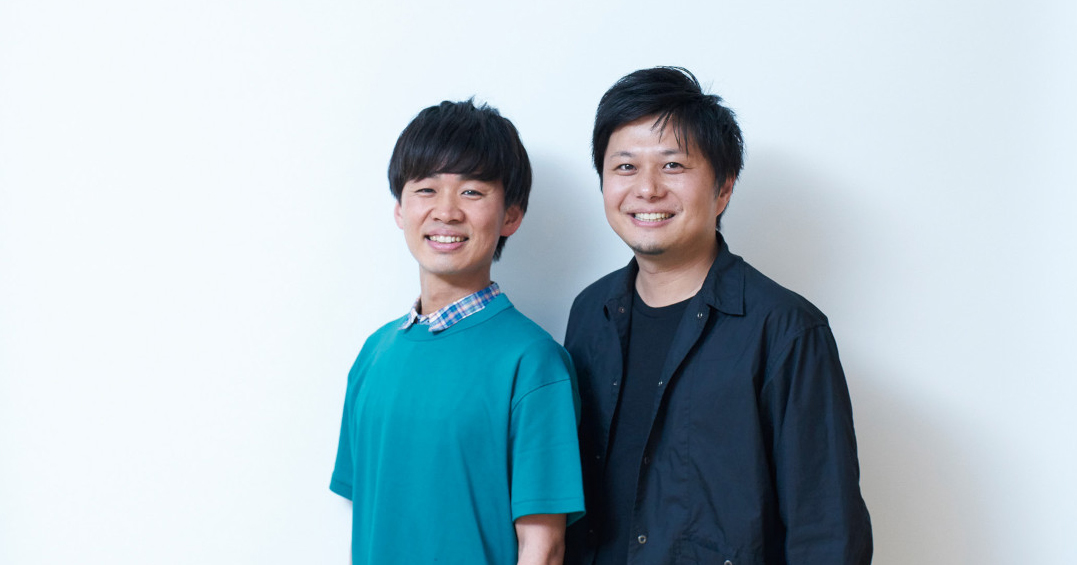広告にとどまらず、幅広い領域でデザインに携わってきた小杉幸一さん。そのアートディレクションのベースには、「世の中の翻訳家」としてクリエイティブを世に送り出すことがある。

onehappy クリエイティブディレクター/アートディレクター 小杉幸一(こすぎ・こういち)
ブランディング、イベントのほか、空間、テクノロジーを使った従来の型にはまらない広告のアートディレクション、アパレルブランドとのコラボレーションなど幅広く活躍。主な仕事に、SUNTORY「特茶」、PARCO「パルコアラ」、STARFLYER「輝く人へ、」、資生堂「50 selfies of Lady Gaga」、SUZUKI「HUSTLER」「XBEE」、ジャニーズ事務所「CIデザイン」、YMO「YMO40」、築地玉寿司「もじにぎり」、福島県「ふくしまプライド。」、B&B「CIデザイン」などがある。
アートディレクターの個性は「考え方」にこそ出る
──入社した頃から現在までに、デザインを取り巻く環境が変わる中で、小杉さんが意識して取り組んできたことは?
16年前の入社当時は、アートディレクターとは、「新聞広告」や「ポスター」など決まったメディアに対して企画、レイアウトをして世の中に出すことが当たり前でした。その一方で、大貫卓也さんによるペプシコーラのボトルキャップキャンペーンや、佐藤可士和さんが手がけたSMAP、佐野研二郎さんのLISMOなどなど、メディアは目的のための手法であるという考え方もあり、アートディクターの変化がめまぐるしい時代でした。
その中で、ただ1枚の「絵」を作るのではなく、世の中、消費者を見て、今どうすれば機能するのか、話題になるのか、またどういうエリアで展開するべきかなど、俯瞰的な視点から「1枚絵」を作る、それがアートディレクターの仕事において重要であることに気づいたんです。俯瞰で描く1枚絵はスタッフ、クライアントとのコミュニケーションにおいて、プラットフォームになるからです。
また、自分が作るビジュアルでは色、形など、すべて言語化しています。きっかけは、佐野研二郎さんから離れて、一人でアートディレクターとしてチームを率いるようになったときの経験。ビジュアルだけをメンバーに見せて「これ何かいい感じだよね」と言っただけでは、みんなにとってのプラットフォームにはならなかった。ビジュアルと一緒に言葉を出してみたら、初めてそれぞれ別々の立場のスタッフが自分ごと化して考えるようになったんです。
クライアントにデザインしたものを見せた時も同じで、自分の感覚だけで話していると、共通言語になり得ないんです。当たり前ですが、感覚だけでは、誰も共感することができない。「デザインは共通言語である」とよく言いますが、それはアートディレクターが感覚を言語化、あるいはルール化した上で、その世界観やメッセージを最初に提示していくことなんだと思っています。それからは、仕事をする上で常に意識していますね。
──今、アートディレクターにはどんなことが求められていると感じますか。
2014年に六本木ヒルズの「特別展 ガウディ×井上雄彦 -シンクロする創造の源泉-」のコミュニケーションを担当しました。そのときに井上さんが面白いことをおっしゃっていて、「これは僕の展示じゃない。僕はガウディを今生きている人にどう届けるかという翻訳家なんだ」と。"翻訳家"という言葉を聞いたときにデザインの仕事とシンクロして、アートディレクターは世の中の翻訳家なんだ!と強く考え始めるようになりました。
そして、この翻訳家に対して必要なものは...