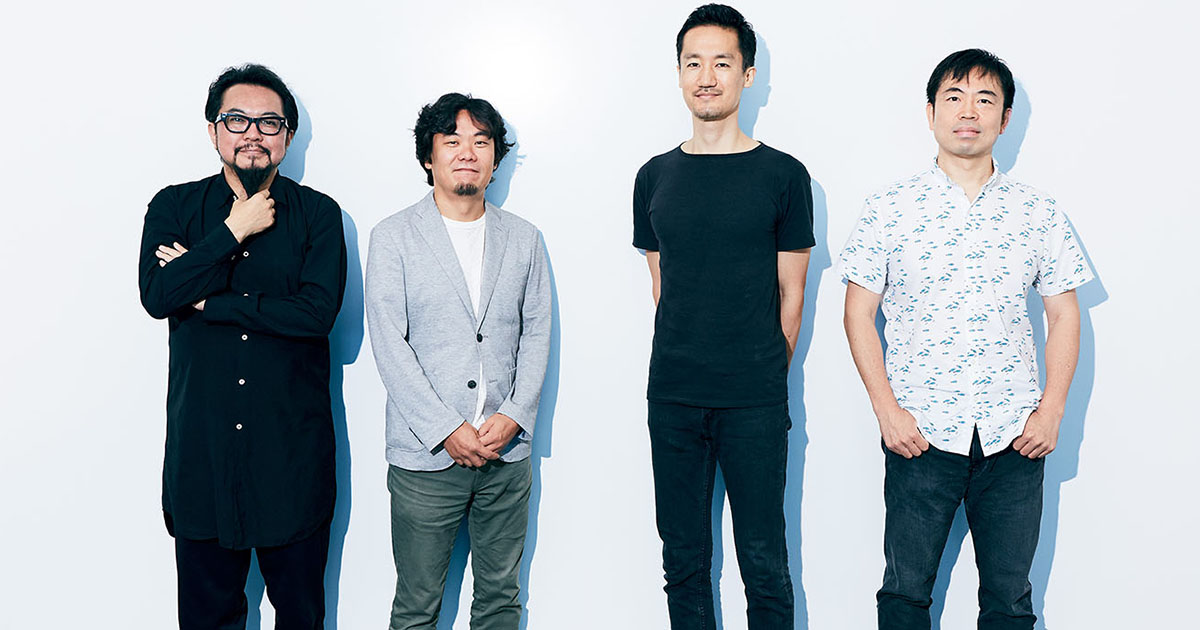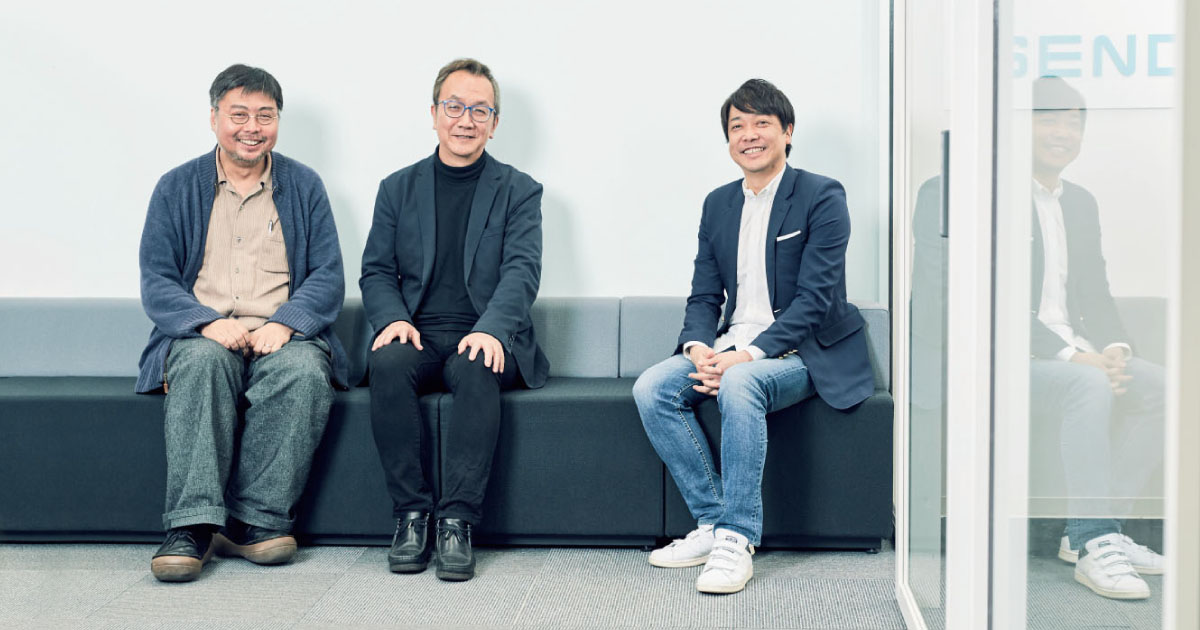今年もD&AD、One Showに続き、カンヌライオンズが終了しました。ここ数年は広告の領域の広がりと共に、部門が増え、複数の領域にまたがって出品される作品が増加。従来の広告よりも、デジタルやイノベーションに注目が集まっていたカンヌライオンズですが、今年はエンターテインメントとしてのフィルム復権の兆しも見られました。社会的な背景が作品に大きく影響し、さまざまな表現や企画、さらにはテクノロジーが混沌と交じりあった今年のカンヌライオンズは、広告界にどんなメッセージを放ったのでしょうか。
今年、セミナーに登壇した電通 エグゼクティブ・クリエーティブディレクター 佐々木康晴さん、本年度エンターテインメント部門の審査員を務めたSTORIES CEO 鈴木智也さん、本年度フィルム部門の審査員を務めたPROJECTOR 代表 田中耕一郎さん、そして今年D&AD、Oneshow、カンヌライオンズすべてに参加したもり クリエイティブディレクター 原野守弘さんに集まっていただき、今年のカンヌライオンズを振り返ってもらいました。
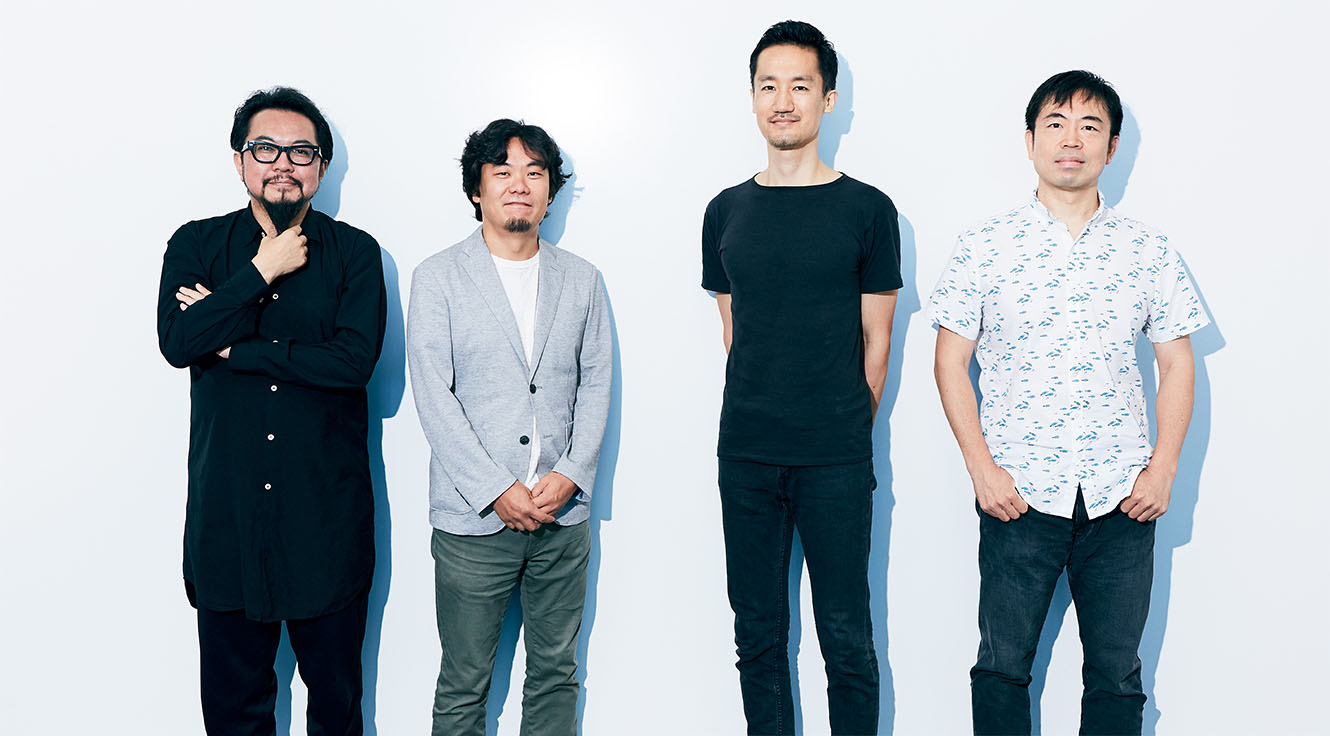
Photo:parade/amanagroup for BRAIN

「分断」から「ユナイト」へ
佐々木: 今年のカンヌライオンズ(以下カンヌ)は日本にとっては難しい年だったと思います。政治や権利、女性、マイノリティなど、大きな括りの話が多かったので、日本企業は同じ土俵では戦いづらいところがありました。ただ、他の広告賞とカンヌは明らかに傾向が違うので、それが世界のトレンドになるとは思っていません。
原野: 数年前に創設されたイノベーション部門やクリエイティブデータ部門の勢いが少し落ち着いた感じがしました。フィルム部門の中でも、タイのサプリメントのCM「CAPTURE」(01)のように「商品広告で面白いもの」をもう一度評価するという傾向になってきたのではないかと思います。

01 タイのサプリメント「SURE」のCM「CAPTURE」。道を通り過ぎようとする男たちを「脂っぽい」という理由で止める警官。彼の正体…実は「キトサン」だった。
田中: ぼくが印象に残ったのは、フィルムの授賞式で、ワイデン+ケネディの2人の女性CCO(チーフ・クリエーティブ・オフィサー)が、何度も檀上に上がっていたことです。
原野: フィルムはワイデンの圧勝でしたね。
田中: まさに「Wieden is back」ですね。面白かったのは、「Wieden is back」と「Nike is back」が重なって見えたことです。北米、EU、ロシア、インド…マーケットごとに表現を変えていますが、躍動する女性像をテーマにしたCMが目立ちました。女性と言えば、今年4つのグランプリを獲得した「FEARLESS GIRL」(02)。
あれは男性VS女性という構図をシンボリックに見せていますが、今の時代のフェミニズムを反映しているのかというと、疑問が残ります。ナイキの広告は、仮想敵を男性社会にするのではなく、女性へのステレオタイプにしているから、問題の立て方も、結果として描かれる女性像も違いますね。

02 国際女性デーの前日にニューヨーク・ウォール街付近に突然現れた少女の像「FEARLESS GIRL」。今年一番の話題をさらった作品。
佐々木: 「FEARLESS GIRL」は強い女性にさらに強さを与える感じがありますよね。それを見た弱い人たちが「私もやらなきゃ」という気持ちになるかと言えば、そうはならない気がします。
原野: 「FEARLESS GIRL」を擁護すると、あれはそもそも"ガラスの天井"、つまり証券会社役員に女性が少ないという問題をテーマにしているので、男性VS女性にならざるをえないんだと思います。
鈴木: 私は普段アメリカで生活していますが、「FEARLESS GIRL」はジェンダーイクオリティだけの問題というより、アメリカにおける格差の問題だとも感じました。要は「VS ウォールストリートを代表するCharging Bull」で、格差を感じている人たちにとってのアイコンになったところが強さだったと思います。私は今回のカンヌは、社会の根底に広がる格差により分断された状態を「どうやってユナイトするか」が大きなテーマとしてあったように感じました。
原野: プロモ&アクティベーション部門のグランプリBoost Mobile「BOOST YOUR VOICE」(03)はよかったですね。

03 低所得者層が多く住むエリアに店舗を持つBoost Mobileは、選挙時に店舗を投票所として開放。投票率を上げることにつなげた施策。
佐々木: あれは日本ではつくれないものですよね。公職選挙法や企業が政治に関与していいのかという問題があるので、真似をしたくてもできない悔しさを感じました。
鈴木: 広告会社としても、そこに手を出すリスクを考えてしまいます。でも、カンヌで評価されるものの根底には、「社会的なインパクト」が必ずどこかにあるものです。
田中: フィルム部門のグランプリは、Channel 4のパラリンピックCM「WE’RE THE SUPERHUMANS」(04)で即決でした。障害を持つ方への無意識の距離が、たった3分のフィルムを体験すると消え去る。というより、ポジティブな意識にパッと変わって感じられる。140名のキャストのパフォーマンスが、映像にしかできない方法で繋がっていく様にも圧倒されます。

04 障害に対する認識を変えることを目的に、障害を乗りこえた人々の姿を描いた「WE’RE THE SUPERHUMANS」。
原野: 「SUPERHUMANS」のテーマは分断の解消で、インクルーシビティを超えていました。「みんな一緒」というメッセージはこれまでもありましたが、真ん中に健常者、まわりに障害者ではなく、障害者の方をむしろかっこよく見せています。中心と周縁を逆転させて、それが違和感なく納得できる映像になっているところがすごい。
鈴木: クライアントがChannel 4で、ソーシャルグッドネスに近いメッセージでありながら、グランプリを獲得しているところも面白いですよね。
佐々木: 「SUPERHUMANS」が注目を集めると、女性について考えたり、ジェンダーイクオリティを扱ったりするキャンペーン=よいキャンペーンのような手段的な逆転が起きるのではないかという懸念があります。以前もソーシャルグッドネスをやるのがいい広告だと勘違いしている人がいましたが、僕たちクリエイターは企業やブランドの本質的な部分を、多くの人たちに伝えて体験させるためのクリエイティブを提案している、それこそが本来の仕事であると言っておきたいです。
田中: ソーシャルグッドネスには、正しいことを表現する危うさや、つまらなさが付きまといますよね。「SUPERHUMANS」は、ソーシャルグッドネスというより、前向きに生きる喜びがすごい熱量で伝わってくる。表現として、テーマを突き抜けている感じがあります。
佐々木: Channel 4ではパラリンピックゲームを放映しているからこのCMを制作したわけで、それを見るのが楽しくなるなど、企業メッセージに落とし込まれているところは素晴らしいと思いました。Channel 4としてのエンターテインメント性があり、パラリンピックを新しく位置づけて、かつ、それ以上に得るものがある広告でした。
7つの賞を受賞した「GRAVITY CAT」
鈴木: PR部門ゴールドを受賞した旅行検索サイトmomondo「THE DNA JOURNEY」(05)に関して、エンタメ部門の審査員は「オーセンティシティ(信憑性)」について話していました。よくできていて、何も知らない人が見たらドキュメンタリー作品に見えるんですが、審査員の間では「このポジションにカメラがないということはリシュート(撮影のテイクを重ねている)だね」と。

05 旅行検索サイトmomondoが行った実験プロジェクト「THE DNA JOURNEY」。他の国に対する印象を聞いた後に、自分のルーツを探るテストを受けると思わぬ結果に。
田中: フィルム部門でも同じ意見でした。こうした実験型のものは、撮る前に決まった結論に向かっていくフレームワークがあるものですが、だからこそ演出力が決め手になる。そこで「本物らしく感じられるかどうか」ということへの突き詰め方が生命線になります。それから、この種の映像は話題にするために、わざとベタに伝わりやすくする「あざとさ」に向き合わなければいけなくなるので、つくり手の倫理観が問われることにもなります。
佐々木: Always「#LikeAGirl」(2014年)あたりから明らかに優等生的なものが増えましたね。
原野: 「#LikeAGirl」の時は、あのフォーマット自体が表現のアイデアだったのでありだと思いますが、真似すると二番煎じ以前に信憑性のほうが気になります。
鈴木: 「THE DNA JOURNEY」も分断がテーマですが、自分たちのルーツというか、血というデモグラ属性に反応する人たちに向けた「多様性」をテーマにした企画です。デンマークのテレビ局TV2が同じようなノンフィクション風の映像「ALL THAT WE SHARE」(06)をつくっていますが、こちらは価値観や行動という本人の意志をもとに「普遍性と多様性」を大切にという企画で、エンタメ部門では高評価でした。ただ、どちらも今の分断された世の中に対して機能していることは感じます。

06 さまざまな質問が続き、参加者のグループ分けが変わっていく。このタイトルが示すものを証明するための実験「ALL THAT WE SHARE」。
原野: 「THE DNA JOURNEY」を見て思ったのは、自分のルーツにドイツ人の血があるとわかっても、何かが変わるわけではない。そこが共感できないところです。一方、「ALL THAT WE SHARE」はいじめ問題など、国を問わず誰もが共感できることをテーマにしている。だから、あの2つには「共感しやすい、しにくい」の違いが決定的にあると思います。
最近は「ソーシャルグッド×ノンフィクション」のフォーマットがいいという風潮がありますが、Donate Life「THE WORLD'S BIGGEST ASSHOLE」(07)はフィクションものの復権を感じさせるフィルムだったと思います。日本に限らず、海外でも臓器移植系のものをつくるとACっぽいというか、きれいな話になりがちですが、あれはちゃんとエンターテインメントに落とし込まれていましたよね。

07 すべてにおいて世界最悪な男。そんな男が唯一なしえたよいこととは?DONATE LIFE「THE WORLD'S BIGGEST ASSHOLE」。
田中: 確かに。全体的には、現実と地続きになったノンフィクション的な手法が増えている印象でしたが、リアリティへのたどり着き方ってそれだけじゃない。「THE WORLD'S BIGGEST ASSHOLE」の、タイトル通りな最低野郎っぷりに、思わず感情が動いてしまう。その瞬間に、リアリティを感じているわけですから。
原野: 単純にノンフィクション、フィクションという分類の話ではないのかもしれませんね。インドのナイキ「DA DA DING」(08)はキャスティングされている人たちのリアリティでノンフィクション性が強化されていました。一昔前だったら、もっとセットアップするなど、違う撮り方をしていたと思います ...