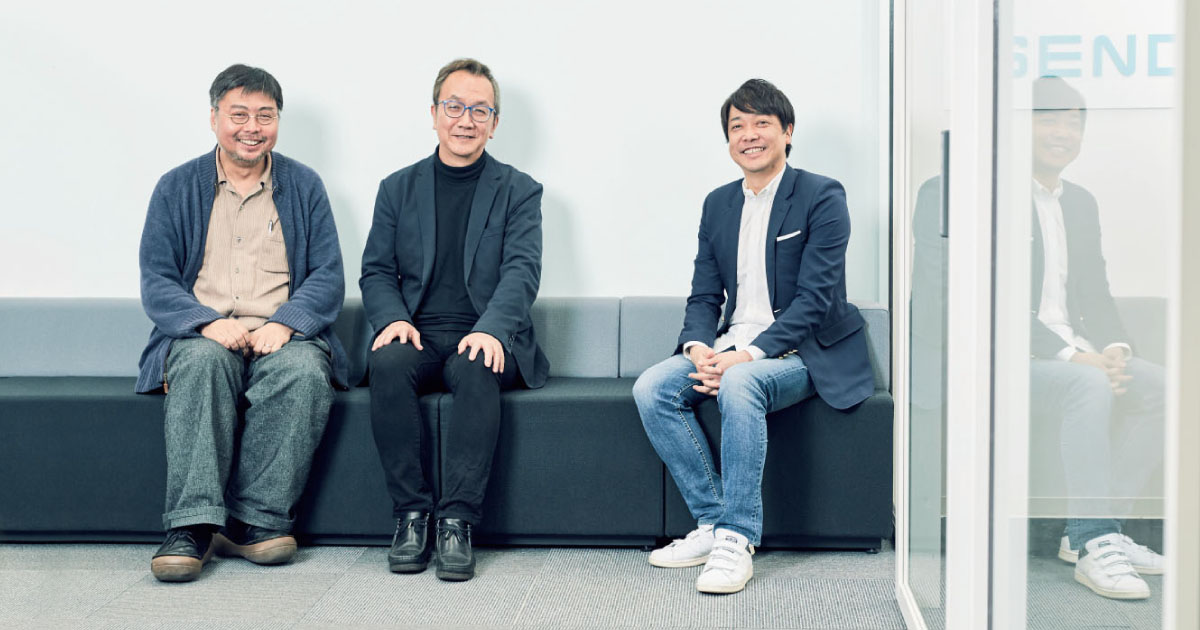デジタルテクノロジーの進化によって、近年ものづくりがどんどん変化をしています。3Dプリンタが登場した頃から、平面だけではなく、立体をも簡単に作ることができるようになり、「DIY」のあり方も変わってきています。テクノロジーやデータの活用によるものづくりの効率化、簡便化にはよい面がある一方で、できあがったものにその人らしさが見えなくなったり、似たようなものが量産されてしまう、さらには人が本来持っている力が発揮されなくなってしまう――そんなことが危惧されます。
そこで、今回の青山デザイン会議では、こんな時代に「手でつくることの意味」をあらためて考えてみたいと思います。BEAMSで「工芸とデザインの橋渡し」をテーマとするfennicaレーベルのディレクター 北村恵子さん、さまざまなブランドで手がけたプロダクトの模型の展示が話題を集めたプロダクトデザイナー 藤城成貴さん、そして広告の仕事をする一方で、自ら企画して広告とアートの中間にある作品をつくり続けるアートディレクター 八木秀人さん。「手でつくる」ことを考え続けている3人にお話いただきました。
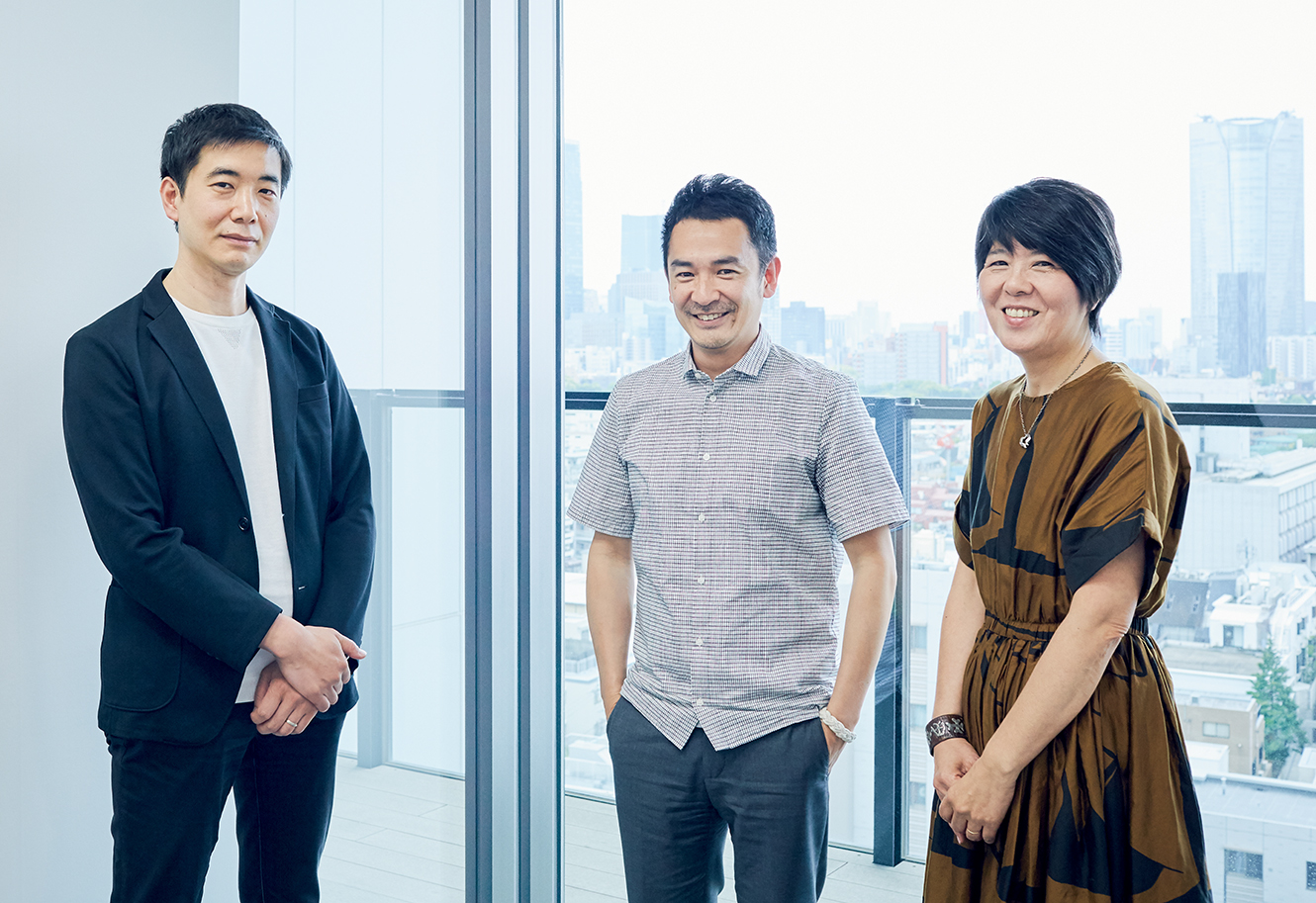
Photo : parade/amanagroup for BRAIN
手作業とテクノロジーをどう組み合わせるか
八木:僕は17年ほど広告の仕事を続けていますが、どんな案件でもまずペンを持ってサムネイルを描いてから企画を形にしていきます。でも、最近は最初からGoogleで探した素材をパワポに貼って企画書をつくる人が増えています。特に広告界はロジックが重視されていて、言葉でうまく乗り越えることがうまい人=デキる人と思われていますが、僕はその考え方に馴染めなくて(笑)。
それは脳から直結する感覚を大事にしないと、どこかで見たようなものが氾濫していくと思うからです。その点、藤城さんは器だけではなく、アディダスのスニーカーのようなものまでリアルな模型をつくられている。そういう仕事の進め方の方がオリジナリティあるものがつくれるのではないかと考えています。
藤城:手だけでつくることがはたしていいのか、難しいところですね。モノによっては機械できれいにつくれるのであれば、そのほうがいいとも思うので。ただ、器のデザインをする際、手で立体物をつくる途中段階が重要だと感じています。3Dプリンタではつくっている途中の「こうしたほうがいい」という感触や時間が得られませんから。
完成品をチェックして考えるのと、手でつくりながら考えるのでは情報量が大きく違います。でも今はかつて手でつくっていた著名なデザイナーの方々も3Dプリンタを使う時代なので、どう使うかという「使い方」によるのでしょうね。どちらも良い面があるので、使う側の問題が大きくなっているような気がします。
八木:おそらくどちらもうまく使っていくのがよいのでしょうね。新しいテクノロジーとクラフトの要素の融合が今の時代には適していて、人肌を感じながらも、新しい要素を取り入れているものがいいものなのかなと漠然と考えていました。
藤城:以前に柳宗理さんのアトリエに行ったことがあるのですが、そこには1種類の皿に対して50枚ぐらいの石膏模型がありました。スタッフの方から全部手でつくられたと聞いたときに、「やっぱりこういうつくり方がいい」と思いました。でも1枚つくった後に、ほぼ同じだけど微差のあるものをつくり続けるのはかなりキツイことなので、僕にはそこまでの根性はないかもしれません(笑)。
北村:BEAMS MODERN LIVINGを1995年に立ち上げたころに、柳さんのバタフライスツールを知り、その後ご本人ともお会いする機会を得ました。生前、柳さんがよくおっしゃっていたのは、「アイデアをどんどん形にしていかないといけない。手を動かすことが大事」ということ。ただ、今は生活様式が変わっているので、かつてのようになんでも手づくりがいいということに固執しないほうがよいと思うし、実際につくる側にも難しさはある。八木さんがおっしゃったように、両方をうまく合わせることが必要なんでしょうね。
SHIGEKI FUJISHIRO'S WORKS

ポリエステル製のロープで編まれたカゴ「knot」。壁掛け用、床置き用とさまざまな用途で活躍。色は赤のみ。

硬質パルプ製スツール「eiffel」。日本以外の全ての海外諸国では RS Barcelona によって販売されている。

2016年“doit yourself"展にて発表されたカーペットとインシュロックで留められたカゴ「carpet basket」。

2016年にイデーより発表されたサイドテーブル「RIB circle」。

2016年のミラノサローネにて発表された有田焼による新ブランド「2016/arita」の1シリーズをデザイン。

2016年に行ったこれまで制作してきた模型の展示会「studies shigeki fujishiro」の一コマ。photo by Gottingham

adidas Originals 84-LAB より発表されたモデル「adidas PREZ」。

adidas の定番商品である STAN SMITH の限定モデル。元々ある通気口にゴム製糸で刺繍が施されている「STAN SMITH PLAY」。
ネットでは得られない情報を 自ら動くことで手に入れる
八木:電通にいると仕事は沢山ありますが、クライアントからオリエンを受けてつくる仕事がほとんどなので自分発のものづくりにはなりません。でも、自分がつくりたいものを形にできたほうが絶対に面白い。そんな思いから、今年4月にスパイラルで「ART BY THE HAND EXHIBITION」という展覧会を企画しました。
きっかけは、あるときに「粘土で巨大な手がつくりたい」と思ったこと。そこでパジコという粘土の会社を訪ねてみたんです。最初は不審に思われたのですが、副社長さんに手でものをつくることの大切さを共感していただき「やってみましょう」となって。最終的にパジコと洋服のオンワード、カッター製造のオルファの3社と組んで、手作業によるアート作品の展覧会を開催することになりました。パジコは粘土を、オンワードは布を、オルファはカッターを通して、手作業によるアート作品を制作し、発表しました。
藤城:その作品は完成後の行く末を考えてつくったんですか?
八木:理想は、アート作品と認められることでした。それを見て欲しいという人が出てきて、売れればという思いはありました。でも、これが純粋なアートかというと、クライアントがついて広告にもなっている。先日、今回に続く展覧会を企画するために、ニューヨークで複数のギャラリーを回りましたが、人によっては「クライアントがついているからアートではない」と言われてしまいました。
アートは純粋にその人自身を表現するものだから、クライアントと絡んでつくっている時点でアートではないと。僕としては広告でもあるけれど、アート作品をつくっているつもりだったのですが、そこには境界があると感じました。ただ、広告とアートの中間というポジションは存在すると思っていて、僕はそこを狙いたい。美しいもの、人を感動させるもの、それが純粋なアートの力だと思っています。
藤城:今回の展示で、なぜオルファやオンワードと組んだのですか?
八木:オルファは一般にブルーワーカーが使っているイメージがありますが、若いデザイナーも使っているので、ブランドとしてもう少しクリエイティブに見せられるのではないかと思ったからです ...