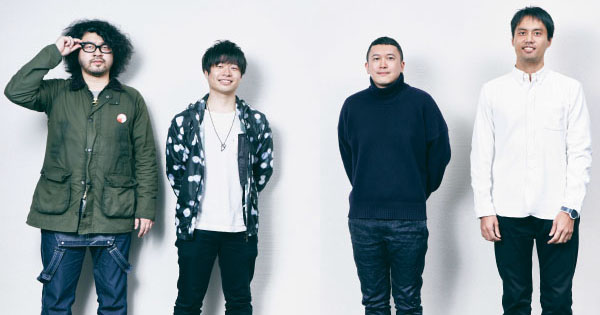クリエイティブに関する仕事は、単純に時間で区切れるものではありません。また、会社務めをしていれば定年がありますが、実際に60歳になったからといって、その能力がなくなるわけでもありません。広告・デザイン界には70歳を過ぎても、80歳を過ぎても現役で働いている方が多くいます。クリエイティブに携わる人にとって定年とは、いわば形だけのようなもの。自分の仕事と人生がリンクしていることもあり、働くことと生きることが同じレベルで続いていくようです。一般に「ワークライフバランス」と言われますが、バランスをとるというよりも、ライフとワークが一つになっている人が多いのではないでしょうか。
それでは年齢を重ねても、元気に、またクリエイティブに働き続けるためには、どんなことが必要なのでしょうか。また、よりよい働き方を続けていくために、いまできることとは?今回は蒸留家としての活動を始めた、元ユトレヒトの江口宏志さん、さまざまな分野で活動をするクリエイティブディレクターの小山奈々子さん、そして「家族」をテーマに、自らの家族で雑誌をつくり始めた中村暁野さんの3人に、自身の人生と働き方を振り返りながら、考えてもらいました。

Photo:parade/amanagroup for BRAIN
これまでのやり方を新しい仕事にスライドさせる

小山:江口さんが本屋から蒸留家へと転身したのには驚きました。
江口:僕は2002年にブックショップ「UTRECHT」をオープンして以来、約13年、ブックフェアの企画や書籍づくりなど、本の仕事に携わってきました。面白い仕事でしたが、その一方で自分がいつまで本を選び続けられるかわからないという不安も感じていたんです。個人商店の本屋は自分がいいと思う本を選べる喜びがありますが、売れるかどうかも大事な要素。
実際に反応が感じられる、店頭に立つスタッフの方が本を選ぶのに適任と考えて、最後のほうは若いスタッフに任せていました。そのとき、今後、自分は何を表現としてやっていくかと考えて思い浮かんだのは、自然を相手にした仕事がやりたいということでした。さらに考えたところ、蒸留家クリストフ・ケラーの仕事がしっくりきたんです。
小山:それで、ドイツに行かれたんですね。何がしっくりきたんですか?
江口:クリストフは僕と成り立ちが似ています。フランクフルトで経営していた出版社を人に譲り、自然の中で子育てがしたいと南ドイツの田舎に引っ越した。その家にたまたま蒸留器があったので、お酒をつくってみたら、みんなが喜んでくれて、どんどんハマっていったそうです。
その彼がつくる酒を飲ませてもらう機会があったのですが、フルーツや植物をそのまま凝縮した味に感動して…。さらに彼はボトルやラベルもこだわっていて、ラベルは活版で印刷して、そこにつくった人のサインと通し番号を入れているんです。そのつくり方を見たとき、これはアートブックのつくり方と似ているし、本よりもダイレクトに人に近づけるものだなと思ったんです。
小山:蒸留の仕事を始める前と後で、変化はありましたか。
江口:あまり変わってないかも(笑)。退路を断って、東京を捨てて…ということではなく、これまでのやり方を蒸留の世界にスライドさせた感じです。春からは千葉県の大多喜町にある薬草園跡地を蒸留所にすべく、本格的に活動を始めます。
中村:私の転機は出産でした。以前はPoPoyansというユニットで音楽を作り、歌っていたのですが、キャリア半ばの25歳のときに予期せず妊娠して。将来のビジョンもないまま結婚、出産、さらに半年後には東日本大震災震災が起こり…。
あまりにいろいろなことが続いたので、そのときは身の回りの全部がダメになっていく感覚に陥りました。そのとき、「私が変わらなきゃ」「子どもを守らなきゃ」と意識の変化があったのですが、当時ギャラリーディレクターであった夫は働き詰めで、ほとんど家にもいない状態だったんです。
小山:一人で抱え込んでしまったんですね。
中村:はい、そのときに私は自分を弱者だと思いました。社会的に何も築きあげないまま子どもを産むと、こんなにも弱い存在になるのかと。音楽でもう少しキャリアを積んでいたら違ったのかもしれませんが、そのときは何も守ってくれるものはありませんでした。
それで体調を崩してしまい、このままでは本当にやっていけないと思って、初めて夫婦で「この幸せじゃない現状をどう打破するか」について話し合ったんです。そのときに出した結論は、「私たちは弱いけど、何とか自分たちで主導権を持って、人生を生きていこう。そのために全部を変えよう」ということでした。
江口:それで雑誌をつくろうとはなかなか思いつかないと思うのですが…。雑誌づくりの経験はあったんですか。
中村:ありませんでした。工程も知らなかったけれど、絆が全くない状態の私たちだからこそ「家族の形って何か」を考える活動をしたいと思い、それを仕事としてできるのが雑誌じゃないかと思ったんですね。
「家族」というテーマはキャッチーではありませんが、幸せじゃない私たちが幸せになりたいという思いをうまく包んだら、雑誌として形になるのではないかと考えて。いつかできたらいいねと2人で話していたら、夫はギャラリーから独立、3カ月後には雑誌『家族』の制作がはじまりました。
江口:『家族』という雑誌を一冊つくってみて、どんな変化がありましたか。
中村:中村家に最大の危機が訪れました。それまで共同作業をしたことがなかった私たちが初めてやってみたら、あまりに違い過ぎて、お互いに腹が立って。編集長が私で、雑誌のクリエイティブディレクターは夫という役割分担でしたが、校了前に私が自宅を破壊し尽くすぐらいの最大のケンカがありました(笑)。1号目を出した感想としては、「夫婦はわかり合えないこと」と、「わかりあえないと思いながら向き合い続けるのが家族」ということでした。
小山:なるほど。私はみなさんと逆で離婚が一番の転機かな(笑)…、それがいまの働き方につながっていると思います。それまでの私は、女性とは、結婚とは、デザイナーとはこういうものであると、ステレオタイプに考えていました。その上、働いていたデザイン会社の人と結婚したので、365日ずっとデザインとその会社のことだけを考えていたのですが、離婚を機に会社を辞め、私の人生が一回0(ゼロ)に戻ったんです。
予期せぬその新しい人生に、「○○はこういうものだ」と決めつけるのをやめよう。自分に降ってくるできごとは、すべて受け入れようと決めたんです。退社後、一緒に辞めた同僚と2年限定の月替わりshop「gg」を立ち上げました。このお店では自分で決めるのではなく、空想の店主に指示される設定で進めていったのですが、そうしたら自分が変わってきましたね。
江口:二人とも思い切りがいい!
小山:何もなくなった状態の私がふと思い出したのは、田舎のおばあちゃんのことでした。長野県の中条村(現在の長野市中条)という2千人しかいない過疎化が進む山奥の村に母方の祖母が住んでいたのですが、仕事を全力でやっていた頃はほとんど行くことはありませんでした。中条村に行って、日々変化する自然の色に気づいたら、「デザイン業界で働き、Macやチップだけで選んでいた色は何だったんだろう。本当のクリエイティブはこっちじゃないか」と思えてきたんです。
江口:それぐらい衝撃があったんだ。
小山:それから中条村に通うようになりました。印象的だったのは、村で出会ったおじいちゃん、おばあちゃんが自分ではなく、自然を中心に動いていること。例えば雪が降る前にこれをやる、秋に収穫するために春にこれをしておくという感じで ...