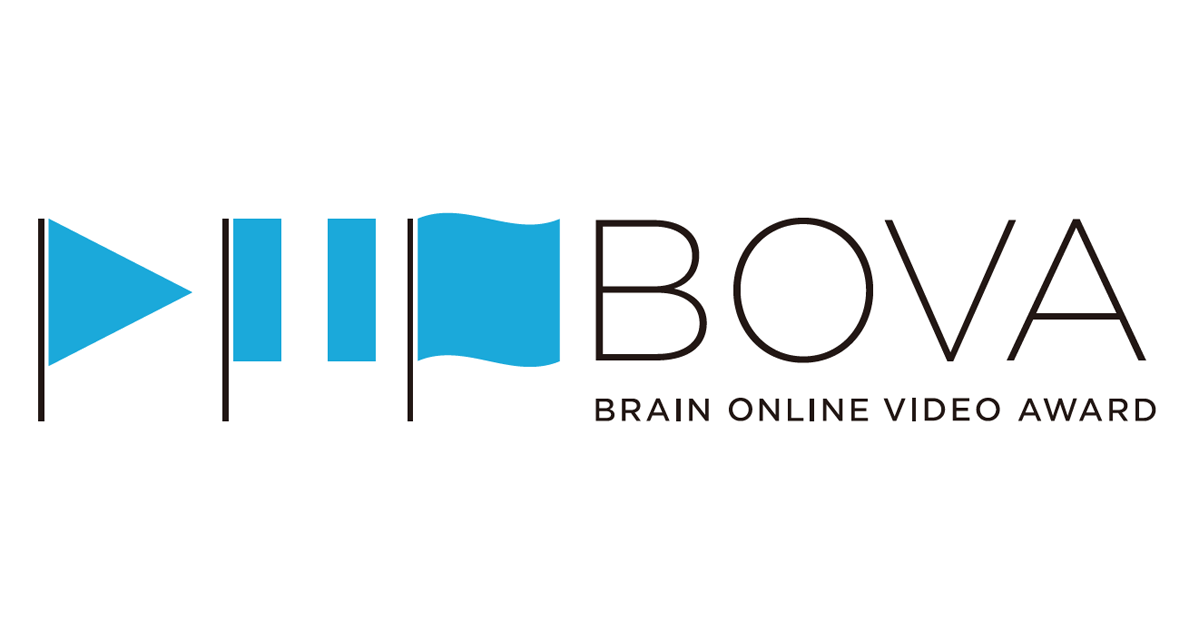いつの世も新しいカルチャーは辺境より生まれてきました。それは、中央(本流)に対する挑戦であり、手垢のついた制度や既成概念に背を向けた勇気と行動力を持つ人たちによって興されてきました。多くの人の賛同を得、批判を真摯に受け止め、プロジェクトを維持・管理する…その道のりは険しく、誰もが知っている、世の「定番」となるには並大抵の努力では成し遂げられないことでしょう。でも、あえてその道を選んだのは、なぜなのか。その情熱と信念、原動力はどこから来るのか?そして、いまの日本にどういうカルチャーを根づかせようとしているのか。
今月号の青山デザイン会議は、音楽、書籍、スポーツ、映画…などさまざまなジャンルを縦横無尽にリミックスして新しいカルチャー創出に挑戦する4人にお集まりいただきました。世界最大のダンスミュージックの祭典「ULTRA MUSIC FESTIVAL」の日本上陸版のクリエイティブディレクターを務める小橋賢児さん、スポーツ弱者でも楽しめる「世界ゆるスポーツ協会」代表で電通の澤田智洋さん、出版と展覧会という二つの軸で事業を展開するブルーシープの編集者・江上英樹さんとプロデューサーの草刈大介さんのお二人。ご自身の体験からお話しいただきました。

Photo:paradeIN inc./amanagroup for BRAIN
説明できることは誰かがすでにやっている
澤田▶ 2020年に向けて日本のスポーツ熱は高まっています。超人的な競技もいいけれど、スポーツには運動音痴の人や障がいを持つ人でも楽しめる多様性、エンターテインメント性があってもいいはず。ある日ふと、そんな新しいスポーツをゼロから作れないかと思い立ち、「世界ゆるスポーツ協会」という一般社団法人を設立しました。
江上▶ 何種目ぐらい作りましたか?
澤田▶ 創設1年で約50種目です。僕自身、スポーツが得意かというとその逆。高校まで海外で学生生活を送っていて、体育の授業には苦い思い出があるんです。身体能力に差がありすぎて、どのスポーツも歯が立たない。手も足も出なかった。ならばと、日本人が外国人に勝てる新しいスポーツ文化を開発して見返せないかと、そんな負の感情が半分(笑)。もう半分は既存の型にはめる従来の体育教育に疑問を抱いていたんです。このままでは新しいスポーツ文化は生まれないし、広がらない。スポーツに対する概念を変えようと思いました。小橋さんが音楽祭を手がけるようになったのは、なぜですか?
小橋▶ 3年前に世界最大のダンスミュージックの祭典「ULTRA MUSIC FESTIVAL」を日本でスタートし、クリエイティブディレクターを務めています。はじめのうち、日本の文化に合わないからやめた方がいいと周囲から言われました。でも、蓋を開けてみれば昨年は3日間で9万人の来場者が集まりました。もっと多くの人に知ってもらいたいと思っています。
草刈▶ 芸能活動を休止して渡米されたんですよね。何か理由があったんですか?
小橋▶ 8歳から芸能界にいたんですけど、黙々と仕事をこなしていくうちに自分の感情を抑える癖がついてしまったんです。タレントであるがゆえに会いたい人とも会えない。好きな場所に出かけることもできない。そんな生活はストレスが溜まる一方でした。いまの環境は自分が望む未来につながっているのか。周囲を説得して26歳の頃に単身アメリカへ渡りました。現地で知り合った友人とアメリカ縦断の旅をする途上でULTRAに出会いました。
澤田▶ 本場のULTRAはいかがでしたか?
小橋▶ さまざまな人種の若者が最先端テクノロジーや音楽を全身で浴びていました。なにものにも縛られず、解放されている様子が本当に楽しそうで、震えるほど感動しました。それから世界中のイベントにでかけるようになって、自分でもさまざまなイベントを企画するようになっていたところ、ある日、突然主催側から連絡があってULTRAのアジア上陸を手伝うことになりました。ブルーシープさんは多くのイベントを企画されているとうかがっているので、いろいろお話をお聞きしたいです。
江上▶ 小学館で約30年間マンガの編集をしてきました。斜陽産業と揶揄される出版業界ですが、本格的に変わらなければいけない時期に差し掛かっています。しかし、古い体質が根強い出版社の中で新しいことを興すのは一苦労。もたもたしていると定年を迎えてしまう。実際に近いんですが(笑)。このまま萎み枯れるのを待つのではなく、5年後に大輪かどうかは別として花を咲かせたいと、2年前に独立の一歩を踏み出しました。共同経営者の草刈は展覧会のプロフェッショナルです。実は出版とイベントってすごく親和性が高いんです。融合・連動すれば新しいことがいろいろできると考えました。
草刈▶ 出版業界同様、展覧会プロデュースの分野も旧態依然としていて、いつか風穴をあけたいと思っていました。従来のようにただ作品を並べて展示しても興味のある人しか集まらない。作品が持つパフォーマンスや時代性を生かしきれていないんです。もっとコンテンツの価値を上げ、ファンを増やしながらビジネスとして広げる活動をしようと朝日新聞社を辞し、江上とともにブルーシープを創設しました。
澤田▶ 組織に属していると思うようにいかないこともありますよね。
草刈▶ そうですね。でも逆に、そういう環境だったからこそいろいろチャレンジできたのも事実です。きっかけは絵本『ミッフィー』の作者、ディック・ブルーナの展覧会でした。絵本の原画は小さくて白黒。それをどうやって大きな空間で展示すればいいのか。初めてのディレクションで大変でしたが、やりがいを感じました。王道と言われる西洋絵画などの展覧会を受け持ちながら、展覧会のコンテンツとしてこれまでになかった絵本やアニメに着目し、その作品をもっと好きになってもらうための場を作るようになりました。
江上▶ 草刈も僕も海外進出を考えているんです。
草刈▶ 新聞社時代に担当した「エヴァンゲリオン展」がとても好評で、韓国などからオファーが来ていました。しかし新聞社としては「ビジネスとしてのリターンがない」などの理由で消極的でした。立場の縛りがなくなったので、いろいろとアイデアが浮かんでいます。
小橋▶ どの職業にも似たような境遇があるんですね。僕も俳優を辞めたことで、さまざまな可能性が広がりました。職種の概念にとらわれずに、信念に従ったアウトプットの方法を考えていきたいんです。俳優、映画監督、イベントプロデューサー、DJ…端から見ると2足も3足も草鞋を履いて中途半端に見えるかもしれませんが、根っこでやってることは一緒なんです。
江上▶ それは何ですか?
小橋▶ クリエイティブを通じて“気づき”のきっかけの場を作ることです。イベントも映画もそこに来る人はさまざまな気持ちを持ってやってきます。そこで何か気分や考えが転換できるような、たった一つの気づきのきっかけが“場”で起きる。それぞれの仕事は一見するとアウトプットは違うけれど、やろうとしていることはどれも同じなんです。
澤田▶ 4、5年前までは何足も草鞋を履いていると中途半端に見られていたけど、今はそれが当然になってきていますよね。「型にはまる」のは慣れない初心者のうちはいいのですが、それが常態化すると危険です。筋肉に例えるのならば、何十年も同じ筋肉しか使っていないから、使わない筋肉はガチガチに凝り固まってしまう。だから動ける場所に飛んできたボールは打てるけど、避けられないボールが飛んで来たら大ケガをする。僕はどんな球でも打てたり避けたりできるように“ライフストレッチ”をしています。毎日未知のことをインプットして、考え、行動する生き方のことです。型を決めないストレッチは、今の時代リスクヘッジにもつながるんです。
小橋▶ 型にはめる「こうあるべき」という固定概念を、日本人ほど繊細に感じる民族はいないのかもしれないですね。集団心理に自分を委ねてしまい、「本当にいい」と思うところに進めない。そんな中でも今日ここに集まった皆さんは変わり者のようですね。世界中が右を指さしても、左に行ってしまいそう。だからこそ、新しいことができるんじゃないかな?
草刈▶ どうせやるのなら、説明できないことに挑戦したいですよね。説明できることは、誰かがすでにやっていますから。
KENJI KOHASHI'S WORKS

ULTRA JAPAN
クリエイティブディレクターを務める「ULTRA JAPAN」は、お台場で開催されている都市型ダンスミュージックフェスティバル。今年で3回目を迎え、海外フェスブームの先駆けとなっている。昨年は3日間で9万人を動員した。

KAWAII MONSTER CAFE
アートディレクターの増田セバスチャンがプロデュースを務める東京・原宿にオープンした「KAWAII MONSTER CAFE」のレセプションパーティーをプロデュース。

Diner en Blanc Tokyo
日本初上陸のディネ・アン・ブランは、25年前にパリでスタートした世界最大級のシークレット・パーティー。2015年、東京での初開催をプロデュースした。白のドレスコードで艶やかに着飾った1600人が集まり、幕を開けた。

DON’T STOP!
監督デビュー作品となった『DON’T STOP!』は、自由人としてマルチに活躍する高橋歩さんと、事故で下半身と左腕の自由を失った通称CAPが仲間と共にアメリカを旅する姿を追ったドキュメンタリー映画。

Dior Addict @FASHION’S NIGHT OUT
毎年9月に行われているFASHION’S NIGHT OUTでのDior Addict ブースのプロデュースを担当。コンテンツ提案、SNS施策、ノベルティ連動で当日は行列ができていた。

イヴ・サンローラン 新作発売記念イベント
イヴ・サンローラン ヴォリュプテティントインオイルの発売を記念したイベントをプロデュース。デジタルサイネージを使用した体験型のイベントを演出。
刺激しあい融合することで新しいカルチャーは生まれる
小橋▶ インターネットで世界中の情報を取得できるようになって便利な反面、現地へ行って経験をしたいという欲が少なくなってきていますよね。でも、行動することで得られる体験は何物にも代えがたい財産です。それをみんなに知ってもらいたい。「ULTRA JAPAN」をはじめた動機の一つは、新しいカルチャーに興味を持ってほしいからなんです。フェスを体験した若者が、「こんなに楽しいことがあったのか」と本場マイアミに行ってみる。それをきっかけに僕のように何かを日本に持ってくる。そうやってカルチャーが刺激しあい融合しながら、いろいろな角度から新しいものが生まれるといいなと思っています。
澤田▶ 気づきという点で僕も小橋さんと同じですね。僕は“ポジティブショック”を与えたいんです。
草刈▶ ポジティブショックって何ですか?
澤田▶ 意識にポジティブな変化を起こすショックのことです。例えば昨年プロデュースした「切断ヴィーナスショー」は、足を切断したことを乗り越えた女性たちによるショーです。来場者の中には思わず涙する人もいるのですが、その感情はウサイン・ボルトが100m走で世界新記録を出した瞬間を目撃した感覚に近い。人間は思っていたよりタフだなとか、美しいんだなと感情を揺さぶられ、「自分には何ができるか」と考える。それがポジティブショックです。
草刈▶ ゆるスポーツにはどういう競技があるんですか?
澤田▶ 社会的課題を解決する手段としてスポーツを使おうという発想で作っています。戦略ターゲットは運動が苦手な人、お年寄り、障がい者といったスポーツ弱者で、スポーツすることをあきらめている人たちです。例えば「ベビーバスケ」は、激しく扱うと赤ちゃんの泣き声がするボールを開発して、ボールが泣かないようにソフトな動きでゆりかごにゴールを決めるゲームです。足が遅い人でも対等に戦えます。介護施設で楽しんでもらおうと開発したのが、プロジェクションマッピングで投映した天井の的に風船を当てると大きな花火が打ちあがるスポーツや、声でトントン相撲をするスポーツなどです。実際に体験してもらうと盛り上がって、参加した人の顔が輝きだすんです。
江上▶ 最近『はじめて投票するあなたへ、どうしても伝えておきたいことがあります。』という本を出版しました。今夏の参議院選挙から18歳にも選挙権が与えられます。ジャーナリストの津田大介さん監修で約240万人の若者に投票へ行こうとさまざまなジャンルの識者が呼びかける本です。年齢を重ねたせいか、なぜかおせっかいになっていて(笑)、最近は目が不自由な人のお手伝いをしたり、道に倒れている自転車を起こしたり、今まで内向的だったためにやりたかったけれどできなかったことに挑戦しています。出版を通してそういう活動ができないかと模索しているんです。
小橋▶ 本はまさに気づきの宝庫、もっとも強いツールですよね。
江上▶ 30年間マンガの編集一筋だった人間に政治を語る資格があるのかとも思うけれど、自分がおかしいと思うことを見ないようにして、エンタメだけ楽しくやっていればいいという気になれなかったんです。だからといって、何をどうやっていくのが一番いい結実の仕方なのかわからなくて。取りあえず本という得意分野からはじめてみようと思いました。
澤田▶ 江上さんが蓄積してこられた編集のノウハウを使えば、社会をよくする「社会編集」ができるのではないでしょうか。編集のお仕事はある素材と素材をかけ合わせて、新しいものを再構築し、発信することですよね。おせっかいの活動とマンガの作家さんをかけ合わせて出版物をつくったり、それと連動して草刈さんが「おせっかい展」を開いたり。妄想が膨らんで話していますけれど「社会をよくする編集」という目線でいうと ...
あと46%
この記事は有料会員限定です。購読お申込みで続きをお読みいただけます。