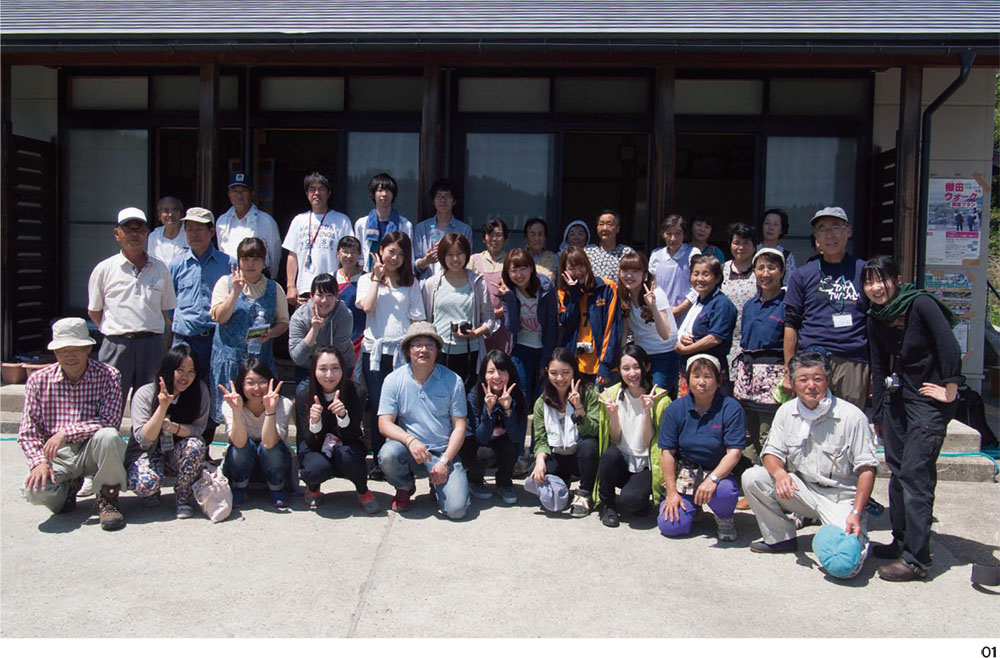世界の人々とコミュニケーションを図り、異文化の理解を深める法政大学国際文化学部。3年次に海外留学が義務付けられており、国際的に活躍する社会人の育成を目指している。稲垣ゼミでは他者と積極的に関わり、理解することでその土地に根付く作品をつくる。
他者を理解し、尊重することの大切さ
稲垣ゼミの学生は必ず、国内外の文化的背景の異なる地域に赴く。地元の人たちにインタビューし、その話の裏付けをとるために資料を調べるなどしてフィールドワークを行い、そこで得られた情報を基にインスパイアされる作品を制作している。自分一人の発想やスキルで作るのではなく、常に他者が関わり、刺激や影響を受けながら作品を作り上げるのが稲垣流。ゼミ生は、自分が興味を持つ社会とアートとの関係、文化人類学とアートの領域を行き来しながら制作活動を行う。
たとえばタイ・チェンマイのプロジェクトでは青果市場で働く人たちにインタビューし、その情報から現地のアーティストや僧侶と共同でパネルや作品をつくり、展覧会を開いたり、地元の児童たちとワークショップを行った。
「獅子の子落としではありませんが、言葉も通じない輪の中へゼミ生を放りこみます。はじめは手振り身振りでディスカッションを試みるのですが、なかなか上手に伝わらない。一歩一歩トライ&エラーを繰り返しながら他者を理解する行動力が自然と養わっていきます」(稲垣立男教授)。
こうした実験的な試みは通常1回限りで終えることが多いが、稲垣ゼミは継続することにこだわる。実際にタイでのプロジェクトは9年目。千代田区内でのワークショップ「こどもアート会議」は3年間継続した。この会議は自分たちの町が元気になるようなアイデアや作品を地元の小学生とゼミ生が共同で制作する企画で、商店街が賑わうためにお店の包装紙をデザインしたり、新キャラを考えたりする。プロジェクトを継続させることで、地域の人々における異世代間交流が図られ、それが地域の活性化を促すことにつながっていく。
「初対面の人でもすぐに打ち解けるようになりました。地域や世代の …