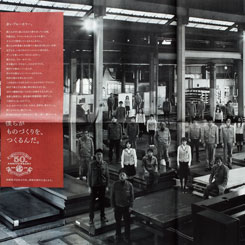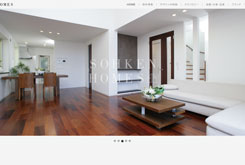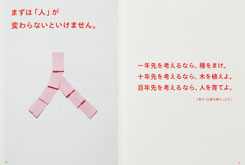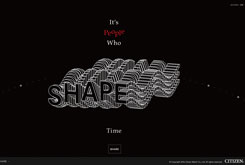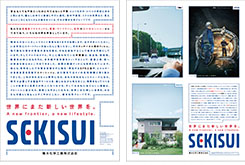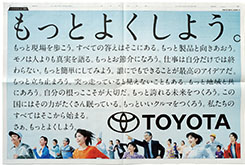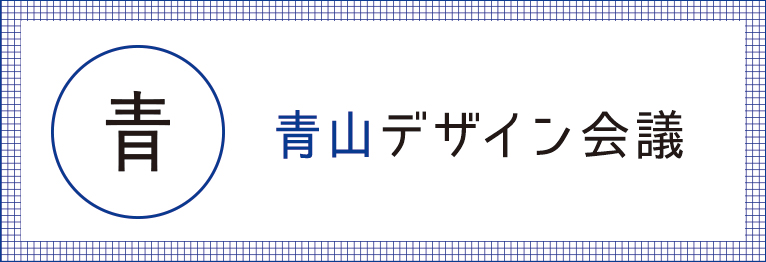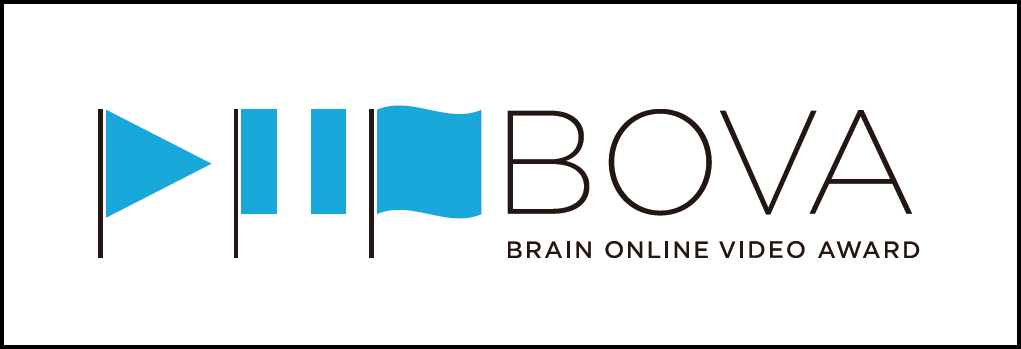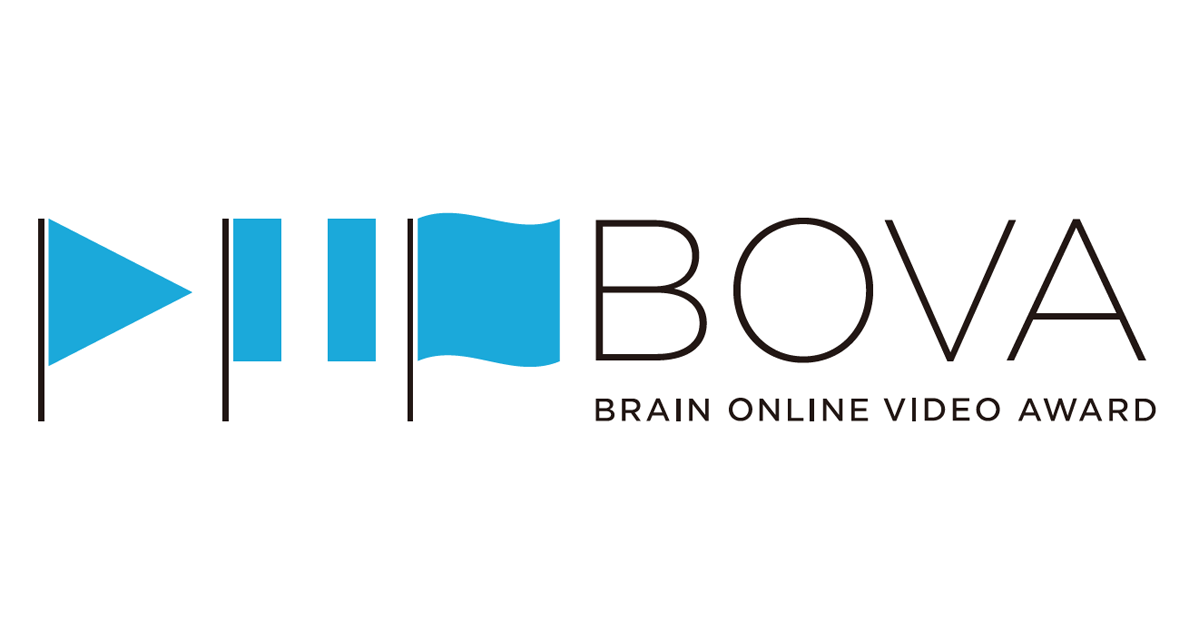消費が多様化したいまの世でブランドはどうあるべきか?いま企業に求められるブランディング、そしてそのアウトプットであるクリエイティブはどうあるべきか?デザインによるブランドに特化したHAKUHODO DESIGNを立ち上げて今年で11周年。代表の永井一史さんに聞いた。

永井一史(ながい・かずふみ)
多摩美術大学卒業後、博報堂に入社。2003年、HAKUHODO DESIGN設立。企業・商品のブランディング、ソーシャル、コミュニケーションデザインなどの領域でデザインの可能性を追求し続けている。ADCグランプリなど国内外の受賞歴多数。
時代環境とブランディングの変遷
80年代の好景気に支えられて、それまで使ってきた自社のシンボルやロゴを見直し、より時代に適したCIを作ろうという、第一次CIブームとも呼べる動きが起こりました。日本企業がデザインの力というものを強く意識した契機だったと記憶しています。ただ、そのときは「シンボルマークを作って管理することが企業のアイデンティティーをマネージメントすることである」という誤解を与えてしまい、表層的に消費されて終わってしまったように思います。
90年代後半になって、経営学者のデービッド・A・アーカーらがブランディングの重要性を、マーケティングや経営領域で説き、方法論を世に提示しました。僕自身も1999年に、博報堂ブランドコンサルティングという組織の立ち上げに加わり、ブランドの重要性を目の当たりにしました。この頃になると、表層的にVIを作ろうということではなく、「企業が提供する価値は何か」「自社のビジョンを考えよう」といった、もっと本質的なことが意識されるようになっていきました。特に大手企業は、ブランドを規定し、同時にスローガンを作り、それをコミュニケーションするという、ブランディングの活動を行っていました。
日本が成熟社会に進む中、日本企業の多くは ...