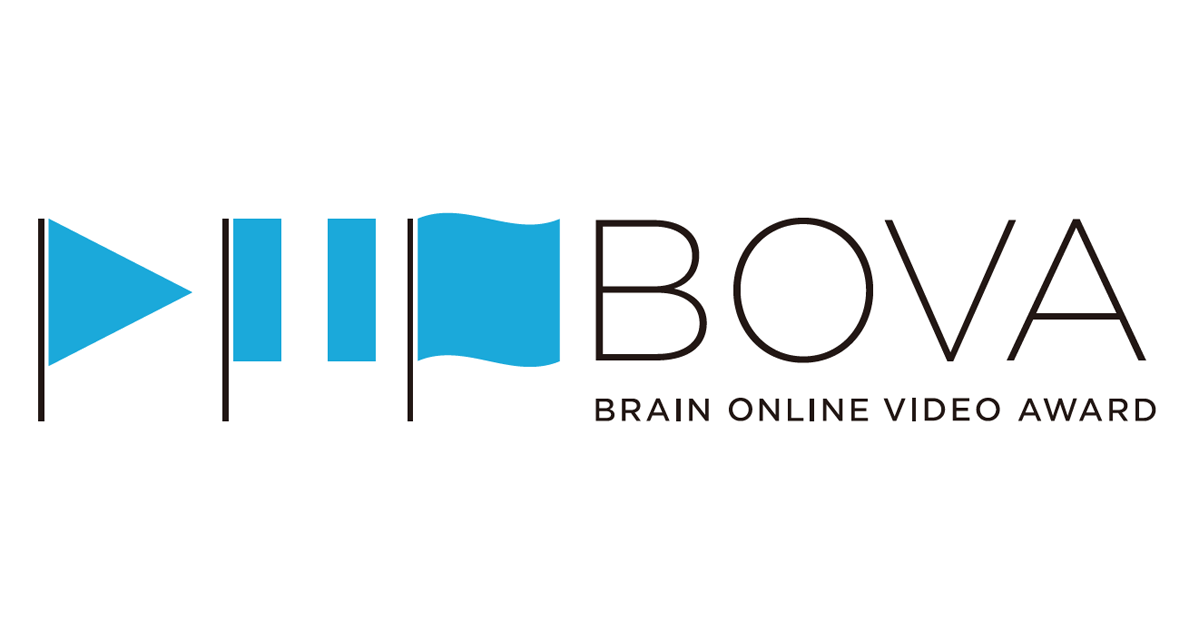9月の半ば、ニューヨークで恒例のアドバタイジングウィークが開催された。お膝元のマディソンアベニューのアドマンたちがそっぽを向いているこのイベントには、毎年、ニューヨーク以外の場所で働くアドマンがつめかける。今年大挙して訪れたゲストは英国のアドマンたちであった。WPP のCEOマーティン・ソレルも訪れ、広告界に対する鋭い意見を披露していた。特にインタラクティブ・アドバタイジング・ビューロー(IAB)主催の「広告とは?」というランデル・ローゼンバーグ(IAB 理事長)との対談では、「『広告』という言葉は死語だ。だから、『コミュニケーション』という言葉を使うが、いま、世界のコミュニケーションはアートから科学に移行した」と断言し、集まったアドマンたちの間で議論を呼び起こした。ビッグデータ、インターネット・オブ・シングス(さまざまな物にインターネットによってインテリジェンスが与えられること)など、確かに、いまの広告は、デザイナーとコピーライターが中心になって作っていた時代から遠く離れた感がある。
とはいえ、広告はいまだにアートだと信じているアドマンも決して少なくない。今月は、そういった2つの「ロマンの残党」を紹介する。
「広告の真実」をテーマにコンテスト
今年5月、シカゴのアートスクール、コ・プロスペリティのギャラリーで、「ル・コミュニック・アートショー」と呼ばれるコンテンポラリーアートの展覧会があった。アートスクールや近くのシカゴ大学の学生などがギャラリーを訪れ、さまざまなスタイル、テーマ、モチーフで描かれた約30点のアートを観賞した(02)。無数の顔が描かれたコラージュ風の極彩色の絵画(03)の前で立ち止まる女性や、よく見るとさまざまな物体が姿を見せる米国旗(04)、無数の白いドットの中の紅一点、不可思議な花のような抽象的なビジュアル(05)などのアートを、それぞれの視点で観賞していた。
が、観賞を終えたゲストたちは、ギャラリーを出るとき、驚くべき事実を知らされる。いま、ギャラリーで観賞した素晴らしいアートは、すべて広告だったのだ。シカゴの広告会社レオ・バーネットのクリエイティブ・チーム(アートディレクター、ヌノ・フェレイラとコピーライター、ライアン・ウーリン(01)が、世界各国から集めた広告から、ロゴやキャッチフレーズを取り除き、広告の土台となったデザインだけを展示したものだったのだ(広告主の名前はキャプション参照)。この事実を知って、びっくりする人、感心する人、中には「改めて会場に戻り、絵画を見直す人もいた」とヌノは言う。
この展覧会は、米国広告界の大元締め米国広告業協会(4A)が行った会員社内のコンテストの結果である。4Aは、ここ10年ほど、優秀な若者たちが広告会社を避け、IT業界やコンサルタント業界、シリコンバレーなどのスタートアップ(新会社)に就職してしまうというトレンドに頭を痛めていた。「原因の多くは、米国の広告業界のイメージにある」と、4Aの広報部長ポーシャ・バッドハム(06)は言う。ちなみに、2007年にギャラップとUSAトゥデー紙が共同で行った調査では、米国の広告業界で働く人たちは「正直さ」や「倫理観」という点で、政治のロビイスト、車のセールスマンに次ぐ下から3番目に位置していた。13年、マッキャンエリクソンと4Aとが共同で行った「アドマンのイメージ」という調査では、業界で働くアドマンたち自身が、一緒に働く広告会社の経営陣や同僚を「信用できない」と感じているという由々しき結果がでていた。さらに、アドマンの56%が「広告でない仕事をしていたい」と感じ、70%が「広告の全盛期は終わった」と述べている。「これが米国広告界のアキレス腱。広告界で働く人たちが自分の職業や職場、同僚に信用と誇り持っていなければ、優秀な若いタレントたちは広告界に集まってこない。この問題の解決が、4Aの急務」とポーシャは言う。
こうして誕生したのが、「The Truth aboutAdvertising(広告の真実)」なるコンテストである。「広告業界のイメージを上げ、広告こそ素晴らしいキャリアだと若い人たちに思わせるキャンペーン」を考えてほしいというのが、このコンテストのブリーフ。4Aの会員社から数百のアイデアが集まったが、その中から、先に挙げた「ル・コミュニック・アートショー」が最優秀作品として選ばれた。