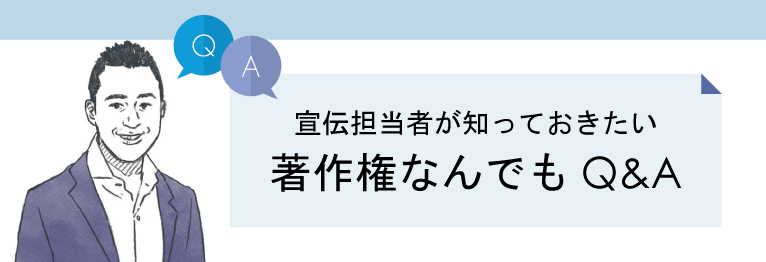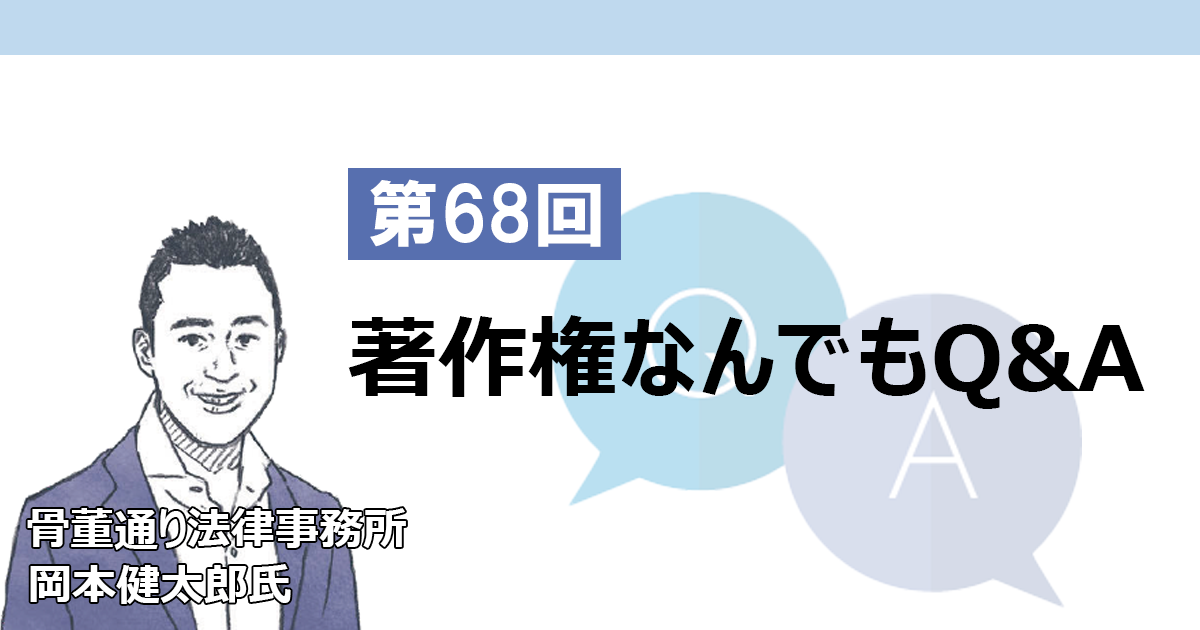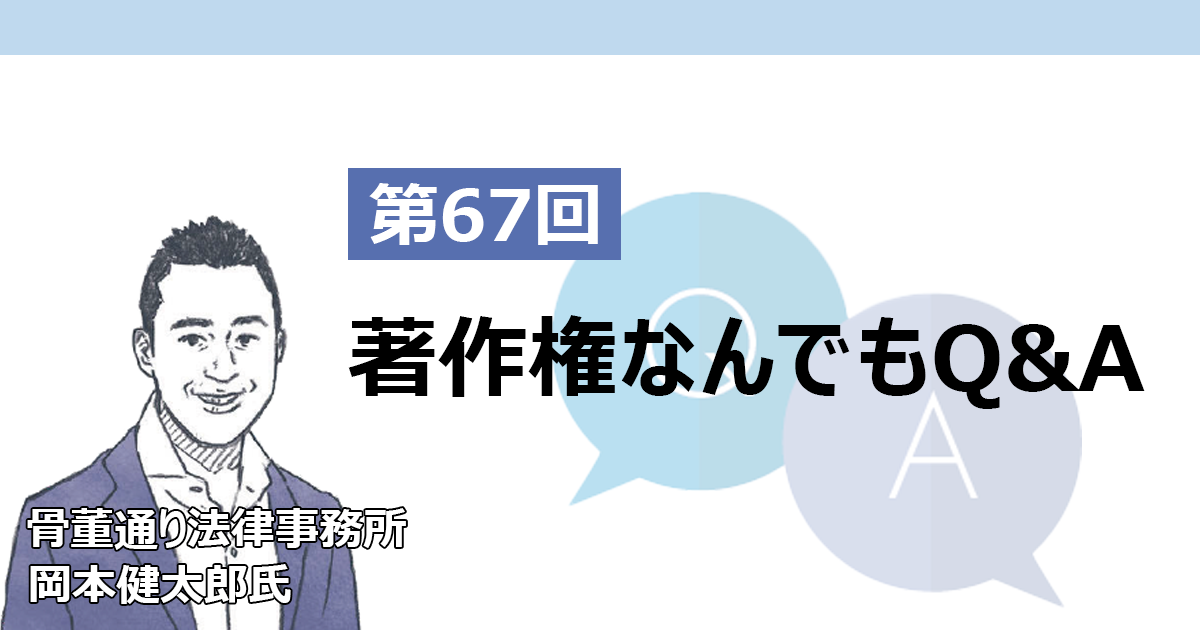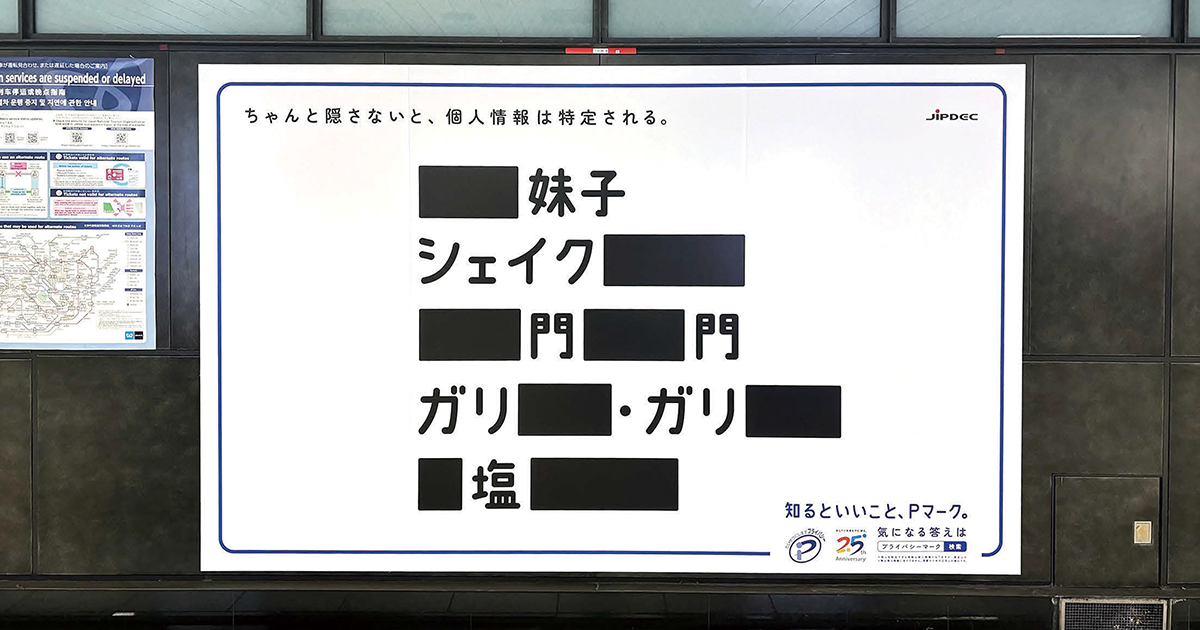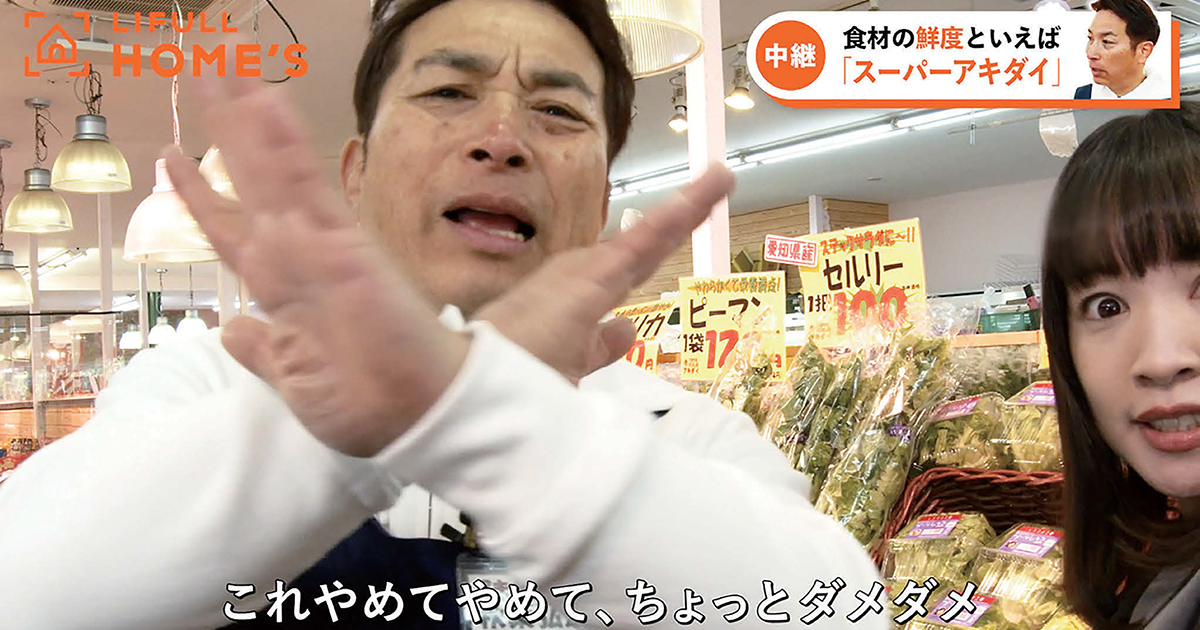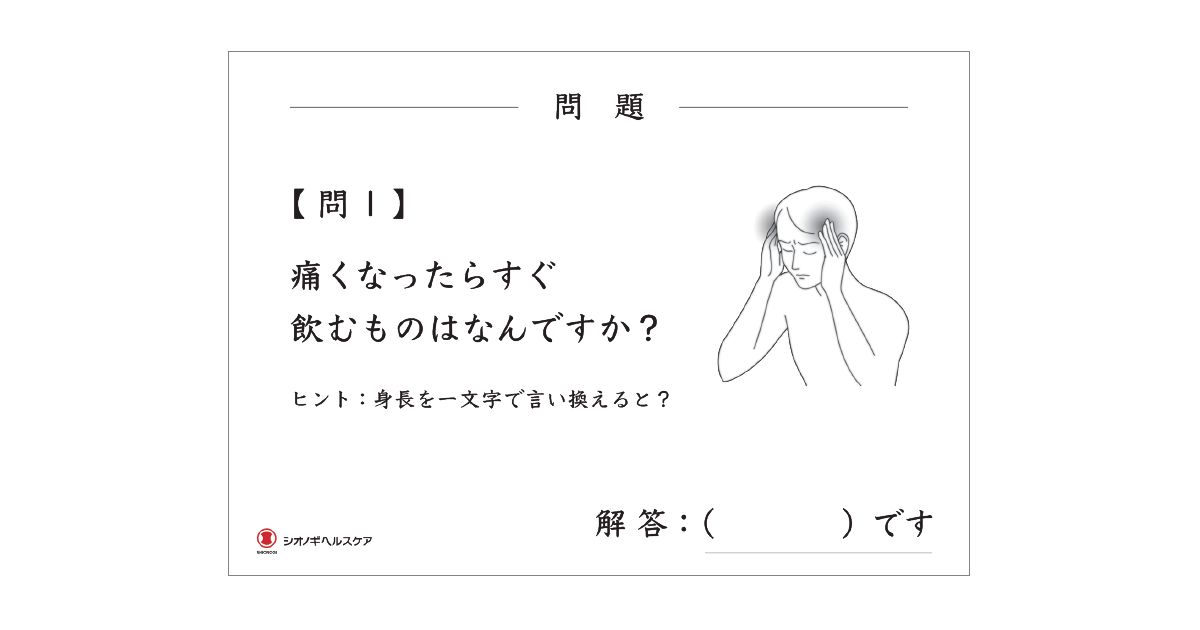6月2~3日、「インターネットフォーラム2015」がANAインターコンチネンタルホテル東京で開催された。9回目を迎えた今回は「マーケターの“WILL(志)”がテクノロジーの可能性をひらく」をテーマとし、企業のデジタルマーケターを中心に、2日間で5264人が来場。講演や展示ブースには、カスタマー・エクスペリエンス、オウンドメディア、動画広告、カスタマージャーニー、DMPなどといった旬なキーワードが並び、デジタルマーケティングの最前線が語られた。4つの基調講演をダイジェストで振り返る。


——デジタル上でコミュニケーションを図る際、どのようなことを考えられていますか。
関口:ボルボというブランドは、現時点ではまだ「プレミアムニッチ」な領域です。特に「プレミアム」を標榜しているので、イノベーティブなイメージは非常に重要であり、デジタル領域での施策を重視しています。ただ、一言で“デジタル領域”と言えど、それがメディアのことなのか、デジタルに特化・最適化したクリエイティブのことなのか、ビッグデータを活用したマーケティング手法なのかを切り分けて考えるべきだと感じています。
三宮:当社のIMC(統合型のマーケティング・コミュニケーション)のプランでは、縦軸に施策の確実性(確実なヒットを狙うのか、空振りしても良いからホームランを狙うのか)、横軸に施策の継続性(短期的な売上目的のキャンペーンか長期的なブランディングに寄与するものか)という4象限に分けた図式にしており、その上でデジタルをどのように位置づけるかを考えています。私が手がける施策で多いのは、全体予算の一部を使い、空振りでも良いからホームランを狙っていこうという戦略です。「トリプレッソ」というブランドで実施した「松崎しげるを探せ!」というキャンペーンは、ただゲームを楽しんでもらうだけではなく、テレビやWebなどのメディアにいかに取り上げてもらうか、ということを軸に企画しました。
関口:三宮さんの4象限の整理に強く共感します。世の中では、いわば「ホームラン」の例はたくさん語られていますが、実際は …