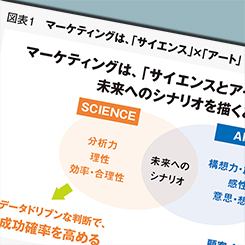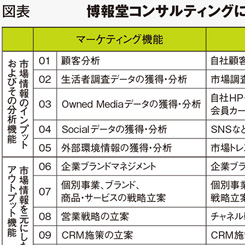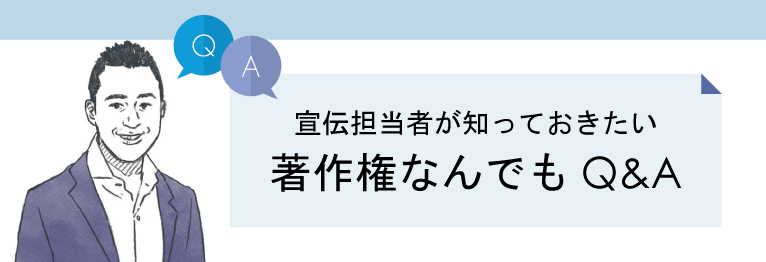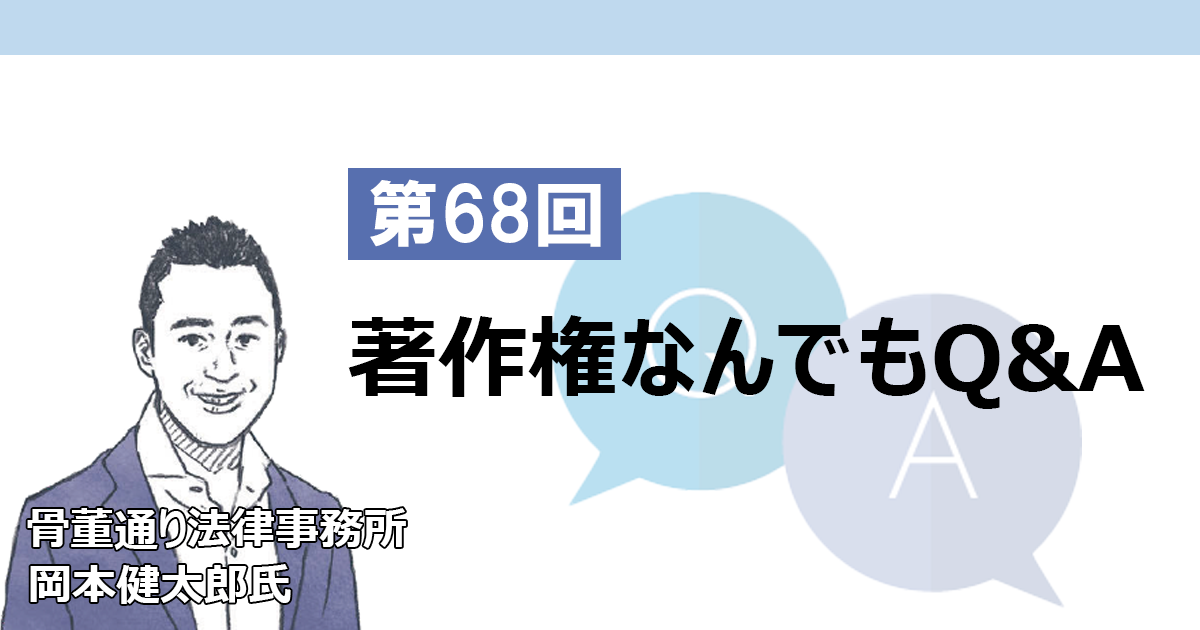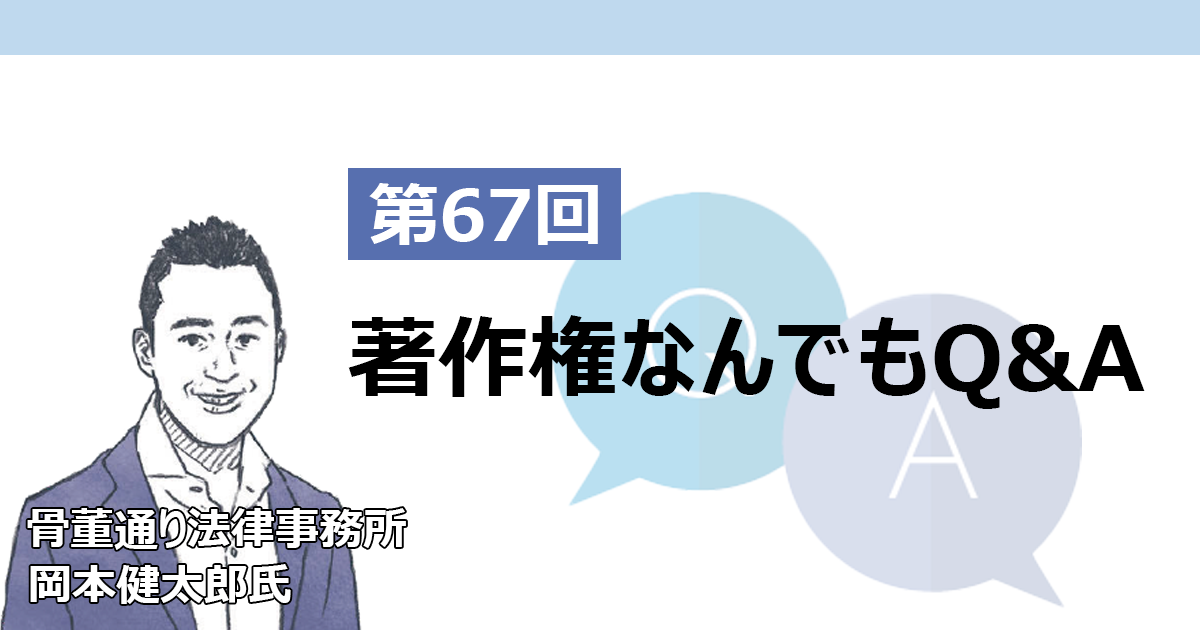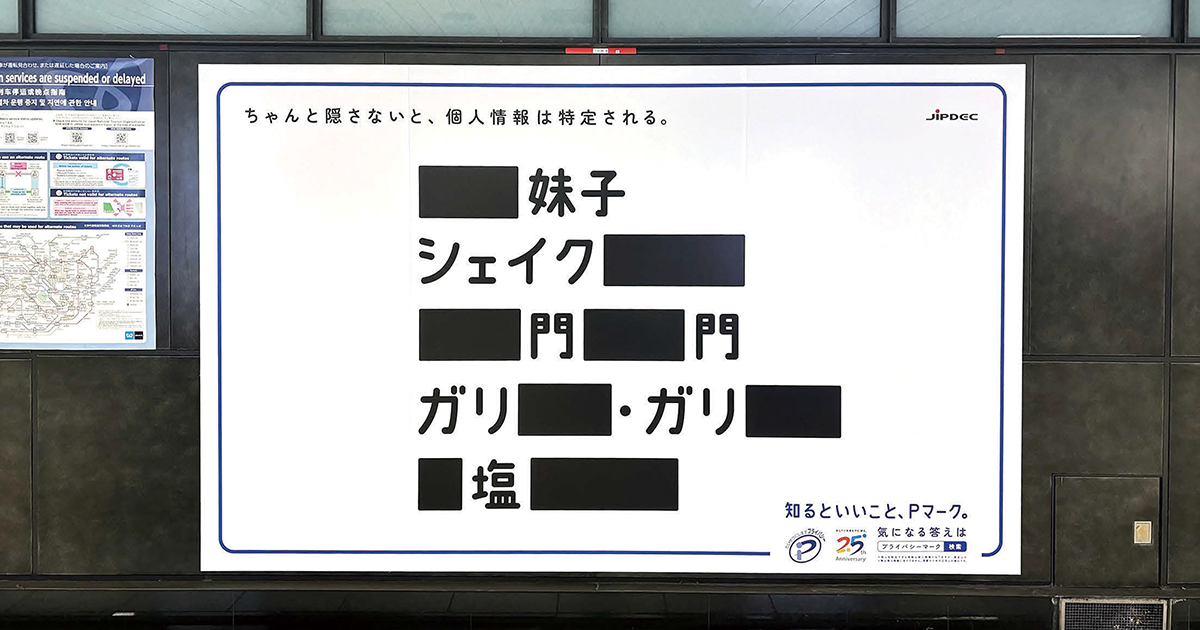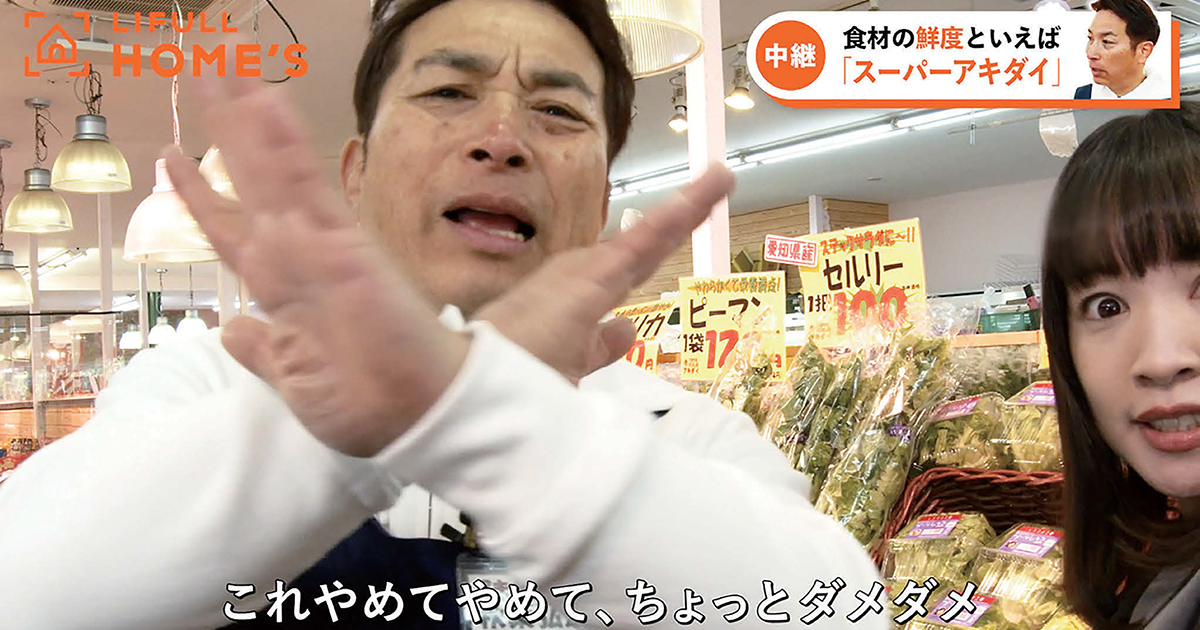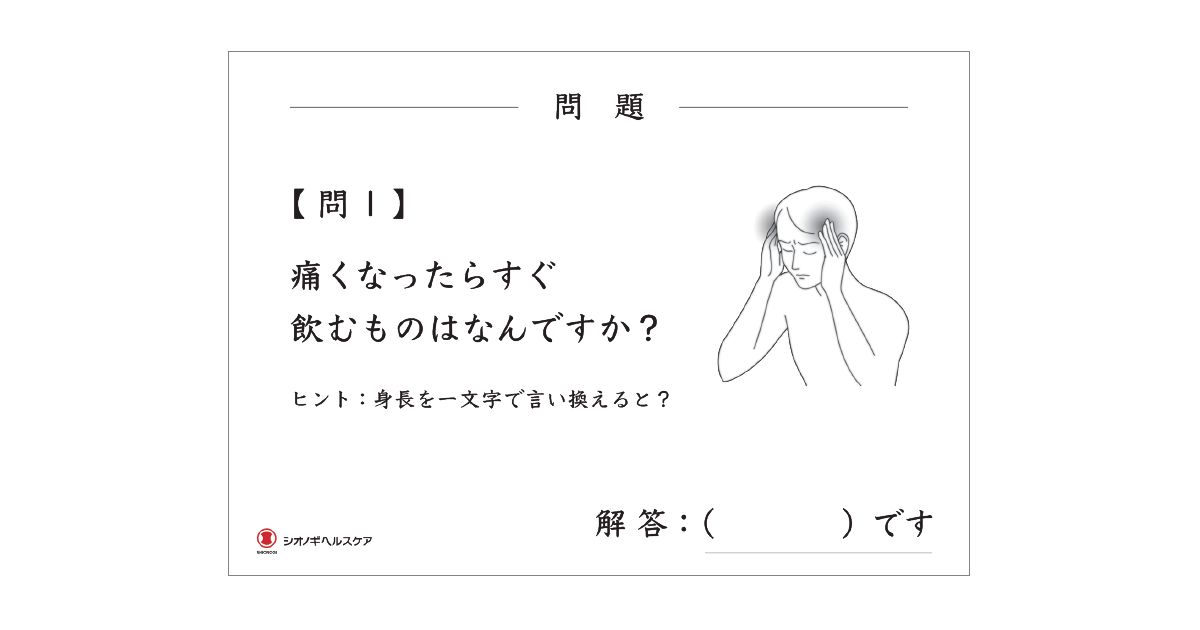あなたの会社に、本当に「マーケティング」はありますか......?表紙の帯で、そんなセンセーショナルな投げかけをした書籍『The Real Marketing―売れ続ける仕組みの本質』が4月上旬、発売になった。著者であるインテグレートの藤田康人氏が考える、日本企業で機能するマーケティング組織とは。
現在はマーケティングコンサルティング会社、インテグレートの代表取締役CEOという立場にあり、それ以前は新卒で味の素に入社し長年、事業者側でマーケティングの実務に携わってきた経験を持つ藤田康人氏。インテグレートにて、クライアントが直面する様々なマーケティング課題解決の道筋を探るプロジェクトに参加する中で、日本企業が抱える課題が見えてきたという。

インテグレート代表取締役 CEO 藤田康人氏
狭義のマーケティング
――新刊著書冒頭で「日本企業は、欧米のグローバル企業と比較するとマーケティングという機能そのものが存在していなかったのではないか?」という指摘をされています。
正確には“高度な”マーケティングが存在していなかった。マスプロモーションに特化した狭義のマーケティング活動に終始していたのだと考えています。私は「日本企業が怠けていたのだ」と言っているわけではありません。幸か不幸か、これまで日本企業が特に国内市場でビジネスをする分には、「高度なマーケティング」は必要なかった。だから、マーケティングが進化・発達することがなかったのです。
高度経済成長期の日本は、消費者の需要が爆発的に拡大。さらに、テレビや新聞など圧倒的なカバー力を有するマスメディアが存在していたため、マス広告を打ち、新製品が発売されたことを知らせれば、高い技術力をベースにした日本企業の製品ですから、それだけでモノが売れていきました。一方で人種、言語、宗教などが多様な人たちが集まる欧米諸国では、メディアも細分化していきますし、日本のようにマス広告を使って効率的に拡大する需要を刈り取るというモデルが通用せず、必然的にマーケティングが進化を遂げていったのです。
しかし商品の機能競争は行き着くところまで行き、日本の市場は成熟化。さらに消費者の情報収集経路が多様化したことで、メディアの影響力も分散化し、マス広告だけが商品を売るための絶対的な解ではなくなりつつあります。なおかつ国内市場でビジネスをしていても、いまや高度なマーケティングを駆使する欧米のグローバル企業が次々と日本市場に進出しており、国内にあってもグローバル企業と伍して戦えるだけの競争力が必要とされています。改めて、日本企業もマーケティングについて考えるべき時が来ていると思います。
“中央集権的”はなじまない
――マーケティング力を強化するために、日本でもCMOが必要だという議論が起きています。
マーケティング活動全体を俯瞰で見る「リーダー」の存在は必要です。しかしCMOという中央集権的なスタイルが、リーダーシップのあり方として日本企業に適しているか、といえば疑問が残ります。
「インテグレート」という、当社の社名が象徴するように、私は「次世代IMC(インテグレーテッド・マーケティング・コミュニケーション)」を旗印に掲げ、サービスを展開してきました。90年代にドン・シュルツ教授により提唱された、IMCの概念はマーケティング活動が複雑化する中、進化・発展を遂げています。多様なコミュニケーション活動、およびその活動を統合するIMC1.0から、生活者のインサイトを探るリサーチ、商品開発、流通施策についての統合的な戦略立案など、すべてのステークホルダーが幸せになれる、ビジネス・プロセスまで含んだマーケティングの仕組みづくりであるIMC2.0。さらにビッグデータの時代、企業が持つ様々なデータを統合し、経営戦略へと反映していくIMC3.0へ...。企業の実践の中で、その概念も大きく変遷を遂げてきました。
グローバル企業では、すでにIMC3.0まで進んでいますが、日本の企業は1.0ですら、多くの企業で実践できているとは言い難い。では、ここに強力なリーダーシップを持った人を配すれば、全てがうまくいくかといえば、そうとも限りません。そもそもマーケティングとは、売れ続ける仕組みをつくること。それならば、この「仕組み」づくりで日本企業に合った形を考えるべきではないか...。本書では、その「仕組み」について、CMOがいなくてもIMC3.0を目指せるマーケティング機能のあり方を解説しています。
ちなみにここで言う「仕組み」とは商品を売ることに関わる、消費者だけでなく社内外のあらゆるステークホルダー全員が、幸せになれる「ストーリー」とも置き換えられます。それがなければ、「売れる」ことはあっても「売れ続ける」ことはありません。このストーリー、設計図を描くマーケターにはリーダーシップは必要ですが、あくまで一人ひとりの関係者全員が主役になれるようなシナリオであるところが、欧米流のリーダーシップのあり方と異なる点です。
――マーケターは消費者“だけ”見ていればよいわけではないということでしょうか。
成熟化した市場では特に顕在化したニーズだけ見ていても、レッドオーシャンの中で厳しい戦いを強いられるだけです。それゆえ潜在ニーズを発掘することがますます必要となっていますし、消費者インサイトの把握が核であることに変わりはありません。またビッグデータの時代、テクノロジーも駆使しながら刻一刻と変化する消費者インサイトを把握し、マーケティング活動において高速でPDCAを回し続けていくことも重要です。
しかし消費者以外の関係者のインサイト、具体的にはメディア、ソーシャル、流通も加えた4つを理解しなければ、売れ続ける“仕組み”にはなりません。かつ、この4つのインサイトの理解の過程で社内外のあらゆるステークホルダーにヒアリングをし、彼らのインサイトを知り、彼らも巻き込んでいくことができるのです。
――デジタルテクノロジーの進展など、マーケティング環境はますます激変しています。
成熟した市場環境下、消費者インサイトは常に変わり続け、それによりマーケティング活動におけるルールも、また変わり続けています。ルールが変わらない前提では、大きいこと、強いことが勝利のための必要条件でした。しかし今はインサイトを正しく、早く知ることこそが、勝利のために必要なことです。企業の規模や歴史に関わらず、マーケターが勝負できる環境が生まれています。その意味で、マーケティングの仕事は、ますます面白くなっているのではないかと思います。
新刊
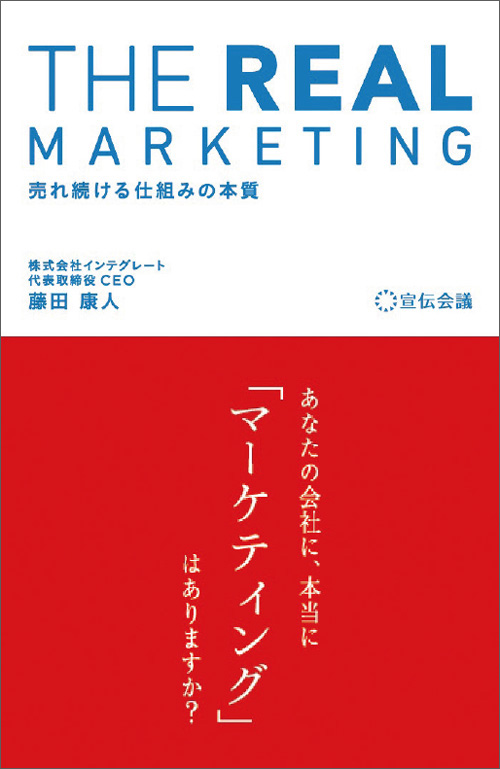
『The Real Marketing―売れ続ける仕組みの本質』
いま、日本企業に必要なのはCMOではない。必要なのは、マーケティング・マネジメントを最適化する仕組みだ。事業に関与するすべてのステークホルダーのインサイトを探り、全員が幸せになるマーケティング・ストーリーを描く。そして全社横断型のオペレーションを実行する...。IMCのパイオニアであるインテグレートCEO藤田康人氏が具体的な事例を取り上げながら、そのノウハウをわかりやすく解説する。