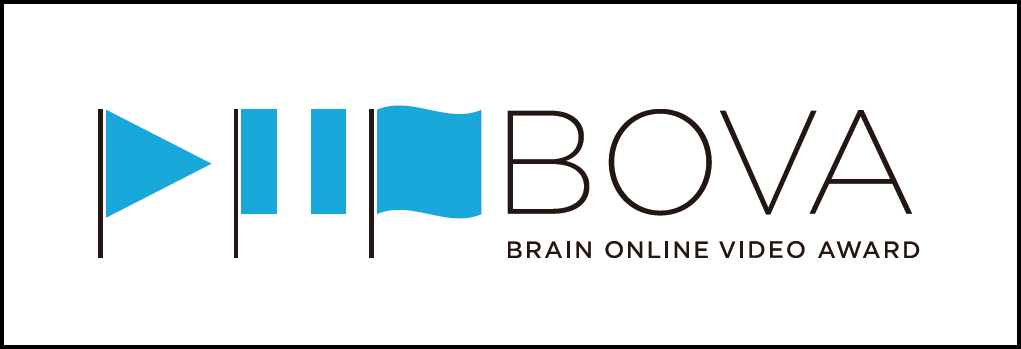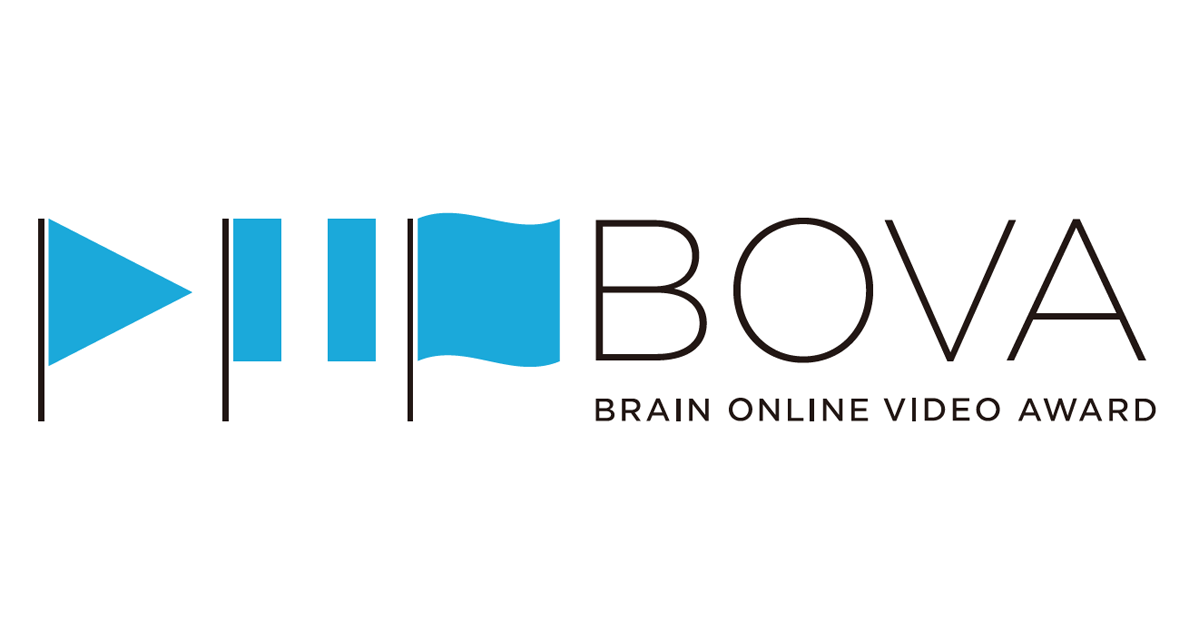オリンピックエンブレム問題に端を発し、揺れた2015年の日本のデザイン。それによって、デザインというものが社会の中でどのように理解されているのか。デザインビジネスの構造はこのままでよいのか。そもそも人々はデザインに何を求めているのか…など、大小さまざまな課題が浮きぼりになりました。デザインに携わる人たちですらデザインの本質を見失いそうになり、社会の中にはデザインに対する誤解や誤謬が広がりました。
浮きぼりとなった課題を課題のままに、そして他人事で終わらせるのではなく、これからのデザインのあり方や本質をデザインに携わる人たちがあらためて考えてみる──。そのことを考えるきっかけが私たちメディア、またデザインに深く携わる方たちにいま求められているのではないかと感じました。
そこで、その一つの機会をつくるべく、今回の青山デザイン会議ではさまざまなプロダクトを手がけるプロダクトデザイナー 柴田文江さん、デザインとエンジニアリングの融合を実践されているデザインエンジニア 田川欣哉さん、そして2016年大きな展覧会など新しいプロジェクトを予定しているグラフィックデザイナー 原研哉さんに参加をいただきました。2015年を振り返りつつ、2016年にデザインは、そしてデザイナーはどうあるべきか、話し合いました。

Photo : parade inc. / amanagroup for BRAIN
移動の喜びをデザインする時代に
田川:最近、デザインの役割が変わってきたと感じています。具体的な形をつくるだけではなく、世の中にイノベーションを起こすための推進力の一つとしてデザインが活用されている。同時にデザイン業界と関わりのなかった人たち、いわば非デザイン業界の人たちがデザインに関心を持ち始めています。それに伴い、私自身も非デザイン業界の人たちと仕事をする機会が増えています。
柴田:私は2015年、グッドデザイン賞の副審査委員長を務めさせていただきましたが、“デザインをする人の立場”が大きく変わったと感じます。というのも、今回のグッドデザイン賞では素晴らしい提案の多くが、デザインを専門としない人や企業から出てきたものでした。メーカーがつくりたいもの、伝えたいものをデザイナーが翻訳して形にすること、それこそがデザイナーの役割だと思っていましたが、もうその次元ではない感じがしています。
原:デザインに限らず、産業そのものが変化していることも大きいと思います。これまでの産業は高度経済成長時代の工業化モデルが根幹にあり、インダストリアルデザインやコミュニケーションデザインがあるというスキームでしたが、いま従来のモデルが崩壊しつつあり、大きな変革が起こりつつあります。それを如実に表しているもののひとつが、世界の旅行者人口の推移です。1964年の東京オリンピックの頃が1300万人だったのに対して、2015年は12億人、2030年には20億人に近づくと予測されています。つまり近い将来、世界人口の4分の1が移動する時代を迎えることになる。
移動に伴う享楽が“世界共通の喜び”になり、行動のモチベーションになる。それによって、デザインやテクノロジーの問題の中枢は「移動の喜びに対して何ができるか」ということに移っていくと考えられるわけです。移動空間のあらゆる瞬間に生活者とのコンタクトポイントがあり、それは単にサインシステムをデザインするというようなことではなく、それぞれの空間におけるエクスペリエンスを根本から考え直していくことが必要になっていくといえるでしょう。
柴田:かつては所有の欲求が断然高かったので、私の主な仕事であるプロダクトデザインは「所有欲求に対していかに価値を提案できるか」を重視していました。今でもメーカーはその幻想を抱いて商品開発をしがちですが、私自身も所有より移動や行動欲求のほうが高くなっているから、ものづくりが所有のためではなくなっていることには大きな納得感があります。
田川:旅の観点から言うと、サンフランシスコという街はUBERの出現によって都市全体が明らかに進化していました。数年前まではタクシーの車両は汚く、ドライバーの対応も丁寧ではありませんでした。しかし、UBERによって、タクシーを呼ぶことから乗車中の体験、そして決済までが、シンプルに解決されました。これはまさにエクスペリエンスのデザイン。世界移動者数の増加とシンクロするように、都市の体験の仕方、場合によっては都市そのものの成り立ちもITによって変化し得ることを示していると思います。
デザイナーに求められる「整理する」力
原:いま、デザインや建築に過大な期待をしない社会になりつつあります。それは格差によって世界が二極化していることが背景にあるように感じます。ある層は所有による満足感よりも身の丈に合った実現可能な満足を模索しています。国立競技場やエンブレムの問題には、社会背景が影を落としているような気がしてなりません。さらに所有格差だけではなく、情報格差も大きく、UBERのような新しいサービスや仕組みを使いこなせなる層とそうでない層の乖離感も生まれ始めている。だから、「デザインをどうする」というレベルの話ではなくなってきているように思います。
田川:所有できない時代になっているからこそ、誰かが所有することに対して非常に敏感になっているのではないかと思います。国立競技場は税金が投入されているので「国民みんなの所有物」と思っていたのに、「クリエイター個人のもの」に見えてしまった。そこに嫌悪感が現れたようにも感じました。
柴田:最近、私が手がけている医療系の仕事では誰かの所有物をつくるのではなく、さまざまな医療機関で全ての人に提供できるサービスを目指しています。それを実現するためには、どんな形をデザインするかよりも、さまざまな職種の人たちといかに組み、その意図をいかに翻訳し、いかにビジョンを示すかということが重要になっています。こうしたプロジェクトの場合、私がプロダクトをデザインしないこともあります。私のように生活関連のプロダクトに関わってきたデザイナーにとっては、新しい仕事の進め方が始まった感じがしています。
田川:私が関わる経済産業省中小企業庁のビッグデータビジュアライゼーションのプロジェクトもそれに近い例です。このプロジェクトでは、政策をつくる現場で働いている人たちの頭の中を言語化し、ロジカルに組み立てた上で、インタラクティブなソフトウェアとして実装しています。今、大規模なデータを直観的に把握可能な形にとして示すことがとても重要になってきていると思います。近年は情報量が激増し、人間の認知限界を超えつつあります。膨大なデータのひとつひとつを見て詳細に分析するのは難しい。でも、それがビジュアル化され、絵として風景化されると、人間はそれらを直観として受け取り、理解することができるようになります。
原:ビッグデータの場合、解析結果をどのようなサービスと結びつけるかがサービスの根幹ですが、それをいかにビジュアライズして見せるかが重要です。僕はそこにデザインの役割があると思っています。多様な産業がせめぎあっていますが、それぞれ個別に勝手な世界観や未来像を描くのではなく、問題やビジョンを投影する共通のスクリーン、あるいはプラットフォームのようなものを持つ必要があると思います。ビッグデータを考える人はデータの解析ばかりを考えがちだけど、その示し方こそ実は非常に重要なのです。
柴田:最近、デザイナーがもっている“整理の仕方”を必要とするプロジェクトは増えていますね。デザイナーは100ある中から不要な50を取り除くことは容易にできる能力をそなえていますから。
田川:デザイン業界以外の人も「ひょっとしたらデザインが形をつくること以外にも使えるかもしれない」と、その力に気づき始めたと言えるのかもしれません。
原:デザインにはいわゆる問題解決型のデザインとアブダクション(仮説形成)、つまり問題提起型があり、僕は主にアブダクションをやり続けてきました。要するに「だったりして」を具体化することをやっているように思うのです。例えば走り幅跳びは、ある人が砂場を跳んでみたら2.5メートルという記録が出て …
あと62%
この記事は有料会員限定です。購読お申込みで続きをお読みいただけます。